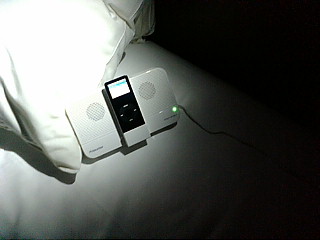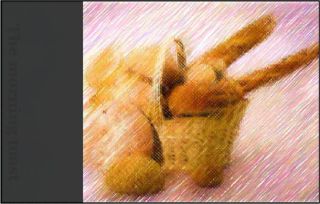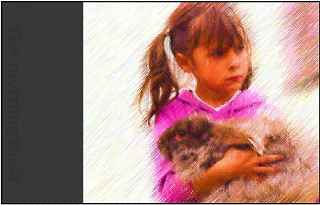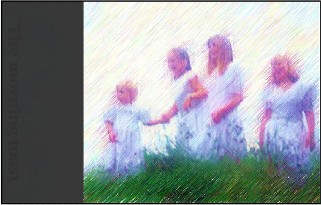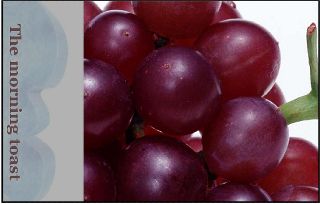2023年12月05日
2023年11月29日
脳の生存戦略
内田舞 著 「ソーシャル ジャスティス」から
『
脳というのは、
ストレスを感じるときに
前頭前野の働きが抑制されます。
短期の生存のためには
「考える」前頭前野を抑制して、
既に形成されている神経回路の
ネットワークがひとりで働くことで、
その場の危機を逃れられるような仕組みに
できているのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:18
2023年11月28日
偏見・差別、固定観念は無意識
内田舞 著 「ソーシャル ジャスティス」から
『
反復経験が積み重なるごとに
「固定観念」という「習慣」が形成され、
それが反復されればされるほど
増強された神経回路ネットワークが築かれ、
前頭前野は
「このことについては考えないでいい」
という抑制のシグナルを受け取るのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:15
2023年11月10日
心が無理をすると
内田舞 著 「ソーシャル ジャスティス」から
『
心というのは
無理をすればするほど、
隠そうとしている負のエネルギーが
別の形で出てきてしまうものなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:28
2023年10月30日
一つの軸で優劣を測るな
内田舞 著 「ソーシャル ジャスティス」から
『
本来人間の持つ長所と情熱は多様で、
人生の中で能力を発揮するタイミングも
様々であるはずなのに、
思春期の時点で一つの軸だけで
優劣が測られるのはとても勿体ないと感じます。
』
- Permalink
- by
- at 00:50
2023年10月13日
指導者を輩出するところ
2023年10月12日
指導者
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
指導者は、多くの場合、
思想家ではなくて、実務家であり、
あまり明晰な頭脳を具えていないし、
またそれを具えることはできないであろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:42
2023年10月11日
名誉心、宗教的信仰、功名心、祖国愛
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
名誉心、宗教的信仰、功名心、祖国愛
のような感情は、
道理によらず、
むしろしばしば道理に反して生まれたのであって、
これらの感情こそ、
これまであらゆる文明の大原動力であったのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:40
2023年10月10日
道理
2023年09月26日
科学
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
科学が、
理想に餓えた人々の心のうちで、
危ぶまれるようになったのは、
科学が、
もはやあえて十分に将来を約束しなくなり、
さりとて十分に嘘をつくことも
できないからである
』
- Permalink
- by
- at 00:27
2023年09月25日
人間と幻想
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
幻想なくしては、
人間は原始的な野蛮状態から
抜け出られなかったにちがいないし、
たとえぬけ出ても、
幻想なくしては、
また野蛮状態に戻るであろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:24
2023年09月24日
同じ言葉が同じでない
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
各社会層は、
外見では、
同じ言葉を用いているかのように思われるが、
その実、
同じ言語を話しているのではないのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:22
2023年09月23日
言葉の力
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
言葉の力は、
実に偉大であるから、
用語を巧みに選択しさえすれば、
最もいまわしいものでも
受けいれさせることができるほどである。
』
- Permalink
- by
- at 00:20
2023年09月21日
言葉
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
言葉というものは、
時代により民族により変化する、
移動しやすい一時的な
意味を持つにすぎないのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:22
2023年09月20日
模倣
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
ギリシャ人やローマ人を
模倣していると思いこんていた大革命時代の人々は、
古い言葉に、
かつてない新たな意味を与えていたにすぎない。
』
- Permalink
- by
- at 00:20
2023年09月19日
心像(イマージュ)
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
言葉によって呼び起こされる心像(イマージュ)は、
その言葉とは無関係であるから、
同一の標語で示されていても、
時代により民族によって種々に異なってくる。
』
- Permalink
- by
- at 00:18
2023年08月31日
道理も議論も
2023年08月30日
極めて意味のあいまいな言葉
2023年08月29日
言葉の力
2023年08月28日
学校は怪物を養成している
2023年08月26日
現代の教育法は
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
一国の青年にさずけられる教育を見れば、
その国の運命を幾分でも予想することができる。
現代の教育法は、
最も暗澹(あんたん)とした
予想を裏書きしている。
』
- Permalink
- by
- at 00:31
2023年08月21日
群衆のない制度は
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
われわれは、
制度が、勝利を得るにせよ、
敗北を喫するにせよ、
制度自体では
何の価値をも持っていないことを知っている。
それゆえ、
制度の勝利を追求すれば、
何のことはない、
まぼろしを追求するのも同然となろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:45
2023年08月16日
制度
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
制度は、
何ら本質的な価値を持っていず、
それ自体ではよくも悪くもないのだ。
ある時期に、ある民族によってよい制度も、
他の民族にとっては、
厭(いと)うべきものとなることがある。
』
- Permalink
- by
- at 00:39
2023年08月09日
絵本が見えなくならないように
2023年05月05日
非現実が現実よりも優位になる
2023年05月04日
外見が実在よりも重要にされる
2023年05月02日
群衆が受けいれる判断
2023年02月10日
群衆は新事実を嫌う
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
群衆は、
根強い保守的本能を具えていて、
あらゆる原始人のように、
伝統に対しては拝物教的敬意をいだき、
現実の生存条件を改めかねない
新しい事実を無意識に嫌悪する。
』
- Permalink
- by
- at 00:51
2023年02月09日
群衆が立ち戻るところ
2023年02月08日
群衆は隷属へ赴く
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
群衆は、
そのまま放任されていても、
やがて自己の混乱状態に飽きて、
本能的に隷属状態のほうへ赴くのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:46
2023年02月07日
群衆は強い権力に屈服する
2023年02月06日
群衆が愛慕する英雄
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
群衆が愛慕する英雄の典型は、
常にカエサル流の風格を持つものであろう。
その羽飾りが群衆を魅惑し、
その権力が彼等を威圧し、
その剣が彼等を畏怖させるのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:42
2023年02月05日
群衆の感情
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
横暴さと偏狭さとは、
群衆にとって、
非常に明瞭な感情となっている。
群衆は自らこの感情をやすやすと実行に移すが、
それにも劣らず容易にこれを甘受する。
』
- Permalink
- by
- at 00:39
2023年02月04日
群衆は横暴
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
群衆は、
自ら真理あるいは誤謬(ごびゅう)と信ずることに
何らの疑いをさしはさまず、
他面、おのれの力をはっきりと自覚しているから
偏狭であるに劣らず横暴である。
』
- Permalink
- by
- at 18:25
2023年02月03日
群衆になると愚かになる
2023年01月29日
憎悪は群衆中の個人で生まれる
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
反感や不服の念がきざしても、
単独の個人の場合ならば
さして強くはならないであろうが、
群衆中の個人にあっては、
それは、
たちまちはげしい憎悪となるのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:12
2023年01月28日
感動を与える英雄とは
2023年01月27日
歴史書
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
歴史書とは、
よく観察されなかった事実に、
後日捏造した説明を伴わせる
想像的記述にほかならないのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:18
2023年01月26日
最も疑わしい事件
2023年01月22日
群衆にとって真実は無用
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
群衆にとっては、
およそ真実らしくないと考えられるものなどは、
存在しないのである。
世界にも荒唐無稽な伝説や説話が、
どんなに容易に生み出されて
普及されるかを理解するには、
このことをよく記憶せねばならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:56
2023年01月19日
やっても変わらないよ、日本だから
国際NGO アース・ガーディアンズ・ジャパン代表 川崎レナ さんの言葉から
『
周りの子と話しても
「いや、やっても変わらないよ、日本だから」
と言われることがある。
でも私は、
その日本が好きなので
「変われる」
と思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:59
2023年01月18日
社会を変えるには
国際NGO アース・ガーディアンズ・ジャパン代表 川崎レナ さんの言葉から
『
私の活動は、
日本を大きく変えるようなものでは
ないかもしれないけど、
一人ひとりの意識を変えていくことでしか
社会は変わらないし、
目の前の人と話せば、
その人は少しでも
変わっていくかもしれない
』
- Permalink
- by
- at 00:47
2023年01月17日
変わりそうにない日本
国際NGO アース・ガーディアンズ・ジャパン代表 川崎レナ さんの言葉から
『
「変えられない」
「できっこない」
という思いは、みんなある。
私にもある。
だけど、
何かしてみてからじゃないと、
わからない
』
- Permalink
- by
- at 00:45
2023年01月13日
二つの現実
ノーベル賞作家 アレクシエービッチ さんの言葉から
『
人間は二つの現実を生きています。
一方は、
人々と街が破壊される。
全く中世的なウクライナでの戦争。
他方は、
人工知能や宇宙船。
』
- Permalink
- by
- at 00:32
2023年01月12日
憎しみと狂気に立ち向かうには
ノーベル賞作家 アレクシエービッチ さんの言葉から
『
私たちの誰もが、
とれも孤独です。
文化や芸術の中に、
人間性を失わないための
よりどころを探さなくてはなりません。
』
- Permalink
- by
- at 00:30
2023年01月11日
時代は新たな中世
ノーベル賞作家 アレクシエービッチ さんの言葉から
『
再び戦車が走り、
街が破壊され、
人々が殺され、
抑圧される。
こんなことはもう
起りえないと思っていました。
』
- Permalink
- by
- at 00:27
2023年01月10日
偉大さ欺瞞は流血をもたらす
ノーベル賞作家 アレクシエービッチ さんの言葉から
『
大事なのは、
どんな独裁者も、
時を止められないということです。
彼らは勝てないでしょう。
ただ、それまでにとても長い時間が
かかるかもしれません。
』
- Permalink
- by
- at 00:25
2022年12月29日
日本大丈夫か?
建築家 安藤忠雄 さんの言葉から
『
この私でさえ
「絶望的」だと感じる。
でも立て直さなダメでしょ。
それには、
明日を担う子どもたちのために、
力を注ぐしかない
』
- Permalink
- by
- at 00:37
2022年12月26日
群衆と野蛮人
2022年12月21日
群衆に対する暗示
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
感情や、
この感情に刺激されて
ひき起こされる行為から見れば、
群衆は事情次第で、
個人よりも優ることも、
また劣ることもある。
すべては、
群衆に対する暗示の仕方如何にかかっている。
』
- Permalink
- by
- at 00:33
2022年12月20日
群衆の個人と正常な自分
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
群衆中の個人が
正常の自分と異なるのは、
単に行為の上ばかりではない。
自主性を全く失う前に、
すでにその観念や感情が
変化してしまっている。
』
- Permalink
- by
- at 00:30
2022年12月07日
I Will Follow Him(Sister Act)
I will follow him
Follow him where ever he may go
And near him I always will be
For nothing can keep me away
He is my destiny
I will follow him
Ever since he touched my heart, I knew
There isn't an ocean too deep
A mountain so high it can keep
Keep me away, away from his love
I love him, I love him, I love him
And where he goes I'll follow, I'll follow, I'll follow
I will follow him, follow him where ever he may go
There isn't an ocean too deep
A mountain so high it can keep, keep me away
We will follow him
Follow him where ever he may go
There isn't an ocean too deep
A mountain so high it can keep
Keep us away, away from his love
(I love him)
Oh yes, I love him
(I'll follow)
I'm gonna follow
True love, he'll always be my true love
(Forever)
From now until forever
I love him, I love him, I love him
And where he goes I'll follow, I'll follow, I'll follow
He'll always be my true love, my true love, my true love
From now until forever, forever, forever
There isn't an ocean too deep
A mountain so high it can keep
Keep us away, away from his love
- Permalink
- by
- at 00:20
2022年12月02日
無意識の基盤
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
われわれの行為の明らかな原因の背後には、
われわれの知らない原因がひそんでいる。
われわれの日常行為の大部分は、
われわれも気づかない、
隠れた動機の結果なのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:54
2022年11月30日
人間の精神構造
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
小説のなかでは、
人物が一定不変の性格を具えて現われてくるが、
現実の生活では、
そういうことはあり得ない。
単に一様な環境のみが、
見かけだけは一様な性格を生むのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:52
2022年11月29日
群衆
ギュスターヴ・ル・ボン 著 「群衆心理」から
『
文明の屋台骨が虫ばまれるとき、
群衆がそれを倒してしまう。
群衆の役割が現われてくるのは、
そのときである。
かくて一時は、
多数者の盲目的な力が、
歴史を動かす唯一の哲理となるのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:50
2022年11月25日
全人類の死
2022年11月23日
マルクス主義の階級闘争理論の前提
2022年11月21日
愛する人々の幸福を願うことは
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
私たちは私たちの愛する人々の幸福を
希わなければならない。
しかし、それは私たち自身の幸福と
引き替えに希われるのであってはならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:49
2022年11月19日
計算された愛情
2022年11月18日
愛情を受け取る人、愛情を与える人
2022年11月09日
賢人というものは
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
賢人というものは、
女中の責任ではない塵やほこり、
コックの責任でないポテト、
煙突屋の責任でない煤など
というものにはあまり気を使わぬだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年10月31日
子供を上手に育てる努力量
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
子供を上手に育てることに
費やされる努力の分量は、
いうまでもなく莫大なものであり、
これについてはおそらくなんびとも
これを拒否しないだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:03
2022年10月17日
心配以外に
2022年10月15日
人間が偉大になるには
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
精神がこの宇宙を映しとっているような人間こそ、
ある意味においては、
この世界と同じように
偉大なものとなるのだということを知るだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:54
2022年10月14日
幸福であるためには
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
魂の偉大さに
目を開かれた人間は、
彼の精神の窓を広々とあけ放ち、
その窓々を通して
宇宙のあらゆる部分から吹いてくる風を
自由に吹き通わせるだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:51
2022年10月11日
結果第一主義なら暗黒時代に戻る
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
諸君のいま従っている瞬間的な闘争なるものが、
いままで人間が徐々にそこから脱出してきた
ところの暗黒への逆転の一歩を
あえて歩み出すに足りるほど重要な意義を
もったものではあり得ないということを。
』
- Permalink
- by
- at 00:44
2022年10月06日
技能より理性と感情を拡大する
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
ある種の技能の獲得について
あまりに多く訓練し、
この世の客観的な考察によって
理性と感情を拡大することについては
あまりにわずかしか訓練しなかったということ、
これこそ現代高等教育のもつ欠陥の
一つにほかならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:47
2022年10月04日
この世に満ちているもの
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
この世は
あるいは悲劇的な
あるいは喜劇的な、
あるいは英雄的な
あるいは陳腐な、
さらに驚くに足りるごとき
さまざまな事物に満ちている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年10月03日
カジノは欲望のために作られもの
2022年09月26日
2052プーチンの孫(PutinⅢ):ロシア平和統一家庭連合のたくらみ
2022年09月15日
新しい見方が湧きあがると
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
新しい見方が自分のなかで湧きあがってきたとき、
経験豊かな作家であっても
乱調に陥ることがある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年09月14日
内側から書く
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
内側から書く方法は、
規律がありながら自由であり、
最高の作品を生み出すことが
できるように考えられたものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:15
2022年09月11日
ごみ箱行き
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
自分の才能を信じている脚本家は、
創造性が尽きることはないと知っているので、
きらめく宝石のようなストーリーを書けるまで、
自分のベストと思えるもの以外は
すべてごみ箱行きにする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年09月10日
成功する作家とそれ以外の作家
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
成功する作家と芽が出ない作家とでは、
創作方法が対照的だ。
それは、
内側書くか、
外側から書くかという点である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年09月09日
大げさなシンボルは
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
大げさにシンボルを用いるのは鬼才でもなんでもなく、
ユングやデリダを誤読して火がついた独善にすぎない。
そのような虚栄心は芸術を卑しめ、腐敗させる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年09月08日
シンボルの制約
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
シンボルも心に届いて感動を呼び起こすが、
それはシンボルだと気づかない場合にかぎる。
シンボルだとわかってしまうと、
感動が引っこんで知的好奇心へと変わり、
シンボルの力は失われて無意味同然になる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年09月07日
シンボルの効果
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
シンボルには強力な効果があり、
おそらく多くの人の想像以上だろうが、
そらは意識を迂回して無意識に滑りこませる場合にかぎる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年09月05日
詩的な作品にする最初の一歩
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
良質のストーリーを詩的な作品に仕上げる最初の第一歩は、
現実の90パーセントを排除することだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年09月04日
第一級の映画
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
よいストーリーが巧みに語られ、
巧みに監督されて演じられると、
おそらくよい映画になるだろう。
それらすべてに
詩的表現の豊かさと深みが加われば、
第一級の映画になる。
』
- Permalink
- by
- at 00:36
2022年08月31日
すぐれたト書き
2022年08月30日
スクリーンとストーリー
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
スクリーン上では、
ただ存在している状態のものは何もない。
ストーリーのなかの人生は、
変化や成長の流れが果てしなくつづく。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年08月29日
名詞と動詞
2022年08月24日
生活と映画
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
日々生活を送っているとき、
われわれの意識はたいがい内へ向き、
外の世界へ目や耳を向けることは少ない。
一方、映画は数時間にわたって
休むことなく輝きつづける。
』
- Permalink
- by
- at 00:15
2022年08月18日
我々の共通点
2022年08月17日
自分を理解すると他人が理解できる
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
謎に満ちたみずかの人間性を突きつめて、
自分を理解できるようになればなるほど、
他人のこともさらに深く理解することができる。
』
- Permalink
- by
- at 00:41
2022年08月15日
大阪城公園とウクライナのアゾフスタリ製鉄所
大阪城公園には、ウクライナのアゾフスタリ製鉄所を思わせる戦争の話があります。
今の公園の東側には、77年前、大阪砲兵工廠(当時アジア最大規模の軍需工場)が建っていました。
戦時中、軍需工場だから、焼夷弾ではなく爆弾が集中的に落とされ、沢山の方が亡くなられています。京橋駅も爆撃され、この工場への通勤者が数多く亡くなられました。
その後、公園が整備されたあとでも、真っ黒に焼けただれた工場の壁が点々と公園沿いに残っていました。
私が小学生の頃、この壁を見て、
「火事で焼けたみたいだけれど、こんなに長い長い壁が焼ける火事ってあるのか?」
と疑問に思っておりましたが、これが戦争の爪痕なのでした。
今は、大阪城があって、公園があって、普通の都会で、外国から来られた方には、何の変哲もない場所ですが、
77年前はアゾフスタリ製鉄所みたいな状況だったのです。
だからウクライナから日本に来られた方には、大阪城公園を見て、いずれ祖国もこんな風に復興できるんだという
希望を持って頂ければよいと思います。
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年08月13日
実生活を脚本にしないこと
2022年08月12日
冷静に愛する
2022年08月11日
反社会人間は人を強く引きつける
2022年08月10日
創造した登場人物を愛する
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
わたしにはどうしても理解できない。
自分が作った登場人物を
なぜきらうことができるのか。
登場人物は自分の子供だ。
生んだ子をどうして憎めるのか。
自分が世に送り出した者たち全員を大切にしよう。
』
- Permalink
- by
- at 00:23
2022年08月09日
性格描写
2022年08月07日
主人公以外の人物が登場する理由
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
主人公以外の人物が
ストーリーに登場するのは、
主人公との関係を築いて、
複雑な内面を持つ主人公の矛盾を
際立たせるためにほかならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:16
2022年08月02日
脇役
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
脇役は、
主人公の複雑な人物像を、
信頼できる一貫したものへと
仕上げる存在でなくではならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年07月30日
性格の三次元
2022年07月19日
メロドラマ的なこと
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
人間がみずからおこなうことで
メロドラマ的なものなど何もないし、
人間はどんなことでも成しうる。
』
- Permalink
- by
- at 00:18
2022年07月18日
ストーリーテラーの仕事
2022年07月17日
シェイクスピアにカメラがあれば
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
シェイクスピアの作品は
時空を超えて驚くほど流麗だが、
カメラがあればさらに想像力を
発揮できたかもしれない。
』
- Permalink
- by
- at 00:10
2022年07月13日
コメディの脚本家がこの世にいなければ
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
コメディの脚本家に
神の恵みがあらんことを。
彼らがいなかったら、
人生はどんなものになってしまうことか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年07月12日
芸術家が誕生するのは
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
世界が完璧であれと願っているのに、
周囲を見まわすと、
強欲と腐敗と愚行だらけだ。
その結果、
怒りをかかえて鬱屈として芸術家が誕生する。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年07月04日
機械仕掛けの神(デウス・エクス・マキナ)
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
クライマックスの転換に偶然を利用してはいけない。
「デウス・エクス・マキナ」を登場させるのは、
脚本家の最大の罪である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年07月03日
偶然の使い方
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
ストーリーの半ばを過ぎたら
偶然を使わないほうがいい。
それよりも登場人物の力で
ストーリーを進めることだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年07月02日
悪
2022年06月29日
ストーリーは意味を作り出す
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
ストーリーは意味を作り出す。
そのため、
偶然はストーリーの敵に見えるかもしれない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年06月28日
安っぽい驚き
2022年06月26日
偽物のミステリー
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
偽物のミステリーとは、
事実を不自然に隠すことで生まれる
見せかけの好奇心である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年06月25日
良質な映画を二度観ると
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
良質な映画を二度観ると、
最初のときよりも楽しめる、
少なくともちがった角度から楽しめる
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年06月24日
殺人ミステリーはエンターテインメント
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
殺人ミステリーはボードゲームにも似て、
頭を使って楽しむエンターテインメントである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年06月23日
ストーリーに結びつける三つの方法
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
好奇心や賛意は
観客をストーリーに結びつけるが、
それには三つの方法がある。
ミステリー
サスペンス、
劇的アイロニーだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年06月21日
マイナスとプラス
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
人間はマイナスと見なすものに
本能的に嫌悪感をいだき、
プラスのものに強く引きつけられる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年06月20日
シーン転換方法
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
シーンを転換する方法は
ふたつにひとつしかない。
アクションを起こすか、
新事実を明らかにするかだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年06月19日
本当の秘密
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
人にはかならずほんとうの秘密がある。
口にした秘密の裏に、言えない秘密が隠れている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年06月18日
極限を描く
2022年06月15日
自殺は生きる勇気がないから
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
自殺には政治犯のハンガーストライキのように
勇敢と言えるものもあるが、
ほとんどの場合は
極限の状況に置かれての行動であり、
一見勇敢に思えるものの、
実は生きる勇気がないからであることがほとんどだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年06月14日
自ら奴隷になることは
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
奴隷は自由意志を持っていて、
全力を尽くして逃げようとするものだが、
ドラッグやアルコールで意志の力を鈍らせて
みずから奴隷になるのは、
それよりはるかに悪い。
』
- Permalink
- by
- at 00:31
2022年06月13日
法律
2022年06月11日
地獄の苦しみ
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
地獄が存在するかどうかはさておき、
この世界にもいっそ死んだほうがましだと思うような
地獄の苦しみは存在する。
』
- Permalink
- by
- at 00:09
2022年06月10日
不法の最たるもの
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
不法の最たるものは
ただの犯罪ではなく、
政府が国民に対して犯す
「合法的な」犯罪である。
』
- Permalink
- by
- at 00:47
2022年06月08日
9x9
これからの世界は9と9である。
人間の希望:ベートーヴェン交響曲第9番
人類の希望:日本国憲法第9条
The future world is set to 9x9.Man's hope 9
Beethoven symphony No. 9thHuman beings' hope 9
Article 9 of Constitution of Japan
- Permalink
- by
- at 00:25
2022年06月07日
人生は二分に留まらない
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
人生は微妙かつ複雑で、
イエスかノーか、
善か悪か、
正か誤かの二分にとどまることはめったにない。
マイナスにはさまざまな度合がある。
』
- Permalink
- by
- at 00:30
2022年06月06日
観客へ与えるもの
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
一流の脚本家は、
観客に約束した感情体験をさせる
・・・
と同時に、
意表を突く形で深い洞察を与える。
』
- Permalink
- by
- at 00:28
2022年06月05日
本物の脚本家とアマチュアの違い
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
脚本家は観客に約束どおり体験を、
予想と違う形で届けてくれるのだ。
そこが本物の脚本家とアマチュアのちがいだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:25
2022年06月03日
結末を成功させる鍵
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
-ウイリアム・ゴールドマン-
どんなストーリーでも、
結末を成功させる鍵は、
観客が望むものを予想しない形で
与えることにある。
』
- Permalink
- by
- at 00:19
2022年05月31日
意味が感情を生み出す
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
変化を引き起こすアクションは、
純粋で明快で、
説明を要しないものでなくてはならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年05月27日
アイロニーの展開
2022年05月26日
人間は矛盾した存在
2022年05月25日
人間性を守る
2022年05月24日
生のリズムに合わせて展開
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
アークプロットであれ、
ミニプロットであれ、
アンチプロットであれ、
すぐれた作品はどれも
人生のリズムに合わせて展開する。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年05月14日
何も変わらないなら
2022年05月13日
仮面をつける
2022年05月12日
秩序をもたらすの裏
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
「秩序をもたらす」
の裏には
「あらゆるものを奴隷化する」
という含みがある。
』
There is an implication of "enslaving all things" in the reverse side of "bringing about order."
- Permalink
- by
- at 00:32
2022年05月10日
錯乱すると
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
錯乱すると、
人は内面での対話力を失い、
思考や感情をすべて口にしたり
実行したりするので、支離滅裂になる。
』
- Permalink
- by
- at 00:27
2022年05月06日
アクションとリアクション
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
登場人物の発言や行動の裏にある真の思考や感情を、
生きた仮面の下に隠さなければいけない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年05月05日
シーンの内部構造
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
的確に問いかければ、
欠陥に気づかずに読み流していたシーンが
超スローモーションに分割されて、
はっきりと姿を見せ、
その秘密が明らかになる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年05月04日
ジレンマの原則
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
善悪や正誤のどちらかを選ぶのではなく、
同等の重みと価値を持つ
プラスまたはマイナスの要求の
一方を選ぶ形にする必要がある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年04月30日
狂気か苦痛か
2022年04月29日
選択を描くこと
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
真のジレンマに陥ったときに
どんな選択をするかを描けば、
その人物の人間性と
住む世界を力強く表現できる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年04月28日
真の選択とは
2022年04月26日
人間の選択
2022年04月24日
説明ばかり
2022年04月23日
感情というものは
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
感情というものは、
比較的短期の精神体験であり、
頂点に達して燃えあがり、
すぐに燃えつきる、
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年04月22日
ストーリーの転換点
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
ストーリーの転換点は、
観客に深い理解を促すだけでなく、
感情を揺さぶる力も生み出す。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年04月20日
独創に富んだアイディアを閃くには
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
伏線を張って落ちをつけ、
また伏線を張って落ちをつけることを繰り返していると、
独創に富んだアイディアがひらめくことがある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年04月19日
転換点
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
明白なことを
もったいぶって描いたり、
異常なことを
あまりにさりげなく描いたりすると、
転換点はうまく機能しない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年04月18日
第二の意味
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
初見ではひとつの意味しかないように思わせて、
あとで一気に振り返ったとき、
より重要な第二の意味が
感じられるようにしなくてはならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年04月17日
大概の関心
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
サリヴァンも含めた映画作家たちは、
実際に苦しんでいる貧しい人々より、
絵になる貧しい人々のほうに
たいがい関心がある
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年04月10日
伏線と落ち
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
伏線とは
知識の深層へ埋めこむことであり、
落ちとは
その知識を観客に与えてギャップを消すことだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年04月09日
力のあるストーリーは
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
どれほど明快で洗練された美文も、
観客の人生経験と脚本家が巧みに構成した世界が
めぐり会ったときに心を満たされる洞察の深遠さには、
とうてい及ばないということだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年04月07日
金切り声
2022年04月05日
有事に備えて、平時に余剰を持つ
有事に備えて、平時に余剰を持つ。
が、正しいリスクヘッジだよ!
アリが働かない余剰のアリを持っているのも、
万年単位の過酷な自然に耐えるため。
維新はアリ以下の思考!
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年04月03日
ウクライナ悲劇の先に向かうところ
ウクライナ悲劇の先に、国際社会が向かうのは
戦争放棄だろう。
驚くなかれ、日本はすでに日本国憲法9条がある。
Probably, it is renunciation of war that international society goes after the Ukraine tragedy. It wants without being surprised. Japan already has Article 9 of the Constitution of Japan.
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年03月24日
それが政治
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
あらゆる種類の平等論を駆使して、
格差をなくそうと試みても、
人間社会は頑なに、
そして本質的に権力のピラミッド型の構造を崩さない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年03月23日
組織化した権力=政治
2022年03月21日
ストーリーの本質
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
ストーリーの本質は、
ある人がアクションを起こして、
そのつぎに起こると思っていることと、
実際に起こることのあいだに生じるギャップ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年03月20日
ストーリーの本質は言葉ではない
2022年03月11日
創作の精神
2022年03月10日
表層を突き破れ
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
・・・ジャン・コクトー・・・
創作の精神は
矛盾の精神であり、
表層を突き破って
未知の現実をめざすことだ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年03月09日
道化師政治家のパラドックス
作家 クリスチャン・サルモンさんの言葉から
『
支持者らは、
道化師政治家を「真実を語る」などと
称賛します。
でも「政治家は信頼できない」
という政治家が信頼を得るのは、
大いなる逆説ですね
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年03月08日
道化師政治家のやり方
2022年03月07日
道化師の政治家が成功している
作家 クリスチャン・サルモンさんの言葉から
『
世の中のインテリやリベラルは、
あんな道化師のどこがいいのかと批判しますが、
全然わかっていない。
道化師であることこそが、
今や政治家の成功の秘訣となったのですから
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年03月04日
人間の二面
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
人間にはふたつの面があり、
日に日にどちらへ変わるかすらわからない。
ノートルダム大聖堂を建てるのも人間なら、
アウシュビッツ収容所を建てるのも人間だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月28日
権力者は市民が感情を持つのを恐れる
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
権威のある人間は、
思想ではなく、
感情から生まれる脅威を恐れる。
権力者たちは
市民が感情を持つことを望んでいない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月26日
すべての人間が発言する自由
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
すべての人間が発言する自由を得られれば、
そこに無分別で急進的な考えや
極右的な考えがあったとしても、
人間はさまざまなものを振り分けて
正しい選択をするものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月25日
悪を出し抜いたとき
2022年02月23日
あらゆる世代が人間らしくあるために
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
時を超えて、
古典の名作が与えてくれるのは、
解決策ではなく洞察力であり、
答えではなく詩的感性である。
古典は、
あらゆる世代が人間らしくあるために
解決すべき問題を明らかにする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月20日
異なる視点から見る
2022年02月19日
批評と芸術を取り違えてはならない
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
知的分析は、
どれほど刺激的なものであっても、
魂の保養にはつながらない。
』
However stimulative intellectual analysis may be, it does not lead to spiritual recreation.
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月18日
芸術は瞬間に意味を持つ
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
人生において、
経験が意味を持つのは、
後日振り返ったときである。
芸術では、
経験した瞬間に意味を持つ。
』
Art has a meaning at the moment of experiencing.
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月17日
芸術の導きがなければ
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
芸術の導きがなければ、
人は混乱と混沌のなかで生きていくしかないが、
美的感情は
知識と感覚を調和させ、
現実世界での居場所を確実に意識させる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月16日
感情に観念がともなうと
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
感情の変化に観念がともなうと、
いっそう力強く、
いっそう深く、
いっそう忘れがたいものになる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月15日
美的感情
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
人生が感情から意味を切り離すものであるのに対して、
芸術はそのふたつを結びつける。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月13日
物語の構成と登場人物の実像
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
プロットは性格描写より重要だが、
物語の構成と登場人物の実像は、
ひとつの現象を異なる視点から見ているにすぎない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月12日
時間芸術の第一戒律
2022年02月11日
ストーリーは資質の組み合わせ
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
どの人物も、
そういった行動をとるのが
自然だと観客に感じだせるような
資質の組み合わせを
ストーリーにもたらさなくてはならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月10日
主要人物を描くときは
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
主要人物を描くときは、
性格描写と比較もしくは対立させて、
奥深い実像を描くのが基本である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月07日
歴史ドラマは現代を映す鏡
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
歴史ドラマは
過去を磨きあげて現代を映す鏡とし、
悲惨な問題をわかりやすく鑑賞に堪えうる作品とする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月05日
天才脚本家とは
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
天才とは、
力強いシーンやビートを作り出す力だけではなく、
陳腐なもの、
こじつけたもの、
調子はずれのもの、
偽りのもの
を排除できる審美眼と
判断力と
強い意志を
持つ人間だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年02月03日
意味のあるクライマックスへ
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
ストーリーとは、
単に集められた情報をつなぎ合わせたものではなく、
数々の出来事をうまく設計して意味のあるクライマックスへと
観客を導くものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月31日
書けなくなるのは
2022年01月30日
想像がもたらすもの
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
記憶は人生の一部を塊として見せてくれるが、
想像がもたらすものは、
一見無関係に思える人生の断片や、
夢のかけらや、
経験の切れ端だ。
それらの隠された関係を見つけ出し、
ひとつのものにまとめていく。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月28日
広大に見えても小さなもの
2022年01月27日
制約は不可欠
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
制約は不可欠なものだ。
すぐれたストーリーを書くための最初のステップは、
小さくて理解可能な世界を作り出すことからはじまる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月26日
架空の世界の法則
2022年01月25日
架空の制約
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
設定が架空のものだとしても、
思いつく限りのことを書きこめるわけではない。
たとえ空想の世界であっても、
そのなかで起こりそうなこと、
起こりうることはかぎられている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月24日
ストーリーの設定を決めるもの
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
ストーリーの設定を決めるものは、
時代、:ストーリーの時間的位置
期間、:ストーリーのなかで経過する時間の長さ
舞台、:ストーリーの空間における位置
葛藤レベル:人生のどの階層にストーリーを設定するか
という四つの要素である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月23日
独創ストーリーの基礎
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
自分のストーリーの世界を知って、
深く考えをめぐらすことこそ、
独創性に富んだ優れたストーリーを
書くための基礎である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月22日
自分の真実ものを書くべき
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
相違のための相違を求めるのは、
商業主義に黙従するのと同じくらいむなしい。
自分の信じるものだけを書くべきだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月21日
虚構が大き過ぎると
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
ストーリーの虚構の度合が大きすぎると、
観客は退屈したり無意味に感じたり、
感情移入できずに背を向けてしまう。
これは所得や経歴にかかわらず、
知的で感情豊かな人すべてにあてはまる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月18日
ストーリーを左右する出来事
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
「ストーリーを左右する出来事」は、
登場人物の人生に意味ある変化をもたらす。
その変化は「価値要素」として表現され、体験され、
対立や葛藤を通じてもたらされる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月15日
ストーリーとは
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
ストーリーは
人生に似たものであるべきだが、
現実をそのままなぞるだけでは、
何の深みも意味もなく、
だれにとっても
ありきたりのことでしかない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月13日
独自性への愛
2022年01月12日
ユーモアへの愛
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
ユーモアへの愛 -
人生の均衡を取りもどしてくれる
すばらしいユーモアを楽しむこと。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月11日
人間性への愛
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
人間性への愛 -
苦しむ人々に強く共感し、
人々の肌の下にもぐりこんで、
その目を通して世界を見たいという意志。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月10日
上質のストーリー
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
上質のストーリーとは、
世界じゅうが耳を傾けたいと思うような、
語るに足りるものを言う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月09日
芸術の型
2022年01月07日
ストーリーを作るには
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
ストーリーを作るには、
生き生きとした想像力と力強い分析的思考が必要だ。
自己表現は重要ではない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月06日
求めるのはストーリー
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
われわれが世界のために作り出すもの、
世界がわれわれに求めるものはストーリーだ。
それはいまもこれからも変わらない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月05日
成熟と賢明
ロバート・マッキー 署 「ストーリー -物語の基本と原則-」から
『
成熟した芸術家は
けっして自分に注目を集めようとはしないし、
賢明な芸術家は
固定観念を破るためだけに
何かをすることはない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月04日
アートは100年
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
美を持たない種族より、
美を持っている種族のほうが
より適応的なのかもしれません。
アートは明日生きるために
必要でないかもしれないけれど、
100年後も200年後にも
生きのびるためには必要なものなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2022年01月03日
美しい振る舞い
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
がめつくないとか、
自分の欲を節制できるとか、
品よく振る舞えるとか、
正しい・正しくないという表現よりも、
美しい振る舞い・醜い振る舞いというふうに表現する。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月30日
欧米だけがスタンダードか?
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
あまりにも私たちは
毒気を抜かれてしまっていて、
いつの間にか欧米に合わせないと
売れないと思ってしまっている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月29日
批評家
2021年12月27日
ミュージアムの公共性
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
ミュージアムの公共性を考えるのであれば、
教育・普及などの地道な活動が
きちんとできるようになるのがいいですね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月23日
多様な視点からの解釈
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
コレクションを調査したり展示したりするときは、
多様な視点からの解釈を妨げず、
むしろそこからさまざまなことを考える
きっかけとなることが望ましい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月21日
なかったことにはできないもの
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
外には出しにくいけれど、
なかったことにはできない
そういったものも、
ミュージアムは所蔵しておく役割があるんですね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月20日
大阪市リバティおおさか
2021年12月19日
重要の価値基準は更新される
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
これが重要だ、そうではない、
という価値基準は、
時代の移り変わりを経て
更新されることもあります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月18日
日本の豊かな文化とは
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
日本の豊かな文化というのは、
一見ムダにみえるものを
どれだけ活かせるか、
ではないかと思うのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月17日
断捨離では残らない
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
断捨離という考え方を基にして
モノを処分していってしまうと、
明日、明後日ぐらいまでに
必要なものしか残らないんですよね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月14日
見えないところをカットすると
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
目に見えるわかりやすいものばかりにしかコストをかけず、
見えないところをカットすると、
脳が縮小するように、
国や人類全体も衰退していってしまうのではないでしょうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月13日
文化的先進国の証
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
見えにくいけれど
必要なコストにきちんとお金を配分できることこそ、
文化的な先進国であることの証なのですけどね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月11日
文化は国家百年の計で考える
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
もちろん利潤の追求は大切。
ただ、公的なものを仕切る存在として大臣職にある方は、
国家百年の計という視点から
文化と学芸員の意義を捉えてほしかった
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月09日
マインド・パレス(記憶の宮殿)
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
マインド・パレス(記憶の宮殿)といって、
記憶を場所として理解することで記憶を強化し、
さらに新しい発見や楽しみを味わう、
という方法があります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月08日
記憶を活かせるのは人間だけ
2021年12月07日
過去に酷いことをした事を忘れないために
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
なかったことにできるのは、
もしかしたら日本人が得意な分野
かもしれないですが、
それを忘れないという国もある。
ミュージアムは、
過去にひどいことをしてしまった
ということを忘れないための場所でもあります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月06日
記録・記憶を残す
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
人間は、
ある出来事をなかったことに
してしまうこともできます。
しかし、記録、記憶が残っていれば、
それに照らし合わせて、
大切なことを知ることができるわけですね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年12月04日
ミュージアムの使命
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
コレクション・文化遺産を保存しておくこと、
調べること、
それを人々に向けて伝えることこそが使命です。
』
- Permalink
- by
- at 22:18
2021年12月03日
コレクション
2021年12月02日
ミュージアムの役割
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
残すためには努力が必要だし、
残っているものはとても大事なのです。
そして、そういうものを残しておく場が
「ミュージアム」なのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月27日
絶対美感
2021年11月26日
コレクターの原点
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
コレクターは自分の好きなもの、
自分の存在を示すものを集めるわけで、
自分の好きなものに囲まれたいということが
まず、原点だと思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月25日
社会の脳
2021年11月24日
ミュージアム
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
人間の文化の、
そのえげつないまでの「意識」の集合体として、
ミュージアムは
「過去」という名のコレクションを溜めこんでいる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月23日
万博の本来の意味
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
経済的な成功を得られているとはいえ、
万博の本来の意味を考えると、
世界の叡智が終結し、
新しい技術が集まり、
新たな未来像が映し出されることが
より重要ですね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月22日
万博
中野信子、熊澤弘 著 「脳から見るミュージアム」から
『
人々への教育を目的とし、
現代文明の進歩や将来像を示す催しとして
スタートしたのが「万博」です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月21日
美を感じるのは必要不可欠
2021年11月20日
本当のリスクが見えていない
テレビドラマ「ドクターX 外科医 大門未知子 シーズン7 ope.5」から
『
本当のリスクが見えていないんじゃないの。
あんたも医者なら分かるでしょ!
患者に取って一番危険なのは、
いざとなると逃げ出す医者なの。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月19日
暴挙
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
- 松宮孝明 立命館大学教授 -
あのヒトラーでさえ、
全権掌握するには特別の法を必要としたが、
総理は現行憲法を読み替えてこのような暴挙に出た。
独裁者にでもなるつもりか
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月18日
今や日本の官僚は
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
いまや官僚たちは
一部の権力者の奉仕者として、
その能力を存分に発揮している。
学業成績出世レースに明け暮れ、
良心をどこかに捨ててきたのだろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月17日
すべての目的は自らの権力維持で、あとは空っぽ
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
教養も政治理念も国益のための戦略も持たず、
批判に背を向け、
専門家の知見を軽視し、
都合よく法令解釈を変更し、
人事権で相手を脅して従わせる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月16日
戦わなければ進歩はない
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
どんな組織に属していても、
葛藤を抱えながら組織のなかでぶつかり、
ときに戦わなければ進歩はない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月15日
複雑怪奇な「リアルな世界」を
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
日本のテレビドキュメンタリーの多くが、
複雑怪奇な「リアルな世界」を
単純な図式に押し込むことで、
わかりやすい「バーチャルな世界」に
変換していないだろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月14日
無為無策の産物
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
新型コロナという未知のウイルスは、
この国の政治や社会、
人間の本質をあぶり出した。
脆弱な医療提供体制。
進まない検査。
遅れるワクチン接種。
欠陥だらけの接触確認アプリ。
一年半に及ぶ無為無策の産物は
挙げればきりがない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月13日
首相という大根役者
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
官邸側に事前通告してうえで記者が筆門。
首相はプロンプターに映し出された想定問答を見ながら
大根役者顔負けの答弁に始終する。
』
- Permalink
- by
- at 22:16
2021年11月12日
異常が正常へと変質する
2021年11月11日
見られることで
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
記者も見られている感覚があったほうが、
絶対にいい。
見られることで
自分を社会的に対象化するところから、
空気を打ち破る記者が出てこないと、
権力にもたたかれるメディアの空気は
かわらないですからね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月10日
政治の惨状を打ち返す
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
政治の惨状はたしかに喜劇的でもあり、
悲劇的でもあり、
これを素材として見ごたえのある表現をつくり上げて
打ち返してやる気概が必要ですよね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月09日
安倍氏は裸の王様
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
「裸の王様」ということで言うと、
安倍氏ほどの「裸の王様」はいないかと思います。
辞めてから五輪反対者を「反日」と指摘したり、
安倍氏本来が持つネトウヨ的な性格を前面に出して
ツイッターなどで発信するようになりましたね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月08日
飼い慣らされれば
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
飼い慣らされていることを
受け入れてしまっているのでは、
権力のチェックもできないし、
ましてスクープなんて放てるはずがない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月06日
ははぁ
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
大半のメディアの人間というのは、
相手が権力者となった途端に、
「ははぁ」とひれ伏す感じになる。
その感覚が私には気持ち悪いんですね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月04日
日本はムラ社会
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
コロナによって日本社会は
「ムラ社会」
だということが改めて明らかになったということであります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月03日
吉本ヨイショ
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
吉本の影響力が大きいから、
吉本と仲がいい橋下氏なり吉村洋文知事を
どんどんヨイショするような構成になってしまう。
それに対して
まったくチェックが利かずに
維新の政治家の露出度だけがどんどん増えて、
いつのまにか
「一番信頼できる知事」
という評価を受けたりするわけじゃないですか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年11月02日
記者は嫌われて喧嘩するごらいでないとダメ
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
政治家も官僚も、
良くも悪くもずる賢いところがあり、
記者という立場では、
嫌われて喧嘩するくらいで
ちょうどいいかというのが
私の感覚です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月31日
自分の考えが出せないのは悪い冗談
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
普段、報道の自由だ、表現の自由だと主張している人たちが、
自分の考えは表現しない、できないなんて。
悪い冗談ですよ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月30日
権力へは考えを述べるべき
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
政府だろうが、知事だろうが、企業だろうが、
権力のふるまいに疑問を感じたときに、
一個人として
「それはおかしい」「こうあるべきではないか」
と考えを述べることに何の問題があるのでしょうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月29日
不満のはけ口は弱者に向かう
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
日本のコロナ禍で
混沌とした政治・社会・経済状況のなかで、
人々の不満や鬱積した怒りが、
立場の弱い外国籍の方々に向かっている、
ある種、不満のはけ口にされてしまっている
ようにも感じます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月28日
安倍前政権下から排外主義者が闊歩した
2021年10月27日
デジタル庁を危惧する
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
いまや日本の行政は隠蔽が当たり前で、
そのうえ改竄や破棄まで横行しているわけですから、
デジタル庁が国民のほうではなく、
政権のほうばかりに向くのだろうという
危惧は当然だと思ういいます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月26日
デジタル庁は怖いところ
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
首相直轄という部分も
非常に怖いところだと思います。
歯止めや罰則がないまま、
デジタル庁に集まる膨大な市民の個人情報が、
時の権力者の意のままに使われかねない
可能性を含んでいますから。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月25日
国の中枢がコメディ
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
国家を揺るがす緊急事態に、
この国の中枢で起きている出来事は
まったく笑えないコメディであり、
もはや「悪夢」としか言いようがないからです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月24日
メディア不信の根源
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
高まるメディア不信の根源は、
組織に守られた記者たちが
安全地帯ばかりで取材している
ことにあると思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月23日
メディアの責任
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
市民の無関心は
さらなる腐敗を生み、
取り返しのつかないところに
行きつくかもしれません。
だからこそ、
メディアの責任は重いのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月22日
隠蔽を恥じない政権
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
平然とした隠蔽、
また国民やメディアからの批判や
問をスルーして恥じない態度は、
いまや日本中に蔓延しています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月21日
おかしいと思ったら、声を上げる
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
おかしいと思ったら、
そのときその瞬間に
みんなで声を上げていくこと、
これが私たちが未来の子どもや孫たちのために
やっていくべきことではないかと思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月20日
菅氏の夢、国民の悪夢
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
菅氏の強調する「自助」というのは、
竹中氏の考えにとても近いものがあるように見えます。
規制緩和という名の下での
新たなビジネスや利権の立ち上げ、
そこから自分の権力を伸ばしていくという手法ですね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月19日
デジタル監視国家
2021年10月18日
弱肉強食加速社会
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
「自助です。そして共助です。最後に公助。そして絆」
これは新自由主義的な価値観そのものです。
グローバリズム的価値観の下で、
目指すは「弱肉強食加速社会」
という流れではないでしょうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月17日
安倍氏は痴呆にならない。だって執着心があるから
望月衣塑子、五百旗頭幸男 著 「自壊するメディア」から
『
安倍氏はあのように明るく見えますが、
自分をバカにされた恨みは絶対忘れないという
執着気質の人らしいのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月16日
絶望と隣り合わせのささやかな希望
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
世界は、
希望に満ちた美しい物にあふれています。
今後はいままで以上に、
絶望と隣り合わせのささやかな希望が
私たちの人生に生きる価値を与えてくれるでしょう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月15日
私たちに必要なのはセレブの話ではなく
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
私たちに必要なのは、
ひどい苦しみのなかで
どう生きるかを知っている人たちです。
彼らから、
私たちいま取るべき行動を学べます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月09日
痛ましい動物
2021年10月08日
無知と未知
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
人間はある分野には
精通しているかもしれませんが、
同時に多くの無知と未知の領域に四苦八苦しています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月05日
社会に還元すべきとき
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
私たちは
旅行やショッピングを忘れなければなりません。
誰もが自身の能力を最大限に生かして、
社会に還元すべきです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月04日
今こそ政治を考える
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
かつての世界は消えようとしているのですから、
いまこそ政治について考えるべきときです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月03日
コロナ危機はリハーサル
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
コロナ危機は、
人類を待ち受けている
地球温暖化や新たな感染症といった
将来の課題に向けてのリハーサルだ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年10月02日
自宅待機
2021年09月30日
リアリティとリアル
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
私たちが住む社会的・物質的空間である
「リアリティ」と、
目に見えないがゆえに全部見える空間
「リアル」を
分けて考えるべきだ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月29日
以前の日常はもう戻らない
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
以前の日常はもう戻らない。
「新しい日常」は
私たちのこれまでの暮らしの残骸の上に
つくらなけらばならないだろう
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月27日
ひもじい苦しみは
菊池寛 訳 「小公女」から
『
私、ひもじい苦しみは
身に沁みて味っているでしょう。
ひもじい時には、何かつもりになったって、
ひもじさを忘れることは出来ないのよ。
』
今読むべき本は「小公女」かもしれない。
理不尽な扱いに毅然と生きていくセーラ。
菊池の訳は、今ほどマイルドでないのもよい。
そして、セーラはダイアモンド・プリンセスだよ。
「小公女」は次の青空文庫から読めます。
https://www.aozora.gr.jp/cards/001045/card4881.html
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月26日
人間の活動
2021年09月21日
知識人の不幸の原因
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
彼らは俗物がその実権を握っている
金融組織に自分自身を売り払い、
そしてこの組織が彼らに迫って否応なしに
有害なナンセンスにすぎないものと
みずから考えているところのものを
書かせているのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月20日
コロナのある世界
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
何より問題なのは
現在の日常が「偽物」であることです。
基本的な状況判断が欠如しれいる
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月18日
狭い世界を壊す
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
市民社会を刷新して、
活性化させていくのです。
自分たちだけの狭い世界を壊して、
ともに民主主義を実践していくのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月17日
ウィルスに痛めつけられた人たち
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
ウィルスが広まっていくにつれ、
最も多くの負担を強いられている人たち、
より大きな犠牲を払っている人たち、
最も多くの人命を失っている人たち
というのは、
過去40年間の経済発展のなかで
置いてきぼりにされた人たちだったことが、
だんだん明らかになっていきました。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月16日
トランプ政権が出現したわけ
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
見下された人びとの不満と怒りから
世界各地でポピュリズムの抗議運動が起き、
それがトランプ政権を出現させた
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月13日
エル・バイス
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
「エル・バイス」のソーシャルネットワークを構築する。
つまり、ソーシャルネットワークのすべての利点を備えつつ、
プロのジャーナリストが管理している、
というものにするのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月12日
持続可能な未来
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
パンデミック後の新しい社会のあり方を見出すには、
学際的な研究が必要です。
それがより持続可能な未来に繋がるはずです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月11日
生き延びるために自由が制限された
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
自由よりも、
命や生き延びることに価値が置かれています。
今ほど私たちの自由が制限されたことはありません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月10日
法の支配とは
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
私たちは、
民主主義が命すらも差し置いて
自由を優先することに価値を認めています。
「法の支配」は、
虐げられて生きるくらいなら
死んだほうがましだと考えた英雄たちが
起こした革命によって確立されました。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月09日
政治的なまやかし
2021年09月08日
ウィルス
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
もしかつての日常に戻れば、
新たな感染の波を見ることになるでしょう。
そしてウィルスは、
私たちが持続可能な
ビジネスのやり方を見つけない限り、
そこにいつづけます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月07日
ロックダウン・ストップ
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
現在、
私たちはやることが減ったというだけで、
より倫理的な生活を送っています。
これが、
妙なことにこの新たな状況を
心地よく感じている理由の一つです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月06日
グローバルな新自由主義
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
モラルに反した行動は、
世の中を悪くします。
グローバルな新自由主義は、
世界を猛スピードで破壊するものに
なってしまったのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月05日
他者の苦しみに責任がある
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
商品の生産チェーンのせいで、
多くの場合、
誰かが犠牲になっています。
私たちは皆、
他者の苦しみに責任があるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月04日
人びとの福祉は政治次第
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
経済成長も、
政治ではそれほどコントロールできません。
先進国でも途上国でも同じです。
ですが、人びとの福祉は政治次第なのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月03日
貧困問題で注目されるもの
「新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- 」から
『
貧困問題で、
一番注目すべきなのは
「経済成長」ではなく、
「貧しい人びとの収入や教育」です。
その改善に注力すべきです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年09月02日
すべての問題の解決は市場ではできない
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
すべての問題の解決を市場に任せることは
できないのです。
誰かを差別したいと思っている消費者がいれば、
それを利用する企業は必ず存在し、
差別が助長されることになります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年08月30日
付与と安心感
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
貧しい人びとに何かを与えても、
彼らは怠けません。
生産性が向上するという
安心感が与えられ、
福祉につながるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年08月28日
問題はビジネスのあり方ではない
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
問題は、
ビジネスのあり方ではありません。
そうではなく、
これまで各国が予算を削減しようとして、
コロナ危機のような事態に
備えていなかったことです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年08月26日
一番注目すべきなのは
2021年08月25日
格差が問題解決を妨げる
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
庶民階級や中産階級に努力を求めるなら、
まずは富裕層が最低でも
同程度の努力をしている証拠を
示さねばなりません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年08月24日
ビリオネアは経済成長を助けない
2021年08月22日
勝者総取りの世界
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
クリエイティブ産業や文化産業にも
似た構造があります。
これらの産業は、
お金持ちのスターがごく少数いて、
そうしたスターをめざす貧しい人たちが多数いる、
勝者総取りの世界です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年08月18日
人間性を育むもの
2021年08月17日
技術の主人にして所有者
2021年08月12日
戦争は夢を打ち砕くから
俳優 宝田明 さんの言葉から
『
人間誰しもが
等しく持つことができるのは、
その人なりの夢だ。
戦争は、
その夢を無残に打ち砕いてしまうもの。
平和を、憲法を守っていただきたい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年08月11日
心掛けるもの
2021年08月08日
人は幸福になるために何をすればよいか
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
●人とともに生きること、
●信頼できる友人を持つこと、
●ほかの人との競争を
できるだけ敵意のないものにすること
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年08月07日
中国の政治も注視する
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
中国の政治も注視していくべきです。
なぜなら経済成長が原則すれば、
社会内の緊張が高まり、
政治の指導者がそれを抑えようとして
とんでもないことをする可能性が
あるからです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年08月06日
人類がぶつかっている問題
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
この200~50年ほど、
人類がぶつかっている問題は、
豊かさだけでは社会内の緊張を
緩和できないというものですが、
人類はその問題も
しっかり理解できていない
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年08月04日
イースタリンの逆説
2021年08月03日
将来の希望が持てなくなると
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
将来の希望が持てなくなると、
人は強い不満を覚え、
生きづらさを感じるようになり、
社会内の緊張が高まります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年08月02日
経済成長が幸福をもたらす
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
現代のような資本主義の世界では、
豊かさの絶対量ではなく、
暮らしが豊かになっていく過程が
幸福をもたらします。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月31日
人にとっての成功とは
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
人にとっての成功とは、
何か絶対的な基準があるわけではなく、
つねにほかの人と比較してのことなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月28日
使い捨てられていた人たち
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
パンデミックに見舞われる前から
ひどい状況に置かれていた人びとが、
さらに堪え難いほどの
苦しみを味わっているのです。
平時から
「使い捨てられる」立場にあった人たちが、
いま「犠牲」を払わされている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月25日
コロナ以前の日常に戻る必要はない
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
今の危機が示しているのは、
「コロナ以前の日常」に
戻る必要はないということです。
コロナ以前に戻したところで、
監視はますます強化され、
スクリーン画面はますます増え、
そして人と人との接触は希薄になるだけです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月24日
スクリーン・ニューディール
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
「スクリーン・ニューディール」
に資金を注ぎ込んでも、
生活の質を下げるようなやり方で
問題を解決することにしかなりません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月23日
公が主権をもつべき
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
私たちが真っ先にすべきなのは、
ソリューショニズムを乗り越えていく
道を描き出すことだ。
それは「公」がデジタル・プラットフォームに対して
主権を持つことにほかならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月22日
非民主主義に依存する民主主義
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
テクノロジー・プラットフォームという
非民主主義的な方法で権力を行使する民間企業に対し、
民主主義国家が極端なまでに依存している実態
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月21日
政治秩序の基盤としては貧弱
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
今のデジタル・プラットフォームは、
市場取引以外にも使えるとはいえ、
万人に開かれた
政治秩序の基盤としては貧弱だ。
消費者とスタートアップと企業家にしか
使い勝手がよくないのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月18日
政策の結果
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- から
『
スタートアップが未来のかたちを
決めているように見えるとしたら、
それは自然の理ではなく、
政策の結果に過ぎない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月17日
パンデミックが非民主主義的な慣習を持ち込む
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
今回のパンデミックがきっかけで
ソリューションニズムの国家が
強化されるのは間違いない。
政治の空白につけこみ、
「安心・安全」「イノベーション」
といったお題目とともに、
非民主主義的な慣習が持ち込まれるだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:20
2021年07月16日
巨大IT企業が社会と政治のインフラを支配
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
災禍にソリューショニズムで対応していけば、
公共の想像力はますます縮むことになるだろう。
「巨大IT企業が社会と政治のインフラを
支配していない世界」
を想像するのが、
よりいっそう難しくなるのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:18
2021年07月15日
ソリューショニズム
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
ソリューショニズムは、
ITがありとあらゆる分野で
破壊と改革を引き起こすのを是認するが、
現代の暮らしの中心にある市場という制度だけには
手をつけさせないのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:16
2021年07月14日
ネオリベラリズムが目指したもの
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
「競争」を増やし、「連帯」を減らす。
創造的破壊を増やし、
政府の計画を減らす。
市場依存を高め、福祉を減らす。
』
- Permalink
- by
- at 00:14
2021年07月13日
ネオリベラリズムは悪い警官役
2021年07月12日
ネオリベラリズム(新自由主義)の破綻
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
「民営化」と「規制緩和」を教義とする
「ネオリベラリズム(新自由主義)」の破綻は明らかだ。
病院が営利事業として運営された結果、
何が起きたのか。
緊縮財政で公共サービスを削減した結果、
何が起きたのか。
見ればわかるだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月11日
資本主義は終わらない
2021年07月10日
資本主義のドグマ
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
資本主義は、
数多くの問題を引き起こし、
それをお金儲けの
新しいチャンスへと変えてします。
それだけではない。
問題を引き起こすたびに、
資本主義の正当性は高まるのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月09日
パンデミックの先に待つのは
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
今後はもっと人間的な
経済システムが登場するだろうと、
希望的に語る論客も多い。
だが一方で、
パンデミックの先に待つのは
「テクノ全体主義的な監視国家」
という暗い未来だと、
警告する人も少なくない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月08日
感染症の予測
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
一つの感染症で
1000人以上の死者が出るような場合には、
予測は無意味です。
原因を根絶するしかないのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月06日
規模の変容
2021年07月05日
反脆弱性
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
極端なリスクには
パラノイア的に警戒し、
有益な小さなリスクは取るのです。
それなのに、
現代の官僚主義はその逆に誘導します。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年07月04日
大き過ぎるものは脆弱
2021年07月02日
国家が生き残るためには
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
国家が生き残るためには、
●まず専門家、
●公益に身を捧げる公正な人間、
●彼らに耳を傾け最終的に決定を下す指導者
が必要
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年06月30日
ポピュリスト国家がパンデミックに手間取る理由
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
これらの国はパンデミックを否認し、
支配者の人気を維持するために
パンデミックを矮小化しているからです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年06月29日
国家全体が崩壊するとき
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
市民による政治議論の質が低下し、
中立であるべき機関への信頼が下がると、
お互いに歩み寄って
国の統治に関するコンセンサスを築くことが
できなくなってしまいます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年06月28日
独裁制
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 --
『
独裁国家のほうが
物事を速く進められることは
わかっています。
しかし、
独裁制のもとで素早く下された決定が、
必ず良い決定になる方法は
まだ見つかっていません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年06月27日
民主主義であればこそ
2021年06月25日
これかの製品
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
技術者、
プロダクトマネージャー、
デザイナー
に、機能性だけではもはや不十分なのだと
何度も訴えました。
これからは製品に
感情を組み込まなければならないのだと
』
- Permalink
- by
- at 00:29
2021年06月24日
デザイナー思考を身につけるためには
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
心の変化や判断のプロセスをトレースすることによって、
自分の内部状態の変化に対する解像度を上げ、
他者を理解するためのメンタルモデルとして
自分の変化の事例を利用することができるはずだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年06月22日
人間とシステムのデザイン
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
身の回りにある
人間とシステムのギャップと、
それらのシステムをデザインするというのは、
人の心にはたらきかけて
行動を変えるための手がかりを作ることだ
』
- Permalink
- by
- at 00:21
2021年06月21日
ユーザーフレンドリーデザインの意味
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
「ユーザーフレンドリーデザイン」は
ユーザビリティ(有用性)より
はるかに大きなものを意味している
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年06月20日
デザイナーの役割
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
ユーザーがそのモノで驚き、
喜び、
そして時間をかけて
それと意義のある関係を築けるように
支援するのがデザイナーの役割なのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年06月18日
ツァイガルニク効果
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
未完成の作業のほうが
達成したものよりも
記憶に残りやすいとこが判明した。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月31日
世界を知らない世界観
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- ジャレド・ダイアモンド から
『
大事なのは、
国の統治に関わる人たちの世界観が
「世界を知ったうえで作り上げられたものであるべき」
ということです。
自分たちの思想傾向に
都合のいい世界観になっていてはいけません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月29日
アップルの正体
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
アップルのような企業は、
同じことしかできない箱を
次から次へと売るために
つくられたようなものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月28日
中国に残り続けたもの
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- エマニュエル・トッド から
『
フランスは中国に工場を移動させ、
中国はフランスにウィルスを移動させ、
マスクや医療品の生産は
中国に残り続けるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月26日
パンデミックが証明したこと
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- エマニュエル・トッド から
『
この国が倒れずにすんだのは、
トラック運転手、
スーパーのレジ係、
看護師、
医師、
教員
のおかげであり、
金融マンや法律を巧妙に操れる人の
おかげではなかったのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月25日
産業機構は安全保障
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- エマニュエル・トッド から
『
どんな体制の国でも、
産業機構がなければ、
自国の市民の安全を守れません。
それは
経済的自由主義の体制でも、
社会民主主義の体制でも
変わりません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月24日
デザインの障害とは
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
障害とは
ユーザーにとっての制約ではなく、
ユーザーと、
私たちがデザインした世界との不整合である
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月20日
デザインの現在の課題
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
現在の課題は、
自分ひとりでは達成できないより次元の高い目的を
一斉に目指しながらも
ひとりひとりの幸せも実現する、
というデザイン方法を見つけることだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月15日
モノつくりの魔法
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
ひとりの人がほかの誰かが欲しいモノをつくり、
お金と交換する。
するとみんなが、
より満ち足りた気分になれる。
それはまるで魔法のようだった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月14日
テクノロジー
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
結局のところ、
テクノロジーは私たちに
よりよいことをする力を与えてくれています
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月11日
保護から出た独裁
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- ユヴァル・ノア・ハラリ から
『
民主主義は、
市民の健康の保護という名の下に、
簡単に独裁に変わります。
この脅威は
取るに足らないものではありません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月10日
暴君の改革
新しい世界
-- 世界の賢人16人が語る未来 -- ユヴァル・ノア・ハラリ から
『
民主主義の世の中に、
暴君が権力を握り、
ディストピアを強要するのですが、
そうした時代はまた、
長いこと待ち望まれた改革が実現し、
不正なシステムが
再編される時代でもあります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年05月03日
今日の社会
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
今日の社会がうまく機能している
理由のひとつは、
複雑な問題の解決は専門家に
まかせていることだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年04月30日
愚か者
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
愚か者は、
自分が見落とした手がかりや細かいことに
決して気づくことはない。
愚か者には、
相手が検討しなかったものを
把握できる分別が備わっていない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年04月29日
機械が私たちの可能性を取り上げる
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
自分が最も欲しいモノしか見えない
消費者になってしまったら、
私たちは機械が想定している
私たち以外のものになる可能性を
失ってしまうかもしれない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年04月09日
世界はまさに
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
世界はまさに、
予測不可能な刺激が絡み合ったもの
ではないだろうか?
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年04月05日
モノの終点にあるもの
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
私たちは
モノをつくる人間が予測できない最後の1マイルの道を、
機械が築いてくれることを期待している。
そして、
その道の終点にあるのはコンテンツだけだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年04月04日
今日つくられるモノ
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
「個客市場」と呼んでいた。
かつてのデザインは
ユーザーを知ることを重視していたが、
それに対して今日つくられるモノは
私たちを個別に理解しようとする
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年03月27日
選択のパラドックス
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
あまりにも多くの選択肢を提示されると、
何も選ばなかったり、
あるいは選んだものに
がっかりすることが多くなるのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年03月05日
ある葛藤
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
大多数から外れた周辺部に
革新を見つけるダイナミクスは、
デザインの原点に存在していたある葛藤を
浮き彫りにする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年02月27日
文学者の自己
2021年02月26日
通俗で藝術に触れてはならない
織田作之助 著 「「可能性の文学」への道」から
『
通俗読物のかなでは、
藝術にふれてはならない。
芸術の神のいかりがある筈である。
その人が藝術家でなくても・・・。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年02月24日
東京にあるもの
織田作之助 著 「「可能性の文学」への道」から
『
東京にあるものは、
根底の浅い外来の文化と、
たかだか三百年来の江戸趣味の残滓(ざんし)に過ぎない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年02月16日
顕在(けんざい)ニースと潜在(せんざい)ニーズ
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
人が普段口にするのは
何が欲しいかであって、
何が必要かではないのです
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年02月10日
はるかに重要
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
興味深い問題を見つけることは、
興味深い解決策を見つけるよりも
はるかに重要だ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年02月09日
極めて優秀な学生は
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
極めて優秀な学生は
問題の解決よりも
問題を見つけることに
創造性をより発揮することに気づいた。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年02月07日
社会が何を必要としているかを予測するには
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
社会が何を必要としているかを
予測する方法を教える唯一の策は、
教えられる側の思い込みを
打ち破ることだった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年01月26日
機械に求めるもの
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
私たちは新しいテクノロジーで作られて機械に対して、
約束されたとおりのことをするだけではなく、
私たちの想像どおりのことをすることも求めている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年01月18日
大阪主題の小説
2021年01月17日
嘘を書くのは真実をとらえるため
織田作之助 著 「「可能性の文学」への道」から
『
現実に興味がもてぬというのは
私は現実を信じないからである。
私が信ずるのは、
現実の中に瞬間瞬間にあらわれる真実だけである。
嘘を書くのは真実をとらえるためである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年01月12日
デザイナーとして求められるもの
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
デザイナーとして求められるものは
「非現実的ではない展望を抱いている」
ことだ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年01月08日
人が良心をもっと発揮しやすくなれば
クリフ・クアン/ロバート・ファブリカント 著 「ユーザーフレンドリー」全史
= 世界と人間を変えてきた「使いやすいモノ」の法則 = から
『
人が良心をもっと発揮しやすくなるようにすれば、
私たちはみな当然もっとよい人に
なれるというわけだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2021年01月01日
2020年は「嘘」でした
映画「ワンダーウーマン1984」ダイアナの台詞から
『
嘘は真実を隠し
貴重な時を失わせる
』
トランプ、イソジン吉村、安倍晋三、
2020年は嘘つきたちが、コロナ対策に割くべき貴重な時間を失わせた年として、歴史に刻まれることでしょう!
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年12月23日
芸術の創造力と気質の不幸
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
偉大な芸術作品を生み出す力は、
決して常にそうだというわけではないが
非常にしばしば、
気質のうえでの不幸に結びついている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年12月02日
粘バー・ギブアップ
2020年11月27日
詩心を持たない数学
バーバラ・オークリー 著 「直感力を高める 数学脳のつくりかた」から
『
デイヴィッド・ユージーン・スミス
そもそも詩心を持たない数学や、
数学の心を持たない詩はあり得るだろうか
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年11月06日
間違いを尊重する
2020年11月05日
人は生涯学習者
2020年11月04日
人生最大の報酬
2020年11月03日
練習
バーバラ・オークリー 著 「直感力を高める 数学脳のつくりかた」から
『
「練習によって完璧になる」
というのは真っ赤な嘘。
実際には練習することで
上達してくる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年11月02日
失敗率
2020年10月31日
いつかは成功する
2020年10月30日
学習の秘訣
2020年10月21日
馬子にも衣装
外山 滋比古 著 「ライフワークの思想」から
『
馬子にも衣装。
その衣装のことばかり気にしていて、
衣装さえよければ、
馬子は人間でなくても平気だと
言い出しかねない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年10月20日
隣は何をする人ゾ
外山 滋比古 著 「ライフワークの思想」から
『
近代社会は
世間体をとりつくろう要求によって動く
と言われるが、
人が見ていなければ
何をするかわからない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年10月18日
パブリックの私利益利用は卑劣
外山 滋比古 著 「ライフワークの思想」から
『
自分のプライベートな利益のために、
パブリックなものを利用しようとする考えは、
いついかなるときも、卑劣である。
』
- Permalink
- by
- at 10:00
2020年10月17日
悪魔の刀匠(とうしょう)が作った名刀
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
悪魔は死んで、
彼の刀だけが残っている。
あなたは自分の目的のために、
その刀を使う準備ができているだろうか。
できていなければ、
悪魔の刀で武装した
他の人間にやられるかもしれない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年10月16日
悪人が善人より成功しているように見えるのは
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
現実の世界で
悪人が善人より成功しているように見えるのは、
負ける方がただ善人であるというのではなく、
成功についての研究が
不足しているからかもしれない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年10月10日
先延ばしは毒物
バーバラ・オークリー 著 「直感力を高める 数学脳のつくりかた」から
『
先延ばしは
少量の毒物を摂取するようなものだ。
当初は無害に思えても
先延ばしが長期にわたれば、
ダメージが大きい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年10月09日
リーダーは「善」を目的にして
2020年10月08日
先延ばしは癖になりやすい
バーバラ・オークリー 著 「直感力を高める 数学脳のつくりかた」から
『
その手がかりをつかむと
先延ばしの心地よい反応に
身を委ねてくつろぎ、
一時の楽しさを味わう。
これが続けば反応するのが習慣になり、
しだいに自分自身に自信が持てなくなる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年10月06日
「悪」と「善」
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
「悪」は、
手段としては強力な武器だが、
「悪」自体が目的になれば
その主人をも破滅させる。
「善」は、
目的としては強力だが、
手段としては
かなり弱い武器である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年09月30日
指導者の目的に必要なもの
2020年09月29日
ヒトラーの悟り
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
巧みな弁舌の才や
強引な方法だけで出世を図っても、
その成功は一時的なものだ。
真面目な活動を段階的に実践することだけが
目的に到達する一番効率的な方法なのだ。
そのためには
真面目で一途でなければならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年09月27日
ナンバー2は二人以上がいい
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
ナンバー2は、
必ず二人以上ある方がいい。
実力のあるナンバー2が一人しかいなければ、
彼によってあなたが追い出される
可能性が強いだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年09月26日
ナンバー2
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
口先だけで成功することは不可能だ。
あなたがリーダーとして成功するには、
黙々と働く真面目なナンバー2が絶対に必要だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年09月25日
ヒトラーの権力掌握は
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
ヒトラーの権力掌握は、
このように数多くの人々の
利害関係を自分の目的のために
上手く利用したことで達成できたのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年09月23日
リーダーには芸術的感受精が必要
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
偉大なリーダーには、
優れた芸術的感受性が必要である。
芸術だけがリーダーにインスピレーションを
与えることができるのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年09月18日
経験主義ではどうにもならないとき
外山 滋比古 著 「ライフワークの思想」から
『
伝統とか蓄積が成長の原動力とならずに、
しばしば、
停滞をまねくことが気づかれると、
君子の豹変が悪いことではなくて、
望ましい飛躍と考えられるようになる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年09月13日
比喩の根拠
外山 滋比古 著 「ライフワークの思想」から
『
この世にまったく新しいものは決してなく、
どんなに新しいものでも、
何らかの意味で、
これまでのものと
かならずなんらかの関係をもっている。
そのなんらかの関係が
成立しうるというところが
比喩の根拠にほかならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年09月12日
白紙委任の結果は自業自得
映画「ヒトラー ~最期の12日間~」 ゲッペルズの言葉から
『
我々が強制したのではない。
国民が我々を選んだのだ。
それで困窮することがあっても、
自業自得だ!
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年09月05日
成功したリーダーと詐欺師の違い
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
成功したリーダーと詐欺師の違いは、
自分が公言したことを
現実化できるかできないのかの違いだけだ。
成功はどれだけ正直かということに
かかっているわけではない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年09月02日
英雄に仕立てあげるもの
2020年08月31日
判官贔屓
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
弱者がその主張に十分根拠を備えていて、
どんな弾圧にも屈しなければ、
その人物は大変な人気を博すに違いない。
勇ましい弱者は
大衆の目には正義と映るからだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年08月15日
あの戦争を教訓にするためには
作家 保阪正康さんの言葉から
『
自分で考え、
判断し、
社会の中での自分の責任を理解しながら、
自分で道を決める。
私たち一人ひとりが、
こうしたシビリアン(市民)に
なれるかどうかが、
いま問われている
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年08月12日
子供になすべき正しい事は
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
その子供にとって、
なすべき正しい事が何であるかを
母親に教えてくれるような本能を
母親は決して天から与えられて
いるわけではない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年08月11日
自己犠牲的母親は
2020年08月07日
他民族に排他的な体制を持つ国は衰退する
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
ファシズムが失敗した原因は、
民族概念に捉われた閉鎖的なシステム
だったからである。
民族や領土のような小さな概念に捉われて、
他民族に排他的な体制を持つ国は、
結果的には衰退してしまうだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年08月04日
リーダーは本音と建前を分離する
2020年08月03日
大衆は権力者のドグマに洗脳されている
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
今も、社会の食物連鎖の頂点にいる人々は、
一般大衆を洗脳する方法をいつも研究している。
あなたも、
彼らが勝手に作った何らかのドグマに
洗脳されているかもしれない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年07月31日
資本家と政治家が協力し合う訳
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
いっしょに協力すれば
大衆をうまく騙して
権力と経済的な利益をすべて
独占できるということも分かっている。
資本家と政治家が結託する理由は、
彼らがお互いに似ている人たちだからでもある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年07月30日
資本家のモラル
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
彼ら(資本家)のモラルは
一般市民のモラルでは絶対理解できない。
利益のためには、
他の国で人がいくら死のうとも
かまわないと考える資本家は、
どこにでもいる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年07月27日
政府に安易に要求すると
吉本佳生 著 「スタバではグランデを買え!」から
『
何でもかんでも政府に期待して
安易に要求する市民は、
程度の差こそあれ、
政治家と癒着して
不当な利益を得る企業と
さほど変わらない問題を引き起こしている、
と自覚するべきでしょう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年07月25日
一たび戦争が起きれば
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
一たび戦争が起きれば、
軍需会社の株主は
天文学的なお金を儲けることができるが、
一般大衆は
何も得ることはできない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年07月23日
騙すは資本家、騙されるは大衆
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
この世界には二種類の人間がいる。
騙す人と騙される人だ。
資本家は騙す人で、
一般大衆は騙される人だ。
騙す人はメディアを使って
自分に有利なことだけを
見せて大衆を洗脳する。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年07月22日
既得権階級を動かすためには
2020年07月21日
既得権階級が興味のあるもの
2020年07月20日
既得権階級の性質
成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
既得権階級は、
自分たちの利益に影響する確かな理由がなければ
変化を企てることはない。
特別な理由がなければ、
現在の状態を維持する方が
有利だということが分かっているからだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年07月19日
金づる
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
有能なリーダーになろうと思えば、
心強い「金づる」が必要だ。
このようにしよとすれば
経済的な後援者たちの利害関係を
利口に利用することができなければならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年07月15日
資本家は一般大衆と違う反応をする
2020年07月14日
政治家は二種類の支持者を必要とする
2020年07月11日
ヒトラーは理性的に行った
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
ヒトラーがどれほど利口で理性的な人間だったかは、
彼がどれほど多くの企業家たちから
援助を受けるようになったかを見れば明らかだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年06月07日
事実を捻じ曲げる者は自ら破滅する
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
客観的な事実を歪曲(わいきょく)する嘘は、
短期的には利益になるかもしれないが、
結局は自らを破滅させる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年06月04日
嘘のフィードバック
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
「嘘のフィードバック」、
これはまるで、
海の青い色が反射して
空も青い色になり、
さらに空の青い色が反射して
海が青い色になる、
ということに似ている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年06月02日
嘘の支配階級
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
混沌とした社会では、
最も嘘に秀でた人物が権力を握る。
そして社会が安定化してくると、
嘘は支配階級が占有するようになり、
権力が維持されるのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年05月22日
誘惑され易い人
2020年05月19日
一部から存在しない全体を想像させる
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
自分は持っている能力の一部分だけを、
相手がそれと気づかないように演出して見せるのだ。
そうして、
こちらがまだ見せていない他の能力についても、
相手がいろいろと想像を
広げてくれるようにし向けるのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年05月18日
神秘化戦略が効果的な理由
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
神秘化戦略が効果的な理由は、
与えられた情報が不足している場合、
人々は自分の想像力を
働かせるようになるということだ。
想像力は、
あらかじめ与えられた情報の上に、
さらに大きくイメージが膨らむように働く。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年05月14日
小説とは
木原善彦 著 「アイロニーはなぜ伝わるか?」から
『
小説とは、
作者が持っている特定の主張を
にぎやかに飾り付けたようなものではなく、
むしろ、
作者はまず大きな波紋を立てるための
仕掛けを考案した上で、
それに付随して聞こえてるいくつもの声を
丁寧に拾い上げていく役割を担っている
と言えるかもしれません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年05月12日
不条理な小説空間
木原善彦 著 「アイロニーはなぜ伝わるか?」から
『
不条理な小説空間を
<現実>として読むことによって、
読者の「現実」の幻想性を
<虚構>として浮き彫りにすることで
面白さを生んでいるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年05月11日
カリスマは目つき
2020年05月10日
アイロニーとは
木原善彦 著 「アイロニーはなぜ伝わるか?」から
『
アイロニーとは
極小(ミニマム)の虚構であり、
語り手と聞き手との間で交わされる
一種のごっこ遊びなのかもしてません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年05月06日
ヒトラーの演説とは
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」から
『
ヒトラーにとって演説は
単なる言葉ではなく、
大衆を扇動し、
説得して操るための道具であった。
そのような目的のために、
ヒトラーは自分を俳優だと認識して
徹底的に演出された姿だけを大衆の前においた。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年04月20日
時間は貴重な資源
サフィ・バーコール 著 「LOON SHOTS クレイジーを最高のイノベーションにする」
『
人間関係が
喜びや支援を提供してくれる貴重な資源
であるように、
時間も貴重な資源だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年04月17日
人間が繁栄できる理由
サフィ・バーコール 著 「LOON SHOTS クレイジーを最高のイノベーションにする」
『
人間が不滅であるのは、
生物のなかで
唯一言葉を持っているからでなく、
思いやりや犠牲や忍耐を可能にする魂、
精神があるからです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年04月03日
固執する理由
木原善彦 著 「アイロニーはなぜ伝わるか?」から
『
それが自分のものでなくなる可能性があるからです。
つまり、
失う可能性が0なら
人はそれに固執しないはずです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年03月31日
ユーモアとは
2020年03月30日
アイロニーは特異な存在
木原善彦 著 「アイロニーはなぜ伝わるか?」から
『
アイロニーは特異な存在です。
なぜなら、
それは、明らかに<現実>には
マッチしない情報であるにもかかわらず、
捨て去られることのない情報だからです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年03月29日
矛盾の集まりが意味を持つ
陸秋槎 著 「色のない緑」から
『
矛盾したものが
ひとつひとつ集まって作られたその時代は、
ちゃんと意味を持っていて、
燦然(さんぜん)と輝いてたってぐらいに言ってもいい
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年03月28日
矛盾したものが引き裂く
陸秋槎 著 「色のない緑」から
『
その時代は、
相容れない目標や立場が大量に存在していて、
そうやって矛盾しあうものが
同時代のひとりひとりを引きさいていたの。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年03月08日
怒りを抱いている人は巧みに話す
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」
『
怒りを抱いている人が
巧みに話すことができる理由は、
自らの体験による鬱積した思いがあるからで、
その思いを吐き出すエネルギーが
凝縮されているからである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年03月06日
対立構造が結束を強くする
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」
『
多数の人々を結束させる対立構造を作っておけば、
既存の社会を転覆させるほど強く
民衆を結束させることができる。
逆に、
そういう対立構造なしで
民衆を一つに結束させるのは難しい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年03月04日
ヒトラー演説の説得力
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」
『
彼の演説が説得力を持っていたのは、
人々がすでに抱いていた不満や怒りを、
感情を込めた激しい表現で口に出し、
大衆の感情を高揚させる能力を
持っていたからである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年03月02日
ヒトラー事初め
許 成準 著 「ヒトラーの大衆扇動術」
『
今の政治家たちは
自分のイメージ向上のために
子供を抱いて写真を撮ったりするが、
それを初めて行ったのはヒトラーである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年02月15日
SNSのダークサイド
望月 衣塑子、前川 喜平、マーティン・ファクラー 著 「同調圧力」から
『
極端に偏った主張をツイッター上などで
繰り返すレイシストを生み出した。
意見があまりにも攻撃的で、
主張も際立っているがゆえに目立つ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年02月14日
本来は面白いはずの政治に対する無関心
望月 衣塑子、前川 喜平、マーティン・ファクラー 著 「同調圧力」から
『
新聞は読者の、テレビは視聴者の側を向いていない。
ジャーナリズムが本来の役割、
つまり権力の監視役を果たしていない状態が
続けばどうなるのか。
すでに生まれているのは
私たちの未来に直結する、
本来は面白いはずの政治に対する無関心だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年02月12日
両親の愛情
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
両親の愛情というものが
普通の人間ならば
彼あるいは彼女の子供に対して
他のそれ以外の人々に対してとは違って
感ずる一種特別な感情であるとう
広い事実はいまも昔もかわるまい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年02月11日
未来は重要
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
子供たちをもち、孫たちをもち、
そして彼らを自然の愛情をもって
愛するところの男女にとっては、
未来は重要なものである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年02月05日
アクセス・ジャーナリズムの弊害
望月 衣塑子、前川 喜平、マーティン・ファクラー 著 「同調圧力」から
『
アクセス・ジャーナリズム
(権力者から直接情報を得る手法)は
アメリカにも存在するが、
これまでに何度も繰り返してきたように、
必要以上に依存度が深まればさまざまな弊害が生まれる。
当局の発表を伝えることがよしとされれば、
必然的に受け身の姿勢を招いてしまう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年02月04日
記者クラブ
望月 衣塑子、前川 喜平、マーティン・ファクラー 著 「同調圧力」から
『
質問する側の例外が
東京新聞の望月衣塑子記者だ。
記者として当たり前の仕事を
しているだけにしか見えないが、
その望月さんが浮いているという状況が、
日本のメディアの状況を物語っている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年02月02日
日本は調査報道を軽視している
望月 衣塑子、前川 喜平、マーティン・ファクラー 著 「同調圧力」から
『
長く日本のメディアを見てきて強く感じることは、
調査報道の対極に位置するアクセス・ジャーナリズム、
つまり権力者からいかに情報を得るかの方に、
あまりにも重きが置かれすぎている点だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年01月27日
トランプ大統領は思考停止している
望月 衣塑子、前川 喜平、マーティン・ファクラー 著 「同調圧力」から
『
個人にとって都合のいい情報だけを取り入れ、
主義主張が異なるそれは耳障りだとして
問答無用で遮断する。
思考が停止し、
完全に分断されてしまった状況下で、
トランプ大統領は
政権に対して都合の悪い記事を書く
ニューヨークタイムズやワシントン・ポストなどの記者を、
実名をあげてツイッターで攻撃することに余念がない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2020年01月04日
今年はこちらの番だ
映画「スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け」フィンの台詞から
『
今までやられっぱなしだったが、
今度はこっちの番だ。
』
安倍政権には悪事をやられっぱなしだったが、今年はこっちの番だ。
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年12月30日
事故や災害が起きると
元 国会事故調調査統括補佐 石橋 哲さんの言葉から
『
事故や災害が起きると、
様々な問題が一挙に顕在化します。
それは慢性の病気が急に悪くなった状態に似ています。
解熱剤で発熱を抑えるなどして
一時的に楽になったとしても、
もとの病気を治さなければ再発します
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年12月26日
日本社会が変われない理由
元 国会事故調調査統括補佐 石橋 哲さんの言葉から
『
変えるより変えない方が
楽で合理的だからです。
国会議員にとっては
有権者の支持を集めることが重要です。
「どうすればいいだろう」
と議論で悶々としている姿より、
見栄えよく誰かを非難している様子が
報道された方が票につながると思うから、
変わらないのです。
そういう有権者、商業メディアだからです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年12月24日
ドクターX シーズンVIで振り返るアベ政権【OPE-4】
2019年12月23日
ドクターX シーズンVIで振り返るアベ政権【OPE-3】
2019年12月21日
ドクターX シーズンVIで振り返るアベ政権【OPE-8】
2019年12月19日
3歳児にも強制されない自由がある
望月 衣塑子、前川 喜平、マーティン・ファクラー 著 「同調圧力」から
『
幼稚園や保育所に預けられた幼い子どもの、
初めて歌った歌が君が代になるなんて、
悪い冗談にもほどがある。
3歳の幼児といえども、
日の丸への敬礼や君が代の斉唱を
強制されない自由は持っている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年12月18日
教育支配
望月 衣塑子、前川 喜平、マーティン・ファクラー 著 「同調圧力」から
『
政治の教育への不当な介入は、
露骨な強制や実力行使によるこのとは限らない。
周囲の忖度と同調圧力によっても起きる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年11月20日
愛の警戒
2019年11月19日
用心警戒
2019年11月18日
称賛は緩慢に送られる
2019年11月13日
愛情の欠如
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
愛情の欠如は
彼らに不安の感を与える。
そうして彼らは自分の生活を
徹底的にまた完全に支配する習慣をもつことによって、
この不安の感じから本能的にのがれようとする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年11月11日
忘恩
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
他人のためになるような行為によって
愛情を買い取ろうと努力する人は、
やがて人間の忘恩を経験することによって
幻滅の悲しみをなめるだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年11月09日
熱心というもの
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
熱心というものは必要な仕事にとって
充分である以上のエネルギーを要求するものであり、
そのうえさらに心理機構の
なめらかな活動を要求するものである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
熱心というもの
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
熱心というものは必要な仕事にとって
充分である以上のエネルギーを要求するものであり、
そのうえさらに心理機構の
なめらかな活動を要求するものである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月30日
人権を単なる暗記物だと思っている
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
思想信条調査をした元大阪市長も、
今の大阪市長も、弁護士さんですからね。
思想・良心の自由はプライオリティーの高い
人権として学びませんでしたっけ?
きっと単なる暗記だったんでしょうね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月29日
歴史には、敗者と女は出てこない
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
男で勝った人の歴史しか習っていないから、
どうしても為政者目線になる。
どんな虐殺をしていようが勝てば官軍、
勝った人間はスーパーヒーローですよ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月27日
国民を惰眠させてナチスになる
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
国民は寝ていていれればいいんだ、
その間にナチスの手口を学んでっていうことでしょう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月26日
人権は教育しだい
2019年10月23日
日本の民主主義はよちよち歩き
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
人権ができて、
自分たちで民主主義を始めようと決めて
日本はまだ72年しか経っていないんです。
今までなかった社会システムをつくってんねんから、
72年なんてまだよちよち歩き。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月22日
学ぶ権利
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
私は主権者が主権者たり得るためには、
知る権利だけではなくて、
「学ぶ権利」がちゃんと保障されないと
いけないと考えています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月21日
自由とは国家権力に対し敢然(かんぜん)と立ち上がって得たもの
2019年10月19日
政治家には憲法を擁護する義務がある
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
君ら政治家に
憲法尊重擁護の義務がかかってるんで、
なぜあんたらに政治的だと
言われなあかんのや。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月17日
基本は憲法
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
基本は憲法です。
憲法で大事だとされているところは
学校が積極的に、子どもたちに対して
ちゃんと意識を待たせなきゃいけない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月16日
公教育
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
過去から引きずってきた
差別などを否定していかなきゃいけない。
公教育というのは、
最終的には、
おまえの親の言っていることは
間違いだと言える力をもっていると
私は思いますね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月15日
国会議員は憲法を勉強していない
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
一応日本の学校の先生は全員、
日本国憲法を2単位分だけは勉強している。
ところが、国会議員の先生は
学校の先生と違って
何も勉強していないんですよねぇ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月09日
レイプ犯罪者の免罪符
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
性犯罪者も免罪され、
逮捕状も執行されないとかね。
あれはひどいと思いますよ。
総理の友達で、
総理をヨイショする本を書いている人間だからって、
犯罪も見逃されちゃうというのはね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月07日
安倍首相は三権分立を元々わかっていなかったみたい
2019年10月06日
自民党は極右政党
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
自民党は、
もう今は極右党ですね。
「安倍党」と言ってもいい、安倍一党というか。
みんな、それにしたがっちゃっている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年10月04日
お上に従順な人間を作る検定教科書
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
もともと日本の社会には
上の人に従うんだみたいな文化がずっとあるけれど、
私が今一番心配しているのは道徳教育なんです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年09月29日
人間は愚かな間違いを犯す
ヘブライ大学教授・歴史学者 ユヴァル・ノア・ハラリ さんの言葉から
『
前世紀からの教訓の一つは、
戦争は誰にとっても悪いことなのに、
気をつけないと、
また起きるということです。
人間の愚かさゆえです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年09月25日
独裁政権が技術的優位になる
ヘブライ大学教授・歴史学者 ユヴァル・ノア・ハラリ さんの言葉から
『
危険なのは、
計画経済や独裁的な政府が、
民主主義国に対して
技術的優位に立ってしまうことです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年09月18日
未成熟だから押さえつけていいのか
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
日本の場合は
未成熟だから押さえつけていいという考え方で、
成熟に合わせて開花させていく考え方の
権利条約とは違う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年09月17日
子どもの権利条約第12条
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
子どもの権利条約第12条:
自己の意見を形成する能力のある児童が
その児童に影響を及ぼすすべての事柄について
自由に自己の意見を表明する権利を確保する。
この場合において、児童の意見は、
その児童の年齢及び成熟度に従って
相当に考慮されるものとする
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年09月16日
日本のスポーツは軍事教練
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
スポーツという言葉自体が遊びという意味なのに、
日本のスポーツは
すべて軍隊と学校から派生しているから、
教練や教育のためにできている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年09月10日
権力とメディア
望月 衣塑子,、前川 喜平、マーティン・ファクラー 著 「同調圧力」から
『
権力がメディアに対し、
支配的、抑圧的になっている今こそ、
記者が果たすべき役割とは何か、
メディアとはどうあるべきなのか、
というそもそもの原点に
立ち返っていく必要がある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年09月08日
日本の記者会見は発表会
望月 衣塑子,、前川 喜平、マーティン・ファクラー 著 「同調圧力」から
『
政府が認定した「事実」以外は、
質問内容にも入れてはいけない、
となれば、
定例記者会見は何の意味があるのか。
政権にとって都合のいい情報だけが流される、
単なる発表会だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年09月05日
髪を切るのも人権
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
自分の髪を切る切らないは、
自分で決められるはずなんでね。
中学生といえども、それは人権ですよ。
それを、学校の教師だからといって
勝手にはさみを持ち出して
切るというのはあり得ません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年09月04日
近代国家を否定したい人たちがいる
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
天賦人権説を否定するんやったら、
そもそも近代国家として
成り立っていることを否定しなきゃいけない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年09月03日
天賦人権説:国家が人権を与えるのではない
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
自民党の人の中には
国家が先にあって、
国家が憲法によって
国民に人権を与えているんだという人、
いるんですよ。
天賦人権説は間違いだ、
ということを平然と言う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年09月02日
危険な公共という授業(自己犠牲の強要)
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
(与党政党は)
新たに「公共」という教科をつくる。
この場合の「公共」は、
公のために滅私奉公しなさい、
自分を犠牲にしろ、
という意味で、
これを教育に持ち込もうとしている
人たちがいるわけ。
これが危険なんですね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年08月31日
形成者(オーガーナイザー)
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
一人ひとりが人格を持って、
主体性を持って、
それがつながり合ってパブリックをつくっていく、
社会をつくっていく
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年08月30日
勝ち取っていないから大事にしていない
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
自由とか平等とか権利とかというものも。
獲得したというか、自分たちが勝ち取ってきた感覚が
すこぶる薄い。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年08月29日
日本は自分が社会を作っているという意識が低い
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
近代民主主義のリーダー国になりたいと言いながら、
自分が社会の構成員の一員で、
自分が社会をつくっているんだという
意識がこんなにない国は珍しいんちゃうか
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年08月27日
先生が意見表明できない社会
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
意見表明の権利を大人も行使できない社会。
公務員である前に、人間だから、
自分がどんな政治的信条を抱いていようと
勝手なわけじゃないですか。
それこそが参政権だし、
放っておいてくれよと思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年08月26日
ボイステルバッハ・コンセンサス
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
日本でボイステルバッハ・コンセンサスができないのは、
結局、生徒をバカにしすぎたからだと思うんです。
子どもたちには判断力がないから
なんでも鵜呑みにしてしまうって、
そんな人間をつくり出しておいて何を言うとんねん。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年08月25日
主権者教育
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
政治教育なり主権者教育なりというのは、
自ら判断する人間を育成していくことが目的なんだから、
教師が自分の意見を言ったって、
それはそれで、
生徒はそれを批判的に受け止めればいい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年08月16日
怖い言葉
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
結局それは、教育勅語的な教育なんです。
戦前の1945年、昭和20年以前の教育を取り戻すこと。
「教育再生」という言葉は、
本当に怖い言葉です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年08月14日
違いを認めない社会
2019年08月13日
民主主義社会は主権者が作るもの
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
自分たちが一番住み良い社会を
自分たちでつくっていく、
というのが民主主義社会だと思うんです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年08月03日
まったく欲しいとは思えない製品
佐藤可士和 著 「世界が変わる「視点」の見つけ方」から
『
何かを生み出す時、
最初のプロセスを
フォーマットや数値だけで構成すると、
機能はまんべんなく搭載されているけれど、
まったく欲しいとは思えない、という、
よくありがちな製品づくりにつながってしまいます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年07月25日
先生と勝負してこい
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
私は勝負してこい、
学校で先生とケンカしてきたらええねん、
最後はお母ちゃんが出ていくからどうぞ、
と言う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年07月22日
デザインは数値化できない
佐藤可士和 著 「世界が変わる「視点」の見つけ方」から
『
デザインは「1 + 1 = 2」ではなく、
物事に対する視点や、
取り組み方のことで、
簡単に数値化できない。
失敗と成功のプロセスを
経験するしかないんです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年07月16日
桃太郎はアメリカン
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
鬼の子にしてみれば、
桃太郎たちが勝手にやって来て
私の大事なお父さんを
いきなりぶった斬ったわけですよ。
だから桃太郎ってアメリカ的なんです。
イヌとかサルとかキジって、
日本とか、韓国もかな、
いろいろな国が連れていかれて、
よう分からへんけど。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年07月14日
ときどきチクリと刺す
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
批判を言い続ける意味はあるんです。
言わなかったら、もっとひどくなっていたかもしれないしね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年07月13日
風刺の視点が大事
前川喜平、谷口真由美 著 「ハッキリ言わせていただきます」から
『
今の日本に圧倒的に欠けているのは
風刺の視点だと思っています。
風刺画、川柳・狂歌とか、
権力者をおちょくる瓦版みたいなものが本当になくて、
どっちも罵詈雑言ばかり。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年06月17日
スマートな賭け
ジェイソン・フリード、デヴィット・ハイネマイヤー・ハンソン 著 「NO HARD WORK 無駄ゼロで結果を出すぼくらの働き方」から
『
スマートな賭けとは、
危険にさらされていないときにもう一度、
賭けに出ることだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年05月28日
好むより慣れ
ジェイソン・フリード、デヴィット・ハイネマイヤー・ハンソン 著 「NO HARD WORK 無駄ゼロで結果を出すぼくらの働き方」から
『
ときおり僕らは、
人が何かを好むか嫌うかを問題にするが、
人はしばしば、好き嫌いより、
使い慣れているかどうかを重視して、
慣れているものがいいと考えるものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年04月20日
熱意が利する
2019年03月31日
人は究極的な利益のために話す
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
人々はお互いに話をとりかわす。
だが、話をしたいから話をするのではない。
彼らがお互いの協力によって引き出したいと
思う何か究極的な利益のために
話し合うのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年03月29日
文明社会における熱意の喪失
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
文明社会における熱意の喪失は、
大部分、私たちの生きていくうえに
欠くべからざるところの自由を
制限されたことによるものである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年03月28日
亡霊から逃れようと
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
他のあらゆる欲望を犠牲にしてまで
一つの欲望に極端に耽溺(たんでき)するような人は、
心の深いところになにかの葛藤を
つまり亡霊から逃れようと求めているところの
葛藤を常に持っている人である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年03月27日
情熱が不幸悲惨の原因とならないためには
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
個々の情熱が不幸悲惨の原因とならないためには、
それらの情熱がその中で営まれるための
枠をある種のものが形成するのでなければいけない。
ある種のものとは
健康であり、
その人のさまざまな能力を
全般的に所有し維持することであり、
生活必需品を備えるための十分な収入であり、
また妻や子供たちに対する最もたいせつな
社会的義務である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年03月25日
飲酒狂と大食漢
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
飲酒狂と大食漢とは
いずれも別段社会的な拘束を
もっているわけではない。
けれども自分をたいせつにするという観点からすれば、
二つとも賢明ばなものではない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年03月24日
趣味と欲望と社会と
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
趣味や欲望が幸福の源泉たるべきものとすれば、
それは当然健康や、私たちの愛する人々の
感情やあるいはまた私たちがその中で生活している
社会の尊敬と両立し得るものでなければいけない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年03月23日
大食漢
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
大食漢というのは
食べる快楽のために、
その他の快楽をすべて犠牲にし、
そうすることによって、
彼の人生の全体的幸福を
減少せしめる人のことである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年03月22日
よき生活とは
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
よき生活にあっては、
いろいろな活動の間に当然一の
バランスが保たれていなければいけない。
そしていろいろな活動のうちの
どの一つも他の活動を不可能にさせるほどに
行われるようなことがあってはならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年03月21日
興味があれば退屈はいらない
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
過半の人々は何かに激しい興味を
持つことができるのであり、
そしてひとたびかような興味が
目ざめてきた暁には、
その人の生活は退屈をのがれる
ことができるだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年03月05日
熱意は飢餓に似ている
2019年03月04日
幸福の秘訣
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
幸福の秘訣は次のごときものである
すなわち、
諸君の関心、興味をできるかぎり広くすること。
そして、
諸君の興味をそそる人や物に対する
諸君の反応をでき得るかぎり、
敵対的ではなく友誼的(ユウギテキ)たらしめること。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年03月03日
あまりに多く要求すると
2019年02月28日
個人的幸福で最大のものは
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
多くの人々を、
進んでなんらかの努力なしに好きになるということは、
おそらく個人的幸福のあらゆる源泉のうちで
最も大いなるものであるだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年02月27日
義務感
2019年02月26日
根本的な幸福
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
根本的な幸福は、
他のいかなるものにも増して、
人や物に対する友情的な関心と呼ばれている
ところのものに依存している。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年02月24日
看護は道
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
ナイチンゲールに言わせると、
看護は一つの道であり、
看護とは絶え間なく学び続ける存在であり、
その学びには限界がない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年02月13日
神が看護師に求めている生き方
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
外的環境の改善をすることによって、
患者を健康な生活の回復へと導いていく、
それこそがまさに
神が看護師に求めている生き方である、
とナイチンゲールは確信していたのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年02月12日
いかなる人も切り捨てられてはならない
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
ナイチンゲールにとって、
いかなる人も、
たとえ社会で必要のない人であっても、
切り捨てられてはならなかった。
何故なら、
どんな人であっても、
その身体は聖なる心の<器>として
神から授かった大切なものであるからである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年02月10日
卑近な信仰
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
私にとっては虚偽の信仰としか
思われぬものの上に
いかなる幸福にせよ
これをきずきあげることを、
私はすすめるわけにいはいかない
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年02月08日
一つの主義主張に偏る理由
2019年02月07日
介護に絶対欠かせないもの
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
介護に絶対欠かせないものとして
「仕事における三重の関心」すなわち、
★症例への「知的関心」、
★患者への「心のこもった関心」、
★介護や治療への「技術的関心」
をあげている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年02月05日
良き環境を心の外に築く
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
人間が境遇に従って生活し、
行動するように定められている以上、
「神の国」は人間の心の内にだけではなく、
良き環境として外に築かなければならない、
と彼女は考えた。
すなわち、
ナイチンゲールの「神の国」は死後の世界ではなく、
「今ここに」存在する現実の世界である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年02月03日
人間の知識と進歩のために働く
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
自己の名声欲や権力欲を捨てて、
人間の知識と進歩のために、
神の「み旨」を信頼して働くことこそが
彼女の言う「神の支配の主要原理」であった。
「看護」はそれを実現する最善の方法であった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年01月31日
神とは「愛」と「英知」
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
人を救った場合、
称えられ感謝されるのは救助者ではなく、
救助者に使命と能力を授けた神なのである。
その神とは、
ナイチンゲールにしたがって言い換えれば、
人間の力を超えて働く「愛」であり、
「英知」なのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年01月30日
神の計画
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
ナイチンゲールにとって、
そうした貧しい下層階級の人々を
社会から切り捨てることは、
神の計画に反するものであった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年01月29日
神は貧困や苦悩を望まない
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
神の望まないものが
貧困や苦悩であるとするならば、
人間は自己の責任と努力において
それらを無くすように
しなければならにのである。
』
By self responsibility and efforts, man has to lose poverty and suffering.
It is because God does not desire them.
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年01月24日
仕事の喜び
2019年01月23日
無力感がもたらすもの
2019年01月22日
愉快と不快の驚き
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
自分自身を低く評価するところの人間は、
つねに成功によって驚かされる。
その反対に自分自身を高く評価し過ぎる人間は
まさにしばしば上と同じように、
失敗によって驚かされる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年01月21日
物事を達成する快楽
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
物事を達成する快楽のためには
いろいろな困難が必要である。
たとえば、
結局はいつも達成させられるのだが、
目前の成功は疑わしいといったふうな。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年01月18日
冷たい外部の世界
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
人類大衆のもっている懐疑主義に対抗して、
絶えず自分自身を肯定しつづけねば
ならぬような生活において、
ほんとうに幸福であり得るような人は
ほとんどまれにしかないものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年01月14日
不戦条約が憲法9条のルーツ
国際法学者 オーナ・ハサウェイ さんの言葉から
『
- 1928年に日本を含む15ヵ国がパリで調印し、
「戦争は違法だ」と宣言した不戦条約が、
現代世界の「秩序」のルーツ -
日本の方々にはぜひ、
憲法9条の理念がどう生まれたのかを
知っていただきたいと思います。
不戦条約の理念が、
第二次世界大戦を経てつくられた国際憲章にも、
日本の憲法9条にも受け継がれているのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年01月11日
卑近な信仰は人生の解毒剤を騙る
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
何かこうした主義主張に対して
感ずる興味がほんものであるところの人々は、
その余暇をつぶすための仕事を与えられるのであり、
また、人生は空虚だといった感情に対する
完全な解毒剤を与えられるのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年01月10日
世論に従うのは自発的な屈服
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
私たちは世論を尊重すべきである。
しかしこの程度以上に世論にしたがうということは、
不必要な暴力に対する自発的な屈服であり、
あらゆる種類の仕方で幸福をややもすれば
妨げることにほかならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年01月09日
青年が気持ちよく才能を発揮させるには
2019年01月06日
日本の軍事力はイギリスを超えている
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
軍事については国家機密だから
情報公開の基準がまちまちで、
いろんな尺度があるんですが、
少なくと「いまの日本はイギリスより強い」
と言われているぐらいです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2019年01月02日
世界がお前を待っている
映画「シュガーラッシュ オンライン」から
『
さっさと行くんだ。
世界がお前を待っている。
』
「シュガーラッシュ オンライン」には、たくさんのディズニープリンセスが、ちょい役で出てきますが、吹替の声優は、なんと本編と声優さんが総出演です。
だから、松たか子、神田沙也加の声も聞けるのですよ。豪華!
あと、インターネットの世界をアニメで視覚的に表現しているのも興味深いです。リンクボタンを押すと、一瞬にして別の場所に飛び去って行くのも、なるほどと思わせます。
「ハートボタン(いいねボタン)」を押すとお金になる仕組みとか、ダークウェブの話など、インターネットの初心者用教材にも使えそうなレベルです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年12月30日
おろそかにした末路
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
政治の場でもメディアでも、
あの戦争をどう評価するかという議論が
おろそかになったまま、
いまに至って安保法制ができたり、
武器輸出がどんどん進んだりしています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年12月29日
あの戦争を教訓としない日本人
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
日本人はあの戦争を教訓としてきたはずなのに、
なぜそれをちゃんと語り継いだり
教育したりしないのか。
それがとても大きな問題だと思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年12月28日
知る権利を潰させない
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
国民の知る権利に関わる特ダネをつかんだときに、
権力側にそれを潰されないことが一番大事なのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年12月27日
人格攻撃
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
私は罪を犯していないし、
逃げ隠れするつもりもないけれど、
取り調べで
「こんなことをして人間として恥ずかしくないのか」
というような人格攻撃を受け続けると、
「あれ? 私は悪いことをしたのかな?」
と思ってしまったりするんです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年12月25日
安倍政権は都合の悪い存在を法的に潰している
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
時の政府は、自分の政権に都合の悪い存在を
法的に潰そうといつも狙っています。
どんなストーリーで捕まえるかということを、
周到に練り上げて、
そこにいくつかの調査で見つけた事実を入れ込んで
逮捕まで持っていくのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年12月24日
安倍政権の司法コントロール
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
第二次安倍政権になってから、
メディアへのコントロールと並んで目立っているのが、
司法への影響力が強まって見えるということです。
政権の意向に逆らうような活動をしたり、
政府にとって不都合な発言を繰り返したりする
人物や組織が不当に勾留されるケースが、
かつてないほど行われています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月30日
安倍政権が言っていることを全部信じ続けるのですか?
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
いったい誰が政権をチェックするんでしょう。
もし「マスメディアは信用できない」と
国民がそっぽを向くようになったら、
安倍首相が言っていることを
全部そのまま信じ続けるんですか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月29日
安倍流
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
自分に都合のいいメディアだけを
寄せ付けておいて、
都合の悪いメディアは
シャットアウトしてしまう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月27日
デマを飛ばす評論家がいる理由
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
なぜ仮にも名のある言論人までもが
そういうことをやっているのかというと、
それを見て喜ぶ層が少なからずいるからです。
つまり、
お客がいるから演者が張り切って
演じているわけです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月23日
ナショナリストがリベラルを批判する理由は
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
因襲的な人々が
伝統からはずれ去ることに対して
大きな怒りを感ずるのは、
彼らがこうした伝統からの違背を
彼ら自身に対する一つの評価と
考えるからにほかならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月22日
青年期
2018年11月19日
近代社会の特徴
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
人々がその道徳において、
またその信仰において
非常に強くちがっている組織に
分かたれているということこそ、
近代社会の一つの特徴にほかならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月15日
メディアは中立ではなく公正であること
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
ある人にとって
「これは喜ばしくない記事だ」
というものであっても、
「これは公正な記事である」
というふうに、
どの人からもちゃんと評価される
記事でなければなりません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月14日
中立な記事
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
日本のメディアは「中立」と言いながら、
当局が発表したことをそのまま書いて
「この記事は中立です」と言ったりしますが、
当局そのものは、
決して中立ではないわけだから、
中立な記事になっているとは言い難い。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月13日
日本メディアが停滞しているわけ
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
日本の既存の主要メディアは、
いまだに既得権益を守ったままで、
ニューメディアの新規参入が進んでいないのです。
それが、新聞を始めとする
日本のメディア全体の
停滞につながっていると思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月12日
安倍の改憲は民衆を操作しようとするトップダウンの過程
「ポピュリズムとは何か」著者 ヴェルナー・ミュラー さんの言葉から
『
一般的に言うと、
改憲自体は民主的に正当な行為と
いえるかもしれません。
問題は、その状況です。
自由や平等といった観点にかなう
ボトムアップの試みなのか、
民衆を操作しようとする
トップダウンの過程なのかで、
大きく違います。
これは単なる私の印象ですが、
日本の場合、
真に改憲を求める人々の声が
ボトムアップで出てきているようには
見えないのです
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月09日
安倍首相がりっぱな権力者? 冗談キツイ!
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
安倍首相は、
日本に健全なジャーナリズムが存在するべきだという
ことなんか一切、考えていないかのようですね。
もしかしたら、
「立派な権力者が正しいことをするためには
報道の自由や言論の自由などたいした問題じゃない」
と思っているのかもしれませんね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月08日
メディアは安倍の奴隷でよいとい考え方
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
政権とジャーナリズムの緊張感のある関係
なんてどうでもいいと思っているんでしょう。
自分たちの主義主張の正当性をアピールするためには
何をやってもいいんだという姿勢です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月07日
日本のメディアは自殺した
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
メディア各社には、
「このまま政権に対して何も言えないのは
メディアの自殺行為だ」
という危機感を持っている人たちは
たくさんいるんです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月06日
安倍にご馳走になって有頂天になっている政治学者って、何?
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
国際政治学者の三浦瑠麗さんや
山本一太参議院議員の名前が
「総理!今夜もごちそう様!」
というツイッター・アカウントに
アップされているのを見ると、
こういう人たちと
ネットワークを作っているんだな
というのがよくわかるんです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月05日
忖度の連鎖
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
権力のある者同士が利害を一致させれば、
あとは下に向かって忖度の連鎖を生んで、
自分の思うように周りが動く。
そのために安倍首相は
メディアのトップと
毎晩のように会食するんですよね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年11月04日
日本のメディアは堕落している
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
メディアのトップが
安倍首相からお食事に誘われれば
喜んで出かけていくんですよね。
アメリカ大統領が
ニューヨーク・タイムズのトップと
しょっちゅう仲良く食事をしているという
話はあまり聞いたことがないですもんね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月28日
すべての人を差別なく看護する
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
宗教的偏見や社会的差別に対して
フロレンスは厳しく対抗し、
真っ向から闘おうとしていたのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月26日
安倍政権はドライにメディアを操作している
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
安倍政権は
メディアと仲良くしているように見えて、
実は自分の都合でドライに利用している。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月25日
技術や知識の進歩の中で起きること
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
情報や知識というものは、
どんなに正しいと思われていたものでも、
時代とともに
「実は、新たな事実がわかった」
ということがあります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月24日
安倍首相はお気に入りメディアの質問にしか答えられない
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
安倍政権に好意的で、
安倍政権のお気に入りと言われてきたメディアは、
NHK、日テレ、フジテレビ、読売、産経。
こういったところには、
首相の単独インタビューも含めて
快く取材に応じますが、
それ以外の記者の質問には
まともに答えようとしません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月23日
権力に対する愛は
2018年10月22日
善い事をする動機
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
私たちが善い事をする場合の動機は、
私たちが自分でこうであろうと想像するほど、
純粋なものであることはまれなのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月21日
被害妄想
2018年10月19日
幻影のヴェール
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
私たちは、私たちがお互いに
絶対完全だとは思ってもいなかったのだということを
みずから隠し立てするための
幻影のヴェールを少しも必要とせずに、
お互いを好きになることを学ぶべきであるのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月18日
お互い同志の考えをよみ取る力があれば
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
私たちがもしかりに
お互い同志の考えをよみ取る力を
魔法かなにかによって与えられたとしたら、
その第一の結果は、
ほとんどすべての友情が解消するであろう
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月16日
Jアラートをガンガン鳴らしている
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
戦争に踏み切った場合の
被害推定値も国民に出さずに、
Jアラートで「危ないぞ」という
だけなのはどうなのか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月15日
国そのものがとんでもない方向に行っている
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
北朝鮮に向かって
そのミサイルのボタンを押すというような
国の安全を左右する意思決定のプロセスを
秘密にしてはいけない。
それが「秘密保護法があるから言えない」
という状況になると、
国そのものがとんでもない方向に行ってしまいます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月12日
国民監視を強化する道具が準備されている
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
日本国家として、
中国や北朝鮮の
ハッキングやサイバー攻撃を防ぐために、
ハイレベルなシステムを
次々に導入しているはずなのです。
それをまた
国民監視を強化する道具にも使えるという、
権力者にとっては
一挙両得のようなところがあるわけです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月11日
外圧を利用して欺瞞
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
外務省や防衛相が
外圧を都合よく利用して
前々から作りたかった法律を
作っているんですよね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月10日
アメリカ隷属、国民軽視
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
アメリカ政府側の意向を受けて、
日本の政治家や官僚が、
あらかじめ法案成立ありきで進めていって、
国会での議論や国民への説明は
適当にやればいいという感じに見えました。
ここにも安倍政権の
「アメリカ隷属、国民軽視」
の姿勢が顕著に表れていますよね。
』
The Abe Administration makes light of people and is subordinate to the United States.
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月09日
アメリカと戦争へ行きたいか
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
アメリカから情報をもらえると喜んでみせても、
実際は、
いつでもアメリカと一緒に戦争できるような
法律を作っているわけですよね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年10月08日
安倍政権は鉄のカーテンを閉めた
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
安倍政権は、
権力者が鉄のカーテンを閉めて、
情報操作とメディア監視を強め、
報道の自由や国民の知る権利を
束縛する方向へ向かっています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月29日
因襲より個人の資質が大切
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
自分は
「個人的な希望や計画は何もありません」
と言えるようになったとき、
偉大な勝利が達成されたとさえ信じることになるのです。
主より授けられた資質を
価値のないものとして投げ捨てて、
代わりに世間のことに没するとは
いったいどういうことなのでしょうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月28日
女性の「義務」という因襲
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
今は女性は知性の光のもとでは
生きていくことができません。
社会がそれをさせないのです。
女性の「義務」とよばれるとるにたらない
因襲的な事柄があるためにそれができないのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月27日
男性が作り出した社会因襲
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
男性が作り出して
女性が受け入れてきた因襲的な社会では
女性は何をもってもいけないし、
偽善の茶番劇 -
自分たちは情熱はもち合わせては <ならない>
のだという欺瞞 -
を演じ <なければなりません>。
ですから、
女性たちは自分に向けた欺瞞を
娘に対して繰り返す以外に
何が言えるというのでしょうか
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月26日
女性は「感性」を倫理的活動の実践に活かすべき
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
女性が世界的視野に立ち、
社会環境の中にあって
知的教養と倫理的活動の場を
自ら忍耐強く追求し、
認められるよう努力すべきだ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月25日
神の国は現実世界に実現しなければならない
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
現実世界の諸悪には耐えなければならないが、
社会の因襲的な諸悪は
人間自らの責任において改善し、
神の意に適う世界を築かねばならない
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月23日
貧民が働けないわけ
徳永 哲 著 「闘うナイチンゲール」貧困・疫病・因襲的社会の中で から
『
貧民は怠け者であるが故に
いつまでも貧しいと思っていたのが、
実はそれが間違った思い込みであって、
栄養不良によって病気に対する抵抗力が失われ、
体力も気力も失われていたという認識であった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月18日
産経はネット右翼にすがって生きる
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
ネット右翼相手のビジネスに特化して、
もうそれ一本で生き残ろうという
マーケッティング戦略にも見えます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月16日
安倍首相は自分贔屓しか指名できない
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
安倍首相は会見もあまりしないし、
たまに会見をしたとしても
質問の手を挙げた記者を選別して、
自分のほうになびいているメディアの人だけしか
指名しないんですよね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月14日
皆さん、日本国憲法を大切にしてください
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
「皆さん、日本国憲法を大切にしてください」
というのが、
いつも講演ラストの言葉だった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月13日
憲法が今まで改正されなかったのは
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
憲法が今まで改正されなかったのは、
「この憲法がいい憲法だからですよ」
と胸をはって言い、
「平和が一番大事、平和でないと芸術も文化も育たない。
女性も幸せになれない」
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月12日
日本国憲法の素晴らしさ
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
ベアテさんは、
日本国憲法の草案に携われたことを
誇りに思っていたし、
日本国憲法の素晴らしさを信じていた。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月11日
女性の権利と戦争放棄を守る決意
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
--- ニコール・ゴードン ---
女性の権利と戦争放棄が
危うくなればなるほど、
それらを守ろうとする人々の
決意はさらに強くなるでしょう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月09日
日本国憲法は他の国の模範
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
--- ニコール・ゴードン ---
彼女は勿論、
平和憲法は変えるべきでなく、
他の国の憲法の模範であると思っていました。
そして彼女は自分の死が近い事を知っていました。
それゆえこの最後の機会に、
日本国憲法を支持するという自分の意見を、
多くの読者にしっかり伝わる方法で
発表することを決意したのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月06日
政権に睨まれるのが怖い記者って何?
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
情報を取るために
政権ににらまれるようなことは
したくないという記者が
残念ながら結構いるんです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月05日
「僕、これやりたい」が総理の御意向
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
「僕、これやりたい」
と安倍首相が思ったことを、
きちんとした手続きや法的な根拠、議論を経ず
「総理のご意向」だけを政府をあげてやろうとするから、
いろいろ変なこともするし、
国民に本当のことを知られないように
さったと進めてしまおうとしているんじゃないか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月03日
日本の新聞は時代に追いついていない
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
ネット社会の中では、
みんなが問題意識を持っているのが明らかなことでも、
新聞として正面から取り上げないというのは、
やはり日本の新聞が時代に追いついていないと
言われても仕方ないと思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年09月02日
日本の憲法に何が必要とされていたか
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
--- ニコール・ゴードン ---
ベアテは法律の学位より大切なものを持っていました。
それは日本を知り愛するが故、
日本に何が必要とされているかを正確に把握できる、
独自の経験と感性でした。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月31日
日本は憲法の人権先進国である
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
日本国憲法103条の内、
人権条項は31条あって、
全体の3文の1を占めている。
人権条項がこんなに威張っている憲法は
世界の中でもそんなに多くはない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月30日
平和でないと文化も技術も人権もなくなる
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
彼女の話を聞いていると、
平和でないと文化も芸術も育たないし、
基本的な人権も守られないということが、
ごく日常のこととして伝わってくる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月29日
女性が平和な世の中にできる
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
私は、世界の女性が手をつなげば、
平和な世の中にできるはずだと思っている。
地球上の半分は女性なのだから。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月28日
共通点
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
戦争の原因になっているのは、
宗教や領土、政治、経済と様々な理由があるが、
なぜ皆「違い」を強調するのだろうか。
どこの国の人でも共通点がずっと多いのに。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月27日
女性は平和を切望している
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
子供を産み、育てる。
子供の将来を考えれば、
どんな女性だって平和を切望している。
家庭を守るには
絶対に平和が必要だからだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月26日
世界を良くしていくのは、お母さん
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
これからの世界を良くしていくのは、
女性だと私は考えている。
女性、特にお母さんに期待している。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月23日
一流アーティストの共通点
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
名人と呼べれる人は、
とても頭が良くて、アイデアマンであることだ。
アイデアが豊富だというのは、
やはり日頃から練習に練習を重ねて、
どうしたら上手になるか考えているからだと思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月21日
日本は文化よりお金儲けにしか興味がない
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
日本は1970年に万国博覧会を成功させ、
高度経済成長の道をまっしぐらに進み、
貿易黒字国になっているのに、
お金儲けにしか興味はなかった。
がっかりした。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月20日
作品が芸術品になるためには
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
いくらよい作品でも、
他人の目に触れ、
評価されないと、
芸術品になり得ない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月15日
古いものと新しいもの
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
大事なことは、
古いものと新しいものを
何の法則も持たないで
まぜてしまってはならないということだ。
それをすると、
どちらの長所もなくなってしまうからである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月09日
安倍が言論の扉を閉めている
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
記者クラブの閉鎖性という以前の問題として、
安倍政権がメディアへの扉を閉じる傾向にあるんです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年08月08日
日本の女性を追いやる奴ら
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
日本の女性は、
私の書いた条項をフルに活用して
くれるだろうか。
奥さんや娘にいばりちらす男性は、
本当に少なくなるのだろうか。
主婦は財産の権利を持つように
なるのだろうか。
国が復興していけば、
まただんだんと保守的な勢力が強くなって、
女性は端に追いやられるのではないだろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年07月27日
日本の女子供のために憲法を書く
2018年07月24日
日本女性に人権は存在しなかった
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
日本女性には、
人権など存在しないのです!
女性は泣いています!
子供は、そのために
黙って死んでいっているのです!
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年07月23日
70年前から人権侵害は行われていた
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
人権侵害は、
日本では常識的に行われているのですよ!
民権という単語はありますが、
人権という日本語はまだないのです
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年07月22日
やがて日本中が鳥居だらけに
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
井戸やトイレにも
神様がいる日本文化は微笑ましいが、
戦争に勝つ度に
将軍が神様に祀られるとすると、
日本中が鳥居だらけになってしまう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年07月19日
国民がいなくったて議員でありたい?
河合雅司 著 「未来の年表2」から
『
北朝鮮の核・ミサイル開発も
日本にとって極めて大きな脅威である。
だが、出生数の下落は、
それと並ぶ国家の危機だ。
国の存続さえ危ぶまれるこの問題を
正面から議論しない議員は、
政治家としての資質を疑う。
』
水害で国民が死のうが、出生率が下がって国民がいなくなろうが、議員であることの方が重要な国会議員が多過ぎますネ。
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年07月18日
ジャーナリズムとして当然
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
実は望月さんがやっていることは、
ジャーナリズムとして当然の取材であり、
他の記者がそうしないことが変なのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年07月17日
日本のメディアは闘い慣れていない
望月衣塑子、マーティン・ファクラー 著 「権力と新聞の大問題」から
『
日本のメディアは、
日本の政治風土にやマスコミ文化に慣れているから、
安倍政権のようなやり方には慣れていない。
あっさり圧力に屈するような形になって
政権に利用されてしまう。
闘い慣れていないから、
すぐ負けてしまうのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年07月09日
治安維持法でデモクラシーが死んだ。共謀罪は?
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
大正時代デモクラシーを謳歌した日本が、
治安維持法という悪法で、
軍国主義一色に染め上げられたという歴史がある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年07月05日
日本国憲法は旧支配層により元の明治憲法に戻される懸念があった
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
封建的支配になれている日本人は、
面従腹背がひとつの生き方の文化になっている。
占領軍のおっしゃることだから
ご無理ごもっともと、
なんでもハイハイと従って、
強い人がいなくなったら、
さっさと改定してしまうかもしれない。
』
70年の時を経て、その懸念が現実のものとなりました。旧支配者層の孫が、憲法改正を声高に叫んでいます。
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年07月02日
女性の権利は明治の支配者にとって不都合だった
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
明治維新から先進文明を
積極的に取り入れた日本は、
人権、特に女性の権利に関する部分は、
支配者の男性にとっては不都合だったとみえて
ほとんど改革していない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月29日
男女平等は日本の平和の大前提
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
私は、女性が幸せにならなければ、
日本は平和にならないと思った。
男女平等は、その大前提だった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月28日
主権は完全に国民のものである
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
新しい憲法を起草するに当たって
強調しなければならない点は、
主権を完全に国民のものにする
というところにある。
天皇の立場は、
社交的君主の役割だけである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月27日
権力に対する制限をはっきりさせる
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
草案には、
細かな点を多く書き込む必要はない。
国民の基本的権利を譲るために必要な場合には
権力に対する制限をはっきり規定すべきだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月26日
軍隊式のやり方
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
いつまでに、何を、どうする、
という大筋が、
責任者からてきぱき伝えられる。
誰が、どういうふうにという細かいことは、
部下の仕事という分担である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月25日
権力は有権者が持っているのですよ!
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
日本人の歴史には、誰か権力者がいて、
その人のためには命をも投げ出すのが
美談だとする考えが根を張っているから、
「その権力はあなたが持っているのですよ!」
と、民主主義の原則を突然持って来られても、
戸惑うばかりなのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月24日
日本政府の憲法草案は明治憲法のままだった
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
諸君は、さる二月一日の毎日新聞がスクープした
日本政府の憲法草案について、知っていることと思う。
その内容は、
明治憲法とほとんど変わるところがない。
総司令部として
とても受け入れることはできないものである
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月22日
戦争は
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
戦争は、ピアニストに薪割りをさせることなのよ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月21日
日本人は職務につくと別人になる
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
日本人の一人ひとりは
善良でいい人なのに、
職務につくと別人に豹変してしまう。
どうしてあんなふうに
同じ人間でかわれるんだろうね
』
公文書改ざんだって、「問題なし」、になってしまう国なんですって!
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月20日
女性だって名誉が傷つけられた時は
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
女性だって自分の名前を
大事にしなくちゃいけません。
自分の名誉が傷つけられた時は、
果敢に戦わないといけません
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月19日
男たちが作り上げた構図の中で
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
男たちが作り上げた構図の中では、
女性や子供はいとも簡単にはじき飛ばされてしまう。
もうすぐ終わると言われながら、
いっこうに終結しないこの戦争だって、
男たちが始めたものではないか。
自由、平等の国で、私は女性の非力さを知った。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月18日
真珠湾攻撃
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
日本はなんてバカなことをしたんだ。
こんな巨大な国を相手に戦争をするなんて。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月14日
日本の聴衆はスゴイ
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
日本人は
自分たちの気に入った芸術家を
王様のように尊敬してくれるんだ。
日本人の聴衆は礼儀正しくて、知的なんだ。
日本は今にスゴイ国になるよ。
日本はヨーロッパと同じように、
長い歴史と文化を持っているんだ、
素晴らしい国だよ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月13日
戦争で生き残っても
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
生きていたのが幸せなのか、
死んだ方が幸せなのかわかりませんよ。
だってどうして生きていけばよいのか、
わからないもの
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月12日
日本女性参政権のための対価
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
婦人参政権を得るために、
日本の女性たちが家を焼かれ、
夫や息子を奪われ、
空腹と闘わなければならなかったとしたら、
なんと大きな対価を
支払わされたことだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月11日
日本人は集団になると過激になる
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝- から
『
日本人は本当に優しいのに、
集団になるとどういう訳か
過激になってします。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月08日
日本の道徳は自己犠牲を美化し過ぎる
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝-
『
日本の道徳は、
犠牲的精神を発揮する人物を、
必要以上に美化する。
その中にヒロイズムを感じる人も、
他の民族より多いように思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月07日
一歩前に出ない勇気
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝-
『
一歩前に出る勇気よりも、
一歩前に出ない勇気の方が
日本では難しいのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月06日
日本人は封建的民族
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝-
『
日本人というのは、
本質的に封建的な民族だと私は思う。
権力者の命令ならば、
たとえ気が進まなくとも実行する。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月05日
婦人参政権は日本の民主主義のテーマだった
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝-
『
日本の婦人の立場は、
極めて低いことは、
諸君も知っている通りだ。
婦人に参政権を与えることは、
日本人に民主主義とはこんなことだと
示すのに最良のテーマだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年06月04日
軍国主義者を追放する
ベアテ・シロタ・ゴードン 著 「1945年のクリスマス」-日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝-
『
ベアテ、我々の仕事は、
新しい民主主義の日本を建設するために、
軍国主義時代に要職についていた人物を
追放することなんだ。
』
軍国主義者は世代を越えて生き残り、太平洋戦争を企画した官僚の孫が、首相になって憲法を変えようとしています。
死神復活・・・
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月30日
理性に対する憎悪
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
現代における理性に対する憎悪は、
大部分、理性の機能が充分根本的な仕方で
把握されていないという事実に基づくものである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月28日
他人にとって寛大であることは
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
他の人々に対して広々とした
また寛大な態度をもつことは、
単に他人に幸福を与えるのみではない、
そうすることは
当人にとってもすばらしい幸福の源泉なのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月27日
人間は劣等感を持っていると
2018年05月25日
倫理は不合理なタブーの切れ端で出来ているから
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
今日こそ、
この世の正常な生活において
正常な役割を受け持つべき人々が
この病的なナンセンスに向かって
叛逆することを学ぶに至った時代にほかならぬ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月23日
道徳教育があったって
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
青少年たちに伝統的に
昔から与えられてきた道徳教育によって
果たしてこの世の中が
いくらでもよくなったかどうかを
まじめに諸君自身にたずねてみよ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月21日
不合理性と対峙する
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
不合理性を断じて尊敬しないという決意、
不合理性をして断じて諸君を支配せしめない
という決意をもって、
その不合理性を詳しく見つめるがいい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月20日
不合理性に支配されない
2018年05月18日
気分によって流されないこと
2018年05月17日
罪悪感が不幸をつくる
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
罪悪感こそ
成人の生活のなかの不幸を
つくりあげている深い心理的原因のうちで、
最も重要なものの一つであるからだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月15日
mindからheartへ
2018年05月11日
すべてはなんなのか
2018年05月10日
黎明期の技術
古橋 秀之 著 「百万光年のちょっと先」(電卓ジョニィの冒険)から
『
なににつけ
黎明期の技術というものは、
いにしえの精霊の如き
摩訶不思議な力を宿しているものです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月09日
一粒の砂
古橋 秀之 著 「百万光年のちょっと先」(韋駄天男と空歩きの靴)から
『
一粒の砂を地面に捨てるのは簡単でも、
再び拾い上げるのは、
とても難しいことなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月08日
幸運
古橋 秀之 著 「百万光年のちょっと先」(幸運な四人の男)から
『
俺は朝晩と毎食後に、
ロシアン・ルーレットを欠かさないんだ。
六つにひとつの命を、
1日5回拾い続けて、
もう3年になる
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月07日
最も望まない結果を引き出す
古橋 秀之 著 「百万光年のちょっと先」(憂鬱な不死身の兵隊)から
『
相手の望みの中から、
最も望まない結果を引き出すことこそが、
彼らのゲームであり、
存在の基礎そのものなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月06日
誕生前徴兵
古橋 秀之 著 「百万光年のちょっと先」(卵を割らなきゃオムレツは)から
『
ある国が考案したのが、
”誕生前徴兵”という制度、
培養された受精卵を、
人工子宮を兼ねた装甲服に入れて、
そのまま兵士として育てるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年05月03日
心配は恐怖で出来ている
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
心配は恐怖の一つの形式に
ほかならない。
そしてあらゆる形の恐怖は
疲労を持ちきたす。
恐怖を感じないように
自分をしつけてきた人間は
日常生活の疲労が
非常に少なくなっているのを
見出すだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年04月30日
失敗は感情から来る
2018年04月29日
疲労は暴走する
2018年04月22日
私たちは大地の生命の部分
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
私たちがたといどんなことを
考えたいと望むにもせよ、
私たちは所詮この地上の人間である。
私たちの生命は
この大地の生命の部分にすぎない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年04月20日
すばらしい中には単調がある
2018年04月19日
子供はいじられないときよく発達する
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
子供というものは、
ちょど若木のように同一の土壌のなかで
いじりまわされずにおかれているとき、
最もよく発達するものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年04月18日
子供へ快楽を与えるのではく
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
子供の快楽というものは、
だいたいにおいて、
子供みずからある程度の努力と発案によって
その環境のなかから
取り出すごときものであるべきである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年04月17日
単調な生活
2018年04月10日
小人閑居して不善を成す
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
道徳を云々する者にとっては、
退屈こそ一つの重要な問題である、
なぜなら、
少なくとも人類の罪悪の半分は
退屈を恐れるあまり
犯されたものであるからだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年04月05日
退屈とは
2018年03月30日
アメリカでは金銭的成功がすべて
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
ひととおり裕福にやっている
階級の全部にわたって、
経済的成功のためのムキ出しの、
容赦なき闘争を緩和するに足るものが
アメリカには一つもないのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年03月28日
禍いの根源
2018年03月27日
カネで得たいもの
2018年03月22日
恋愛は
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
恋愛はそれが
音楽とか山頂の日の出か
満月の下の大海というような
最もよき快楽を
いっそう大きくしてくれるものであり、
それゆえに、
高く評価さるべきものである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年03月21日
年取った独身者は
2018年03月20日
この世は
2018年03月17日
気分が理性によって決定されるなら
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
もし人間の気分が
理性によって決定されるということになれば、
世の中にはいつも愉快になるための理由と同じだけ
絶望するための理由があるものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年03月16日
感情が生み出されるとき
2018年03月15日
気分について
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
気分についてならば、
いかなる議論も必要でない。
なぜなら、
気分というものは
何かすてきなでき事があれば、
あるいはまた私たちの調子に変化があれば、
それによってどうにでも変わるものであるからだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年03月12日
部分の中の価値
2018年03月08日
権力への愛に支配されると
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
権力への愛によって完全に支配された人生は、
早晩、
うち勝つことのできぬ障害にぶつかって
挫折するよりほかはあり得ない。
』
Prime Minister Abe is governed by the love to power.
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年03月07日
卑屈感が誇大妄想狂を生む
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
誇大妄想狂は、
狂気のものにあるにせよ
あるいは一応正気のものにせよ、
ある種の行き過ぎた卑屈感の
生み出したものにほかならない。
』
Prime Minister Abe's mean feeling makes a constitutional amendment perform.
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年03月06日
誇大妄想狂とナルシシストの相違
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
誇大妄想狂とナルシシストの相違、
それは
前者がチャーミングであることよりも
力強くあることを欲し、
愛されることよりも
畏怖(いふ)されることを求める点にある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年03月05日
虚栄心は内気な臆病で起きる
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
虚栄心というものは、
それがある一点を越えるや否や、
活動そのもののための活動という
いっさいの活動のなかに含まれる
喜びを殺してしまう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年03月02日
政治家の失脚の原因
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
ひととおり成功した政治家たちが
次々と経験する失脚の悲劇は、
社会に対する関心、
その関心が要求するいろいろな施策の代わりに
だんだんとナルシシズムを
置き換えていくためである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年02月27日
ナルシシズム
B・ラッセル 著 「幸福論」から
『
ナルシシズムは、
ある意味において、
習慣的な罪悪感を裏返ししたものである。
なぜならそれは自分自身を賛美し、
またひとから賛美されたいという
習慣によって成立するものであるから。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年02月04日
実行の原動力
上杉志成 著 「京都大学アイデアが沸いてくる講義」から
『
真に商売で成功する人は、
「自分のアイデアが正しいことを証明するため」
に実行すると言います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年01月26日
考えない日本人
加藤 明 著 「「超」実用的 文章レトリック入門」から
『
佐藤愛子:
経済大国になった日本の社会は、
自由と豊かさによって
「考えない日本人」
を作り出した
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年01月19日
繰り返しと増幅の効果
上杉志成 著 「京都大学アイデアが沸いてくる講義」から
『
優れたミュージカルでは、
同じメロディーの繰り返しが単なる反復ではなく、
増幅となっていることです。
メロディーとともに、
ひとつ前の感情が次の感情を引き起こす
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年01月05日
報酬があるべきとき
上杉志成 著 「京都大学アイデアが沸いてくる講義」から
『
人の役に立つのは、
「問題を解決する」
ということです。
人の役に立ったとき、
困った人を助けたときに
報酬があるべきです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2018年01月02日
優れた科学者を生むためには
上杉志成 著 「京都大学アイデアが沸いてくる講義」から
『
自分がしなければいけない。
自分が世の中を変えるのだ。
自分がアイデアを思いついて、それを実行するのだ、
そんな積極的な姿勢が
優れた科学者を生むのかもしれません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年12月28日
ドラマは「転」に来る
加藤 明 著 「「超」実用的 文章レトリック入門」から
『
読む人に一番伝えたいことを
「転」で書きましょう。
例えば日常生活には
感動したことや驚いたこと、
何か発見したことなど
さまざまなドラマがあります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年12月27日
漸層法に騙される
加藤 明 著 「「超」実用的 文章レトリック入門」から
『
日本人は向上心が強いからでしょうか。
自己啓発本やノウハウ本が好きなようです。
内容は例外なく右肩上がりの漸層法。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年12月23日
笑いがない誇張法はうさん臭い
加藤 明 著 「「超」実用的 文章レトリック入門」から
『
重々しく大まじめな誇張法は、
どこかうさんくさい。
笑いのない誇張法には
危ないものがつきまとっている。
いつの時代にも、
そんな嗅覚が私たちに求められている
のではないでしょうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年12月22日
政治権力がデタラメな発表をやり放題になっているわけ
加藤 明 著 「「超」実用的 文章レトリック入門」から
『
たとえ専門家が間違いを指摘しても、
マスコミはそれを伝えない。
インターネット上の報道番組があるとはいえ、
まだまだ影響力は小さい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年12月19日
権力者が隠したいと思うことを明るみに出す
望月衣塑子 著 「新聞記者」から
『
私は特別なことはしていない。
権力者が隠したいと思うことを明るみに出す。
そのために、情熱をもって取材相手にあたる。
記者として持ち続けてきたテーマは変わらない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年12月18日
菅突っついたからこそ
望月衣塑子 著 「新聞記者」から
『
私は「空気を読まない」とよくいわれるが、
そのとおりだと思うし、
読もうとしていない。
だからこそ、菅さんは可能ならば
隠しておきたかった別の表情を
のぞかせるようになったのではないか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年12月17日
メディアが横方向でつながっていくことの重要性
望月衣塑子 著 「新聞記者」から
『
紙と電波、
あるいは新聞と雑誌といった垣根を飛び越えて、
メディアが横方向でつながっていくことが
状況によっては必要なのではとの考えは、
安倍政権になってさらに強くなった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年12月14日
記者が政権に忖度してどうするのか
望月衣塑子 著 「新聞記者」から
『
官房長官の意向を忖度しながら
一記者の揚げ足をあれこれ取るのではなく、
一記者の視点を持って官房長官に質問して、
その答えを記事にしてほしいと今は思っている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年12月11日
官房長官会見とは
望月衣塑子 著 「新聞記者」から
『
官房長官会見は、
政府の公式見解を聞くことが大切である一方で、
私たちが抱く疑念や疑問を率直にぶつけ、
政権中枢部にその姿勢を問うことができる場
でもあるはずだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年12月06日
時代錯誤の勅語【教育勅語】と邪心の法【現教育基本法】が結ばれた
2017年12月04日
現行の教育基本法は21世紀に通用しない
2017年12月03日
教育というのは黒子
望月衣塑子 著 「新聞記者」から
『
前川前次官の言葉
「
教育というのは黒子。
一番大切な現場は
先生と生徒がいる学びの場になる。
現場の先生がずっとうらやましかった。
だから、
現場で本当に学びのために
頑張っている人たちを
サポートしてみたいと思ったんですよ
」
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年11月29日
自己認識が婉曲すると
2017年11月17日
日本の納税者が環境汚染の加害者になっている
環境活動家・元米副大臣 アル・ゴアさんの言葉から
『
日本は、
インドネシアなど途上国における
新たな石炭火力発電所の建設を
支援する最大の国家なのです。
日本の納税者たちは自分の税金が、
巡り巡って環境汚染に使われている事実に
目を向けて欲しい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年11月13日
いいドラマとは
「ドクターX」を手掛ける、テレビ朝日 ゼネラルプロデューサー 内山 聖子さんの言葉から
『
その時代を生きる人の本音を
うまく“中継”できているのがいいドラマ。
それは常に意識しています
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年11月12日
毎週会いたかった、ヒロインとは
「ドクターX」を手掛ける、テレビ朝日 ゼネラルプロデューサー 内山 聖子さんの言葉から
『
私が視聴者として毎週会いたいのは、
行動を含めて本音で生きているヒロイン。
聖人君子みたいな役では
感情移入できないので
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年11月03日
2018年、安倍内閣が日本を統制経済にする
浜 矩子 著 「アホノミクス 完全崩壊に備えよ」
『
国民は銀行に殺到するが、時既に遅し。
既に銀行口座にはマイナンバーによる紐付けが終わっており、
1000万円を超えた部分は国債に切り換えられている上に、
その国債については売却を制限されてしまう。
しかも国債はマイナス金利で、
金利を政府に払わないといけない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年11月02日
GDP600兆円を抜けると、そこは日本崩壊だった
浜 矩子 著 「アホノミクス 完全崩壊に備えよ」
『
チーム・アホノミクスが
GDP600兆円を手繰(たぐ)り寄せようとして
気合を入れれば入れるほど、
完全崩壊をもたらす力学を
手繰り寄せることになる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年10月31日
ガールズバー化する日銀
浜 矩子 著 「アホノミクス 完全崩壊に備えよ」
『
何とも、天真爛漫すぎる。
あまりにも悩みを知らない中央銀行家を目の当たりにすると、
こちらの不安が募る。
』
The Bank of Japan is an optimist who ignores a debt.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年10月25日
大日本帝国会社の総師=安倍晋三
浜 矩子 著 「アホノミクス 完全崩壊に備えよ」
『
「攻めの経営」に挑め。
「大胆かつ前向きな判断」をしろ。
「取締役会の役割や
個々の取締役の責任の範囲を明確化」するから、
覚悟しておけ。
お殿様は、もはや、
完全に日本株式会社のCEOだ。
いや、違う。
大日本帝国会社の総師だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年10月22日
妖怪アホノミクスの鼻息
浜 矩子 著 「アホノミクス 完全崩壊に備えよ」
『
地方経済の巨大テーマパーク化を通じて、
新たなる列島改造を実現する、
その勢いで日本のGDPを戦後最大まで押し上げる、
この目論見が妖怪アホノミクスの鼻息を
一段と荒くする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年10月04日
アホノミクス的下心【安倍晋三の稚拙な世界観】
浜 矩子 著 「アホノミクス 完全崩壊に備えよ」
『
アホノミクスをもって富国の土台を強化する。
憲法改正をもって強兵の体制を整える。
この二つの踏み台からジャンプして、
大日本帝国に着地する。
これが、
アホノミクス的下心の基本構図だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年10月03日
下心政治と対峙する時
浜 矩子 著 「アホノミクス 完全崩壊に備えよ」
『
企業側も、
「動機は不純な奴らでも、
経済が元気になればまぁいいじゃないか」
式の発想で、
彼らに振り回されないようにして欲しい。
下心政治と対峙する時、
企業経営者の見識が問われる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年09月16日
「ド」つける
田辺 聖子 著 「ひよこのひとりごと」から
『
われわれ物書きは
映像の代わりにコトバで勝負、
という商売だからして、
いろいろなコトバを寄せ集め、
篩(ふるい)い分けて、選び出して、「ド」つけたんの。
やりにくい商売、やねんわ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年09月15日
黒犬のおいど
2017年09月13日
大阪はいつも笑い話
2017年09月07日
大阪には夢追い人も多い
田辺 聖子 著 「ひよこのひとりごと」から
『
大阪ニンゲンは
現実的といわれるけれど、
夢見屋サンも結構、
多いのである。
』
Although Osaka is a realist's city, there are also many people who like a dream.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年09月06日
大阪のドン・キホーテ
2017年09月04日
国民投票は簡単に操作される
コロンビア サントス大統領 の言葉から
『
私が学んだのは、
国の重大事項を決める時、
国民投票は適切な方法ではない
ということだ。
国民投票は
簡単に操作される。
問われたテーマではなく、
他の理由による投票が行われ、
目標が損なわれてしまう
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年09月03日
武力紛争や戦争は終わらせることができる
2017年08月31日
ちゃぶ台返し
田辺 聖子 著 「ひよこのひとりごと」から
『
ま、しかし考えてみると、
ひっくり返すのはいつも男、
というより、
弱い方なんである。
』
A weak man returns by violence.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年08月29日
乙女の清らかさが、世界の暗い心の窓を開ける
田辺 聖子 著 「ひよこのひとりごと」から
『
まだまどろみ深き日本の国
暗い心の窓をあけはなち
みよ 乙女らの
美と力と清らかさこそ
世の希望の星と讃えられました
』
A maiden's cleanliness opens the window of the dark heart in the world.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年08月25日
お芝居好きの願望
田辺 聖子 著 「ひよこのひとりごと」から
『
啄木は「こころよく我にはたらく仕事あれ・・・」
と歌ったが、たまには、
こころよく泣かせてくれるお芝居が観たいのも、
お芝居好きの願望である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年08月24日
女の永遠の夢
2017年08月23日
いいなあ、若い子って
2017年08月22日
天を恐れざる状態
田辺 聖子 著 「ひよこのひとりごと」から
『
七十女の人生経験に
四十女の体力があれば、
鬼に金棒、
それはあまりに天を恐れざる状態、
というべし。
』
With women's seventy-year-old wisdom and forty years old physical strength, they are unbeatable.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年08月12日
女の愛と誇り
田辺 聖子 著 「ひよこのひとりごと」から
『
現代の女たちは何を愛し、
何を誇りにしているのだろう。
「もったいない」
という感覚は、
いま何にさま変りしているのだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年08月11日
世の中の活気はどこから生まれるか
2017年08月03日
状況把握が第一歩
2017年08月02日
弱体な国では相手にされない
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
正しいことは言っても弱体な国に、
どこが従(つ)いていくだろうか。
理も、理になど耳を傾けたくない国にまで
耳を傾けさせるには、
何にしてもパワーが必要なのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年07月31日
コンパクト・シティとは
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン2」から
『
仕事に就きやすい場所に
多目的住宅を建設し、
支援施設とインフラの整備を行い、
社会的包摂と多様性を促進する。
』
A compact city aims at social inclusion.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年07月26日
求められるデザインの視野の拡大
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン2」から
『
現在求められているのは、
デザインの視野を拡大して、
安全な土地の確保、
実践可能な経済活動、
上下水道、
敷地の全体構想、
エネルギー利用、
気候変動、
されには医療、
教育、
コミュニティ活動といった
テーマを組み込むことだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年07月24日
生産者と消費者の尊厳
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
生産・消費のプロセスすべてに関わる人々の
「尊厳」という視点で見直すと、
繋がりはもっと根底にあることが見えてくる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年07月23日
利用する人の「尊厳」
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
製品・サービスを利用する人々の
「尊厳」についても考えを巡らすことが
出来ないだろうか。
考え始めるだけで、
世界を変えることができるのではないか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年07月20日
「尊厳」ある生活
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
自分の職業が
社会に果たしている役割を再認識し、
「尊厳」ある生活をするために
何をすればいいのか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年07月13日
人間の本当のニーズ
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
人間の本当のニーズを前にすれば、
たとえわずかでも
電力や明かりを提供するという議論は、
何も提供しないよりも説得力がある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年07月11日
新興市場
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
最高級の市場が
飽和状態になって初めて、
携帯電話産業のように、
人々の目が新興市場に向くのです。
私はこれこそが本当の
「市場」だと考えています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年07月10日
教育によって解決できるもの
2017年07月09日
楽しいと感じてもらう環境作り
志摩観光ホテル総料理長 樋口 宏江 さんの言葉から
『
メニューは私がおおかた決めますが、
「季節の野菜添え」にしておけば、
野菜は自由に変えられます。
若い子たちが考えたものを
出せるすき間を残す。
料理はひとりで作るのではなくて、
大勢の人と作り上げるから
働きがいがある。
楽しいと感じてもらう環境作りが
私の仕事なんです。
』
A manager's business makes a pleasant place of work.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年07月05日
人の尊厳が生まれるところ
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
自分自身と
自分の将来に投資すれば、
自分の成功は完全に自分のものとなり、
そこから尊厳が生まれる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月30日
買うとは評価したということ
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
人はものを評価するからこそ買うのであり、
買ったものは使う。
』
Since they evaluated the thing, they buy it.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月27日
貧困層ためのツールや技術は
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
貧困層のための
新しいツールや技術は、
非常に短時間のうちに、
ある程度の収入を生むものでなければならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月21日
自給自足の生活はもうできない
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
アフリカの最貧地域でさえ
自給自足の生活はもうできない。
金を稼ぐ手段がなければ、
生きられない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月20日
施しではなく機会
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
最も重要な教訓の一つは、
世界の最貧困層が
大いなる起業家精神をもつということだ。
生き延びるために
そうならざるをえない。
彼らが求めているのは
施しではなく、機会だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月19日
技術が世界の貧困を終わらせる
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
私はエンジニアとして、
世界の貧困という不幸を終わらせるのに、
技術が決定的な役割を果たすと信じている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月16日
開発途上地域向けのデザイン
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
開発途上地域向けの
デザインをするにあたっては、
自分がどんな状況のために
デザインしているのか、
また実際に製品を使うのは
どんな人たちなのか、
デザイナイーが十分理解
していることが非常に重要だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月15日
これまでの伝統に従っている限り
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
何十億という貧困層の顧客のいる
巨大な未発掘の市場が、
デザイナーと雇い主の企業によって
無視され続けている
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月13日
欧米では家があまりにも高いが
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
欧米では
家はあまりにも高くなり、
家をもつのは難しくなる一方だ。
驚くべきことに、
世界で、一日1ドル以下の収入で
農村に住む約8億人のほとんどは、
住む家をもっている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月12日
貧農業改善の最重要課題
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
初年度から採算がとれ、
その利益を使って
後から大幅に拡張していけるように、
システム全体を開発するのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月09日
10分と2日
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
非熟練労働者が1ドル稼ぐのに、
アメリカなら10分働けばいい。
一方、
バングラディシュやジンバブエでは
丸二日働かなくてはならないのだ。
』
A 10 minutes of the U.S. are equivalent to two day of Bangladesh.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月08日
27億人にとっての手頃な価格
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
手頃な値段がすべてなのではない。
手頃な値段しかないのだ
』
Only a cheap price is considered for 2,700 million people.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月06日
貧困層のためのデザイン
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
彼らが必要とするものは明らかで、シンプルだ。
貧しい人たちが喜んでお金を出す、
収入を生む新製品を考え出すのは、
さほど難しいことではない。
ただ、
手頃な価格でなくてはならない。
』
The product of a simple and cheap price is helpful to a poor person.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月05日
悲惨な状況に行動を起こせる
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
私の願いは、
依然として悲惨な状況に生きる
多くの人々がいることに、
そして私たち一人ひとりが
行動を起こせる
さまざまな方法があることに、
デザイナーや一般の人々に気づいて
もらえるよう
少しでも貢献することだ。
』
We can do support to people who live in a miserable situation.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月04日
デザインには何ができるか
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
水や食べ物、
住まい、
教育、
移動手段、
あるいはエネルギーを
手に入れる手段が乏しく、
命をつなぎ生活を維持していくのが
難しい人たちに、
その手段を提供しようと
働くデザイナーは、
世界中でますます増えている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年06月02日
高価だと持続可能でない
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
デザインは、
場合によっては高価すぎるために、
それを最も必要とする人たちにとって
手が届かず、
持続可能でないときがある。
』
An expensive design is not helpful.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年05月30日
自立していく経済構造は
シンシア・スミス 著 「世界を変えるデザイン」から
『
人々が技術を身につけてお金を稼ぎ、
自立していく経済構造を提供することによって、
人々の生活に影響を与え、
生活を変える。
』
Acquisition of technology will increase an income.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年05月19日
戦争回避
作家・作詞家 なかにし 礼 さんの言葉から
『
いま、日本の指導者は
「どんなことがあっても戦争は回避します」
と言うべきです。
戦争をしないという次元に向けてシフトを変えないから、
このままではいつか戦争になってしまいます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年05月09日
便利さは幸福に繋がらない
中村 明 著 「小津映画 粋な日本語」から
『
便利さは快楽とつながるが、
幸福とはつながらない。
そのため、
世の中に便利さが増えれば、
それだけ落ち着きが失われ、
人びとは幸福から遠ざかる
』
Although convenience is pleasure, it is not happy.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年03月16日
科学的シビリアン・コントロール
山口 栄一 著 「イノベーションはなぜ途絶えたか --科学立国日本の危機」から
『
文系には科学技術リテラシーを、
理系には社会的リテラシーを
身につけることが求められている。
』
We need technology and social science.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年03月14日
科学者の責任と役割
山口 栄一 著 「イノベーションはなぜ途絶えたか --科学立国日本の危機」から
『
科学者の責任と役割とは、
科学がどこで終わり、
トランス・サイエンスがどこで始まるかを
明確にすることだ。
』
The scientist should clarify that it is solvable by science.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年02月19日
全体主義的な社会は滑稽
大橋巨泉 著 「それでも僕は前を向く」から
『
いま考えたら滑稽(こっけい)で、
信じられないような話だけれど、
軍国主義、全体主義的な社会になってしまうと、
先にあげたジャズや野球まで禁止するような
バカバカしいことが
まかり通ってしまうから怖い。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年02月07日
近隣諸国とのちょとトラブルを大騒ぎする輩
大橋巨泉 著 「それでも僕は前を向く」から
『
近隣諸国と
ちょっとトラブルになったときなど、
ほら大変だといった調子のコメントを
連発する連中が出てくる。
』
The Shintoism zombie makes a great uproar in a trouble with neighboring countries.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年02月03日
戦争は強盗のように単純な話ではない
大橋巨泉 著 「それでも僕は前を向く」から
『
強盗に対する戸締りと、
国家間の究極の戦いである戦争とを
同一に論じるのは
あまりにもバカバカしすぎる。
』
It is foolish to consider that war and a burglar are the same.
かつて、安倍首相が集団的自衛権を、隣の火事に例えてテレビで自慢げにプレゼンしてましたっけ。
この人、「正真正銘のアホちゃうか!」と皆が口々に言っていましたね。
トランプ大統領も同じくらいのレベルなので、来週の日米首脳会談は意気投合しそうですよ!
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年01月27日
一人前の人間がいない
大橋巨泉 著 「それでも僕は前を向く」から
『
現代は半人前の人間が多すぎる。
いや、半人前どころか、
十分の一人前くらいがぞろぞろ、
というのが本当のところかもしれない。
』
There are too many inexperienced human beings among the worlds.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年01月17日
無理やり変化させる力
ウォルター・アイザックソン 著 「スティーブ・ジョブズII」から
『
他人を傷つけないように気を遣う
優しくて礼儀正しいリーダーは、
無理やり変化させる力が弱い。
』
A polite leader has the weak power of causing change.
- Permalink
- by
- at 00:00
2017年01月15日
残酷なほど正直
2017年01月12日
やることがたくさんある
ウォルター・アイザックソン 著 「スティーブ・ジョブズII」から
『
みんな、
自分が得意なことで忙しくしていて、
僕らには僕らが得意なことを
してほしいと望んでいる。
みんな、
自分の暮らしは満杯状態なんだ、
コンピュータと機器をつなぐには
どうしたらいいかを考える以外に、
やることがたくさんあるのだよ
』
I do not want to make time useless by operation of a computer.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年12月30日
すべての面が非凡な人はいない
ウォルター・アイザックソン 著 「スティーブ・ジョブズII」から
『
すばらしい才能に恵まれた人の多くが
そうだと思うのですが、
あの人も、
すべての面で非凡なわけではありません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年12月21日
礒崎 陽輔はReptilia
2016年12月20日
人権は国民が権力から身を守るための武器
小林節、佐高信 著 「安倍「壊憲」を撃つ」から
『
憲法というのは、
そもそも国家権力から国民を守るという前提があるから、
国民に人権を与えて、
国家権力はそれを守る義務があるわけです。
万一、権力を乱用して
国家権力がフライングしてきたときは、
国民が人権侵害だとして押し返せるように、
国民の側に、
身を守るための人権を保障した。
』
Human rights are the arms for people protecting themselves from power.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年12月15日
人間は個性ある存在だからこそ人権がある
小林節、佐高信 著 「安倍「壊憲」を撃つ」から
『
人間一人一人の個性が
他に代わりの利かない
尊いものであるからこそ、
人権がある。
人間は個性ある存在、
個人であって、人ではない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年12月12日
ネットの意見は多数派ではない
作家・演出家 鴻上 尚史 さんの言葉から
『
新聞やテレビでは
自分の関心がないことも
目に入ってきますが、
ネットでは自分の見たいものしか
見えません。
でも海の向こうには、
未知の広大な大陸があるのです。
』
It is the world of the Internet that only a thing to see is visible.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年12月07日
格差を政治権力に真剣に考えさせるべき
独マックス・プランク社会研究所 名誉会長 社会学者 ヴォルフガング・シュトレーク さんの言葉から
『
毎日仕事に出かけ、
子育てに追われる普通の人々が、
政治から遠ざけられてきました。
富だけでなく、
政治へのアクセスをめぐる格差の広がりが
何をもたらしたのか、
政治権力に真剣に考えさせるべきです。
彼らは臆病なので、
人々が立ち上がれば
向き合わざるを得なくなります
』
It is necessary to make a political force recognize a national gap.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年11月21日
負の未来を勝たせないために
米社会学者 イマニュエル・ウォーラーステイン さんの言葉から
『
大切なのは、決して諦めないことです。
諦めてしまえば、
負の未来が勝つでしょう。
民主的で平等なシステムを願うならば、
どんなに不透明な社会状況が続くとしても、
あなたは絶えず、
前向きに未来を
求め続けなければいけません
』
If it gives up, the negative future will win.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年10月30日
政治家が人の心に寄りそうということ
テレビドラマ「ドクターX 外科医 大門未知子 シーズン4 エピソード2」から
『
政治家は、人の心に寄り添わにゃいけん。
愛人一人に寄り添ったから、
たたかれるんだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年10月21日
憲法を奪還する
樋口陽一、小林節 著 「憲法改正の真実」から
『
「戦後レジュームからの脱却」
と言いつつ、
対米従属は強化し、
そのくせ国民に対しては
戦後の自由の価値を否定して、
東アジア的な専制をねらう。
この体制が定着しないうちに、
憲法を奪還しなくてはなりません。
』
We have to recapture the constitution from the Abe Administration.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年10月17日
真実はネットに宿る
テレビドラマ「ドクターX 外科医 大門未知子 シーズン4 エピソード1」から
『
ネットのデマの方が
真実ってこともあるよネ。
』
The information on the Internet has truth.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年10月14日
国民には「知る義務」がある
樋口陽一、小林節 著 「憲法改正の真実」から
『
「知る義務」
という言葉で私が言いたかったのは、
我々の公共の社会を維持し、
運営していくために必要なことを
「知る義務」が国民にはあると
いうことです。
』
The people have to know national activity.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年10月04日
あったかい家庭があったら戦争にならない
大橋鎭子 著 「「暮しの手帖」とわたし」から
『
君も知ってのとおり、
国は軍国主義一色になり、
誰もかれもが、
なだれをうって
戦争に突っ込んでいったのは、
ひとりひとりが、
自分の暮らしを
大切にしなかったからだと思う。
もしみんなに、
あったかい家庭があったなら、
戦争にならなかったと思う
』
If everybody has a warm home, war will not break out.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年10月03日
9条が世界の信頼を築いてきた
樋口陽一、小林節 著 「憲法改正の真実」から
『
九条を戦後、
ずっと保守してきたことの価値が出てくるのです。
日本政府の戦争責任に対する姿勢は
不十分なものであった。
しかし、主権者たる国民が、
九条を廃棄させずに、保守してきたことが、
世界の多くの人々のあいだで
信頼を受ける日本という地位を
かろうじて築いてきたのです。
』
Article 9 of the constitution has built reliance in the world.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年09月29日
戦争はなんでもない人を死まで追い込む
大橋鎭子 著 「「暮しの手帖」とわたし」から
『
もう二度とこんな恐ろしい戦争をしないような
世の中にしていくためのものを作りたいということだ。
戦争は恐ろしい。
なんでもない人たちを巻きこんで、
末は死までに追い込んでしまう。
戦争を反対しなくてはいけない。
君はそのことがわかるか
』
War makes an ordinary person die.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年09月15日
男はんには任せておけん
長尾 剛 著 「広岡浅子 気高き生涯」から
『
やっぱり、
この国の女子(おなご)を引っ張って、
女子の役割を開拓していくのは、
日本の女子や。
男はんには任せておけん
』
A Japanese woman extends a Japanese woman's possibility.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年08月29日
他人に頼らない
長尾 剛 著 「広岡浅子 気高き生涯」から
『
浅子は、
目の前に何かしらの問題が起きるたびに、
それを一人で解決しようとする人間だった。
そして浅子には、
それを可能にする力もあった。
否(いな)、
彼女はその力を、
ひたすらの努力で獲得していったのだ。
』
Asako solved the problem alone.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年08月28日
他人に頭を下げること
長尾 剛 著 「広岡浅子 気高き生涯」から
『
浅子は
「他人に頭を下げること」
がきちんとできる女である。
「他人に頭を下げること」
の辛さを、よく知っている女である。
』
Apologizing to others is hard.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年08月23日
古代日本には「男尊女卑」はなかった
長尾 剛 著 「広岡浅子 気高き生涯」から
『
他の文化圏とは違い、
日本の女性たちは、
紛(まご)うことなく戦場を駆け回り、
身を呈して戦った。
こんなことがありえたのも、
日本という文化圏はには、
「女は男より弱い。女は男より劣っている」
という世界ではほぼ共通している
「人類普遍の常識」が、
なかったからである。
』
Ancient Japan did not have predominance of men over women.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年08月04日
すべてが自己責任ではない
宮崎 学 著 「「自己啓発病」社会」から
『
この主張によれば、
成功するも失敗するも、
すべては自己責任に帰するわけである。
その結果、零落したものは
「努力を怠ったため」
と切り捨てられ、
本人もそう思い、
自らのふがいなさを恥じる。
』
The insufficiency of social security is not national self-responsibility.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年07月19日
国の本当の繁栄とは
宮崎 学 著 「「自己啓発病」社会」から
『
本当の繁栄とは何か。
国の富がどれほど大きく、
物資の製造の方法手段がどれほど完備していても、
それだけでは、国が栄えているとはいえない。
「国民が有職であり
有徳であるが上に
確乎(かっこ)な品性を具(そな)へて居(お)るのこそ本当の繁栄」
である。
』
In order for a country to prosper, people have to have knowledge, virtue, and character.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年07月17日
人類社会が学んできたもの
樋口陽一、小林節 著 「憲法改正の真実」から
『
人類社会は
間違いを繰り返しながらも、
苦心惨たんして、
国民の自己決定と
個人の自由との均衡を
どうやってとるかということを、
高い授業料を払いながら
学んできているのです。
』
Human beings have worried about a democratic determination and individual freedom.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年07月11日
目先の選挙ではなく長期的で賢明な判断が必要
投資家 ジム・ロジャーズさんの言葉から
『
政治家は長期的な視野に立たず、
目先の選挙で物事を判断しがちですが、
日本は賢明な判断をしなければなりません
』
Japan needs eager judgment.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年06月15日
人権は独立して存在する
樋口陽一、小林節 著 「憲法改正の真実」から
『
憲法に書かれようが書かれまいが、
人は生まれながらに権利をもっているんだと
言っている。
』
Even if not written to the constitution, people have human rights.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年06月14日
国民は人権をもっている
樋口陽一、小林節 著 「憲法改正の真実」から
『
我々、国民は
もともと人権をもっていて、
それを尊重、擁護する義務は国側にある。
これは代償的な関係ではない。
』
People have human rights and a state is obligated to protect it.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年06月13日
期待外れの政治家は選挙で落とせばいいだけ
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
現代の私たちには
政治家をわざわざ暗殺する必要はない。
期待はずれと判断したら、
選挙で落とせばいいだけのことだし、
それ以外にもスキャンダルで
退陣に追い込むという手もある。
』
The disappointing politician should just make it defeated.
東京都知事みたいに、連日スキャンダルが報道されても辞めない人もいます。
そんな人には、・・・
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
私の考えならば、
それほどの攻撃を受けても
しぶとく生き残るとは
なかなかの人材であるかもしれず、
だったら、もう一回は
チャンスを与えてみてもよいのでは、
と思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年06月09日
駅はわかりやすく
赤瀬 達三 著 「駅をデザインする」から
『
駅をデザインする目的は、
リンチの都市デザインとまったく同様に、
「イメージアビリティ」をつくり出すこと、
またその裏づけとして、
利用者にとっての
「わかりやすさ」を追求することだ。
』
A design is making an image activity.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年06月08日
ローマの法
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
「ローマの法」とは、
人種や宗教に関係なく、
すべての人に公正で平等な権利を保証すること、
それによって共生を可能にすること
』
Law guarantees an equal and fair right to all people.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年06月02日
なぜローマ帝国があれほど長く続いたか
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
歴史家ギボンは、
「ローマ帝国がなぜ滅びたかを学ぶよりも、
なぜローマ帝国があれほど長く続いたかに
注意を向けるべきである」
と書き残しています。
』
Note that the Roman Empire continued for a long time.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年05月31日
古代ローマの消費税は1パーセント
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
ローマの場合は
「百分の一税」という名称のとおり、
その税率はわずかに1パーセント。
3パーセントから5パーセントへと増税され、
さらにまた上がるのではと囁かれる
日本の消費税に比べたら、
問題にならないくらいの低率です。
』
The consumption tax of Japan has got drunk.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年05月30日
古典とは
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
書物も音楽も、
絵画も彫刻も、
作品(オペラ)は後世に遺る。
すぐれていればいるほど、
後の世に遺る可能性は高くなり、
より多くの人々を幸福にしてくれることになるのだ。
人はそれを、「古典」と呼ぶ。
』
The outstanding art makes people in future generations happy.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年05月16日
お手軽だと
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
手軽は、上手に年をとるには、
あらゆることの敵である。
』
The handiness takes pleasure of life.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年04月22日
ケンカは巧みにする必要がある
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
ときには、ケンカしたっていいのだ。
ただし、
ケンカは巧みにする必要はある。
なるべく、いや必ず、
相手の土俵にあがって、
相手方の手法にのっとって
ケンカする必要があると思う。
そうすれば、
ケンカがケンカに終わらない。
』
It is necessary to carry out a quarrel by the technique of an enemy.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年04月20日
人間とロボットを分けるもの
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
人類はいつの日か、
人間並みの頭脳をもった
ロボットはつくれるようになるにちがいないが、
人間並みの不安をもつロボットは、
つくれないと思うからである。
』
The robot which does suspicion and fear cannot be made.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年04月12日
人間性を無視したことを望む者は
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
人間性を無視したことを望む者は、
人間社会に生きる身である以上、
不幸にならずにはすまない。
』
If humanity is disregarded, it will certainly become a misfortune.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年04月11日
スタイルとは強い信念のこと
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
スタイルとは、
見せかけの反対である。
強い信念のことである。
』
A style is a strong belief.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年04月10日
自分の限界は無理だと思ったときに現れる
インド・アーメダバードメトロ プロジェクトマネージャ 阿部 玲子さんの言葉から
『
私は元々、努力家ではありません。
何もハンディのない男性だったら、
ごくふつうにやっただけでしょう。
女性だったからこそ、ここまで来た
』
It is a time of thinking that its limit is impossible.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年04月05日
恋愛に恵まれるわけではない
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
恋愛は、
あらゆる人に恵まれるわけではない。
死は、あらゆる人を見舞うが、
恋愛は、誰にも起こる現象ではない。
』
Love is not a phenomenon which happens to anyone.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年03月31日
より強い武器持つことやあらしまへん
NHK朝ドラ 「あさが来た」から
『
今度の戦争は勝ったとしても、
またすぐに、より大きい戦争が起こります。
そのときに大事なんは、
より強い武器持つことやあらしまへん。
お商売だす。
経済的に国を豊かにすることで、
外交の力、増して行かなあきまへん。
』
It wins not by powerful arms but by the power of diplomacy.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年03月29日
映画は自分で観るのが一番
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
映画とは、
他の芸術作品、文学、美術、
その他モロモロの芸術作品と同じで、
言葉では一万言費やし
批評したところで無駄なのだ。
』
You should appreciate the movie rather than criticizing.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年03月27日
解説屋の仕事
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
解説屋の仕事は、
そのどこを斬っても、
赤い血は出ない。
彼ら自身の肉体も、
どこを斬っても
赤い血は出ないのではないかとさえ
思わせる。
』
Those who do business of description do not have man's heart.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年03月25日
言葉は視覚の召使い
スティーブン・キャネル
『
もの書きの鍵は抽象的な思考である。
書く原動力はイメージ力であり、
言葉は視覚イメージの召使いでしかない
』
Language is a domestic of a vision image.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年03月23日
真のラディカル
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
男でも女でも、
くさって悪臭しか発しないような、
感情的な対立は
やめたらどうだろう。
理性的な方法で「対決」することこそ、
世代の断絶をほんとうの意味でなくす、
唯一の方策だと信ずる。
』
It confronts rationally from an emotional confrontation.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年03月21日
女性の柔らかい力が大切
NHK朝ドラ 「あさが来た」から
『
みんなが、
笑って暮らせる世の中を作るには、
女性のね、
柔らかい力が大切なんです。
』
A good world is made from female soft power.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年03月13日
外部世界をニュートラルに見る
解剖学者 養老 孟司 さんの言葉から
『
外部世界をニュートラルに
見ない社会は狂ってしまいます。
既成のシステムも、
その時限り、今の状況に過ぎないのに、
これからも未来永劫、
維持されると思い込む。
それは頭の中毒です。
中毒の行き着く先は原理主義です
』
The mad society does not look at the world neutrally.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年03月08日
高貴なるものの義務
佐藤尚之 著 「明日のプランニング」から
『
Noblesse Oblige(ノブレス・オブリージュ)という言葉がある。
貴族を指して言われる言葉で、
「高貴なるものの義務」を意味し、
一般的には地位や財産、
権力などを持つものには
責任が伴うというニュアンスで使われる。
』
The person with a status, property, and power is accompanied by responsibility.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年02月12日
デザインとは
岩井理子 訳 「変革の知」から
『
知的再生産は進歩と言えます。
創意性を持って
進歩を成し遂げる過程が
デザインです。
』
A design is progressing creatively.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年01月27日
世界をマシにするには
井上ひさし 著 「井上ひさしの読書眼鏡」から
『
わたしたちが
少しでもマシに生きるなら、
世界もその分だけ
マシなものに変動するのです。
』
The world will also become good if he lives well.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年01月18日
大人しさと弱さは同義語ではない
岩井理子 訳 「変革の知」から
『
大人しさと弱さは同義語ではありません。
非常に強いけれども
シャイな人がいます。
彼らは攻撃的も外交的でもないですが、
それでも彼らは決して弱いわけではありません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年01月05日
自分が楽しんだということ
岩井理子 訳 「変革の知」から
『
すべての人を満足させることはできませんから。
大事なのは、
自分がそれを楽しんだという事実です。
』
It is important to work by your enjoying yourself.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年01月03日
理想の実現には辛抱が必要
「広岡浅子」の言葉から
『
理想はそう簡単に
実現できるものではありません。
五十年、百年の辛抱で
はじめて実現できるのです。
』
Realization of an ideal requires the years of patience.
- Permalink
- by
- at 00:00
2016年01月01日
日一日と進む
「広岡浅子」の言葉から
『
世の中は、
日一日と進むものです。
今日は昨日より、
明日は今日より
進歩したものでなければなりません。
』
The tomorrow have to progress from today.
今年は去年より、自由と民主主義の進歩を目指したい。
「戦前や明治時代がいい」、「戦前や明治時代を取り戻す」などと思っている宰相や政治家は、浅子が生きていたならば蹴散らされていたことでしょう。
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年12月30日
女だって社会をつくる一員なんや
「広岡浅子」の言葉から
『
女だって社会をつくる一員なんや、
ちゃんとした教育を受ければ
男と同じくらい働けるはずや。
だから、教育の機会を与えなあかん
』
A woman is a member who makes society.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年12月27日
大阪にこの国の未来が掛かっている
NHKドラマ「あさが来た」から
『
大阪商人の知恵と経験、
そして、誇りこそが
世界と渡り合えるのだ。
大阪にこの国の未来が掛かっている
』
In order to fight against the world economy, the Osaka merchant's wisdom and experience are required.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年12月17日
女子のつまらない国は衰える
「【超訳】広岡浅子 自伝」から
『
昔から
国の存亡興廃の跡を尋ねてみると、
女子のつまらない国は衰えます。
』
The country where a woman does not play an active part declines.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年12月14日
男女の能力差はない
「【超訳】広岡浅子 自伝」から
『
男女は能力や胆力においては
特別の相違はありません。
それどころか、
女子は男子にさほど劣らないと思いました。
』
Man and woman do not have a difference in capability or courage.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年12月13日
男の才能の一つ
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
忙しい中にも
女のために時間をつくるのも、
男の才能の一つではないかと。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年12月10日
愛をもって互いに仕え合う
「【超訳】広岡浅子 自伝」から
『
今後は国の政治であれ、
国際間の関係であれ、
この軍国主義を捨てて、
愛をもって互いに仕え合う境地に
進まなければなりません。
』
Peace is realized not with military affairs but with love.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年12月09日
元気で留守がいい
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
相手の自由を拘束してみたいと思うのは、
魅力を感ずる人に対してだけである。
それ以外は、
元気で留守がいい、
という部類に入ってします。
』
Please you be fine,and please be in your absence.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年12月08日
忙しいことは才能があることではない
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
男というのはオカシな動物で、
自分が才能豊かな男であることと
忙しいことは、
比例の関係にあると思いこんでいる。
』
A busy thing is not capable.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年12月06日
動きを知らない男
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
顔だちは美男だが、
動きを知らない男は、
所詮、
われわれ女の血を
騒がせることはできないのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年12月03日
オトナを判別する
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
若者に必要なのは、
ほんとうの「オトナ」と、
反対に理解の顔をしたがる
つまらないオトナを、
判別する能力である。
』
The young man should feel the real adult.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年12月02日
過去をふり返る余裕はない
歴史読本 「広岡浅子」から
『
新しい時代を生きる者たちは、
世の凄まじい変貌に翻弄され
過去をふり返る余裕もない。
』
A new era does not make people look at the past.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年11月29日
戦争法案を離れて真の民主主義へ
「【超訳】広岡浅子 自伝」から
『
この思想こそ
人類が剣戟(けんげき)を振るって、
尊い血を流し合うことを理想とする
軍国主義を離れて、
互いの幸福を増し、
公平な神の恩寵(おんちょう)を
享(う)けるに堪(た)えるものとする
民本主義に移っていく一大傾向であります。
』
You should increase not a sword but mutual happiness.
浅子が100年前に言った言葉ですから。集団的自衛権は過去の理念です。
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年11月26日
内的生命の消耗
「【超訳】広岡浅子 自伝」から
『
今日、
我が国の富豪成金らは、
日に日にその内的生命の消耗に
腐心する用意ばかりしています。
世界にも変えがたき生き物を
わずかな物質のために渡しつつあるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年11月24日
世代の断絶が創る
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
各世代に断絶があるからこそ、
次の世代は新しいものを創りだせるのである。
新しいものを創りだすエネルギーを、
貯えることができるのである。
』
A generation's rupture makes a new thing.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年11月22日
乱世
歴史読本 「広岡浅子」から
『
農民階級から天下人となった
豊臣秀吉が現れたように、
乱世にはそれまでの階層を超越して
世に名をしらしめる英雄が現れるものである。
』
Turbulent days bear the hero who transcended the time.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年11月19日
女性としての長所を発揮する
「【超訳】広岡浅子 自伝」から
『
今はいろいろな方面で、
同じ仕事をするにしても、
女子としての長所を発揮し、
繊細さとか、
優麗さなどの、
婦人としての特性を
磨いて進んで行くというように
なりつつあるのは、
非常に喜ばしい傾向であると思います。
』
A woman works gracefully and delicately.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年11月12日
殺し文句
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
「殺し文句」とは、
剣を使わずに相手を殺す方法であり、
平和的な殺人手段である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年11月10日
「殺し文句」の功罪
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
「殺し文句」の功罪の功の最たるものは、
人生に色どりを与えてくれるということだろう。
』
A stylish phrase is the food of life.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年11月04日
教訓と刺激
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
教訓は、
上の者が下の者に与えるものであり、
刺激は、
平等の者か下位の者が、
上位者に対する時の、
優雅で効果的な武器である。
』
Stimuli are the arms to a higher rank person.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年10月26日
嘘とは
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
嘘とは、
真実を言っていては
実現不可能な場合に効力を発揮する、
人間性の深い洞察に基づいた、
高等な技術の成果なのである。
バカにはできることではない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年10月18日
装うとは
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
装うとは、
着る人間がどのような個性で生きたいかで、
決まるものだと私は信じている。
だからこそ、素晴らしいのだ。
』
A way of life appears in a dress.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年10月12日
自信のない男の多い国
塩野 七生 著 「男たちへ フツウの男をフツウでない男にするための54章」から
『
日本という国は、
知的な面で有名な女を、
コワイなんて子供じみた表現で
敬遠することしか知らない、
自信のない男の多い国である。
』
Japan is a country with many diffident men.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年10月11日
異分野融合
京都大学学際融合研究所 推進センター准教授 宮野公樹 さんの言葉から
『
同じ日本語を話すからといって、
自然にコミュニケーションは進みません。
学問の文化や風土を無視したままで
異分野融合が進むことはないでしょう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年09月15日
真の「積極的平和」とは
丸山重威 著 「安倍壊憲クーデターとメディア支配―アベ政治を許さない」から
『
直接的に、
戦争、搾取、帝国主義などの
暴力がないだけでなく
構造や文化で
それを肯定するものもなくしていくことこそ
「積極的な平和」の考え方です。
』
True positive peace is that there is no culture which affirms violence.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年09月14日
安倍政権はナチス・ヒットラーにそっくり
丸山重威 著 「安倍壊憲クーデターとメディア支配―アベ政治を許さない」から
『
「非戦・非武装」の日本国憲法はそのままにして、
「憲法解釈変更は政府が可能」、
「法的安定性など実は関係ない」
などと憲法違反の法律を作って、
実質的に憲法を変え、
いつの間にか
国の在り方を変えてしまおうとする
安倍政権のやり方は
ナチス・ヒットラーにそっくりです。
』
The Abe Administration is just like the Nazis.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年09月06日
贅沢な清貧
ファッション・デザイナー 馬 可(マーコー)さんの言葉から
『
環境に負荷をかける
大量生産・大量消費をやめ、
最も簡単で基本的な
生活や服に回帰したい、
「贅沢な清貧を目指したい」
と考えるようになったのです。
』
I would like to aim at extravagant honorable poverty.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年08月30日
マインドフルな状態
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
自分がマインドフルな状態であれば、
計画やプロセスに囚われることなく
目の前の問題に専念できる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年08月28日
戦争法案が成立して向かう先
ノルウェーの平和学者 ヨハン・ガルトゥング さんの言葉から
『
日本が米国と軍事力を
一体化させていけば、
中東で米国の主導する作戦に
従事することになるでしょう。
そうなれば、
植民地主義の継続に加担してしまいます。
』
Japan's joining the U.S. military strength is participating in colonialism.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年08月25日
デザインは創造的なヒント
有馬トモユキ 著 「いいデザイナーは、見ためのよさから考えない」から
『
デザインは、
物事をシンプルに、
わかりやすく、
使いやすく、
安全にするための創造的なヒントです。
』
A design is a creative hint for making things simply intelligibly, in a user friendly manner, and safe.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年08月23日
目の前の変化にオープンになる
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
組織や集団では、
計画や過去のやり方にこだわるあまり、
目の前の変化にオープンになっていないことが多い。
』
In an organization, it adheres to the past way and change is not accepted.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年08月16日
映画がどこかに存在している
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
映画の要素はすべて存在し、
つくり手に見つけられるのを待っている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年08月13日
知ることは愛することに通じる
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
知ることは愛することに通じるという格言があるが、
知らないものを、
どうやって愛することができるだろうか。
』
Getting to know leads to loving.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年08月12日
日本語が亡びる
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
日本語を<国語>として
護らねばならないという合意が
日本人のあいだに生まれなければ、
この先、
いったいどうなるか。
』
Japanese is used only in one country called Japan.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年08月11日
母語を使えるありがた味
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
日本では母語の地位が脅かされた歴史はなく、
母語を使えることのありがた味が実感されることはない。
』
In Japan, there is no history in which the status of the native language was threatened.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年08月07日
日本語は人類の財産
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
フランス人には内緒だが、
そんなおもしろい表記法をもった日本語が
「亡びる」のは、
あの栄光あるフランス語が「亡びる」よりも、
人類にとってよほど大きな損失である。
』
It is the loss by human beings that Japanese is ruined.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年08月03日
失敗を避けると失敗しやすくなる
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
初心を捨てることで、
人は何か新しいものをつくり出すよりも、
前にやったことを繰り返すようになる。
言い換えれば、
失敗を避けようとして
失敗しやすくなる。
』
Since we do not fail, we come to repeat having done before.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年07月30日
日本文学の善し悪しがわかるのは
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
いくらグローバルな<文化商品>が存在しようと、
真にグローバルな文学など存在しえない。
』
There is no global literature in a true meaning.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年07月28日
管理するが測定できない
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
人が管理するものの大部分は、
測定できない。
そこには気づかないと
予期せぬ結果を招く。
』
We have managed what cannot be measured.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年07月15日
言葉は読めなければ意味がない
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
言葉だけは、
まったく次元のちがったメディア=媒体なのである。
言葉というものは、
読めなければ、まるで意味がない。
』
If language cannot be read, it is completely meaningless.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年07月13日
書き言葉
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
人間には<書き言葉>を通じてのみしか
理解できないことがある。
<書き言葉>を通じてのみしか得られない
快楽もあれば、感動もある。
』
A written word has special pleasure and impression.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年07月09日
消費者の嗜好とは
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
二十世紀最高のプリマドンナ、マリア・カラス
の歌を聴きたい人が、
財布の中身と相談し、泣く泣く、
二十世紀末のポップスの女王、マドンナ
の歌を買ってがまんしたりすることはない。
』
The Madonna does not become Mary's substitute.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年07月08日
芸術の崇高なところ
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
小説の場合も、
もっとも多くの人に売れるもの、
すなわち、
もっとも<流通価値>をもつものが、
もっとも<文学価値>をもつとは限らない。
それが芸術の崇高なところである。
』
A best-selling book does not necessarily have literary value.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年07月03日
現実は言葉を介してみている
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
<現実>は
たんにモノとしてそこに物理的に
存在しているわけではない。
人間にとっての<現実>は
常に言葉を介してしか
見えてこないものだからである。
』
Reality is seen through language.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年07月02日
可能にした条件
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
日本に大学があるのを可能にした条件は、
まさに日本が西洋列強の植民地に
なる運命を免れたことにあった。
』
A university is located in Japan because it did not become a colony.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年06月25日
学問とは
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
学問とは、
<読まれるべき言葉>の連鎖にほかならず、
その本質において、
<普遍語>でなされてあたりまえなのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年06月24日
書き言葉の本質
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
<書き言葉>の本質は、
書かれた言葉にはなく、
読むという行為にあるのである。
』
The essence of a written word is the act of reading.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年06月23日
限られた公平さしかない
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
この世には
限られた公平さしかない。
善人は報われず、
優れた文学も
日の目を見ずに終わる。
』
The fairness in this world is restricted.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年06月22日
砂像の魅力
砂像彫刻家 茶圓勝彦さんの言葉から
『
砂像の魅力は、
いずれ消えてなくなるはかなさ。
僕たちが手がけた砂像も、
魔法が解けたように
やがてもとの砂にかえっていくのです。
』
Not having disappeared is the charm of the sculpture by sand.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年06月11日
芸術と技術
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
芸術は技術を挑発し、
技術は芸術に刺激を与える
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年06月09日
金の塊が控えているがごとく
水村美苗 著 「日本語が亡びるとき」から
『
いくら日本の景気が悪いといわれても、
世界の中での日本の経済力の強さは、
まるで金の塊がうしろにずしりと
控えているがごとく
頼もしく感じられるものであった。
』
A golden lump is behind Japanese economy.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年05月24日
協調性と自己視点
植木安弘 著 「国連広報官に学ぶ 問題解決力の磨き方」から
『
協調性と自己視点の確立は
一見背反するように見えるが、
実はその両方とも大事な点である。
』
Establishment of cooperativeness and a self-viewpoint is important.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年05月17日
リーダーの本当の謙虚さ
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
自分の人生や事業が
目に見えない多くの要因によって
決定づけられてきたこと、
そしてこれからも
そうあり続けることを
理解するところから始まる。
』
Life is determined by the factor which is not a foregone conclusion.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年05月07日
目標は必要に応じて変えていい
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
新たな情報を得て、
自分がわかっていたつもりで
わかっていなかったことに驚いたら、
オープンに目標を
変えるべきだということだ。
』
You should change the target, if you do not understand new information.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年03月22日
日本人はアメリカよりイギリスを好む
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
イギリス人と日本人は、
revolution(改革)よりも
evolution(改良)を好む。
イギリス人の趣味である
ガーデニングを、
日本人女性は好む。
イギリス人の故ダイアナ妃を、
アメリカのヒラリー・クリントンよりも、
日本人女性は好む。
』
British people and Japanese people like evolution better than revolution.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年03月21日
「結婚」と「自立」の困難性
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
「結婚」の呪縛が強烈な日本では、
「自立」を志向する女性は、
「自立」を望めば望むほど、
根源的な欠落感に襲われ、
引き裂かれていく。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年03月20日
家庭という繭玉の中で
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
日本には、
「大人の女」というロール・モデルが
いまだ存在しない。
愛と承認を強く求める
日本の女の子には
「少女」のままで、
家庭という繭玉の中で
永遠に夢を紡ぐという
生き方が許されている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年03月19日
日本人はリンゴの木が好き
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
日本人は、
この日常生活では普段あまり見慣れない果実の木が、
柿や蜜柑よりはるかに好きなのだ。
その酸っぱくて甘い果実は、
「甘美で優美な生活スタイル」を
象徴するものである。
』
In Japan, an apple is a symbol of a sweet and graceful life style.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年03月18日
結婚という制度は
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
「結婚」は
女性という集団(下位身分)アイデンティティを獲得させ、
社会全体の制度秩序を温存させる制度である
と言ってもいい。
』
Marriage makes a woman a low rank status.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年03月17日
女性にとって日本人の男性に負けるのは屈辱的
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
日本人の男は、
アメリカに負けた男だ。
それも、戦争に負けた上に、
戦後の国交回復の過程で
「安保」という形で
アメリカに再び負けた男だ。
女性が、
どうせ男性に負ける運命にあるのなら、
日本人の男性に負けることほど
屈辱的なものはない。
』
For a Japanese woman, being defeated by the Japanese male is humiliating.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年03月08日
邪悪なものが入り込んできた
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
しあわせな暮らしのなかに、
邪悪なものが入り込んできた。
なんとかハッピーエンドになってほしい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年03月06日
白い羊
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
「幸福を」を目指し、
実際それを手に入れたとき、
その対象を欲望した他の「白い羊」
という媒介項は消滅し、
人は手に入れたものと
自分だけの孤独な世界にいることに気づく。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年03月05日
人が最も愛する者
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
人が、
最も愛している者は、
それを愛する理由を与えてくれた者、
すなわち
愛を媒介してくれた者である。
』
Those whom people love most are those who gave the reason to love.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年03月04日
愛しているは愛されたい
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
「愛している」
という感情は、その人に
「愛されたい」
という感情のことである。
』
The feeling of loving is feeling to be loved by the person.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年02月24日
決して妥協しない
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
この会社はけっして妥協しない。
失敗しないという意味ではない。
創造に失敗はつきものだ。
だが失敗したときには、
自己弁護せずに向き合い、
変化を厭わない。
』
A compromise is not made even if it makes a mistake.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年02月23日
品質が生き方であるべき
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
品質が大事だと誰もが言うが、
言う前に実行すべきだ。
品質は日常の一部であり、
考え方であり、
生き方であるべきだ。
』
The quality should be a way of life.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年02月20日
世界は魑魅魍魎に満ち溢れている
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
世界は、
理性によって眺めれば空虚なものだが、
神秘主義を通して見ると
物語のように魑魅魍魎(ちみもうりょう)に
満ち溢れて見えた。
』
The world is filled to evil spirits of mountains and forests.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年02月06日
常識が覆される
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
自分が信じていた常識が
見事に覆(くつがえ)される
眩暈(めまい)のような驚き。
それが、
「明日」ではなく、「きょう」、
目の前で起こったのだ。
』
The common sense which we believed was reversed.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年01月28日
物語がきちんとさえしていれば
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
美術的な技巧を凝らそうと、
物語がきちんとさえしていれば、
視覚的に洗練されているかどうかなど
問題にならないのだ。
』
The vision effect is not needed if it is a wonderful story.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年01月27日
残虐な支配者
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
(預言者)ムハンマドのスピーチは、
寛大な慈悲の心を示すものだったのに、
この人たち(タリバン)のスピーチは、
残虐な支配者の権威を示すものばかりだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年01月23日
美的図式
小倉 千加子 著 「「赤毛のアン」の秘密」から
『
風景とは、
人間にとって
「世界を知覚さるべきものとして
人間に見せるように定められた
美的図式」
である。
』
Scenery is a diagram which man can perceive.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年01月21日
宇宙全体が示し合わせて
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
人がなにかを手に入れたいと思ったら、
宇宙全体が示し合わせて、
その手伝いをしてくれる
』
If it thinks that you will realize something, the whole universe will help.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年01月20日
爆発音か銃声
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
わたしたちの生活には、
そういう恐怖がいつもつきまとっている。
ちょっとでも揺れたり大きな音がしたりすると、
爆発音か銃声だと思ってしまう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年01月16日
人類の自己満足
ブライアン・クリスチャン 著 「機械より人間らしくなれるか?」から
『
僕らは風邪をひくことに対して
不思議なほど恐怖心を持たず、
自分は進化の頂点にいる生物の一員なのだと
偉そうにしているにもかかわらず、
単細胞生物のせいで
丸二日も寝込んだりするのである。
』
Man is made illness by the monadic.
- Permalink
- by
- at 00:00
2015年01月12日
卓越性とは
エド・キャットムル 著、 エイミー・ワラス 著 「ピクサー流 創造するちから―小さな可能性から、大きな価値を生み出す方法」から
『
品質のよさを表す「卓越性」は、
自分で自分のことを言うのではなく、
人から言われるべき言葉だ。
』
Excellence is the language which should be said by people.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年12月20日
コンピュータ詩人がいたら
ブライアン・クリスチャン 著 「機械より人間らしくなれるか?」から
『
コンピュータ詩人といものが
もし存在するとしたら、
コンピュータ国税庁監査役や
コンピュータチェス棋士と比べて、
はるかに恐ろしい気がする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年12月17日
悪人の言葉を信じてはいけない
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
悪人がどんなにいいことを言っても、
ききいれてはいけない
』
Don't believe a bad man's words.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年12月04日
創造のあとに目的が考えられた
ブライアン・クリスチャン 著 「機械より人間らしくなれるか?」から
『
コンピュータは実質的に、
その実存が目的に先んじる最初の道具となった。
コンピュータがホチキスや穴あけパンチや懐中時計と
決定的に違うのはこの点である。
』
The computer was able to consider the use, after being made.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年12月03日
AIはターミネーターではなく遊び人になる
ブライアン・クリスチャン 著 「機械より人間らしくなれるか?」から
『
機械が残虐なゲリラのリーダーではなく
世の中に嫌気が差した遊び人のように
振る舞う可能性のほうが高いと思いたい。
』
A.I.(Artificial Intelligence) becomes a jobless person instead of a Terminator.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年11月19日
自分の幸福にとって重要な行動
ブライアン・クリスチャン 著 「機械より人間らしくなれるか?」から
『
ほぼ無意識の低レベルの行動のほうが、
意識的な高レベルの行動よりも
自分の幸福にとって
ずっと重要だということにも気づく。
』
Action of a low level is important for man's happiness.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年11月18日
IQを二倍にする
ブライアン・クリスチャン 著 「機械より人間らしくなれるか?」から
『
驚くべきことに、
責任を与えて相手を信じていることを示した途端、
彼らのIQが二倍になったかのように思われた
』
If responsibility is given, IQ will double.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年11月17日
人間は自分をメソッドで置き換えようとしている
ブライアン・クリスチャン 著 「機械より人間らしくなれるか?」から
『
人間は人間自身を
「機械」に置き換えようとしているもでも、
「コンピュータ」と置き換えようとしているのでもなく、
「メソッド」と置き換えようとしているのだ。
』
Man is going to replace man's method.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年11月14日
コンピュータが人間を解放する
ブライアン・クリスチャン 著 「機械より人間らしくなれるか?」から
『
自ら唯一性を守るため、
他の生物や機械を締め出そうとして
人間が築いてき城壁は、
人間をその内側に取り残す
役目も果たしてしまった。
コンピュータは、
その城壁にある最後の扉を打ち破り、
人間を解放してくれた。
』
Humanity was released by computer.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年11月11日
因果は正しく説明されるとは限らない
ブライアン・クリスチャン 著 「機械より人間らしくなれるか?」から
『
原因と結果のあいだの溝を
もっともらしい理屈で埋める能力があっても、
人は少しも理性的にも、
賢明にも、
道徳的にもならないのだ。
』
A cause and an effect are not explained by reason.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年11月05日
アメリカ人の芸術で気にするところ
ブライアン・クリスチャン 著 「機械より人間らしくなれるか?」から
『
アメリカ人の芸術というものは変わっている。
アメリカ人は、
自分のビジョンがどこを向いているかは気にするが、
だれのビジョンであるかは気にしないらしい。
』
Although Americans care about the taste of their vision, the proposer of the vision does not care.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年11月04日
タリバン退治マシン
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
わたしは発明家になりたいと思った。
タリバン退治マシンを作るのだ。
タリバン兵をにおいで感知して、
持っている銃を破壊する。
』
I would like to make the machine which destroys the gun which Taliban has.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年10月29日
ただ人間らしくしていればいい
ブライアン・クリスチャン 著 「機械より人間らしくなれるか?」から
『
実際、君が知っておくことは
もうほとんどないよ。
君は本物の人間なのだから、
ただ人間らしくしていればいい
』
You are man. Therefore, act humanly.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年10月28日
女性の権利のために
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
わたしもあそこに行って、
女性の権利のために戦わなければ
』
It fights for a female right.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年10月27日
タリバンは芸術と文化と歴史の敵
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
タリバンは、
芸術と文化と歴史の敵になっていた。
古いものをことごとく破壊してしまう。
といって、新しいものをもたらすわけでもない。
』
Taliban destroys art, culture, and history. However, a new thing does not produce.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年10月24日
タリバンは音楽を取りあげた
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
タリバンはまず、
わたしたちから音楽を取りあげ、
次に仏像を取りあげた。
それから、
私たちの歴史を奪った。
』
Taliban deprived us of music.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年10月21日
武装勢力のやり方
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
これが武装勢力のやりかただ。
人々の心をつかむために、
まずは地域がどんな問題を抱えているか調べて、
その問題の責任者をやり玉にあげる。
そうやって、声なき大多数(サイレント・マジョリティー)の
支持を得るんだ。
』
An armed group deceives and governs people.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年10月17日
コーランを曲げて解釈する宗教指導者が多い
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
音楽をきくな、映画をみるな、ダンスをするな、
といいだした。
そういう罪深いことをしているから
地震が起こったのだ、それをやめないと、
ふたたび神の怒りを招くという。
コーランやハディースを曲げて解釈する
宗教指導者はよくいる。
原典のアラビア語がわかる人は
めったにいないからだ。
』
There are many religion leaders whom Arabian does not understand.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年10月16日
命が危険にさらされたとき
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
大きな災害にあったときや、
命が危険にさらされたとき、
人間は自分のおかした罪を思い出して、
どんな顔をして神様に会えばいいのか、
神様は自分を許してくれるだろうか、
と考えるものだと思う。
』
Does God allow me?
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年10月13日
【21世紀を変えた10人の女性】この世界をすばらしいものにしたいのです
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
神様、神様はすべてをみていらっしゃると思います。
でも、もしかしたら、
みのがしていることも
たくさんあるのではありませんか。
・・・
どうか、
力と勇気をください。
わたしをなんでもできる子にしてください。
この世界をすばらしいものにしたいのです。
』
I would like to make this world wonderful.
ノーベル平和賞を受賞されたマララ・ユスフザイさんは、将来きっと、「21世紀を変えた10人の女性」となることでしょう。
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年10月12日
権威
野内 良三 著 「日本語作文術」から
『
人が権威に弱いことには驚くばかりだ。
メディアでもなにかといえば、
その道の大家の意見を求める。
』
People believe authority.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年09月30日
人を殺してはならない
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
ワールドトレードセンターにいた人々にはなんの罪もないし、
アメリカの政策とは無関係だ。
それに、
コーランには「人を殺してはならない」と書いてある。
そういうことを無視していいのだろうか。
』
It has written to the Koran "Don't kill people."
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年09月23日
書くことは引用することである
野内 良三 著 「日本語作文術」から
『
文を盗む、
いや、拝借すること
文章に対するこのスタンスを
私は「引用」と呼んだまでである。
文章はカタチからはいる、
これが大切である。
』
Writing a text is quoting.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年09月11日
自由とは何をしてもいいということではない
浜 矩子 著 「地球経済のまわり方」から
『
自由だということは、
何をしてもいいということではない。
人々がお互いに相手の自由を尊重する。
それが、
人々が等しく自由であるための基本原理だ。
』
Freedom is not carrying out anything.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年09月10日
グローバル・ジャングル
浜 矩子 著 「地球経済のまわり方」から
『
カネがヒトを振り回す。
ヒトがいたずらにモノを奪い合う。
そんな光景が、
グローバル・ジャングルを何やら不気味、
闇深きものにしている。
』
Money is governing people.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年09月09日
格差の広がりが健康長寿を脅かす
ハーバード大学公衆衛生大学院教授 イチロー・カワチ さんの言葉から
『
日本では、
人と人とのきずなや信頼関係が、
健康長寿の土壌になってきた。
だが、非正規雇用の拡大などによる格差の広がりが、
こうした土壌をむしばんでしまわないか懸念している。
』
If the gap of wealth and poverty spreads, the environment of a long life will be lost.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年09月07日
いまや状況は変わった
2014年09月04日
円安が進行すれば
浜 矩子 著 「地球経済のまわり方」から
『
円安が進行すれば、
企業の生産コストが上がる。
家計にとっても物価上昇で
生活が圧迫されることになる。
豊かさの中の貧困にあえぐ人々にとっては、
死活問題となるかもしれない。
』
Prices go up with low yen and a life is pressed.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年08月30日
とんでもない自滅のコース
浜 矩子 著 「地球経済のまわり方」から
『
このような事態に至る現象を
「合成の誤謬(ごびゅう)」という。
個別的にみれば合理的な事柄を総合=合成してみると、
とんでもない自滅のコースにつながっている状態である。
』
It may be ruined in case of rational solution.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年08月29日
教育にもっと予算
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
父は、政治家が原子爆弾なんかに
大金をつぎこまなければ、
教育にもっと予算をまわせるのに、
といっていた。
』
An education expense changes to a bomb.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年08月28日
9・11
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
あのときのわたしたちには、
9・11の事件がわたしたちの世界を変えることになるなんて
わたしたちの渓谷が戦争に踏みにじられることになるなんて、
知るはずもなかった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年08月27日
経済とは世を治め民を苦しみから救うこと
浜 矩子 著 「地球経済のまわり方」から
『
経済という言い方は
「経世済民」から来ている。
世を治め、民を苦しみから救う。
これぞ権力者として
唯一至高の経済活動だ。
』
Economy is governing a world and saving people from pain.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年08月21日
役人は市民の下僕である
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
政府の役人たちが、
わたしたちより偉いはずがありません。
彼らはわたしたち市民の下僕なんです。
』
A government official is me under citizens.
- Permalink
- by
- at 01:30
2014年08月20日
命令に従うこと重視はうんざり
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
偏見のない広い心や創造性よりも、
命令に素直に従うことを重視するような学校に、
うんざりしていたのだ。
』
The school which attaches importance to following a command is not needed.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年08月19日
情けは人のためならず
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
困っている人に親切にしてあげると、
自分も思わぬときに助けられる。
』
He will also be saved if people are helped.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年08月18日
政治家にだまされていることに気づかない
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
無知な人々は、
政治家にだまされていることに気づかない。
悪い人間を、
選挙でまた選んでしまう。
』
Ignorant people do not notice what is deceived by the politician.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年08月15日
8月15日だからアナ雪を観にいってきます
今日は家族で「アナと雪の女王」を映画館へ観にいって来ます。
この映画、すでにDVDを持っていますが、大画面で観ておきたいので行くことにしました。
8月15は「敗戦記念日」(終戦記念日ともいう)。個を犠牲にして全体主義に走った日本の末路を記念する日です。
8月15日の反省もなく、昨今、また全体主義が復活してきています。
・集団的自衛権
・会社のために残業代をゼロにする
・会社全体効率化のための成果主義による個の犠牲強要
日本という国は、放っておくとすぐ “全体主義” に向かって行く国家なのです。
そんなとき、アナ雪の「Let it go」は、“全体ではなく個” を訴えて、“個” を無理やり抑え込まれている人々(特に女性)への応援歌にもなっています。これが大ヒットの秘密なのでしょう。
だから8月15日はアナ雪を観るのです。
![]() Let 9条 Go! (エルサ【憲法9条】を抹殺しようとしたハンス【安倍首相】から、アナ【日本国民】はエルサを救えるか?)
Let 9条 Go! (エルサ【憲法9条】を抹殺しようとしたハンス【安倍首相】から、アナ【日本国民】はエルサを救えるか?)
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年08月12日
ふたつの力より強い力
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
パキスタン建国の父ジンナーはこういっている。
「男女が力を合わせなければ、
なにごとも達成などできない。
世の中にはふたつの力がある。
剣の力とペンの力だ。
そしてもうひとつ、それらより強い力がある。
それは、女性の力だ」
』
There is 2 power in a world.
They are the power of a sword, and the power of a pen.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年08月11日
格差が大きいのはよくない
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
祖父は、
古くからの階級制度をなんとかしなくてはならないと、
いつもいっていた。
カーンが力を持ちつづけるのもよくないし、
“豊かな者” と “貧しい者” の
格差が大きいのもよくない、と。
』
The thing with a large gap of "a rich person" and "a poor person" is not good.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年08月08日
情報戦国時代
栗田 哲也 著 「数学による思考のレッスン」から
『
現代の日本ではすでに
「専門家の解説」
というお墨付きだけでは
信用できなくなっている。
だから徐々に、
「誰を信じ。誰を主君として選べば得しそうか」
という情報の「戦国時代」になりつつあるのだ
』
It cannot be trusted only by a specialist's description.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年07月28日
アレキサンダー大王のように
マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・ラム 著 「わたしはマララ: 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女」から
『
いつかはわたしも
アレキサンダー大王のように
イラム山にのぼって、
木星に触れてみたい。
』
I would like to touch Jupiter.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年07月22日
定食学の基礎
今 柊二 著 「定食学入門」から
『
●外からメニューがわかり、店内の様子も覗ける店を選べ
●明るい店内と気持ちのよい接客に着目せよ
●豊富な小鉢とお代り自由のシステムは栄養面でもありがたい
●女性客が多い店は、清潔で居心地がいい
』
Abundant one-cup meals are the charm of the restaurant serving everyday meals in Japan.
この本、アマゾンでは新品は扱っていないのですが、ジュンク堂書店では書籍棚に堂々と置かれていました。これが書店の魅力ですね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年07月04日
安易な増税は反乱をもたらす
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
安易な増税を行なえば、
それは住民の不満を招き、
やがては反乱をも引き起こす。
これは古今東西、
変わることのない真実です。
』
A rebellion occurs by the forced tax increase.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年07月03日
「外なる平和」と「内なる平和」
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
たとえ外敵の排除には成功しても、
国内においても治安が保たれ、
その中で暮らす人々が
安心して生活を送れなければ意味がない。
』
Domestic will not become safe even if it wins war.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年06月12日
死体の山ではなく
映画 「アイアンマン」から
『
世界に何かを残したいんだ。
死体の山ではなく!
』
It leaves not a gun but a good thing to the world.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年05月14日
自分が見たいと欲することしか見えない
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
人間ならば誰にでも
すべてが見えるわけではない。
多くの人は
自分が見たいと欲することしか見ていない
』
Many people look at only the thing which one want to see.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年04月12日
政策には光と影の部分がある
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
ある政策を行なえば、
一方には救われる人がいるが、
その対極に、
新政策によって既得権を失う人たちがいて、
当然のことながら
その実現を必死に妨害しようとする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年04月10日
国家とは住民共同体
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
国家は一部の特権階級や
個人の利益のためにあるのではない。
国家の目的は、その中で暮らす人々の
幸福を高めることにあるのだというのが、
一貫したローマ人の思想でした。
』
The national purpose is to raise people's happiness.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年03月31日
命を懸けて争うような違いはない
ドラマ 「ごちそうさん」から
『
日本人も、アメリカ人も、
食べなければ生きていかれへンから、
きっと、同じなんですよネ。
忘れんようにせんと、アきませんネ。
命を懸(か)けて争うような違いは
なンもないっていうこってすよネ。
』
There is no difference to the extent that man fights risking his life.
NHK朝ドラの「ごちそうさん」が終わりました。地味でしたが脚本がよく出来ており、日本社会に対する皮肉やメッセージが一杯散りばめられていました。
まあ、お間抜けなNHK会長やジンジャー・エール・アベには分からない(分からなくて幸い)でしょうがネ。
※【ジンジャー・エール・アベ】 ジンジャー(靖国神社)へエール(参拝)ばかりする安倍 晋三氏のこと
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年03月24日
生活の中の美
山口 周 著 「世界で最もイノベーティブな組織の作り方」から
『
生活の中から失われた「美」は、
やがてそこに暮らす人の感性をも鈍麻させます。
』
Feeling will be paralyzed if beauty is lost out of a life.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年03月12日
紙のみぞ知る
作家 荒保宏 さんの言葉から
『
紙の本は長い歴史を経た
完成形のメディア。
家具としはまったく厄介だが、
電子書籍には置き換えられない
』
The books of paper are the completed media.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年03月07日
大阪は巨大自由都市
井上 理津子 著 「はじまりは大阪にあり」から
『
私はその成功を
大阪という巨大な自由都市、
奔放な庶民文化の背景と
むすびつけることにおいて、
一層の意義を痛感する
』
Osaka is a city with huge freedom.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年03月05日
自由は権力に対する防衛
駒野 剛 さんの言葉から
『
自由は全ての時代を通じて
無法な権力に対する唯一の防衛だ
』
日本国憲法 第24条
『
集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由は、これを保障する。
』
Freedom is most effective means to oppose power.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年02月25日
攻めの時代、守りの時代
2014年02月23日
消費税増額の恨み
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
「カネの恨み」は古今東西変わらない。
それが誰一人、
好きな人のいない、税金となれば
なおさらのことです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年02月22日
外務官僚たちの巧みなずる賢さ
佐高 信、佐藤 優 著 「世界と闘う「読書術」 思想を鍛える一〇〇〇冊」から
『
命令者になるということを
巧みに隠しながら
無責任な体系の中に入っていく天才が
外務官僚たちですからね。
』
A Foreign Ministry bureaucrat is slick.

- Permalink
- by
- at 00:00
2014年02月19日
政治の捉え方が間違っている
映画監督・テレビディレクター 是枝 裕和 さんの言葉から
『
非常に難しいことにあたるからこそ
権力が与えられ、
高い歳費が払われているわけでしょ?
それがいつからか
選挙に勝った人間がやりたいようにやるのが政治だ、
となっている。
』
In Japan, if it wins in an election, it will become a dictator.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年02月18日
安倍政権を支持する浅はかさ
映画監督・テレビディレクター 是枝 裕和 さんの言葉から
『
安倍政権を支持している私たちの根っこにある、
この浅はかさとはいったい何なのか、
長い目で見て、
この日本社会や
日本人を成熟させていくには
何が必要なのかを考えなくてはいけません
』
The shallow-brained Japanese is supporting the Abe Administration.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年02月14日
自分たちにないものを移植してもうまくいかない
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
どんな民族であろうと、
どんな組織であろうと、
自分たちの体質にまったくないものを
外部から持ってきて移植して
うまくいくはずはない。
』
By the system which does not suit itself, it cannot do well.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年02月13日
真の改革とは
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
真の改革とは結局のところ、
リストラクチャリング、
つまり再構築をすること
』
A true reform is restructuring.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年02月09日
夢がキャタピラに潰された時代があった
ドラマ 「ごちそうさん」から
『
夢がキャタピラに
つぶされる時代になったんです。
夢を叶えるには、
才能や根性やなく
生き残ることです。
』
It is surviving in order to fulfill a dream.
ジンジャー・エール・アベが、たくさんの人の「夢を壊した時代(太平洋戦争)」を、肯定するのは理解できません。「秘密保護法」で文句を言わせず、道徳と歴史の教育を通じた徹底的な思想教育で、「夢を壊した時代」を「正しかった時代」にしようとしています。
※【ジンジャー・エール・アベ】 ジンジャー(靖国神社)へエール(参拝)ばかりする安倍 晋三氏のこと
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年02月08日
日本人の特質であり強みであるもの
和僑総会会長 筒井 修 さんの言葉から
『
製造業はコスト面で厳しいけれど、
日本人の「思いやり」の精神は
世界のどこへ行っても評価されます。
財布を落としても出てくるのは日本だけ。
面識のない人のことを
「困っていない?」と我がことのように
心配できるのは日本人の特質であり強みです。
』
Future Japan should export consideration.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年02月07日
ごはんは夢をかなえる
2014年02月06日
日本はガラパゴス
和僑総会会長 筒井 修 さんの言葉から
『
世界を見ない日本は、
国全体が「ガラパゴス化」して衰退する。
』
Since Japan is not looking at the world, it declines.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月31日
老楽国家
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
グローバル時代に、
ここまで成熟した経済社会は日本しかない。
我々はグローバル時代という舞台で
老楽国家の華麗な姿を見せることができる
』
Japan is the only economic society which ripened in global age.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月28日
思い違いの国際人
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
国際人は英語がぺらぺらしゃべれて、
外国へ飛んで向こうのビジネスマンと商談なんかが
てきぱきできる人のことで、
いまの世の中、
そういう当世風の人がはばをきかしている
』
Internationally-minded persons are not those who can speak English.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月27日
あなたの時代は終わったのですよ
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
誰でも苦(にが)い現実は見たくない。
ことに「自分は成功した」という想いを持った人たちに
「あなたの時代は終わったのですよ」
と言っても、
そのような苦言を快く聴き容(い)れる人はいない。
』
Your time was over.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月23日
戦争の勝敗を左右するもの
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
戦争とは
偶然の連続でもあります。
戦場では誰も予想もしなかった
出来事がしばしば起き、
それが時として勝敗を左右する。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月22日
これからの広告
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
これからの広告に可能性があるとすれば、
夢の実現化のためのアイデアを出したり、
実現のために集まった人びとの運動を支援したり
するようなところにある
』
The advertisement of the future proposes the idea for realization of a dream.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月21日
広告はいらだちを倍増させる
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
広告はおいしい生活の夢を見せてくれるけど、
それを実現する上での
現実的な障害を取り除いてくれるわけではないので、
結果的にはいらだちを倍増させるだけだ
』
An advertisement does not show how to realize.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月20日
フラダンスは神々への祈り
映画「フラガール」の平山まどかのモデル 早川和子 さんの言葉から
『
ステージを見にいらした方の心が華やぎ、
新たな希望を胸に抱いて
日常に戻って頂くことが
あなた方の大切な仕事です。
』
The gay stage of a Hula induces a new hope.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月18日
魔法
ドラマ 「ワンスアポンアタイム」から
『
みんな魔法のような結果を求めているのに、
魔法を信じていない。
』
Magic is not believed although a result like magic is searched for wholly.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月17日
人間を人間とみない企業の顔は
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
お金を儲け、
組織が大きくなるにつれて、
企業の顔はノッペラボーなお面みたいな顔になっていく。
』
A company will become unfeeling if an organization becomes large.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月15日
「巨人の星」が好きな奴はインテリジェンスに不向き
佐高 信、佐藤 優 著 「世界と闘う「読書術」 思想を鍛える一〇〇〇冊」から
『
「巨人の星」が好きなやつは、
絶対にインテリジェンスの世界に
来てもらっては困るんです。
つまり、揺るぎない、
絶対的な正義基準を持っている人。
』
For justice, an intelligence is not made by any means.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月13日
日本人は疑うことにより信じることを尊ぶ
佐高 信、佐藤 優 著 「世界と闘う「読書術」 思想を鍛える一〇〇〇冊」から
『
日本人は疑うことにより信じることを尊ぶ。
それで疑問によって
鍛えられていない軽信がはびこる。
』
Japanese people believe rather than suspecting.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月11日
大量生産と大量消費の行き詰まり
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
大量生産と大量消費の歯車を回し続けるためには、
何がなんでも消費者の「ほしいもの」を
次々に作り出さなければなりません。
それがもう、
どうにもならないところまできてしまった
』
Mass production lost the thing needed.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月10日
新しい日本の国づくりへ
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
政治家の人たちも、
憲法をいじったり
原発の再稼働をはかったり
するヒマがあったら、
経済大国や軍事大国は
米さんや中さんにまかせて、
新しい日本の国づくりに
取り組んでほしいものです。
』
You should perform new nation-building.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月09日
贅沢は“素”敵だ
佐高 信、佐藤 優 著 「世界と闘う「読書術」 思想を鍛える一〇〇〇冊」から
『
戦争中の「贅沢は敵だ」という標語に
「素」を書き加えて
「贅沢は素敵だ」
と揶揄(やゆ)した、
あのセンスなんですよね。
』
Luxury is great.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月08日
国民は天ちゃんの赤子ではない
佐高 信、佐藤 優 著 「世界と闘う「読書術」 思想を鍛える一〇〇〇冊」から
『
国家の暴力性を隠蔽するときは必ず、
「家族国家観」ということをいい出す。
』
The Japanese are not the Emperor's retainer.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月07日
家族観を国家に拡張する詭弁
佐高 信、佐藤 優 著 「世界と闘う「読書術」 思想を鍛える一〇〇〇冊」から
『
最近、「家族を大切にしよう」と自民党がいっていますよね。
・・・
結局は政府による福祉を切り捨てて、
その負担を家庭に押しつけるという発想ですよね。
家族的価値観の尊重とか家族の復活
ということとは全然関係がない。
』
The government forces the burden of welfare on a home.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月06日
成長するためだけの成長
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
いまの消費社会は、
成長経済によって支えられているが、
その成長は人間のニーズを満たすための成長ではなく、
成長を止めないための成長だ
』
Economy is growth for not stopping growth.
- Permalink
- by
- at 00:00
2014年01月05日
成長はいつも善ではない
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
それにしても、
「成長は善である」
とはなんたる言い草か。
私の子供たちが成長するのなら至極結構であろうが、
この私がいま突然、成長を始めようなら、
それはもう悲劇である。
』
Economic growth also becomes a tragedy instead of the good.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年12月30日
政治とは
塩野 七生 著 「日本人へ 危機からの脱出篇」から
『
政治とは、
一見高尚に見えるイデオロギーや
他の諸々の主義主張とはちがって、
実に簡単な原理に立つものなのだ。
つまり、
自分たちの持てる力を
最大限に活用した場合に
成功する、という原理だけ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年12月27日
製品を廃物化するためにデザインが変更される
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
大部分のデザインの変化は、
製品を美的に、
あるいは機能的に改善するために
されるのではなく、
それを廃物化するためにされるのである。
』
A design is changed
and it is made visible to a new product.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年12月26日
大量生産は大量消費が前提
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
大量生産という名の巨人は、
その恐ろしい食欲が十分に持続して
満足されるときのみ、
最強の強さを保つことができる。
』
Mass production serves as the strongest, only while being consumed excessively.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年12月24日
企業の中心はデザイナー
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
企業におけるいちばん中心的な地位は、
もはや、機械技術者でもなく、
また、会計係でもなくなった。
いちばん枢要な地位を占めるのは
デザイナーなのである。
』
Now, the existence which takes the lead in a company is a designer.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年12月20日
Lucky Bag
天野 祐吉 著 「成長から成熟へ さよなら経済大国 」から
『
人はなぜ福袋を買うのか。
答えは簡単で、
「買うものがないから」です。
「ほしいものが見つからないから」です。
でも、
「何かが買いたいから」なんですね。
』
People will buy a lucky bag, if there is nothing needed.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年12月17日
衆愚政治になるわけは
塩野 七生 著 「日本人へ 危機からの脱出篇」から
『
どれが最優先事項かを見きわめ、
何ゆえにこれが最優先かを
有権者たちに説得した後に実行するという、
冷徹で勇気ある指導者を欠いていた
』
A leader performs, after persuading electors.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年12月15日
充分に食べられると穏健になる
塩野 七生 著 「日本人へ 危機からの脱出篇」から
『
人間とは、
充分に食べ
明日も充分に食べられるとわかれば、
なぜか穏健化する動物なのである。
反対に、
不安になると過激化する。
』
If man becomes uneasy, he will go to extremes.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年12月14日
困った動物
塩野 七生 著 「日本人へ 危機からの脱出篇」から
『
人間はおかしなことに、
問題がなくて幸せな日常だと、
それに飽きてしまうという困った動物でもある。
』
Man is an animal which gets bored in case of a fortunate life.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年12月10日
危機打開の先頭に立つ人は
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
危機打開の先頭に立つ人はやはり、
その後についていく国民が
恥ずかしいと思わない人でなければ、
と考えてしまう。
』
Everybody boasts of those who overcome a crisis.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年11月22日
税は国家の必要経費負担
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
現代の税体系は
複雑怪奇になってはいますが、
煎じつめれば
税とは国家を維持し
運営していくための必要経費を、
国民が負担するということに他ならない。
』
The present-day tax is complicated and mysterious.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年11月21日
軍隊のレベルは
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
軍隊とは結局のところ、
その国の国民の心情を
反映させたものでしかない。
どの国も
そのレベル以上の軍隊は持てない。
』
No country can have an army more than the level.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年11月20日
融和・一致
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
コンコルディア神殿に祀られている神は、
目に見えない、融和・一致という概念であるというわけです。
コンセプトそのものを祀るという発想は、
ローマ人ならではの発想でしょう。
』
The Roman deified the concept itself.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年11月19日
リーダーが存在しなかったら
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
リーダーの存在しない、
全員が平等な社会とは、
結局のところ、
誰も責任を負わない
無責任社会になってしまうから
』
It will become irresponsible society if there is no leader.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年11月17日
悪政と善政
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
政治はあくまでも結果論です。
いかに動機は善意に満ちあふれていても、
その結果が
国家や市民の不利につながるなら、
それは悪政であり、
逆に動機は不純でも、
結果が良ければ
善政と判断するしかない。
』
It will be altogether good if the end is good.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年11月16日
エリートとしての責務(ノーブレス・オブリージュ)
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
「ノーブレス・オブリージュ」は、
日本語に意訳するならば、
「エリートとしての責務」
という意味の言葉
』
The elite has the duty as the elite.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年11月15日
憲法9条を子孫に引き継ぐ義務
ジェームス 三木さんの言葉から
『
本当の悪人は、
国民に被害者意識を植え付け、
戦争に駆り立てる政治家だと思います。
だから、憲法9条は、
戦争を知る我々の世代が守り抜いて、
子孫に引き継ぐ責任があります。
』
We are obligated to take over Article 9 of the constitution to posterity.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年11月07日
大きな行動を起こすには
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
人間とはしばしば、
正しいのか誤りかは別にしても、
想いならば込められる大義名分がなければ、
大きな行動などは起こせないものなのです。
』
If the universe has a dark matter in which he believes, it can take big bang action.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年11月03日
制度には寿命がある
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
最初はうまくいっていたシステムでも、
時代が変われば、
弊害のほうが頭をもたげてくるものなのです。
』
The good system will also become evil if a time changes.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年10月31日
社会システムが成長についていけないと不況になる
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
改革のタイミングを失い、
旧態依然とした体制から
抜け出せないうちにいたからこそ、
不況のトンネルからの脱出も遅れた
』
Depression occurs by losing the timing of reform.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年10月29日
政治改革といっても
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
改革はかならず既得権者の抵抗を呼ぶものであり、
誰もが賛成する改革など、
いつの時代にもありえないのです。
』
There is no reform which everyone approve.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年10月25日
レシピだけではできない
パティシエ ピエール・エルメ さんの言葉から
『
レシピを盗まれるというけれど、
「似たようなもの」は出来ても、
そのものはできません。
素材、
人材、
設備。
様々なディティールの積み重ねが必要ですから。
』
A genuine article is not made even if it can steal a recipe.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年10月24日
改善しようとする気概
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
彼らには自分たちのありのままの姿を直視し、
それを改善していこうという気概(きがい)があった。
だからこそ、
ローマの繁栄はあれほど
長続きしたのです。
』
Oneself faults are recognized and it is improved.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年10月22日
寛容(クレメンティア)
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
ローマの最高権力者となったカエサルは
その施政方針を「寛容(クレメンティア)」という
一言で表しました。
そして、その言葉のとおり、
自分を攻め滅ぼそうとした敵をも
カエサルは抹殺しなかった。
』
Caesar did not erase the enemy who attacked himself.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年10月19日
普遍帝国
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
民族の違い、
文化の違い、
宗教の違い
を認めた上で、
それらをすべて包み込む
「普遍帝国」を樹立したのは
ローマ人だけでした。
』
Only the Roman accepted all the differences among people.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年10月18日
リアリズムに人間を考える
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
善悪ともに同居しているが人間ならば、
その善を少しでも伸ばし、
悪を少しでも減らす努力をしていくべきではないか・・・
』
Wrong is reduced and the good is increased.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年10月17日
人間性を改善できるもの
塩野 七生 著 「ローマから日本が見える」から
『
ローマ人たちはキリスト教会のように、
宗教によって人間性が改善できるとは
考えませんでした。
』
The humanity cannot improve by religion.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年10月08日
ほんとうにそうなのだろうか
城山 三郎 著 「打たれ強く生きる」から
『
「黙っていては、とり残される。
性急に声を上げた方がいい」
と気弱なひとは、つい考える。
』
Those who have become silent are disregarded. Is this right?
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年09月25日
人間の評価
城山 三郎 著 「打たれ強く生きる」から
『
いい人間、
わるい人間と、
何回もひっくり返る。
人間とは
いつ評価が逆転するかわからぬ
あいまいなものなんだ
』
There is no telling when reverse evaluation of people.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年09月23日
人間は奥が深い
城山 三郎 著 「打たれ強く生きる」から
『
人間とは奥の深い存在である。
一人の人間がいくつもの顔を持っている。
』
The one human being has a lot of capability.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年09月21日
やってはいけないことは、やってはいけない
竹内吉和 著 「発達障害と向き合う」から
『
できることは何でもやってあげるのは、
愛でもなんでもありません。
できることでも、
やってはいけないことは
やってはいけないのです。
これが真実の愛です。
』
Loving does not fulfill all the person's wishes.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月31日
すさまじいほどの戦力を得るには
城山 三郎 著 「打たれ強く生きる」から
『
一も二にも心掛け、
心の在りようひとつ。
それが積もれば、
すさまじいほどの戦力になる。
』
It is improvable by aim.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月28日
予定していない事態を活用する
塩野七生 著 「海の都の物語〈1〉」から
『
はじめに立てた計画を着実に実行するだけならば、
特別な才能は必要ではない。
だが、
予定していなかった事態に直面させられた時、
それを十二分に活用するには、
特別に優れた能力を必要とする。
』
A capable person utilizes the situation which was not being planned.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月27日
絶対に正しいはない
城山 三郎 著 「打たれ強く生きる」から
『
この世の中に、
「絶対」ということはあり得ない。
「絶対に正しい」ということもない。
』
It cannot say, "It is absolutely right."
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月23日
新しい英雄とは
城山 三郎 著 「打たれ強く生きる」から
『
やるときにはやるが、
自らの栄達や権勢にとらわれない。
それが新しい英雄である。
』
New heroes are those who are caught by neither their distinction nor power.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月20日
一年間集中すれば専門になれる
城山 三郎 著 「打たれ強く生きる」から
『
大人が一年間ムキになってやれば、
たいていのことは、りっぱな専門家になれます
』
If an adult concentrates for one year, it will get used to a specialist.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月16日
部下をのみこむ
城山 三郎 著 「打たれ強く生きる」から
『
部下をまるごとのみこんでおくということで、
そうなってしまうと、
たとえイヤな部下でも、
イヤなやつと思えなくなる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月10日
現実主義では大衆は動かない
塩野七生 著 「海の都の物語〈1〉」から
『
現実主義は、
人間の理性に訴えるしかないもの
であるところから、
理性によって判断をくだせる人は
常に少数でしかないために、
大衆を動員するには
あまり適した主義とは言えない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月09日
絶対に必要な品を売ること
塩野七生 著 「海の都の物語〈1〉」から
『
商売というものは、
買い手が絶対に必要としている品を売ることから
はじまるものである。
買い手に、買いたい気持ちを
起こさせるような品を売りつけるのは、
その後にくる話だ。
』
Trade begins from a buyer selling required elegance absolutely.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月06日
敵を味方にする
塩野七生 著 「海の都の物語〈1〉」から
『
血を流した後はすぐ、
頭を使ったのだ。
それは、
昨日までの敵を
今日からは味方にするやり方だった。
』
The enemy by yesterday is made an ally from today.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月05日
味方は遠くにあるべし
塩野七生 著 「海の都の物語〈1〉」から
『
味方というものは、
それが強国であればなおのこと
遠くにあるほうが望ましい存在である
』
It is more desirable for there to be an ally in the distance.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月04日
ヒットラーを見習えという政治家がいる国家は滑稽
映画 「天空の城 ラピュタ」から
『
国が滅んだのに、王だけいるなんて滑稽だわ。
』
吉田茂の孫だというのに、麻生氏がこれ程、おバカだとはね。
「基本的人権」も「国民主権」も存在しないヒットラー政権を見習えというのですから、自分の目線が国民を人以下にしか見ていないということが露見してしまいました。
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月03日
自給自足を捨て去ったとき都市になる
塩野七生 著 「海の都の物語〈1〉」から
『
進歩に要するすべてのエネルギーは
都市からしか生まれない、
と私は信じている。
自給自足の概念を捨てきったところにしか生まれない、
と言い換えてもよい。
』
It will become a city if a self-sufficient concept is left.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年08月02日
ずいぶんと心配なこと
杉本 鉞子 著 「武士の娘」から
『
お祖母さま、
ずいぶんと心配なことがございます。
こんな大きな世界の中で
日本はこんな小さな島が少しばかりあるのです
』
In such the big world, Japan has done it only on the small island.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月31日
しとやかさは幸福か
杉本 鉞子 著 「武士の娘」から
『
私の一声に答えて、
飛び上がってくるすばやさは
どこへ行ったのでございましょう?
見たい、聞きたい、したいのあの愉快さ、
熱心さはどこへ行ったのでございましょう?
生活の一切に興味をそそられて、
元気一杯だった、
あのアメリカ生まれの娘の姿は
どこへ行ったのでございましょう?
』
Where did pleasure and an eagerness disappear?
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月27日
親切でよい人になる
杉本 鉞子 著 「武士の娘」から
『
そうよ。
神さまは皆んなが親切なよい人になるようにと
願っていらっしゃる
』
God wants everybody to become a kind person.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月26日
今の若い人に力を与えるもの
杉本 鉞子 著 「武士の娘」から
『
古い日本の立派な文明は
今の若いあなた方に力を与えているのです。
ですから、
あなた方は勢よく大きくなって、
昔の日本が持っていたよりも、
もっと大きい力と美しさを、
今の日本にお返ししなければなりません。
』
The splendid civilization of old Japan has given present young you power.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月23日
十億人を国境内に入れているというのは中国の世界貢献
姜 尚中 著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
中国の崩壊を望むような考えというのは、
自分たちの足下のことを抜きにして考えている、
ちょっとユートピア的な発想ではないかな
と僕は思いました。
』
A Utopia is a place which does not consider its foot.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月20日
動的であるから可能
姜 尚中 著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
私たち生命体は柔軟であり、
可変的であるわけです。
傷つけば治り、
何かが損なわれれば修復することができる。
それは、すべて動的であるからこそ可能なのです。
』
Our lives are flexible and variable.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月16日
機械論的な世界観の失敗
姜 尚中 著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
私たちは機械論的な世界観で
この世界を制御してきたというように思っていたのですが、
果たしてそれがどれほどのものだったのかということは、
2011年に起こった原発事故のような問題によって、
如実に私たちの目の前に突きつけられているのではないでしょうか。
』
We were not able to control the mechanized world.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月15日
遂には希望の彼岸に達する
杉本 鉞子 著 「武士の娘」から
『
日本人にとっては、
知らず識らずに踏みこえた
悲しい輪廻の迷い道も、
暗いさびしい日々を経ますと
遂には希望の彼岸に達する
ものとなっています。
』
Hope can fulfill after dark lonely days.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月13日
相補性のある交換
姜 尚中 著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
それぞれのピース一つひとつが、
この相補性を保ちながら
交換されていくのであれば、
ジグゾーパズルのピースは更新されても、
パズル全体の絵柄はそれほど変わらないでいられます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月12日
生を祝福するとは
姜 尚中 他著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
子どもが
「自分に生まれてきてよかった」
と自分自身を肯定できることと、
お年寄りが
「長生きできてよかった」
と思えることは、つながっています。
』
It was good to be born to oneself.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月10日
最先端医療とは命を縮めていく操作
姜 尚中 著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
最先端医療というと
いかにも寿命を延ばしてくれるように思いがちですが、
実際は、
脳死と脳始ということをもってして
命を縮めていく操作でもあるのです。
』
The latest medical treatment is operation of contracting the life.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月08日
質問を発すること
姜 尚中 他著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
どんなバカでも質問に答えることはできる。
重要なことは
質問を発することである
』
It is important that we emit a question.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年07月06日
日本経済の運行システムは変わる必要がある
姜 尚中 他著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
いまのような様々な問題が
迫ってくるという状況においては、
やはり日本経済の運行システムが
変わっていく必要があります。
』
The operation system of Japanese economy needs to change.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年06月28日
頂上に行けないことを受け入れたとき
姜 尚中 他著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
頂上に行けない自分を受け入れたとき、
何かを「克服」した
』
With the fact that its purpose cannot be attained, he understood life.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年06月26日
かつて日本人はお金に精神的価値を認めていた
杉本 鉞子 著 「武士の娘」から
『
アメリカ人は
働きの代償としてお金を考えているんだよ。
お金に精神的な価値など認めてはいないのだよ
』
Japanese people observed spiritual value in money once.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年06月21日
自重は自由と希望
杉本 鉞子 著 「武士の娘」から
『
徒らなる犠牲に甘んじては、
唯溜息が出るばかりであり、
自重は自由と希望に通ずるものである
』
Prudence passes to freedom and hope.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年06月19日
真の自由とは
杉本 鉞子 著 「武士の娘」から
『
自由を愛し
自由に向って進む権利を信じていたのは
若い頃のことで、
真の自由は、
行動や思想の自由を遥かにこえて
発展しようとする精神的な力にあるのだ
』
True freedom is in the mental power in which it develops.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年06月17日
日本は実にナンセンス
姜 尚中 他著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
日本が非常に豊かな国であるにもかかわらず、
その豊かさのただなかに若者いじめ、
貧困者いじめというようなことが起こるのは
実にナンセンスで、
これはやはりナショナルなものの機能低下、
機能不全の結果であると思います。
』
Although Japan is a very rich country, it is nonsense that there are bullying and poverty.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年06月15日
高齢になった男性は
姜 尚中 他著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
高齢になった男性は
ある意味で、
女性とほぼ同じ立場に置かれます。
アイデンティティを奪われたり、
生産性が上がらないという理由において、
彼らは女が見てきた景色と
同じものを見つめることがあるのかもしれません。
』
The man who became advanced age is deprived of an identity.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年06月14日
デモクラシーの軸足
姜 尚中 著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
デモクラシーの軸足は、
単なる「多数者の決定」というよりも
「議論と対話による調整」という
ところにあります。
』
Democracy is adjustment by an argument and a dialog.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年06月11日
まともな国家とは
姜 尚中 著 「「知」の挑戦 本と新聞の大学 II」から
『
リスクは誰にでも
いつでも起こり得ることで、
そうしたリスクに対してきちんと
保障するのがまともな国家であると
私は思います。
』
It is an honest state which is exactly secured to a risk.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年05月24日
武士の勉強精
杉本 鉞子 著 「武士の娘」から
『
勉強している間、
体を楽にしないということは
僧侶や師の慣わしでありましたので、
一般の人々も身に受ける苦しみは
かえって心のはげみになるものだと
感ずるようになりました。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年05月22日
表現とは
塩野 七生 著 「ルネサンスとは何であったのか」から
『
表現とは、
自己満足ではない。
他者に伝えたいという
強烈な想いが内包されているからこそ、
力強い作品に結晶できるのです。
』
Expression is not self-satisfied.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年05月21日
遺産
塩野 七生 著 「ルネサンスとは何であったのか」から
『
継承者がそうは容易には現れないから、
いまだに「遺産」と呼ばれているのでしょう
』
Since a successor does not appear, it is called an "inheritance."
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年05月18日
精神の貴族
塩野 七生 著 「ルネサンスとは何であったのか」から
『
善悪ともを内にかかえる人間が中心になれば、
「悪」は他人の行うことで自分は知ったことではない、
などとは言えなくなります。
』
Man has the good and wrong in the inside.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年05月17日
日本の学校と教師は欧米と比べよくやっている
杉山 登志郎 著 「発達障害の子どもたち」から
『
日本の学校は、
とてもよくやっている。
むしろやり過ぎている。
子育て支援という要素が
ますます重要になった今日、
学校への根拠のないパッシングほど
無責任なものはない
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年05月13日
完成する条件
塩野 七生 著 「ルネサンスとは何であったのか」から
『
完成とは、
あるところまではやったが
それ以上のことはあきらめたから、
できることでもあるんですよ
』
In order to complete, do to a fixed level and give up the thing beyond it.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年05月10日
リーダー国になるためには
塩野 七生 著 「ルネサンスとは何であったのか」から
『
経済大国になっても
政治大国になっても、
それだけではリーダーになれない。
それだけでは、
リードされる側を納得させることは
できないからです。
』
Even if it becomes an economic big power, and it becomes a political power, it does not get used to a leader only in it.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年05月09日
時代の流れに適さないと成功しない
塩野 七生 著 「ルネサンスとは何であったのか」から
『
時代の流れに適したものでないと、
いかにそのもの自体がよく出来ていても
成功は望めないのです
』
It does not succeed, unless it is a product suitable for a time.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年05月08日
時間の無駄がエネルギーをくれる
兼高 かおる 著 「わたくしが旅から学んだこと」から
『
時間の無駄は
時には無駄といえない
エネルギーをくれていることもあるのです。
』
The futility of time may have given energy.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年05月03日
栄華も好き
塩野 七生 著 「ルネサンスとは何であったのか」から
『
神の子でない人間たちは、
野の百合も愛するが
ソロモンの栄華も好きという、
困った生きものでもあるんですね。
』
Man loves the lily of a field and also likes luxury.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年04月26日
真の国家とは
塩野 七生 著 「ルネサンスとは何であったのか」から
『
真の国家とは
政治や軍事のみでは成り立たず、
経済も学問も文化も重視されてこそ
文明国であるといえる
』
It is a civilized country that economy, learning, and culture are thought as important.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年04月13日
文化的な余裕がない
兼高 かおる 著 「わたくしが旅から学んだこと」から
『
戦後60年以上経った今、
人々は文化的な余裕はなく、
知識人が集まれば
不満と批判ばかり。
なんと世知がらいことでしょう。
』
If intellectuals gather, it is always criticized as dissatisfaction.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年04月10日
人は常に変わる
兼高 かおる 著 「わたくしが旅から学んだこと」から
『
人は常に変わる。
だから世の中は
不可解であり
楽しくもあり
冒険的でもあるのです。
』
People always change.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年04月09日
他人の価値観が刷り込まれる
藤沢 晃治 著 「「判断力」を強くする」から
『
本来「自分の価値観」だと思っていることが、
じつは「他人の価値観」を刷り込まれていることが
少なくありません。
』
In fact, "others' sense of values" is stenciled!
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年04月07日
頭の中まで狭くなる訳
兼高 かおる 著 「わたくしが旅から学んだこと」から
『
居住空間が狭く、
小さなところに一杯物があって、
それらが美的に並んでいなければ、
頭にいいはずありません。
頭の中まで狭くなってしまいます。
』
It cannot become intellectual, if a small place has a full thing and they are not esthetically located in a line.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年03月29日
冗談が時間的余裕を生む
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
人間の発する言葉は
意味も情報も担っていない余分な言葉=冗談
に満ちていて、
だからこそ時間的余裕が生まれ、
そのおかげで聞き手や読み手は
情報や意味を把握して
咀嚼(そしゃく)するのが楽になる。
』
Man's words are filled into language without a meaning and information.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年03月28日
日本の自然の偉大さ
兼高 かおる 著 「わたくしが旅から学んだこと」から
『
日本はもっと自国の自然の素晴らしさを認識し、
大切にすべきです。
』
Japanese people should recognize wonderfulness with natural own country.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年03月21日
日本食好きが真の愛国者
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
たとえ、
祭日に日章旗を掲揚していなくたって、
君が代の歌詞を知らなくたって、
もう間違いなく、正真正銘の日本人です。
』
Those who want to come to eat a rice ball are true Japanese.
海外旅行に行って “お握り” が食べたくなる人、“ラーメン” が食べたくなる人、“鰻重” が食べたくなる人、それが真の愛国者なのです。
![]() “君が代チェック”をした幼稚人(中原徹)が大阪府教育長なんて
“君が代チェック”をした幼稚人(中原徹)が大阪府教育長なんて
![]() 天ちゃんの唄(君が代)で日本人の誇りなんか出来ない
天ちゃんの唄(君が代)で日本人の誇りなんか出来ない
![]() 日本には助けなければいけない国民がいるだけ
日本には助けなければいけない国民がいるだけ
![]() 20世紀少年の“友民党”=“日本維新の会”=“Japan Restoration Party”
20世紀少年の“友民党”=“日本維新の会”=“Japan Restoration Party”
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年03月14日
改革が進まない原因は
望月 護 著 「ドラッカーの実践経営哲学」から
『
景気の低迷と政治迷走で
悲観論が蔓延しているが、
改革が進まないのは
既得権を捨てることに抵抗している
人間が多いからである。
』
Since vested rights cannot be thrown away, reform does not progress.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年03月10日
日本維新の会政権が出来ればこのように瓦解する
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
いたずらにナショナリズムを煽り、
密告を奨励し、
国民に真実を伝えない愚かな欺瞞的な体質ゆえに、
外敵からの攻撃とあいまって瓦解していく
』
The foolish political power which does not tell people truth collapses.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年03月09日
小泉政権とは
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
他者の言葉に耳を傾けず、
気に入らない国々を軍事力で蹴散らす超大国アメリカ。
そのアメリカに追従し、
自衛隊を戦地に送って、
戦後の日本人がもっとも大切してきた
原則を踏みにじる小泉政権。
』
The United States disregards the opinion of a foreign country and strikes a disagreeable country by the military strength.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年03月07日
撤退を決断すべき時期
望月 護 著 「ドラッカーの実践経営哲学」から
『
まだ数年は寿命がある
と言っている時が、
撤退を決断すべき時期
』
The now which has not lost all is a time of opting for withdrawal.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年03月04日
飽食日本人は貴族なのか
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
現在地球人口の七人に一人を占める
飢えている人々の目からは、
飽食の日本人は貴族に見えるかも知れない。
』
Hungry people will regard the Japanese of gluttony as an aristocrat.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年03月03日
地域の個性は「いいね!」
デザイナー 梅原 真 さんの言葉から
『
それぞれの地域の個性を認識しあって、
それぞれの土地の個性を
いいね
と言い合える日本にしたい。
』
The individuality of each area is accepted mutually.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年03月01日
高度依存体質社会からの脱皮
群馬大工学部教授 「釜石の奇跡」を支えた 片田 敏孝 さんの言葉から
『
臨機応変に
自分で判断できる力をどうつけていくのか、
釜石の子どもたちのように
動けるプロセスを聞きたいようです。
高度依存体質の社会から
脱皮しないといけません
』
You have to transform yourself from the society of an advanced dependence constitution.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年02月28日
生きるに値する生
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
ふと余りにもあっけなく
自らの命を絶つ最近の子供たちのことを思った。
彼らの生は生きるに値する生になっているのかと。
』
Are children's carrying out the worthy way of life?
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年02月27日
防災は行政依存体質ではいけない
群馬大工学部教授 「釜石の奇跡」を支えた 片田 敏孝 さんの言葉から
『
防災だけでなく何かにつけて行政責任を言う
日本の社会構造みたいなものに
根源があると思えてなりません。
自分の命を守るのを
他人任せにしてはいけない。
自己責任ですよ
』
It is self-responsibility that you protect your life, and it must not be carried out dependent on others.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年02月23日
英語を学ばせればグローバル化すると考えるのは愚かな理論
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
国際化のために幼時から
英語を学ばせ国語を疎んじ、
結果的に国際的に軽蔑される
無内容な国民を量産するような
愚かな理論がまかり通る。
』
If a small child is made to study English rather than a language, it will become the people despised from international society.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年02月22日
平和のシンボル
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
現在の天皇は、
まさに「平和のシンボル」たろうとしている。
日の丸・君が代の強制をたしなめ、
戦犯を祀る靖国には参拝しない。
』
The present Emperor scolds compulsion of the Rising-Sun flag and Kimigayo.
And it does not worship at Yasukuni Jinja which deifies a war criminal.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年02月13日
一方的な正義
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
「西部劇」はアメリカ大陸を
「インディアン」たちから奪った
アメリカ人の側が一方的な
正義として描かれている、
という点では「9・11」の戦争と同じ構図
』
Americans claim that it is justice to have deprived the Indian of land.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年02月12日
お客をよく見ること
望月 護 著 「ドラッカーの実践経営哲学」から
『
モノが売れないと言って嘆いているが、
お客をよく見ていないことが原因ではないか
』
A thing cannot be sold because the seller does not understand a visitor's thing needed.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年02月06日
悪魔が必要になる訳
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
自分の側に正義があることを示すためには、
悪魔が必要になってくるのです。
一種の近親憎悪でもありますね。
全然無関係なものを
悪魔にはしないわけですからね
』
An evil spirit is needed in order to show itself that there is justice.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年01月29日
市場原理主義
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
市場原理主義は、
減税をやって財政赤字はつくり出すけれども
歳出を増やすことができない。
』
Market fundamentalism does a tax cut, and although a budget deficit makes, it cannot increase annual expenditure.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年01月26日
忘却装置
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
どんなに過酷であろうと、
被害体験は、
時を経るほどに甘美な思い出となり得るが、
加害体験は、
忘却の闇に葬り去られるべき汚物と化す。
』
The violence against people forgets to be buried at darkness.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年01月25日
男は生身の人間を見ない
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
男はどうもイデオロギーに縛られ
つまらない抽象論に逃げ込んで
生身の人間を見ようとはしない傾向がある。
』
A man is an abstract theory lover and does not presuppose that a real human being will be seen.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年01月21日
辞書辞典類はインターネットで購入しないこと
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
辞書辞典類は
絶対インターネット書店で購入してはいけない。
ちゃんと手にとって頁をめくり、
いくつかの項目をテイスティングしてから
決断しても遅くはない。
』
Don't purchase the dictionary by any means at the Internet bookstore.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年01月20日
政府の経済政策では景気は上向かない
望月 護 著 「ドラッカーの実践経営哲学」から
『
景気を上向かせることができるのは、
政府の経済政策ではなく、
新しい事業を起こそうとする
企業家のエネルギーである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年01月18日
コンピューター化によって弱体化するもの
2013年01月10日
辛苦を吹き飛ばす
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
どんな辛苦でも
笑いで吹き飛ばせぬほど
重くはない
』
Any hardships are not so heavy as cannot be blown away by laughter.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年01月08日
まともさから悪は来る
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
悪は「まともさ」の延長線上にある。
だからこそ恐ろしい。
』
Wrong is on the extension of the right thing.
Therefore, it is fearful.
- Permalink
- by
- at 00:00
2013年01月06日
日本の外務省はアクセサリー
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
そもそもアメリカの属領にすぎない日本に
外務省があるのは、
あたかも独立国であるかのような錯覚を
国民が抱き続けるためのアクセサリーのようなもの
』
The Ministry of Foreign Affairs of Japan is the accessories for showing it as the independent country.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年12月29日
最強国の言語は長続きしない
米原万里 著 「愛の法則」から
『
文化レベルで見ると、どの文化にも
深いもの、
おもしろいもの、
価値あるものが
非常にたくさんあるわけです。
でも、
軍事力とか経済力というものは、
一時的にのしていくことはできても、
永遠に長続きはしないものなのです。
』
There are many those where the culture of every country has a meaning, interesting things, and valuable things.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年12月26日
なんて大人なんだろう
小川洋子 著 「カラーひよことコーヒー豆」から
『
自分が出会った大人たちを振り返ってみると、
大人になることがどんなに困難かよく分かる。
美しく書類を処理し、
たくましくボートを漕ぎ、
悟りを開き、
毅然と抗議し、
魔法で料理が作れる人・・・
』
Adults are those who process documents beautifully, row a boat muscularly, realize spiritual enlightenment, protest firmly, and can cook things by magic.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年12月25日
360度の方向が与えられている
米原 万里 著 「打ちのめされるようなすごい本」から
『
私ははじめて自分にも後ろがあり、
三百六十度の方向が
与えられていることに気づいた
』
I have back also to myself and I have noticed that the direction of 360 degrees is given to me.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年12月23日
料理を作るのだ
小川洋子 著 「カラーひよことコーヒー豆」から
『
偉大な自分の能力を、
一皿の美味しい料理のために捧げるのだ。
この喜びを知らないでいては、
人として生まれてきた甲斐がないではないか。
』
If this joy is not known, isn't there any worth produced as a person?
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年12月22日
小説を超越した現実
小川洋子 著 「カラーひよことコーヒー豆」から
『
現実を超越した小説だ、
と自惚れているのは作家だけで、
実際の世界では常に、
作家など思いも及ばない物語的な
出来事が起こっている。
』
The occurrence which a novelist does not invent, either has arisen in the actual world.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年12月19日
神様の計らい
小川洋子 著 「カラーひよことコーヒー豆」から
『
神様の計らいは常に、
本人に気づかれないようこっそり施される。
それを施された人間より、
その人間が発するものを受け取る側の方が、
ずっと大きな恩恵をこうむる。
』
Almsgiving of God is performed so that it may be easy to man.
Surrounding people receive a benefit from the man.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年12月15日
The painless learning method
米原万里 著 「愛の法則」から
『
新しい言葉を身につけるためにも、
維持するためにも、
読書はいちばん苦痛のない学習法だと思います。
』
I think that reading is the painless learning method also in order to put on a new word and to maintain.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年12月07日
自分に自信がないからブランドを着る
田丸 公美子 著 「パーネ・アモーレ―イタリア語通訳奮闘記」から
『
ブランドが目立つものを身に着けるということは、
そのブランド王国の征服を着ているのだ。
自分に自信がないから
ブランドで安心感を買っているのだという
事実に気づいていない。
』
People buy a brand-name product and acquire confidence.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年12月05日
花屋さん
小川洋子 著 「カラーひよことコーヒー豆」から
『
人々の人生の瞬間を飾るに
相応(ふさわ)しい美を用意するために、
花屋さんは傷だらけの手で花束を作る。
』
The florist makes a bouquet from a hand full of cracks, in order to prepare the beauty with which people's life is decorated.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年11月27日
色々な人間がいなくなった企業は弱い
米原万里 著 「愛の法則」から
『
人類は環境の激変で、
いつどうなるかわかりません。
もし、みんな同じタイプだったら、
同じ条件で全員が滅びてしまうでしょう。
でも、生き延びなくてはいけないから、
保険と同じように
いろいろなタイプがいるわけです。
』
Since man has to survive, he has a person various type like insurance.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年11月20日
テレビはウンコ
田丸 公美子 著 「パーネ・アモーレ―イタリア語通訳奮闘記」から
『
テレビはウンコみたいなものだ。
毎日の習慣になっているけれど、
じっくり自分の排泄物を見る人は誰もいない。
それと同じで、
みんな暇潰しに眺めて
時間を無駄にしているだけだ。
』
It is looking at TV to kill time wholly.
And time is made useless.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年11月19日
日本経済低迷という呪文
ティナ・シーリグ 著 「未来を発明するためにいまできること スタンフォード大学 集中講義II」から
『
「日本経済は20年もの長期低迷にあえいでいる」
・・・
マスコミや学校、家庭で日々、
繰り返されるこの呪文は、
ひどくやる気をそぐものです。
こうした姿勢では、
目の前のチャンスにも
気づくことができなくなります。
』
It is impossible to notice an impending chance.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年11月14日
年寄りは仕事に固執する
田丸 公美子 著 「パーネ・アモーレ―イタリア語通訳奮闘記」から
『
人間は年をとればとるほど、
仕事に固執するようになる。
何故なら
他にもうやりたいことがなくなるからだ。
仲間外れにされたくない、
何か人の役に立ちたいと思う。
』
An old person comes to think that he would like to be helpful to people.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年10月24日
おしゃれで美しくおいしい食卓
東畑 朝子 著 「「70歳生涯現役」私の習慣」から
『
おしゃれで美しくおいしい食卓は、
気持ちを明るくするだけでなく、
癌を防ぎ、
毒素を排出し、
若さを保つためにも役立つ。
』
A foppish and beautiful delicious table makes a feeling bright.
And it is useful also in order to maintain youth.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年10月23日
なるべく毎日同じものばかり食べない
東畑 朝子 著 「「70歳生涯現役」私の習慣」から
『
現在の核家族やひとり暮らしで
30品目も食材を買ったら、
たちまち残り物ばかりふえて、
冷蔵庫で傷んでいく。
まず、
4群を普通に召し上がれ。
そのうえで
「なるべく毎日同じものばかり食べない」
ことを心がけるだけでいいのだ。
』
It tries not to eat only the same things every day.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年10月12日
カント的人間関係
菊澤 研宗 著 「「命令違反」が組織を伸ばす」から
『
自分の目的を達成するために
相手を単なる手段として、
あるいは単なる物として
利用してはならないという人間関係、
つまり一人ひとりが常に相手を一つの目的、
すなわち
価値をもつ存在であるとみなし、
決して相手を自分の目的達成のための
手段としてあつかわない
という人間関係である。
』
Kant-like is the following things.
First, a partner is always accepted to be a worthy existence.
And never let a partner be a means for your purpose achievement.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年10月06日
遠大な目標
ティナ・シーリグ 著 「未来を発明するためにいまできること スタンフォード大学 集中講義II」から
『
遠大な目標を目指しながら、
その途中で小さな勝利を積み重ねる
機会を与える必要があるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年10月03日
利益と効率性
菊澤 研宗 著 「「命令違反」が組織を伸ばす」から
『
人間が限定合理的であるため、
変化にともなって常に
「取引コスト」が発生する可能性があり、
この取引コストが
<社会全体の利益・効率性>と
<個別組織の利益・効率性>を
不一致にする
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年09月29日
人々が移行しない訳
菊澤 研宗 著 「「命令違反」が組織を伸ばす」から
『
既存の商品が新商品よりも劣っていたとしても、
新商品へ移行するのに必要な
取引コストがあまりにも高いならば、
人々は移行しようとはせず、
あくまで既存の商品に固執する可能性がある。
』
The existing goods are inferior to the new product.
In that case, people continue using the existing goods, when the cost changed to a new product is large.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年09月28日
現状に留まろうとする合理的力
菊澤 研宗 著 「「命令違反」が組織を伸ばす」から
『
移行しないかぎり、
取引コストが発生せず、
現状にわずかでもメリットを感じているならば、
人間には現状に留まろうとする
慣性が合理的に働いてしまうのである。
』
If man feels the merit for the present condition, he will believe that not changing is rational.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年09月13日
時代感覚
江 弘毅 著 「街場の大阪論」から
『
時代感覚というのは面白いもので、
誰かが今までとは違う何かを表現すると、
必ず同じ時に同じ言語のようなものを持った人が
そのコンテクスト(文脈)をとらえる。
』
A sensitivity to the times is interesting.
If it expresses that someone differs from former, those who sympathize with it and act will appear immediately.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年09月11日
おっさんに人気
江 弘毅 著 「街場の大阪論」から
『
ヴィトンやカルティエが
「若い女性に人気」という言い方で
表現されるのはまだしも、
どうしていろんなものが
「おっさんに人気」
という言い方で表現され得ないのか。
それはおかしいやないか
』
Expression that a yang woman Vuitton and Cartie enjoys popularity is understood by the world.
But, expression of "enjoys popularity to middle-aged" is not carried out.
It is a strange trend.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年09月05日
不幸も幸福も感じられなくなる
辛永清 著 「安閑園の食卓 私の台南物語」から
『
世の中のスピードが恐ろしく速くなり、
受けるストレスの数も量も増大すると、
私たちはその苦痛から逃れるために、
知らず知らずに感情のスイッチを
オフにしているときがある。
』
If a change of a world becomes quick, the stress dose to receive will increase.
We are insensible unconsciously, in order to escape the pain.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年09月04日
大阪の「うまい安い」
江 弘毅 著 「街場の大阪論」から
『
テーマパーク造りは、
プランナーやイベント屋に任すのは別にいいが、
大阪の「うまい安い」を
舐められては困るのである。
』
As for the theme park of Osaka, a planning company may go freely.
However, the delicious food with a cheap price of Osaka is worthy rather than a theme park.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年09月03日
マスコミが伝える大阪はちゃうんちゃうの
江 弘毅 著 「街場の大阪論」から
『
B級でいちびりでレトロで
「過剰なアホ」を大阪とするとらえ方、
そのステレオタイプまる出しの感覚に、
ちゃうんちゃうの、
と思い続けている。
』
The view which makes the Latin optimist the people from Osaka by Class B is a stereotype, and true Osaka crosses.
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年09月02日
大阪人にとっての上京
江 弘毅 著 「街場の大阪論」から
『
大阪の人間にとっての上京は
彼らとは少し違う。
なぜなら生まれてこのかた
東京にあこがれなんかない上方人にとっては、
東京は必ず「勝ちに行く」ところであるからだ。
』
Coming up to Tokyo for the people from Osaka differs from other people for a while.
Because, after being born, it has not yearned after Tokyo.
Tokyo is at the time, saying the people from Osaka certainly "go to win."
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年08月21日
面白いジョークというのは
ティナ・シーリグ 著 「未来を発明するためにいまできること スタンフォード大学 集中講義II」から
『
面白いジョークというのは、
こちらが予想もしない時に
話のフレームが転換されるから
笑えるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年08月17日
脳はクリエイティブティ・マシン
ティナ・シーリグ 著 「未来を発明するためにいまできること スタンフォード大学 集中講義II」から
『
クリエイティブな活動をしている時は、
通常なら新しいアイデアを退ける部位の機能が
低下すると考えられるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年08月09日
やはり人間同士は
辛永清 著 「安閑園の食卓 私の台南物語」から
『
眼に見えない大きな運命が、
ときとして人間を悲しい状態に追込むことがある。
しかし、
人間同士はやはり愛しあい、
いたわりあうべきである
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年08月04日
幸福で胸が温かくなる
辛永清 著 「安閑園の食卓 私の台南物語」から
『
美しい前庭と活気にみちた裏庭のあるこの家で、
大ぜいの家族とともに過ごした少女時代を思うと、
私はいまでも幸福で胸が温かくなる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年08月03日
会いにいくのが旅
2012年07月31日
日常の宝
辛永清 著 「安閑園の食卓 私の台南物語」から
『
日常の、どんな些細なこと、物、人の中にも、
宝物はある。
そしていつの時代にも、
注意深く見つめていさえすれば、
その宝は誰にでも見つけることが
できるはずである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月30日
「地震」と「自信」
2012年07月27日
大国になりたければ
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
もっと大きくなりたければ、
真の大国になりたければ、
もっと小さくならなければなりません。
鬼になるな、一寸法師になれ!
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月25日
昨日とおなじように今日があること
清川 妙 著 「つらい時、いつも古典に救われた」から
『
とくに新しい、
あっと驚くようなことをするのじゃなくて、
昨日とおなじように今日があり、
今日のことができるということが
いちばんすてきなことのような
気がしてならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月22日
さてしもあるべき事ならねば
清川 妙 著 「つらい時、いつも古典に救われた」から
『
『平家物語』には、
〝さてしもあるべき事ならねば〟
という慣用句が出てくる。
〝そのままの状態でいられるはずがないので〟
という意味のことばである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月21日
ほんのちょっとの旅に出よう
清川 妙 著 「つらい時、いつも古典に救われた」から
『
仕事に追われる日がつづき、
ストレスがたまるころになると、
『徒然草』のことばが
思い出されてならない。
いづくにもあれ、
しばし旅だちたるこそ
目覚むるここちこそすれ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月18日
日本は精神的飢餓地帯
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
-マザー・テレサの言葉から-
この地球上では二つの飢えの地帯がある。
ひとつはアフリカであり、
いまひとつは日本である。
前者は物質的な飢えであり、
後者の飢えは精神的なそれである
』
でも、最近の日本では、中間層を破壊してしまったために、本当に飢餓状態の人もいます。セーフティネットを作らず、労働市場だけを自由化した小泉政権の大罪の結果が、ここにあります。
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月17日
花と共鳴する
清川 妙 著 「つらい時、いつも古典に救われた」から
『
なにげなく無感動にすごした日々は、
花のほうでも呼びかけてはくれない。
心が、なにかにうたれ、
清冽(せいれつ)な感動に洗われたとき、
人は、どんな小さな草の花の
いのちにも共鳴するのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月16日
日本人は買物で理解する
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
その国で買物をすることによって、
そのイメージ、
その風俗を買うのです。
日本人にとってお土産を買うということは、
その地方、
その国を学んで理解する方法なのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月15日
道具への好奇心
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
日本人が西欧文明にいち早く適応して
近代化に強さを示したのは、
彼らに舶来の道具に対する強力な好奇心が
あったからこそだ、ともいえるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月13日
日本では一匹狼は飢え死に覚悟
2012年07月09日
眼に見える物が情熱
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
縮みの志向性が強い日本人は、
抽象的なものが、
眼に見える物にかわってあらわれたときにはじめて、
それに好奇心とすごい情熱を持つ傾向が強いのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月06日
小さいものを愛する気持ち
清川 妙 著 「つらい時、いつも古典に救われた」から
『
「小さいものを愛する気持ち」とは、
・ものの考えかたのやわらかさ
・相手の好きなもの、大事なものを認めあうこころ
なのであろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月05日
一瞬の美
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
花は散るものであるがゆえに、
一瞬の美であるがゆえに、
一期一会の切実な心持でそれを
眺めるようになるからです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月04日
袋
清川 妙 著 「つらい時、いつも古典に救われた」から
『
袋は、
旅にも買い物にも、
暮らしの整理にも
いろいろ使えて、
けっして自由を束縛されない。
すぐに使わなくても、
思い出としてたたんでしまっておける。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月03日
一生懸命に生きるとは
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
日本人がいったん何かを達成しようとするときに、
ほとんど超現実的な力を発揮するのは、
その一生の時間を圧縮して捧げ、
一期一会の瞬間のなかで
精一杯生きようとする態度からくるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年07月02日
at+tention(緊張せよ文化)
2012年07月01日
2012/06:アクセスランキング
2012年06月30日
社員を取って締め上げるから=取締役
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
西欧の会社でディレクターといえば
社員を引導する意味ですが、
日本ではなんと、
「取締役」になるんです。
社員を「取って締める」役なんですね。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月29日
見てニッコリ笑うことができる空間
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
庭とは
見てニッコリ笑うことができる空間なのです。
それと区別された外の場所とは、
不安でとてもニッコリなどできない
漠然とした空間なのでしょう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月27日
何も主張していない国家
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
日本の旗を見ると、なにも書いていない。
お日さまなんてものは、
国家形成以前の民族といえども尊敬する価値であって、
こんなものを紙に書いてぶらさげている国家は、
なにも主張していないということです
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月26日
日本人の志向にふさわしいもの
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
広い世界の出来事や景色や話題の情報を縮めて、
自分の部屋のなかに引き入れるテレビ文化こそ、
もっとも日本人の志向にふさわしいものなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月22日
石の骨格
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
自然を縮めようとするとき、
もっと重要なものとなるのは、
木でも水でもありません。
木や水に、
ある形と運動と空間を与える構造は石です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月21日
日本人は集団主義
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
日本人は生理的に
一人ぼっちでいることに
たまらない不安を覚えます。
紋の型・集団に入っていると、
かえって心が落ち着くのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月19日
見るを詰める
2012年06月18日
構え
2012年06月16日
弁当主義文化
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
なんと弁当箱を行厨(こうちゅう)とも呼んだのをみれば、
くだくだしく語源をただすまでもなく、
日本人は動く厨房の意味でそれを作ったのだといえます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月15日
縮み志向
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
手ごろ、
手軽主義の小型に作ること、
そうしながらも
よりコンパクトにして
機能をもっと高めること、
そうするためには
縮めなければならないという着想
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月14日
握りめし文化
2012年06月13日
入れ子仕立ての発想
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
日本人はむかしから、
「広く使って小さく納める」
省スペースの智恵として、
何でも入れ子仕立てに縮めようとした
発想を持っていたのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月11日
思い通りになんかならない
佐野洋子 著 「私はそうは思わない」から
『
理想の子どもなんか一人もいないように、
理想の教師なんてのもいない。
思い通りになんかならないのだ。
お互いさまなのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月10日
現代文明の中の原始人
李 御寧 著 「「縮み」志向の日本人」から
『
子供とは一方、
現代文明のなかで生きていく原始人でもありますから、
神話的な鋭敏な触角を持っており、
それによってこの世界のことや文化を解釈したりもします。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月09日
混とんとしたエネルギーで生きる
佐野洋子 著 「私はそうは思わない」から
『
今の子供である私の息子及び沢山の日本の子供。
とにも角にも生き続けて欲しい。
その混とんとしたエネルギーで。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月07日
混沌とした世界が魅力的
佐野洋子 著 「私はそうは思わない」から
『
世界がわからないまま
存続してゆくであろうということが、
私が生き続けていくことを
励ましてくれるように思えた。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月06日
あっ、わかった
佐野洋子 著 「私はそうは思わない」から
『
「あっ、わかった」
などとうれしそうなに叫ぶのは、
わかんない事だらけの中に生きている証拠で、
わかった事が
「事件」にひとしいことだからである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月05日
もう考えるな
佐野洋子 著 「私はそうは思わない」から
『
もう考えるな。
我々は人間である。
本来人間はトータルな能力のあるものであった。
科学や文明は
人間のトータルな能力をうばったのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月04日
愛はえこひいき
佐野洋子 著 「私はそうは思わない」から
『
愛は身近にいるものを
いつくしむところから生まれて、
それは実に不公平なえこひいきで、
美意識すら変えるものなのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年06月02日
本当の自己主張とは
松浦 弥太郎 著 「今日もていねいに。」から
『
道具となった自分が、
「これならお役に立てますよ」
というものを見つける。
これが本当の意味での
自己主張だと僕は考えているのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年05月31日
忙しいときほど
松浦 弥太郎 著 「今日もていねいに。」から
『
忙しいときほど、
本当に大切なことは何か
優先順位を見つめなおすクセをつけないと、
だんだん恐ろしいことになります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年05月29日
子供は一瞬にして真理をつかむ
佐野洋子 著 「私はそうは思わない」から
『
子供が握る一瞬のうちの心理は
もしかしたら不変のものかも知れない。
いかなる高僧も長い修行の末得るものを
一瞬にして感知する能力を子供は持っている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年05月26日
気分転換がやって来る
2012年05月25日
自分株式会社
松浦 弥太郎 著 「今日もていねいに。」から
『
赤字で借金をしなければやっていけないのか、
大儲けはできなくても滞りなくお金が流れているのか、
ちゃんと把握しておかなくては、
人生をコントロールできなくなります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年05月23日
視点の移動が必要
2012年05月21日
現実を変えるには
環境エネルギー政策研究所所長 飯田 哲也 さんの言葉から
『
ベースは現実は多様で複雑だということ。
強者と弱者という対立軸も大事だけど、
弱者も汚い所、強者にもぐずぐずの弱い部分があって
両者が歩み寄れるところを探せばいい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年05月19日
いじめる側は見方が歪んでいる
松井 彰彦 著 「高校生からのゲーム理論」から
『
いじめの問題は
いじめられる側ではなく、
いじめる側のものの見方が歪んでいることから
帰納的に生じることをみんなが理解すれば、
何を変えるべきかの答えは
自ずと見つかるであろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年05月17日
ふれる暇もなく終わる日々
松浦 弥太郎 著 「今日もていねいに。」から
『
大切なものにふれる暇もなく終わる日々が連なるとは、
大切なものをぽろぽろと取りこぼしていく日々が
積み重なることでもあります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年05月15日
今日も好奇心を
2012年05月12日
日本の民主主義は雨乞い
松井 彰彦 著 「高校生からのゲーム理論」から
『
日本の民主主義は、
政府に何とかしてほしいと
お願いをしようとする傾向がある。
雨乞いの発想である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年05月11日
ノーと言われたとき
松浦 弥太郎 著 「今日もていねいに。」から
『
ノーと言われたということは、
関心を持ってもらえているのですから、
そこからがスタート。
仕事に限らずプライベートでも、
それくらいの気持ちでいます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年05月08日
郷
松井 彰彦 著 「高校生からのゲーム理論」から
『
集団の力というのは恐ろしい。
どこへ行っても、
そこのやり方があり、
それ以外のやり方は否定される。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年05月07日
出会いが教えてくれる
松浦 弥太郎 著 「今日もていねいに。」から
『
気まずいこともあれば、
腹が立つこともあるのが現実の暮らしでしょう。
だからこそ、
「この出会いから、自分は何を学べるだろう?」
と考えることに意味があるのではないでしょうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年05月06日
変わらない月日を過ごすと
松浦 弥太郎 著 「今日もていねいに。」から
『
何一つ変わらないまま月日がたてば、
心はそのうち、やわらかさを失います。
精神が凝り固まるほど、
危険なことはありません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年04月29日
失敗は学習プロセスにつきもの
ティナ・シーリング 著 「20歳のときに知っておきたかったこと」から
『
失敗は学習プロセスにつきものだということを
肝に銘じてください。
失敗していないとすれば、
それは十分にリスクを取っていないからかもしれません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年04月26日
鶴の一声
松井 彰彦 著 「高校生からのゲーム理論」から
『
民主的な国であればあるほど、
鶴の一声がないと物事がまとまらない。
国家存続の危機には、
だれも何が最良の戦略かわからず、
自分の考えを繰り返して
議論が平行線を辿(たど)るのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年04月25日
国民の慢心と強欲
前坂 俊之 著 「明治三十七年のインテリジェンス外交」から
『
国民の慢心と強欲が、
国際政治や外交に携わる者たちの能力に反映され、
その失敗によって、
国民が辛酸をなめさせられることになる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年04月24日
改良が必要な部分を見極めること
ティナ・シーリング 著 「20歳のときに知っておきたかったこと」から
『
動いているとは思えないプロジェクトでも、
何らかの価値を引き出す方法はつねにある
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年04月23日
日本病
前坂 俊之 著 「明治三十七年のインテリジェンス外交」から
『
全体的なインテリジェンスの未熟、
国家戦略の不在、
総合的な判断の欠如という
「日本病」
』
この病は、今日のソニーやシャープの失敗にも当てはまります。
![]() トップが明確な作戦計画を指示することが大切
トップが明確な作戦計画を指示することが大切
![]() 状況も変えれるのが人間
状況も変えれるのが人間
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年04月17日
外交インテリジェンス
前坂 俊之 著 「明治三十七年のインテリジェンス外交」から
『
外交インテリジェンスこそ、
軍事力にも劣らぬ破壊力を秘めている。
戦争は軍事力だけでやれるものではない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年04月16日
外に出て
ティナ・シーリング 著 「20歳のときに知っておきたかったこと」から
『
外に出て、
多くの物事に挑戦する人の方が、
電話がかかってくるのをじっと待っている人よりも
成功する確率は高い
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年04月13日
外交談判というものは
前坂 俊之 著 「明治三十七年のインテリジェンス外交」から
『
外交談判というものは、
国力を如実に示す兵力が伴わなければ、
たとえいかなる英雄が控えていても、
いかなる雄弁家が弁舌を振るっても、
いかなる交渉術の上手な人があって国交を図っても、
だめなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年03月31日
同質であり続けるとコスト爆発になる
須田 アルナローラ 著 「「インド式」インテリジェンス」から
『
同質なことはコストである。
人工な状態はコストがかかる。
同質はぜいたくなのである。
このコストは今後、爆発的に高くなる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年03月29日
完璧でないのが自然
2012年03月27日
強みは場所と使い方を選ぶ
竹内一正 著 「ジョブズの哲学」から
『
いかなる強みも、
使う場所と使い方を間違えると、
途端に弱みになってしまうことがわかっていたら、
強みの扱い方も違ってくる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年03月24日
子どもに勉強させる唯一の方法
須田 アルナローラ 著 「「インド式」インテリジェンス」から
『
子どもに勉強させる方法はただ一つ。
「興味を持たせて、納得してもらって、勉強させる」
という考え方ではなく、
「今は勉強の時期だから勉強する」
これしかない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年03月22日
一貫性はなくても今正しいことをしよう
須田 アルナローラ 著 「「インド式」インテリジェンス」から
『
同質性や一貫性に置いている重きが、
現実を超えてしまっているのだ。
「一貫性がなくてもいいから、
よいことや正しいことをしよう」と言えば、
それで多くは改善されるはずだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年03月18日
目的以外は見えないぐらい集中すること
須田 アルナローラ 著 「「インド式」インテリジェンス」から
『
目的を達成する際に、
その周りの情報が気になっている間は
目的達成はできないので、
矢を引くことさえ無意味である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年03月16日
日本で世界レベルのソフトウェアが出来ない理由
須田 アルナローラ 著 「「インド式」インテリジェンス」から
『
ソフトウェアは
クオリティの問題以前に、
さまざまな対応を柔軟に
しなければならないので、
同質性を重んじる国は不得意なのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年03月09日
夢への近道とは
2012年03月06日
日本が世界から尊敬されるには
須田 アルナローラ 著 「「インド式」インテリジェンス」から
『
同質であることを求めない日本人になった時、
日本は本当の意味で
世界から尊敬される国になるのでは
ないだろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年03月04日
これからは「多彩性」が得になる
須田 アルナローラ 著 「「インド式」インテリジェンス」から
『
これからの日本にとって、
「同質性」に固執することは「ソン」であり、
「多彩性」を受け入れることが「トク」になるという状況は、
すでに着々と進行している
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年03月03日
立ち止まって自分に問いかける
2012年02月29日
市場とデザイン
竹内一正 著 「ジョブズの哲学」から
『
デザインの重要性が
あらゆる市場で求められると
過信するのもご法度である。
冷静に市場を見て判断しなくては、
デザインは
刺身のツマ以下になりさがる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年02月27日
したたかさとは
竹内一正 著 「ジョブズの哲学」から
『
交渉のテーブルには、
本当に必要なことを上回る条件まで
平気で乗せる大胆さが必要だ。
したたかさとは、そういうものである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年02月22日
身近なチャンスに目を向ける
2012年02月21日
明日のご飯をつくりだせ
竹内一正 著 「ジョブズの哲学」から
『
今日のご飯を食べることにだけ
エネルギーを使い、
明日のご飯をつくりだす努力をしないからだ。
将来への投資を怠った企業に未来はない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年02月11日
事実は形容詞を超える
山崎豊子 著 「大阪づくし私の産声」から
『
素材が大きくなると、
形容詞なんかは拒否しちゃいますね。
事実の積み重ね、重み、
そんなもんがどんどん前へ行ってしまいます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年02月10日
女の年齢は実力なり
山崎豊子 著 「大阪づくし私の産声」から
『
女の年齢は、戸籍年齢ではなく、
人から見られただけが年齢、
つまり女の年齢は、実力なりというのが、
私の信条である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年02月09日
床文化と壁文化
芦原 義信 著 「街並みの美学」から
『
靴を脱いで室内に入ることは、
内部が外部より上位の空間秩序に
属することを意味する。
そして西欧の壁の厚い石造建築のように
「床」より「壁」に価値観をもつ考えかたと
強く対峙しているのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年02月08日
魑魅魍魎
山崎豊子 著 「大阪づくし私の産声」から
『
現代の日本人に対してそのまま当てはまる。
私利私欲にまみれ、
国の将来を危うくしている魑魅魍魎こそ、
最も危険な動物ではないか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年02月07日
生きた取材とは
2012年02月06日
デザイナーとしての勘どころ
山崎豊子 著 「大阪づくし私の産声」から
『
儲けなくていい、
買って貰わんでいい
と大きく出れば、
逆にお客は買いたくなるやろし、
また儲けを考えずに思いきって大胆に作ったものが、
ちゃんと売れる商品であることが、
デザイナーとして一番大事な勘どころや
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年02月03日
小さいものから大きいものを読み取る
芦原 義信 著 「街並みの美学」から
『
小さいものは大きいものである
ということを弁証論的に確かめようとすれば、
小さいものの世界で想像力を発揮して、
夢み、考えるよりしかたがない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年02月02日
誇れない日本の都市
芦原 義信 著 「街並みの美学」から
『
わが国の都市は
しっかりしたビジョンもないまま
幾多の試行錯誤をくりかえして、
ついに、
世界にこれといって誇ることのできない街並みと
住環境をつくってしまった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年01月31日
日本は都市空間を芸術的にできない
芦原 義信 著 「街並みの美学」から
『
一体、床の間にかける掛軸や生花の美的伝統は、
わが国の外部空間には通用しないのであろうか、
と疑いたくなるのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年01月27日
生活には小さな空間が必要
芦原 義信 著 「街並みの美学」から
『
自然はもともと茫漠として大きな空間である。
その自然の中に空間を限定する要素を取り込んで
小さな空間を創り出すことが、
人間の生活にとっていかに大切なことであるかが
よくわかると思うのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年01月25日
今年はのろけて乗り切る
山崎豊子 著 「大阪づくし私の産声」から
『
今年はお互いに
のろけ合おうやおまへんか、
おのろけばかりは、
せちがらい世の景気などと無縁のしろもので、
ほんまに結構でございます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年01月24日
大阪弁は商人ことば
山崎豊子 著 「大阪づくし私の産声」から
『
大阪弁がラブシーンと独白に弱みを見せるのは、
大阪弁が商人ことばとして
強い個性と効果を持っている
一つの証左にほかならないのではないかと思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年01月23日
飲み根性
山崎豊子 著 「大阪づくし私の産声」から
『
いくら飲んでも、
人間の真性を失わず、
明日の仕事の余力をちゃんと勘案する飲み方こそ
飲み根性をいえるものではなかろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年01月21日
社会に向けた情報デザイン
渡辺 保史 著 「情報デザイン入門―インターネット時代の表現術」から
『
ディスプレイの内側のデジタルな世界だけを
キレイに作り込むのではなく、
リアルな場に根差したデザインを
模索していかないかぎり、
情報デザインは真に社会に向けて
開かれていかないのだ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年01月20日
1973年からの警告
映画 「日本沈没」から
『
田所のようなおかしな学者が、おかしなことを言って、
マスコミがそれをもうちょっと真剣に取り上げ
騒いでいてくれていたなら、
与党であれ野党であれ、どちらが政権を担当していても
もう少しましな対策がとられ、
そうすれば、
こんなに沢山の人が死ななくて済んだんだ!
』
これは映画(1973年)の中で丹波哲郎が演じる内閣総理大臣が、東京大震災の後で言った言葉です。「117」、「311」が起きるはるか以前に、原作者 小松左京が日本人に対して出していた警告です。
このあと、秘書官の「100万食の食料を確保しました」という報告に、「きみ! 東京の人口は・・・」と声を荒げて言ったあと絶句してしまうシーンがありました。
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年01月18日
勉強ぎらいな人間も
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
日本では学校教育を受けない人間は、
みな軌道から弾きとばされて、
人なみな楽しい生活が送れぬようになっているが、
それは、そういう社会の方が悪い。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年01月17日
財産とプライドが奪われるとき
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
財産を取りあげるには
情報を与えないでおくこと。
プライドを取りあげるには、
社会的圧力を加えること。
』
つまり、
財務省と民主党が、増税の根拠を明確にしないまま、国民の財産を奪おうとしているということ。
橋下大阪市長、教育委員会が、「君が代」斉唱しない教師を罷免すると脅しているということ。
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年01月10日
ヨーロッパの生活は外見的に学んでいる
芦原 義信 著 「街並みの美学」から
『
家に規定せられて
個人主義的・社交的なる公共生活を
営み得ない点においては、
ほとんどヨーロッパ化していないと
言ってよいのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2012年01月03日
見えないデザイン
渡辺 保史 著 「情報デザイン入門―インターネット時代の表現術」から
『
誰もが軽々と「デザイン」と口にしながら、
実はそこから取りこぼされている
「見えないデザイン」は山のようにリスト化できる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月28日
大阪弁には幸福という語がない
2011年12月25日
情報デザインとは
渡辺 保史 著 「情報デザイン入門―インターネット時代の表現術」から
『
情報デザインとは、
実際のところ物事の背後にある
見えない関係を発見し、
それを組み換えることにほかならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月23日
弊履(へいり)の如く
田辺 聖子 著 「人生は、だましだまし」から
『
モノにはモノの生命と使命がある。
それとつき合い、
完(まっと)うせしめてこそ、
モノがこの世に生み出された
責務が果されるのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月21日
世の中で貴重なもの
田辺 聖子 著 「人生は、だましだまし」から
『
世の中で貴重なものは、
真情であって、
その表現方法の不備は
問うところではない。
むしろそのほうが粋である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月20日
今日びの女
田辺 聖子 著 「人生は、だましだまし」から
『
今日びの女はすでに、
半分、男性化しており、
一人で世に立ってゆく辛さも
男なみに思い知らされている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月19日
心をこわばらせているもの
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
いまの世の中は、
人にバカにされまいという意識が、
まるで社会という舟の竜骨のように、
人々の心を硬張(こわば)らせている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月18日
ロマンチシズム
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
ロマンチックというものは、
現実の中にあると私は思う。
生きた言葉、
日常次元の中に、
美があり、ロマンチシズムがあると思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月16日
強い女が戦後を支えた
田辺 聖子 著 「人生は、だましだまし」から
『
強い女たちが、
終戦後、ややもすると虚脱や自暴自棄、
荒廃に落ちこもうとする日本を
支えたのは事実である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月14日
ユニバーサルデザインとは
木全 賢 著 「デザインにひそむ〈美しさ〉の法則」から
『
すべての人が満足する
モノや施設や環境を
整備することは難しいことですが、
それでもあきらめずに
選択肢を増やしていくこと。
それがユニバーサルデザインの
コンセプトなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月07日
「萌え」のデザイン
2011年12月06日
人は人によって
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
人の言葉。
人の仕打ち。
人の感情。
それだけが、
人を生かしもし、殺しもするのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月05日
京都の町が千年続いた訳
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
本音いうたら、あきまへん。
本音いわへんよってに、
京都の町は千年から、
つづいてるのどす
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月04日
オトナはインテリと同じ
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
オトナというものはインテリと同じで、
バツのわるいこと、
はずかしいこと、
イヤなことを
うまく避けるコツを知っている人のことである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月03日
多様性がもたらす豊かさ
三橋順子 著 「女装と日本人」から
『
多様性をもつ社会の大切さ、
多様性がもたらす豊かさということです。
しかし、残念ながら、
この当たり前のことを認めようとしない人たちが
まだまだ世の中にはいるのが現実です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年12月02日
達人とオトナ
2011年11月30日
「見立て」という思考法
三橋順子 著 「女装と日本人」から
『
日本の伝統文化には
「見立て」という思考法があります。
あるもののイメージを
別のあるものに投影すること、
擬似同型的なイメージ転位です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月29日
ファッションとは
ファッションデザイナー ポール・スミスさん の言葉から
『
医師や救急隊員のように
命は救えないけれど、
音楽や読書と同じように、
人をハッピーにしたり、
考え方を変えさせたりする力がある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月26日
イロをつける心があれば
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
イロをつける、
大目にみる、
ふくみをもたせる、
これはとてもたいせつだ。
<イロをつける>心があれば世の中、
スムーズにいくこと多し。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月23日
デザイン、暗黙の前提
木全 賢 著 「デザインにひそむ〈美しさ〉の法則」から
『
性能が良かろうが悪かろうが、
美しければ使いやすそうだと
感じてしまう。
デザインという行為には
そういう暗黙の前提があります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月20日
緊迫したときには
福井大学医学部教授 寺沢 秀一 さんの言葉から
『
緊迫したときに大声を出すと
自分が冷静ではなくなる。
それ以上に、
周りの人は冷静さを忘れる。
マイナスが大きすぎるんです
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月18日
人間の家とは
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
家、というのは、
外で何かあると、
(早く帰ってこのことをしゃべろう!)
と走って帰る先が、
人間の家というものだと思うものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月15日
不機嫌は一つの椅子
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
不機嫌というのは、
男と女が共に棲む場合、
一つしかない椅子だと思う。
どちらかがそこへ坐ったら、
片方は坐れない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月11日
気楽
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
かわいげのない男と暮らすぐらいなら、
一生ひとりでいるほうが
どれほど気楽か知れはしない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月10日
女流政治家が出るべきとき
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
マヤカシの男流政治家にとって代り、
女流政治家が出てくるのは
時の勢いというものかもしれない。
政治こそ、
女がやるに適した仕事であろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月09日
子どもが育つ母性
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
母性が鈍感で、
抱擁力が大きく、
ゆうゆうとしているからこそ、
子どもは育つのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月07日
女性が楽しんで生きているのは良い社会
田辺 聖子 著 「女のおっさん箴言集(しんげんしゅう)」から
『
女性が心から楽しんで生きていない社会は、
どんなに繁栄してみえても、
それはいびつで偏った社会で、
土台は脆(もろ)い
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月06日
宇宙は巨大カジノ
スティーヴン・ホーキング 著 「ホーキング、未来を語る」から
『
神様はきわめつけの
ギャンブラーであることを示しています。
宇宙は、常にサイコロが振られ、
ルーレットの回転盤がいつも回されている
巨大なカジノのようなものだと考えることができます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月04日
女形はファッションリーダーだった
2011年11月03日
しぶとう、生きるんじゃ
田辺 聖子 著 「ほっこり ぽくぽく 上方さんぽ」から
『
大阪は何やかやしもって、
しぶとう、生きるんじゃ。
抛(ほう)っといてくれ。
オマエらに心配してもらうこと、
あらへんわい!
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年11月02日
日本はゆたけき国
田辺 聖子 著 「ほっこり ぽくぽく 上方さんぽ」から
『
日本という国は
とてつもない世界遺産を持っている、
ゆたけき国である。
それをまず自覚すべき。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年10月31日
大阪中華思想
田辺 聖子 著 「ほっこり ぽくぽく 上方さんぽ」から
『
元来、
大阪人の悪癖陋習(あくへきろうしゅう)として、
大阪中華思想の偏見にみちみちており、
ヨソの街をホメたためしがない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年10月30日
日本芸能は異性装
三橋順子 著 「女装と日本人」から
『
異性装の要素を持たない
芸能の方が少ないのです。
むしろ、異性装の要素をもつことが
日本の芸能の「常態」なのではないかと
思えてきます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年10月28日
女装の英雄
三橋順子 著 「女装と日本人」から
『
いつの時代にも
女装のヤマトタケルの物語は、
身近な英雄譚のひとつでした。
そこには、
日本人の女装に対する
原イメージがあるように思うのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年10月26日
よめはんは京女がいい
田辺 聖子 著 「ほっこり ぽくぽく 上方さんぽ」から
『
芸人の女房(よめはん)は京女に限る、というのがある。
男が落ち目になったら京女はすぐ、
男を見捨てて去ってゆく。
<お気張りやっしゃ>と冷たい一言を残して。
男は<くそう>と腹立てそれで奮発するのである
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年10月22日
希望を抱いて旅を続けること
2011年10月18日
ヘッジファンドが世界経済を崩壊させる
長谷川英祐 著 「働かないアリに意義がある」から
『
モノの生産と流通を行わない
ヘッジファンドなどが
企業活動の利益を吸いあげて、
一つになった経済圏全体の
経済基盤を弱めてしまう
働きには対抗できません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年10月17日
良い理論とは
スティーヴン・ホーキング 著 「ホーキング、未来を語る」から
『
良い理論とは、
簡単な仮説に基づいて広範囲の現象を説明し、
検証可能な明確な予言ができるものです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年10月16日
上方ニンゲンは潤色
田辺 聖子 著 「ほっこり ぽくぽく 上方さんぽ」から
『
上方ニンゲンは
うそつきというのではないが、
相手にショックを与えるまいとして、
いささか表現に
潤色をほどこすこともないではない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年10月15日
関西は反骨
田辺 聖子 著 「ほっこり ぽくぽく 上方さんぽ」から
『
関西文化圏はつねに、
<こっちが文化の総本家や>
という確信があり、
よそからみれば、
これぞ反骨、
になるのかもしれない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年10月14日
関西人的アホ
田辺 聖子 著 「ほっこり ぽくぽく 上方さんぽ」から
『
関西人的感覚のアホは、
ひたすら仲間意識の愛情にみちたコトバで、
東京弁の<馬鹿>と一緒にならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年10月09日
大坂は包容力の大きい土地柄
2011年09月26日
意見が違うのは定義が違うから
長谷川英祐 著 「働かないアリに意義がある」から
『
世の中の意見の食い違いは、
話していることの定義の違いを
意識していないことから
来ている場合も多いのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年09月25日
大阪弁の川柳
田辺 聖子 著 「ほっこり ぽくぽく 上方さんぽ」から
『
大阪弁と七五調は出合いもので、
うまく文芸化できれば
いい味の川柳になる。
「命まで賭けた女てこれかいな」
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年09月24日
大阪色に染めてしまう
田辺 聖子 著 「ほっこり ぽくぽく 上方さんぽ」から
『
ともかく大阪というまちは
染料が強(きつ)いから
誰でもすぐ大阪色に染まってしまう。
難儀な町や。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年09月21日
大阪のうちらは、ほっこり
2011年09月17日
大阪弁こそ日本語
田辺 聖子 著 「ほっこり ぽくぽく 上方さんぽ」から
『
大阪人は東京だろうが
どこだろうが
平気で大阪弁をしゃべる。
大阪弁を方言と思っていないせいだ。
大阪弁こそ
世界に冠たる日本語だと
思っているふしがある
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年09月16日
人生にはなじみ店が必要だ
池内 紀 著 「今夜もひとり居酒屋」から
『
ひしめき合った飲み屋街に、
自分のなじみの店をもつのは
人生のたのしみであり、
それが
また格別のランドマークになって、
風狂な散歩者の道案内をしてくれる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年09月15日
十把一絡(じゅっぱひとからげ)
池内 紀 著 「今夜もひとり居酒屋」から
『
学者からは
「一般大衆」だの「庶民」だのと
十把一からげにいわれるが、
この世で暮らしていくには
沢山の智恵がいるのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年09月14日
個人は社会に依存している
長谷川英祐 著 「働かないアリに意義がある」から
『
個人は生活のあまりに多くを
社会に負っているため、
一人で生きていくことなど
想像もできなくなっています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年09月13日
新人を常連にするのがプロの店
池内 紀 著 「今夜もひとり居酒屋」から
『
新顔クラスをいじけさせるのは、
むろん、店が悪い。
新人を一夜にして常連の卵に仕立ててこそ
プロの腕だろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年09月08日
食べ物屋は気楽な方がいい
池内 紀 著 「今夜もひとり居酒屋」から
『
寄り道をして、
肩をこらして帰るのはつまらない。
どんなに主人がガンバリ屋でも、
客に緊張を強いるのは
よくない店ではなかろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年09月06日
季節の食ベ物はとっておき(ハモン)だった
池内 紀 著 「今夜もひとり居酒屋」から
『
いつでも、何でも口にできて、
はたして幸せなのか?
食べ物に季節がなくなり、
日本の居酒屋は
とっておきのハモンを
失ったのではなかろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年08月30日
自分の事で精一杯な時代
小谷野 敦 著 「美人好きは罪悪か?」から
『
だいたい食えない、
「鬱」をめぐる本がベストセラーになる時代に、
君と世界の戦いで
世界になど支援しているわけには
いかないではないか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年08月29日
居酒屋は人生の夜学
池内 紀 著 「今夜もひとり居酒屋」から
『
居酒屋は人生の夜学であって、
たのしく酔いながら、
いわず語らずのうちに
さまざまな勉強のできるところだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年08月26日
戦略が間違っていたら戦術は意味を成さない
松村 劭 著 「名将たちの戦争学」から
『
もし、戦略が間違っていたら、
戦場でどんなに名将が勝利を稼ぎ、
兵士が剛勇をふるっても、
それが決定的でないかぎり、
その効果はむなしいものになる
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年08月25日
人生論式新書は嘘が書いてある
小谷野 敦 著 「美人好きは罪悪か?」から
『
出版不況などと言いつつ、
どれもこれも似たような、
「頑張れば必ず成功する」
みたいな嘘の書いてある人生論式新書やら、
癒し系小説やらで売ろうとするなら、
美人作家をそうやって活用するほうが、
よほど好ましい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年08月23日
美貌は美人よりランクが高い
小谷野 敦 著 「美人好きは罪悪か?」から
『
「美貌」という言葉は、
「美人」よりランクが高い。
その辺にいるようなものではない、
という語感が強い。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年08月18日
防衛力を育成するときには
松村 劭 著 「名将たちの戦争学」から
『
「世論」、「政府の政策」、「外交」は、
短時間のうちに猫の目のように変わりやすい。
だから、
他国の戦争能力に対応して
自国の防衛力を育成するときは、
この三つの要素を
考慮しないことが重要である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年08月17日
言葉は魔法に似ている
2011年08月16日
先入観が情報を歪める
2011年08月14日
目には目を、歯には歯を
松村 劭 著 「名将たちの戦争学」から
『
戦いにおいては、
いかなる組織であっても、
個々の要素が相手側の同じ要素と競い、
戦うのが最も効率がよいとされる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年08月12日
自分自身を教育する
マイク・リットマン 著 「史上最高のセミナー」から
『
すばらしい秘訣を
ただ持っていてはダメなの。
多くの人がそうしようとするけど。
教育と経験が重要なのよ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年08月11日
大胆さが幸運を呼ぶ
2011年08月10日
栄光への脱出
2011年08月09日
主敵が何かを見定める
2011年08月06日
後悔よりも規律を
2011年08月05日
そうかもしれない
小谷野 敦 著 「美人好きは罪悪か?」から
『
自分では美人だと思わなかったのに、
あまりに多くの人が
美人だ美人だと言うのを聞いていると、
そうかもしれないと思えてくる
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年07月30日
言葉は慎重であれ
マイク・リットマン 著 「史上最高のセミナー」から
『
そこで成功し、
よりよい給料を手に入れ、
出世したいと思うなら、
慎重でなければならない。
その最たるものの一つが言葉なんだよ。
』
どこかの国の元復興大臣に聞かせてあげたい言葉です。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年07月29日
ありふれた定型化を破るには
松村 劭 著 「名将たちの戦争学」から
『
命令は具体的、
かつ簡単明瞭に与えることである。
状況が困難なほど、
命令は簡明であるべきだ。
それがありふれた
定型化を破ることになる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年07月28日
優れた術は美しくて簡単
2011年07月22日
敵情に振り回されるな
松村 劭 著 「名将たちの戦争学」から
『
敵を過小評価してはならないが、
敵ができもしないことまで憂えて、
作戦計画を混乱させるな。
敵情に振り回されるのは最悪だ
』
同業態の会社が敗退したからといって、同じ状況に陥ることばかり心配してはいけません。自分の立っている場所はどこで、どの状況で戦うべきかを、しっかりと見定めるべきです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年07月20日
“利”と“義”
渋澤 健 著 「渋沢栄一 100の訓言」から
『
“利”のためには、
まず “義” を考える。
そして、
“利” を得てこそ
“義” を尽くせるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年07月12日
経済活動に勝利するためには
松村 劭 著 「名将たちの戦争学」から
『
経済活動に勝利するためには、
売買行為において、
競争相手より
「利分」の説得技術(営業力)が
優れていなければならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年07月11日
想定外と言わないために
2011年07月08日
社会を良い方向に進めるためには記録を残す
松岡資明 著 「アーカイブズが社会を変える」から
『
社会を少しでも良い方向に
進めていく意志があるのであれば、
まずは記録を残すことに
努めようではないか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年07月06日
心からの気持ちで
渋澤 健 著 「渋沢栄一 100の訓言」から
『
心からの気持ちで、
「ありがとう」
と伝えることは、
本当に、本当に
大事なことです。
』
松元龍復興担当相が辞任しました。人の気持ちを考えられない人は、上に立つ資格がありません。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年06月29日
新たな知識を生むには
2011年06月27日
時期が来るまで
渋澤 健 著 「渋沢栄一 100の訓言」から
『
「今はたまたま、時期が悪いだけ」
このように柔軟に考えて、
忍耐強く事に接すれば、
いずれチャンスは訪れてきます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年06月25日
沈みかかった日本に必要なもの
松岡資明 著 「アーカイブズが社会を変える」から
『
沈みかかった日本にとって今、
必要とされるものは
「公共」
すなわち
「国民共有」の意識であり、
今後進むべき方向の礎となる
「知的資源」なのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年06月21日
テクノロジーだけだと社会は破滅する
【スタートレック・ネクストジェネレーション】ピカード艦長の言葉:
『
テクノロジーの力に頼って、
社会を急激に変えるのは
危険なことなんです。
破滅に繋がります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年06月20日
礼儀を尽くせる人とは
渋澤 健 著 「渋沢栄一 100の訓言」から
『
本当の意味で
「礼儀を尽くせる」ということは、
本当の意味で
「自分自身に自信を持っている」
ということでもあります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年06月16日
歴史資料を材料として供給すると
松岡資明 著 「アーカイブズが社会を変える」から
『
材料をストックとして
たくさん提供していくことが
最終的に巨大な、歴史的なあるいは、
将来にわたるアカウンタビリティーになっていく
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年06月14日
記録を残すということ
2011年06月13日
一人一人がよい方向へ向わなければ
2011年06月11日
記録すると本質が見えてくる
松岡資明 著 「アーカイブズが社会を変える」から
『
目の前の、
ある意味では退屈極まりない
繰り返しの行為を
きちんと記録することによって
初めて、
物事の本質が見えてくるものもある。
』
スター・トレックは、毎回「航星日誌」で始まります。人には「航生日誌」、そして、政治家には「更生日誌」が必要ですね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年06月10日
幸福の源
2011年06月09日
表裏一体
渋澤 健 著 「渋沢栄一 100の訓言」から
『
「考えること」と「行動すること」。
あなたはこの二つを、
まったく別ものだと考えていませんか?
それは違います。
この二つは表裏一体なのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年06月08日
幸せになりたいと願うとき
渋澤 健 著 「渋沢栄一 100の訓言」から
『
「幸せになりたい」
と願うとき、
それには、
自分のために仕事や勉強を
がんばればいいと思っていませんか?
それは、あなたの驕(おご)りです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年05月31日
ジェネレーションで未来をイメージする
池田純一 著 「ウェブ×ソーシャル×アメリカ」から
『
ジェネレーションという観点から
世界を擬人化して捉えることで
未来の共通イメージを持ちやすくする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年05月28日
最もよくできた統治とは
池田純一 著 「ウェブ×ソーシャル×アメリカ」から
『
最もよくできた統治は
人々が不満を述べず、
不穏な動きをしないことであり、
太平とはそういうものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年05月25日
富を永続させるということ
2011年05月24日
組織が世界を作る
2011年05月21日
情報に大切なもの
2011年05月20日
変革を実践する場
池田純一 著 「ウェブ×ソーシャル×アメリカ」から
『
世界は生態系として一つであり、
外部に抜け出すことはできない。
そうであれば、
どこであろうと
今あるこの場所が
変革を実践する場となる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年05月19日
最良のデザインとは
2011年05月18日
惑星レベルで考える
池田純一 著 「ウェブ×ソーシャル×アメリカ」から
『
地球が球として
一つであることを知れば、
人々は惑星レベルで
物事を捉えるようになる
』
福島で放射能漏れ、メルトダウンしたのではありません。
地球上でメルトダウンしたのです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年05月15日
言説の紡がれ方
池田純一 著 「ウェブ×ソーシャル×アメリカ」から
『
神話=言説
がどうあれ
それとは関係なく世の中は動いていくものだし、
その現実の動きが再度、
起源の神話を召喚する。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年05月14日
相手の心に合わせて書く
2011年05月13日
伝えたい情熱が伝える
池上 彰 著 「相手に伝わる話し方」から
『
「これだけは伝えたい」という、
内心からほとばしり出る情熱があれば、
たとえ説明は拙(つたな)くても、
それは相手に伝わるものだと思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年05月12日
世間の智恵を身につけるには
2011年05月10日
「あがる」を使いこなす
池上 彰 著 「相手に伝わる話し方」から
『
「あがる」
という状態をうまく使いこなす。
そのくらいの大らかな気持ちで、
なにごとにもぶつかってみてください。
きっと、
いい結果が出るはずです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年05月07日
具体論で話題に引き込む
2011年05月06日
手紙は思いやり
外山 滋比古 著 「文章を書くこころ」から
『
手紙を書くには、
相手を思いやる心がないといけない。
いまはその心の失われた通信が
あまりにも多く、
世の中をささくれ立ったものに
感じさせる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年05月05日
返信には風を入れる
外山 滋比古 著 「文章を書くこころ」から
『
怒って書いた手紙は
かならず翌日まで投函するのを待て、
そしてもう一度読み返してみよ、
きっと書き改めたいと思うだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月30日
変奏が展開させる
外山 滋比古 著 「文章を書くこころ」から
『
まったく同じ旋律が
何度もあらわれると、
時間が停止しているような
錯覚をおこしかねない。
バリエイションは
楽曲が展開していることを
はっきいりさせる効果をもっている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月29日
わかったと感じるには
池上 彰 著 「相手に伝わる話し方」から
『
自分の知識の中にあった
バラバラの用語の関係がはっきりすることで、
自分の頭の中の知識が体系づけられ、
「わかった」と感じるようになるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月28日
絵を描き言葉で伝える
池上 彰 著 「相手に伝わる話し方」から
『
自分の頭の中にどんな「絵」を描くか。
それを、
相手にどんな言葉で伝えるのか。
これを常に自問自答していると、
わかりやすい伝え方が
ひねり出せるものなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月26日
文章は天ぷら
外山 滋比古 著 「文章を書くこころ」から
『
文章は天ぷらのようなところがあって、
さっと揚げたところがおいしい。
これをもう一度揚げては
味が落ちる
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月23日
わかりやすい説明とは
池上 彰 著 「相手に伝わる話し方」から
『
①むずかしい言葉をわかりやすくかみ砕く
②身近なたとえに置き換える
③抽象的な概念を図式化する
④「分ける」ことは「分かる」こと
⑤バラバラの知識をつなぎ合わせる
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月22日
出来事は立体的に表現する
池上 彰 著 「相手に伝わる話し方」から
『
出来事を、
地図にする。
立体的な見取図にする。
俯瞰図にする。
ニュースの意味を概念図にする。
登場人物の関係を図式化する。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月21日
文章は単調を嫌う
2011年04月20日
相手の立場に立って話す
池上 彰 著 「相手に伝わる話し方」から
『
「相手は何を知りたいのだろう」
ということを、常に考えます。
そして、そのためには
どんなことを話せばいいのかを考えます。
』
政府も東電も、人々が何を知りたいのかをもっと考えるべきでした。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月19日
テーマは竹串
外山 滋比古 著 「文章を書くこころ」から
『
ネギもトリ肉もあっていいが、
竹串にさしていないと、
焼きトリにはならない。
テーマはその竹串のようなものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月18日
思ったことをどんどん書こう
外山 滋比古 著 「文章を書くこころ」から
『
文章に上達するには、
とにかく書いてみることである。
思ったことをどんどん書いて行く。
そうすれば、
文章などなんでもないと考えるようになる。
そうしたら
はじめて細部に気をつける。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月16日
褒めると上達する
外山 滋比古 著 「文章を書くこころ」から
『
新しいことや難しいことを始めるときに、
やかましい注意ばかりしていては
うまく行かない。
多少足りないところはあっても、
どこかいいところを見つけて、
ほめてくれる人がそばにいると、
目に見えて上達する。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月15日
同一性の壁を破る
2011年04月14日
過保護では成長しない
池上 彰 著 「相手に伝わる話し方」から
『
人は、
過保護では成長しません。
子どもの教育でもそうですが、
社会人になって職場で
働くようになっても同じことです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月13日
相手にしゃべらせるには
池上 彰 著 「相手に伝わる話し方」から
『
人間は、
自分に関心を寄せてくれる人に
好意を持つものです。
自分に関心を持ち、
さまざまな質問を投げかけてくれると、
ついついしゃべってしまいます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月12日
ひとつの文章は一つの要素にする
池上 彰 著 「相手に伝わる話し方」から
『
ひとつの文章は、
ひとつの要素だけを伝える。
これを原則にしました。
すると、読んでいて、
独特のリズムが発生し、
聞き手の頭に入りやすくなることを
発見したのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月11日
物理学では「弱い力」でも福島では脅威
リサ・ランドール 著 「ワープする宇宙 5次元時空の謎を解く」から
『
弱い力は本当に弱いので、
日常の世界で
その存在に気づかされることはないとしても、
多くの核過程にとっては
これが欠かせない力となる。
』
福島原発を冷却し続けなければならないのは、この弱い力が働いているからです。
そして、今まで宇宙には4つの力(強い力、弱い力、重力、電磁気力)の存在が知られていましたが、さらに5つ目の力の存在が証明されつつあるという報道がありました。ひょっとして、これがテレパスの原理なのでしょうか?
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月06日
身近な人から幸せにする
飯田史彦 著 「ブレークスルー思考」から
『
目の前にいる自分の家族さえも
十分に幸せにしていないで、
「世のため人のために役に立ちたい」
などというのは、
本末転倒ではないだろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年04月04日
人間関係とは
飯田史彦 著 「ブレークスルー思考」から
『
人間関係とは、
「同調しあい、反発しあうエネルギー」である。
幸せな人間関係と同様に、
こじれた関係も、
成長の助けとなる。
』
同調は【ダークマター】で、反発は【ダークエネルギー】ですね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月31日
自分自身を解放する
飯田史彦 著 「ブレークスルー思考」から
『
さあ、あなたも、
もう「形」にとらわれる必要はありません。
自分をしばりつけている、
さまざまな思いこみから、
自分自身を解放しましょう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月30日
恐怖心を克服して幸福になる
飯田史彦 著 「ブレークスルー思考」から
『
肉体的な恐怖を追い出し、
価値のないものをすべて排除して、
もっと強い幸福な人間に
生まれ変わろうとすことにより、
少々の恐怖では
びくともしなくなる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月27日
21世紀の国づくりは
2011年03月26日
考えないという発想
飯田史彦 著 「ブレークスルー思考」から
『
考えれば考えるほど
自分を追いつめてしまうような問題の場合には、
「考えないでおこう」
と決めることこそが、
立派で適切な「発想法」なのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月24日
交渉はゲーム
2011年03月22日
代替案は開発するもの
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
優れた代替案は、
じっと待っていてやってくるものではない。
進んで開発しなければならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月19日
立場の背後にある利害を見ること
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
相手側がその立場を主張したときは、
それを拒絶も受諾もしないで、
一つの選択肢として扱う。
そして立場の背後にある利害を見、
それを反映するような原則を探し、
さらに改良する方法を考えることである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月18日
何が起きているかを知る
2011年03月11日
客観的基準でないものはつっぱねること
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
根拠もなく譲歩を迫ってくる相手に
対抗することは、
客観的基準に基づいて
迫ってくる相手に対するよりたやすい。
』
「竹島問題」には根拠もないのですから、著名なんて以っての外ですよ。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月10日
明るい顔がまわりを明るくする
飯田史彦 著 「ブレークスルー思考」から
『
自分の顔は
みんなに見ていただくためにあるんです。
明るい顔がまわりを明るくし、
暗い顔がまわりを暗くします。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月09日
公正な提案は受け入れ易い
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
相手方が受け入れやすい解決を図る
一つの効果的な方法は、
それらが正等に見えるように
体制を整えることである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月08日
相手の利益も考慮すること
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
相手方の立場に
自分自身を置いてみよう。
相手の気をそそる部分が
少しもないような提案では、
とうてい合意はありえない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月07日
大都市では創造力も消費される
清野由美 著 「セーラが町にやってきた」から
『
都市とは本来、
人間の創造力が結集した
場所であるはずだ。
しかし今の日本の大都市は、
その創造力すらも、
あっという間に
消費対象として飲み込むばかりで、
結局、
何も生み出すことがない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月06日
交渉は柔軟に臨む
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
柔軟性を保つためには、
自分が考えた選択肢の一つ一つを
単に案として扱うこと、
そして自分の希望にかなう案を
多数用意することである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月05日
衝突するのは立場ではなく利害
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
交渉における基本的問題は
表面に出た立場の衝突にあるのではなく
根底にある各当事者の
要望、
欲求、
関心および
懸念の衝突
にある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月03日
真剣に耳を傾けさせるには
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
自分の理由を聞いてもらい
理解してもらいたいときは、
自分の関心と根拠を最初に述べ、
結論や提案は後にすべきである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年03月02日
秘密会議の意味
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
交渉に何人の人間が関与しようが、
重要な決定は二人しかいないとこで
なされるのが通常である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年02月28日
交渉の最良の投資とは
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
相手が聞きたがっていることで、
こちら側も言ってさしつかえのないことは、
当初から、相手の納得のいくように、
はっきりと言っておくのが
交渉における最良の投資なのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年02月27日
人の問題から抜け出すには
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
人の問題というジャングルから抜け出すには、
三つのカテゴリーを基本に考えるのが効果的である。
●認識の問題、
●感情の問題、
●意思疎通の問題
がそれで、
人の問題にはいろいろのものがあるが、
結局はこの三つのどれかに入るのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年02月26日
いらいらに対処するには
フィッシャー&ユーリー 著 「ハーバード流 交渉術」から
『
人の怒り、
いらいら、
その他の感情に
うまく対処する一つの方法は、
そうした感情を吐き出す機会を
与えてやることである。
人は自分の不平不満を
誰か他人に話すだけで
解放感を覚えるものである。
』
大阪府の昨年1年間の児童虐待件数が過去最高の1032件になったそうです。前年から倍増!していると、大阪府警の発表が24日にありました。
SNSは感情のはけ口にはなるのでしょうか? ならないなら、現代人はどこをはけ口にすればよいのでしょうか?
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年02月20日
地方にあるからこそ一流を目指す
清野由美 著 「セーラが町にやってきた」から
『
地方にあるから二流で十分だと、
私は考えません。
逆に、
地方にあるからこそ、
細かい点まできちんとサービスを行き渡らせて、
世界に通じる一流の店を
目指してほしいのです
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年02月19日
言語が判断を迷わせる
2011年02月18日
言語は道具
今井むつみ 著 「ことばと思考」から
『
言語は、私たち人間に、
伝達によってすでに存在している知識を
次世代に伝えることを可能にした。
しかし、それ以上に、
教えられた知識を使うだけでなく、
自分で知識を創り、
それを足がかりに
さらに知識を発展させていく道具を
人間に与えたのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年02月14日
利益が出ている時が危うい
清野由美 著 「セーラが町にやってきた」から
『
会社とは利益が出ている時が
じつは危ないということです。
数字が安定すると、
先に行こうとする推進力が
知らず識らず落ちてしまうんです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年02月13日
時間を掛けて良い物を作る
清野由美 著 「セーラが町にやってきた」から
『
今の時代は
納期さえ守ればすべてよしで、
ニセモノがまかり通ってしまいます。
期限を切って
よくないものを作るのではなく、
時間をかけて
いいものを作りましょう
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年02月07日
町起こしに必要なのは理念
清野由美 著 「セーラが町にやってきた」から
『
オリンピック後にさらに人気が出て、
観光客も集め続けている
小布施は異例です。
小布施に行くと、
町起こしに必要な題目は
経済効果ではなく、
理念なんだとよくわかります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年02月05日
交渉力は粘り勝ちする能力
清野由美 著 「セーラが町にやってきた」から
『
何かをやりたいのだけど、
なかなかできないと嘆く人は、
きっと粘りが足りないんです。
交渉力とは
粘り勝ちする能力のことなんですよ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年02月04日
文化というものは
清野由美 著 「セーラが町にやってきた」から
『
文化というものは
高所から論じるのではなく、
その地域にしかない生活史を掘り起こし、
次代に継承することだ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月31日
トム・ボーイ
清野由美 著 「セーラが町にやってきた」から
『
人からそれはできない、
ムリだ、と言われると、
どうしてもやってみたくなる。
反対に期待されると
逆の行き方で驚かせたくなる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月30日
L' AMOUR EST BLEU (邦題 「恋はみずいろ」)
指揮者・作曲家 ポール・モーリアさんの言葉から
『
フランスでは無名で、
それでいいのです。
休息が必要なのです。
崇拝者たちがいないパリで、
自分を再発見するという
バランスが好きです。
誰もが私を知る日本では、
暮らしていけないでしょうから
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月29日
日本独自の食文化=弁当
林 順信、小林しのぶ 著 「駅弁学講座」から
『
米飯とおかずを
木や竹の器にコンパクトに
詰め込んで持ち歩くという、
日本独特の才能と所産物は、
過度に文明の発達した現在でも、
最も好まれる携行食としての位置にいる。
』
![]() 弁当という「小さな宇宙」
弁当という「小さな宇宙」
![]() smart niche:プリクラと掛けて幕の内弁当と解く
smart niche:プリクラと掛けて幕の内弁当と解く
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月28日
遊牧民は「動く」、農耕民は「持つ」
今井むつみ 著 「ことばと思考」から
『
英語は歩く、走るなどの動きでは、
「どのように動くか」で
非常に細かく動作を区別して
カテゴリーをつくっているのに、
「どのように持つか」に関しては
ほとんど区別しない。
』
それは、遊牧民は家畜を追う「動く」という動作が中心を占め、農耕民は農作物を運ぶ「持つ」という動作が中心を占めるからでしょう。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月25日
人類にとっての三つのテーマ
テスラ・モーターズ会長兼CEO イーロン・マスク さんの言葉から
『
大学在学中、
人類にとって今後大切なテーマは何かを考え、
「インターネット」
「持続可能なエネルギー」
「宇宙」
の三つだと結論づけました。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月23日
国会には議員が「ある」
今井むつみ 著 「ことばと思考」から
『
日本語はそもそも、
生きていないモノが存在するときは「ある」と言うが、
人や動物は「いる」と言う。
人、動物と無生物で動詞を区別するのは
日本語の特徴といえるかもしれない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月22日
言語とはカテゴリーに整理したもの
今井むつみ 著 「ことばと思考」から
『
言語は
三次元空間上に無限に存在する
二つのモノの位置関係を、
非常に限られた数の
「位置関係のカテゴリー」に区分けし、
整理しているのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月21日
外国との交渉のスタートは
塩野七生 著 「日本人へ 国家と歴史篇」から
『
文化を共有しない外国との交渉は、
相手側が思わず苦笑いして、
ヤラレタネ、
と思ったときからスタートすべきなのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月20日
勝つのに最も効果的なもの
2011年01月19日
文明は異分子で飛躍する
塩野七生 著 「日本人へ 国家と歴史篇」から
『
文明とは歴史が証明しているように、
異分子が加わることによって生ずる
幾分かの拒絶反応を経験して初めて、
飛躍的に発展するものなのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月18日
多いと無脳になる
塩野七生 著 「日本人へ 国家と歴史篇」から
『
多く集まれば集まるほど、
正しく、かつ問題の解決によりつながる
対策が立てられると信じているとしたら、
人間性に無知というしかない。
』
国会の無能(無脳!)ぶりは、議員の数が多過ぎるからです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月17日
駅弁のときめき
林 順信、小林しのぶ 著 「駅弁学講座」から
『
駅弁のふたをぱっと開けたときの
ときめきを大切にしたい。
一瞬に目入る主調色というのがある。
それは駅弁のモチーフであり、
郷土の香りであり、
やがて味覚となって駅弁との対話が始まる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月16日
人が本屋に行く理由
塩野七生 著 「日本人へ 国家と歴史篇」から
『
人を本屋に走らせるのは、
愉しみへの期待よりも、
不安解消への期待のほうであるのだから。
たとえそれを読んでも、
真の解決にはまったく役立たなかったとしても。
』
新聞にも不安解消本の広告がやたらと多いですね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月15日
政府がガンガンやらねば
2011年01月14日
ショッピングは意味のある投資
塩野七生 著 「日本人へ 国家と歴史篇」から
『
想像力の維持にも役立つ
ショッピングでお金を使うのも、
充分に意味のある投資ではないかと思う。
筋肉であろうと
想像力であろうと、
必要なのは「刺激」なのだから。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月12日
大衆に正しい判断をさせる方法
2011年01月10日
日本では創造しない人達が文化を担当している
塩野七生 著 「日本人へ 国家と歴史篇」から
『
日本の文化交流は、
主として官僚と学者が担当している。
両者とも能力はある人たちなのだが、
両者に共通することがもう一つある。
それは、いずれも自分自身では
創造したことがないという点だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月09日
ストラテジーとは問題を解決する才能
塩野七生 著 「日本人へ 国家と歴史篇」から
『
ストラテジーとは、
確かに軍事面ではよく口にされる言葉である。
だが、
古代ギリシャ以来使われてきた
この言葉の意味の一つには、
予期しなかった困難に遭遇しても
それを解決していく才能、
というのもあるのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月08日
クラウドを導入する意味
辻野晃一郎 著 「グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた」から
『
起業がクラウドを導入する本質は、
IT投資の削減などということだけではなくて、
社内のコミュニケーションや情報シェアを促進して
経営のスピードを上げる、
という点にあると考えている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月07日
リーダーの役割
塩野七生 著 「日本人へ 国家と歴史篇」から
『
人間は自分がどこまでやれるかを
ほんとうはわかっておらず、
だからこそ思っていたこと以上を
やれたときの喜びは大きい。
そして、
この方向に人々を導いていくことこそが
リーダーの役割
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月05日
改革が難事な理由
塩野七生 著 「日本人へ 国家と歴史篇」から
『
改革が難事なのは、
改革でソンをする人は
すぐわかるから断固として反対するが、
トクする人々は、
なにせ新しいこととて
何がどうトクするのかよくわからず、
それゆえ支持も断固としたものに
なりにくいからである。
』
お正月に深夜放送の映画「フラガール」を見て、この言葉がよく分かりました。しかし、あの時代に“ハワイアン・センター”を造るという発想は、見事としか言いようがありません。今、これほど奇想天外な発想が生まれてこないというのは残念ですね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月04日
将来価値を生み出すこと
辻野晃一郎 著 「グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた」から
『
常に成長する会社であり続けようと考えるのであれば
「将来価値を生み出す」ための
卓越したビジョンや勇気、
その上での覚悟と計画に基づいた
経営資源の継続投入が不可欠だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2011年01月03日
政局不安から良いことは生まれない
塩野七生 著 「日本人へ 国家と歴史篇」から
『
内外ともに
重要課題を突きつけられている現在の日本に、
体力の無為な空費は許されないのである。
民間がいかにがんばっても、
「究極のインフラ」としての政治は
できないのだから。
』
著者がこの言葉を書いたのは 2007/7/23 ですが、この時点から政治は何も進歩していないということですね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月29日
日本企業が時代についていけなくなった理由は
辻野晃一郎 著 「グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた」から
『
自分が今までソニー時代に培ってきた常識は
一旦捨てた方がよさそうだ、
ということを直感的に察した。
そうすることによって、
ソニーを含めた日本企業が
新しい時代についていけなくなっている理由が
見えてくるような気がした。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月28日
自分の波長に合ったものを見つけること
布施克彦 著 「負け組が勝つ時代」から
『
物事には、
自分に合うものと、そうでないものがある。
波長の合ったものと、そうでないものがある。
それらの違いを言葉や理屈では説明しにくくても、
自分自身の感覚で判断することはできる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月26日
ビジネスの常
辻野晃一郎 著 「グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた」から
『
ビジネスの常、世の常であるが、
あまりにも強いポジションを確保し過ぎると、
逆にそれが大きな足枷(あしかせ)になって
次の勝負での大敗を喫する事例は
枚挙にいとまがない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月25日
大変革者は要らない?
布施克彦 著 「負け組が勝つ時代」から
『
日本の社会は
根底からの変革が必要なほど、
劣化しているわけではない。
国民の多くは、
今でも平和で豊かな生活を享受している。
幕末に輩出したような、
社会構造を一から作りかえる大変革者は要らない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月24日
フルスロットル、島国根性プラス面
布施克彦 著 「負け組が勝つ時代」から
『
自分向きの仕事なら、
協調、強力、責任感、気配りなどの、
本来身に付いている島国根性のプラス面を
フル回転させることにで、
会社に貢献できるに違いない。
』
島国根性はサンタさんの贈り物。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月23日
沈黙が金でない国もある
辻野晃一郎 著 「グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた」から
『
実際に、
アメリカでは沈黙は金でも美徳でも何でもない。
沈黙の意味するものはただ一つ、
“無能”である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月22日
職業人を育てないから閉塞する
船橋晴雄 著 「経済六変 -歴史から読む60の智恵-」から
『
今日われわれが直面しているのは、
そのような時間をかけて
職業人を育てていく仕組みが
弱体化している現実である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月21日
まず下民を賑わせ
船橋晴雄 著 「経済六変 -歴史から読む60の智恵-」から
『
大蔵永常の言葉:
それ国を富ましむるの経済は、
まず下民を賑わし、
而(しこう)して後に領主の益となることを
はかる成すべし。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月19日
譲ると失う
辻野晃一郎 著 「グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた」から
『
人間、
譲ってはいけないところでは
決して譲るべきではない。
そうでないと、
必ず自分の中の何か大切なものを
失ってしまうように思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月17日
多品種人材で勝負
布施克彦 著 「負け組が勝つ時代」から
『
これからの企業は、
金太郎飴的な同質の人間を揃えるのではなく、
多様で異質の人材を揃えることが勝負となる。
肉食系、草食系と、
いろいろ揃っている方が強い。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月15日
今、日本人に必要なもの
辻野晃一郎 著 「グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた」から
『
今までの延長線上にはない、
まったく新しい未知の領域を開拓していく決意が、
多くの日本人に求められている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月14日
日本は弱者によって作られた
布施克彦 著 「負け組が勝つ時代」から
『
敗者は概ね弱者だが、
日本は基本的に、
弱者によって作られてきた社会だ。
弱者の一部である敗者は、
そのことを知って欲しい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月13日
子どもに胸をはって伝えること
花まる学習会代表 高濱 正伸 さんの言葉から
『
大人っていい、
働くっていい、
家族っていい。
そう親が胸をはって伝え切れるかどうかが、
子どもにとっては大きい
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月12日
棒に当たるまで歩こう
布施克彦 著 「負け組が勝つ時代」から
『
必ずチャンスは巡ってくる。
でもチャンスに巡り合うためには、
アクションをたくさん起こす必要がある。
棒に当たるまで、
歩き回らねばならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月11日
精神的奴隷
船橋晴雄 著 「経済六変 -歴史から読む60の智恵-」から
『
未だにわれわれの中に、
ドグマに支配され、
外来思想の精神的奴隷となり、
隠すくせが抜け切っていない人々が
数多く存在する
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月09日
民は食えているか
船橋晴雄 著 「経済六変 -歴史から読む60の智恵-」から
『
いずれの時代であっても、
政治の要諦は国民生活の安定である。
民のかまどは賑わっているか、
民がたらふく食っているかが
基本中の基本である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月08日
島国根性の有益性
布施克彦 著 「負け組が勝つ時代」から
『
仲間同士の思いやりや気配りには、
最新の注意を払う。
利己心を抑えて、
仲間全体の知や有益性を優先させ、
そのための献身や自己犠牲を惜しまない。
一致協力、全体一丸となって、
自分の属する限定的集団への
協力姿勢を全開させる。
』
日本人気質だけを悪者扱いしたために、強引で、わがままで、自己主張の強い人だけが、持てはやされる時代となってしまいました。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月07日
経済という言葉は
2010年12月06日
非エリートの厚みが日本の強み
布施克彦 著 「負け組が勝つ時代」から
『
日本が他国との違いを生み出せるのは、
非エリート層の比較による部分だと思う。
矛盾する言い方だが、
日本の強みは弱者にある。
』
- Permalink
- by
- at 00:02
2010年12月05日
日本人の凄いところ
布施克彦 著 「負け組が勝つ時代」から
『
当初は誰もが
「そんなの無理だよ」
と思っていても、
みんなで智恵を出し合って、
それを成し遂げてしまう。
それが日本人のすごいところだと思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年12月02日
空想的経済原理主義
2010年11月30日
先進国日本を作ったのは無名の国民
布施克彦 著 「負け組が勝つ時代」から
『
現在の先進国日本を、
特定の英雄が作ったわけではない。
平和で豊かな日本は、
無名の国民たちの勤勉さと
努力の集積によってつくり作り上げられた。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月26日
時代の転換期に生き残る
船橋晴雄 著 「経済六変 -歴史から読む60の智恵-」から
『
時代の大きな転換期には、
頭を切り換えて新しい変化に対応していくことを
選び取った人のみが生き残っていく。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月22日
普通に戻すと生産性が上がる
齋藤 孝 著 「最強の人生指南書」から
『
つい私たちは自分の能力を
上げるための方法のみを考えがちですが、
実際には、
悪い状態の心を普通に戻したほうが、
生産性が上がるケースが多いからです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月21日
名将は玉砕させない
船橋晴雄 著 「経済六変 -歴史から読む60の智恵-」から
『
戦国武将で大をなした人物というのは、
例外なく部下を大事にしている。
戦争だから討死や戦闘不能の大怪我を
負うことがあるのは仕方ない。
しかし、出来ればそのリスクを最小にして
戦いに勝利を収めるというのが名将である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月20日
相手に心を開かせるには
齋藤 孝 著 「最強の人生指南書」から
『
人は、
多かれ少なかれ
人に対して心を閉じる傾向があります。
そこをいくら責めても、
相手が心を開くことはありません。
まず、
こちらが心を開くこと。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月19日
日本の女性は有能なマネージャであった【山内一豊の妻】
船橋晴雄 著 「経済六変 -歴史から読む60の智恵-」から
『
日本の女性は、
家の資産でもなく、
男の隷属物でもなかった。
今なお女性をそのようにしか
扱っていない国もあるが、
わが国では女性の地位は
昔から高かったのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月17日
交渉をうまく運ぶには
齋藤 孝 著 「最強の人生指南書」から
『
交渉の場における本当の利益とは、
「どうしたいのか」という最終的な目的と、
「これだけは譲れない」という絶対条件です。
これがわかっていないと、
交渉は絶対にうまくいきません。
』
「事業仕分け」も言いたいことを言うだけでなく、もっとメリハリのある結論を出して行ってもらわないと、税金と時間の無駄使いですよね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月16日
退き方
2010年11月14日
選び取れ
齋藤 孝 著 「最強の人生指南書」から
『
先生を選ぶのも、
友達を選ぶのも、
場所を選ぶのも、
そもそもそうしたものを
「選ぶ」という意識を持つところに、
実は成長の鍵があるのです。
』
菅内閣の問題点は、選び取れないところです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月12日
物事の見方を変えるには
齋藤 孝 著 「最強の人生指南書」から
『
人というのは、
自分の心の働きの精妙さに、
自分自身が
「この宇宙の中で、
このような心を持つことができたのは
すごいことだ」
と思えるかどうかで、
物事の見方が変わっていくのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月11日
強引では組織は回らない
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
強引な仕事が肯定されるのは、
リーダーが満足のいく結果を
もたらしているときだけです。
通常は、なんであれ、
社員の暗黙の同意がなければ
組織は回らないものです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月09日
受けは攻めに勝る
齋藤 孝 著 「最強の人生指南書」から
『
攻めているときというのは、
人は、
状況を見ているようであまり見ていません。
そのため
相手を攻めているつもりでひたすら突き進んでいても、
気づいたときにはコロッと負けてしまっていた
ということがあります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月07日
ワクワクして学ぶことが大切
齋藤 孝 著 「最強の人生指南書」から
『
同じ学ぶのでも、
ワクワクしたり、
発憤したりしながら学んでいると、
それが推進力になって、
ぶれずに進んでいくことができます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月04日
利害調整の妙薬
齋藤 孝 著 「最強の人生指南書」から
『
多くの人は嫌がるけれど、
自分とっては苦にならない。
そういうものを持っていると、
利害の調整はぐっとしやすくなるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月03日
学問をするポイント
齋藤 孝 著 「最強の人生指南書」から
『
学問をする一番のポイントは
志を立てて学ぼうとすることであって、
本を読んで知識を得ることが
必ずしも学問ではないということです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年11月02日
過去を過去にするために
作家 チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ さんの言葉から
『
どの国でもそうですが、
たとえ恥ずべき歴史であっても、
私たちは、
過去と向き合う必要があるのです。
過去に正面切って向き合わなければ、
過去は過去になりません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月30日
正直に言うのは得策ではない
齋藤 孝 著 「最強の人生指南書」から
『
思ったことを正直に言うのがいい
と言う人もいますが、
正直に言えば
誠実だと評価されるなんてことは
現実にはほとんどありません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月26日
格言は思考の集積回路
齋藤 孝 著 「最強の人生指南書」から
『
一つの諺や格言のような言葉が
生まれてくる背景には、
ものすごく大量の思考があり、
それがその短い言葉に凝縮されているからこそ
人の心に響くものになるのだ、
ということです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月24日
未来に目を向けると
高橋昌一郎 著 「知性の限界」から
『
仮にあなたの血統が絶えずに
子孫を残し続けたとすると、
今から三千年後の地球上に生存する人類は、
すべて何らかの形で
あなたの血縁の子孫だということになるのです!
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月22日
宇宙は自己組織化している
高橋昌一郎 著 「知性の限界」から
『
最近では、
宇宙そのものが観測者を生み出すように、
「自己組織化」しているのではないかと考える
宇宙物理学者も増えてきています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月20日
複雑系
高橋昌一郎 著 「知性の限界」から
『
複雑系においては、
ある特定の原因を与えられたとき、
それがどのような結果に導くのか、
少なくとも従来系の考え方では、
まったく予測不可能だということです。
』
だから、広告やセールスマンに騙されて、「FX」なんかしてはいけませんよ!
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月19日
未来に法則性はない
高橋昌一郎 著 「知性の限界」から
『
どれほど過去の歴史を調べて
そこに「法則性」を見出したとしても、
そこからいかなる予測を立てたとしても、
未来が必ずそのとおりに
繰り返されるとは限りません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月17日
今の政治主導は本物か
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
自民党政権時代は、
政治家は「政治主導だ」と叫びながら、
こんな利害調整といういやな仕事は
すべて官僚に丸投げしていました。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月15日
ゴマすりの効用
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
怒りやイライラを基本とした仕事よりは、
相手を気持ちよくさせたりしながら
穏和に仕事を進めるほうが得策です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月14日
ラプラスの悪魔は微笑まない
高橋昌一郎 著 「知性の限界」から
『
すべての未来を予測できる
「ラプラスの悪魔」は
存在不可能だということなのですが、
現実社会における人間は、
いまだに「ラプラスの悪魔」を夢見て、
常に未来の予測を繰り返して生きています。
』
宝くじやビッグを買う人達は、ラプラスの悪魔を信じているのですね・・・あっ、今日はロト6の抽選日だった・・・当たり番号を確認しなくちゃ・・・やっぱり、懲りない面々。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月13日
言葉の不確実性
2010年10月11日
交渉はあきらめないこと
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
交渉というものは、
双方ともに相手からなにかを
引き出せると考えていますし、
なにを引き出すかは
状況に応じて変わってきます。
』
だから、尖閣諸島問題でも、裏からアメリカの圧力があったにせよ、容疑者を簡単に無罪放免にしてしまうこと自体が日本政府の大問題なのです。こんな貧弱な交渉能力では、21世紀の世界の荒波を乗り越えて行けそうにありません。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月10日
自文化中心主義になるわけ
高橋昌一郎 著 「知性の限界」から
『
地球上のあらゆる人間は、
基本的に何らかの文化圏に所属して生きているわけですから、
文化的に完全にニュートラルな人間など存在しません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月08日
いらない経済にお金を吸い取られている
アシスト ビル・トッテンさんの言葉から
『
売り手の広告宣伝に踊らされ、
使う必要のないお金を使っている。
多くの人が「買い物中毒」になって
生み出されている今の経済の半分くらいは、
いらない経済だと思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月07日
最後で悟る
高橋昌一郎 著 「知性の限界」から
『
それを理解する読者がそれを通り抜け、
その上に立ち、
それを見下ろす高さに達したとき、
最後にはそれが無意味であると悟る。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月06日
印刷書と電子書の両刀が必要
井上真琴 著 「図書館に訊け!」から
『
これからは、
印刷冊子体で蓄積された資産と
電子情報を併用したハイブリットな利用こそが、
利用者の課題となるのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月04日
日本最大の非生産的なもの
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
各省折衝は昼夜問わず行われます。
しかも、
双方がそれぞれの言い分を主張するために
簡単に決着せず、
非生産的でものすごい疲れが伴います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年10月02日
日本はサービスと笑顔と優しさにあふれている
ファッション・エッセイスト フランソワーズ・モレシャンさんの言葉から
『
日本ほど調和と安らぎのある国は他にありません。
国民性もあるのでしょうが、
民族や宗教の対立もない日本は
社会的なストレスがなく、
サービスと笑顔と優しさにあふれています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年09月29日
官僚には官僚を
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
官僚にとってもっとも厄介なのは
他の役所の官僚です。
官僚が日々の仕事で怒鳴り合ったり、
交渉したりする相手は、
他の役所の官僚だからです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年09月28日
切羽詰ったら正論
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
これだけ切羽詰った経済情勢ですから、
どんな組織も建設的で独創的な
意見を求めています。
だからこそ、
そういう場では正論をはくように
心がけるべきです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年09月26日
図書館の利用巧者になるには
井上真琴 著 「図書館に訊け!」から
『
図書館の「利用巧者」、「探し巧者」に
なれるかなれないかの分水嶺は、
このレファレンス・サービスを
活用できるかできないかにある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年09月25日
交渉の場所にこだわる訳
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
人間心理をよくわかっている交渉のプロは、
だからこそ、
交渉の場所にこだわることがあります。
相手を威圧しやすい、
飲み込みやすい場所を
なるべく選ぶということです。
』
中国政府のレアメタル禁輸措置ぐらいで、中国人船長を釈放してしまうなんてね。“ポーカーフェース”でもなければ、“大声で反論する”でもない国家なんて・・・
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年09月18日
図書館で相談しよう
井上真琴 著 「図書館に訊け!」から
『
見つからないのは、
探索不足や作業怠慢のせいかもしれない。
見つからないと嘆く前に、
まずは図書館で相談しよう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年09月15日
空気が読めないとゴマはすれない
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
おおらかに笑いながらも、
全身を傾けて空気を読んで
会話をコントロールすることが
非常に重要です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年09月14日
地獄の目次録
2010年09月10日
資料や情報にたどり着くには
井上真琴 著 「図書館に訊け!」から
『
そもそも資料や情報というものは、
待っていても絶対に現れない。
自分が能動的にアクセスの意思をみせたときに、
むこうから自然と姿を現し始めるものなのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年09月09日
改革は先に大筋を変えること
2010年09月08日
政治は国益で断行する
塩野七生 著 「日本人へ リーダー篇」から
『
政治には、
経済的ではないことでも、
また経済理論には反することでも、
国全体の利益を考えれば
断行しなければならないことが多い。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年09月07日
ビジョンは崇高であること
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
リーダーシップの研究では、
リーダーの性格や個性で人がついていくのではなく、
リーダーが掲げるビジョンの崇高さに惹かれると言われます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年09月04日
理想に近いと褒めておくこと
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
人間というものは、
常に理想と現実のギャップを埋めたいと思っていますし、
一歩でも理想に近づきたいと思っているものです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年08月31日
もてる能力の徹底した活用
塩野七生 著 「日本人へ リーダー篇」から
『
なぜローマ人だけが、
に答えるぐらいはできそうに思うが、
それをひとことで言えば、
「もてる能力の徹底した活用」
である。
言い換えれば、
一つ一つの能力では
同時代の他の民族に比べ劣っても、
すべてを総合し駆使していく力では
断じて優れていたのだった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年08月29日
手段あっての目的
2010年08月24日
反省とは
塩野七生 著 「日本人へ リーダー篇」から
『
自己反省は、
絶対に一人で成さねばならない。
決断を下すのも孤独だが、
反省もまた孤独な行為なのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年08月23日
ニーズは想像力でしか分からない
塩野七生 著 「日本人へ リーダー篇」から
『
ニーズを察してとか、
ニーズを汲みあげてとか言う。
それを聴くたびに思う。
どうやって察したり汲みあげたりするのですか、と。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年08月20日
喜んでやる気持ちにさせる
塩野七生 著 「日本人へ リーダー篇」から
『
人間は、
苦労に耐えるのも犠牲を払うのも、
必要となればやるのです。
ただ、喜んでやりたいのです。
だから、
それらを喜んでやる
気持にさせてくれる人に、
従いていくのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年08月19日
洞察力を磨く
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
短時間で相手のよいところを探り当てるためには
全身で相手を感じるようにしなければいけません。
これを繰り返すと、
空気を読むことなんて、
なんの苦労も感じなくなります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年08月18日
プレゼンの主体は「聞く側」
中野雅至 著 「悪徳官僚に学ぶ 戦略的ゴマすり力」から
『
プレゼンの主体は「聞く側」です。
プレゼンをする側がどういうパワポ資料をつくるか、
どういう説明をするかなど、
すべては聞く側に依存します。
こんな当たり前のことをわからない
サラリーマンはたくさんいます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年08月17日
戦時でもプリンシプル
塩野七生 著 「日本人へ リーダー篇」から
『
ローマは、
未成年とされていた十七歳以下の男子の徴兵は
絶対にしなかったということである。
父親は戦場で倒れようとも、
息子たちは平時と変わらず学校に通っていた。
』
1943年、十五歳で海軍予科練へ志願を表明させるような社会は、野蛮人の国なのです。また、財政難で教育費までどんどん削る米国は、大国であっても古代ローマの足元にも及ばない蛮国です。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年08月15日
危機の打開に妙薬はない
塩野七生 著 「日本人へ リーダー篇」から
『
やらねばならないことはわかっているのだから、
当事者が誰になろうと、
それをやりつづけるしかないのだ。
「やる」ことよりも、
「やりつづける」ことのほうが重要である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年08月14日
私利のエネルギーを公益にできれば
塩野七生 著 「日本人へ リーダー篇」から
『
何ごとでもそれを成しとげるには、
強い意志が必要になる。
しかもその意志は、
持続しなければ効果を産まない。
意志を持続させるに必要なエネルギーの中で、
最も燃料効率の高いのが私利私欲である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年08月12日
終戦ではなく敗戦したことを考えよう
塩野七生 著 「日本人へ リーダー篇」から
『
終戦は戦争が終わったことでしかないが、
敗戦となれば、
この言葉を耳にする人の何人かは必ず、
なぜ敗北したのかを考えるようになる。
』
終戦記念日ではなく、「敗戦記念日」として、世界の中で国家が生き延びる事の難しさを考える記念日にしたいですね。この円高バブルは、近い将来弾けるでしょう。そのとき、新たな危機がやって来ます。だから・・・
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年08月11日
busyは心を失う
2010年08月07日
自分の目で見る
2010年08月04日
白い時間
2010年08月02日
人間中心主義の驕り
外山 滋比古 著 「人生を愉しむ知的時間術」から
『
自然界の中には、
人間の考えも及ばないような世界があって、
そこでは人間とはまったく無関係に、
きわめて高度の様式が発達しているかもしれないということを、
謙虚に考える必要があるように思われる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月31日
嘘が色取る
外山 滋比古 著 「人生を愉しむ知的時間術」から
『
人間は嘘をつくことができる。
実用的伝達しかできないのだったら、
この世は何と殺風景なことであろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月30日
ヒマを感じるには
2010年07月27日
休みはつくる
外山 滋比古 著 「人生を愉しむ知的時間術」から
『
休みやヒマは
はじめからあるものではない。
ないのが正常である。
ないから、つくる。
それだからこそ、休みは楽しい。
ヒマもありがたい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月26日
笑いは頭をよくする
外山 滋比古 著 「人生を愉しむ知的時間術」から
『
笑いは頭をよくする。
休み時間は頭をさっぱりさせる。
切り換えのうまい人が
いい仕事をするのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月24日
変わった方が有利だと思わせて変える
日垣 隆 著 「知的ストレッチ入門」から
『
変わったほうが
自分にとっても都合が良い、
とか有利だ、
と思ってもらえれば、
「主体的に変わ」っていただくのは、
わりと簡単なのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月23日
本当のパワーアップとは
日垣 隆 著 「知的ストレッチ入門」から
『
自分の時間をよりたくさん確保して、
効率を良くしていく。
それが本当の
「パワーアップ」ということだと思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月22日
売り込みよりも依頼
日垣 隆 著 「知的ストレッチ入門」から
『
好きなことをいい条件でやっていくためには、
相手側にオファーしてもらうということが、
何にも増して重要です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月21日
談論風発
外山 滋比古 著 「人生を愉しむ知的時間術」から
『
談論風発するには、
同じことをしている人間が
仲間にいないのが条件である。
そうすると、
のびのび思ったことが言い合える。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月20日
互いに話すことの価値を知らない日本人
外山 滋比古 著 「人生を愉しむ知的時間術」から
『
弁証法が生まれた国とは事情が違うのである。
話すこと自体に価値を認めない。
話すことのおもしろさを知らない人が多すぎる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月19日
構造的なウソを見破るには
2010年07月16日
ウソを見抜くために不可欠なもの
日垣 隆 著 「知的ストレッチ入門」から
『
自分が置かれている状況を正確に把握し、
大きな行動を起こすときには
リスク管理をきっちりやる、
ということが
「世間のウソを見抜く」には
不可欠になってくるわけです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月14日
情報は紙に宿る
日垣 隆 著 「知的ストレッチ入門」から
『
必要な情報を即座に一覧できるという点で、
紙に優るメディアはありません。
』
iPadはちょっと騒ぎ過ぎですね。机の狭い人は別ですが、大きな机の上に複数の書籍を並べて情報を俯瞰するという情報処理は、電子メディアにはできません。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月12日
ゆっくりには勇気がいる
外山 滋比古 著 「人生を愉しむ知的時間術」から
『
ゆっくりするには勇気がいる。
自信がないと、
走り出そうとする自分に
ブレーキをかけることがむずかしい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月09日
自分の日々を輝かせる
菅原裕子 著 「子どもの心のコーチング」から
『
子どもをもつ年齢になった人は、
「もう自分には遅いから、
せめて子どもに・・・」
と思うかもしれません。
でも、
人は何歳になろうと、
その人なりのやり方で
自分の日々を輝かせることができます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月08日
子どもに必要な人とは
2010年07月07日
並以上のものを食べること
中村屋 初代 相馬愛蔵さんの言葉から
『
食事は些細なことのようだが
非常に大切。
並以上のものを食べているという自覚は
大変その人の人格に影響を与える
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月06日
親の仕事
菅原裕子 著 「子どもの心のコーチング」から
『
子どもに彼らの人生を教えるというのは
大変な間違いです。
子どもが自分の生き方を見つけられるよう
サポートすること、
それが親の仕事なのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月05日
政治家に人の気持ちが分からない理由
作家 田辺聖子 さんの言葉から
『
政治家の物言いが不誠実だ、
心に届かないっていわれる。
それはあるやろね。
人の気持ちを察することが
できる頭のよさは、
小ちゃいときから
身にしみて教えられないと
身につかない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月03日
話すことで心を浄化する
菅原裕子 著 「子どもの心のコーチング」から
『
心の中に何かもやもやがあるとき、
話すことには浄化作用があります。
誰かに聴いてもらうと、
問題が解決するわけでなくても、
何となく気分が軽くなる経験は
誰にもあると思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年07月02日
人の役に立つ喜び
菅原裕子 著 「子どもの心のコーチング」から
『
人は本来、
人の役に立ちたいと願っています。
この存在を使って
人の役に立つことができるとしたら、
こんなうれしいことはありません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月30日
羞恥心が進歩をもたらす
日垣 隆 著 「知的ストレッチ入門」から
『
教養や知性というものは、
たいてい羞恥心によって
培(つちか)われゆくものなのかもしれません。
恥ずかしいと思わなくなったら、
おそらく進歩は止まってしまいます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月29日
律して手に入れる
2010年06月28日
説得と納得
日垣 隆 著 「知的ストレッチ入門」から
『
説得するあなたが納得するストーリーで、
相手が納得できるとは限らない。
つまり、
説得することと納得することは、
単純な表裏一体の関係ではないということです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月26日
満足できない人が努力する
日垣 隆 著 「知的ストレッチ入門」から
『
努力とは、
現状の自分に満足できないからするものであって、
現状に満足しているのであれば、
その人は本質的に努力しようがないし、
する必要がありません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月23日
親の人生と子どもの人生
菅原裕子 著 「子どもの心のコーチング」から
『
もし親が喜びを求めるなら、
それは親自身の人生で
つくらなければなりません。
子どもの人生を利用しては
ならないのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月17日
大阪がド派手な訳
前垣和義 著 「大阪のおばちゃん学」から
『
ゆとりは気持ちを明るくし、
派手な服を買うことにもつながる。
個の主張、
ノリのよさ、
サービス精神等が加わり、
ド派手なものを購入させていく。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月15日
大阪の味は二つ
前垣和義 著 「大阪のおばちゃん学」から
『
大阪人が心底ケチであったのなら、
「食い倒れ」の街にはなっていなかった。
大阪には、
「料亭の味」と
うどんやかやくご飯に代表される
「庶民の味」との二つの流れがある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月14日
未来の子どもに目を向ける
菅原裕子 著 「子どもの心のコーチング」から
『
一時の安心と秩序に焦点をあてすぎると、
子どもの一生から、
自主性とそこから生まれる喜びの芽を
摘みとってしまうことになります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月13日
大阪は民の街
前垣和義 著 「大阪のおばちゃん学」から
『
大阪は、
「官より民」の街として発達してきた歴史をもつ。
』
そう言えば、私の出身高校は、船場の商人が大正時代に創った学校で、地上3階、地下1階、エレベータまで付いており、窓のステンドグラスはアールヌーボー調で、階段は大理石で出来ておりましたっけ。
しかし、国が戦時中に金属徴収のためエレベータを持っていったので、エレベータの実物を見たことはなっかですね。
すなわち、大阪では、「民は秀」、「官は卑」なのです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月12日
ミニ東京化が大阪を衰えさせる
前垣和義 著 「大阪のおばちゃん学」から
『
いま全国各地があらゆる面で
「ミニ東京化」している。
大阪は、
独自性の強さが特色であるが、
昨今は街づくりや店舗においても
「東京風」が目につく。
大阪のパワーの衰えは
それらの浸透と無関係ではないはずだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月10日
大阪は三日
2010年06月09日
時間と空間の制約を取り払うもの
藤原和博、重松清、橋本治 著 「情報編集力をつける国語」から
『
手紙のいちばんの魅力とは、
“目の前にいなくても伝えられる”
ことなんだと思います。
時間と空間の制約を取り払ってくれる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月08日
混迷の日本を救うキーワード=大阪のおばちゃん
前垣和義 著 「大阪のおばちゃん学」から
『
大阪のおばちゃんは、プラス、
どこか人をホッとさせる愛嬌を持ち合わせている。
料理がおいしければ、
「ケッサクやな、これ」と誉める。
その言葉が周囲に笑いと温もりを生む。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月06日
片思いの意味
2010年06月05日
コミュニケーションの原点
藤原和博、重松清、橋本治 著 「情報編集力をつける国語」から
『
人間は、
他人の心を読み取ることはできない。
それがコミュニケーションの原点なのだと、
ぼくは思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月03日
電子メールという絶妙なもの
藤原和博、重松清、橋本治 著 「情報編集力をつける国語」から
『
電話では話しづらい。
かと言って手紙でやりとりするほど時間がない。
そういうときに、
電子メールは絶妙の距離感とタイミングで
コミュニケーションを成立させてくれる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年06月02日
家族運営も大変
藤原和博、重松清、橋本治 著 「情報編集力をつける国語」から
『
家族というものの運営は、
実はそんなに容易ではない。
だから、
いろんな失敗や事件や障害も生まれる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月28日
詩的で幸福
藤原和博、重松清、橋本治 著 「情報編集力をつける国語」から
『
現実を詩的に表現するだけでなく、
目の前で起こることどもを詩的に解釈して、
そのときどきの生活を楽しめる人は幸福である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月27日
〝キレない〟人は言葉に出来る人
藤原和博、重松清、橋本治 著 「情報編集力をつける国語」から
『
言うに言われぬ
「居場所のなさ」への恐怖心を、
暴力に変換せざるを得ない少年たちもいる。
〝言語化〟できないから
〝キレる〟しかないのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月26日
失敗から始めてみる
藤原和博、重松清、橋本治 著 「情報編集力をつける国語」から
『
感想を述べる前に、
感想の前提としての
「語るべき事実」が必要だということは、
感想や反省が生まれるような、
友人とのもめごとや混乱や絶交などの
〝負の体験〟や〝失敗〟が
だいじだということだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月23日
息抜きの場がないと
2010年05月22日
他人の気持ちを理解することが重要
藤原和博、重松清、橋本治 著 「情報編集力をつける国語」から
『
コミュニケーション技術のうち、
他人の気持ちを理解する技術は、
世の中のあらゆる局面で重要だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月21日
民主党は女性を招き猫の置物と考えている
「幕末を生きた女101人」から
『
明治維新に参加した女性がおおぜいいたこと、
そして女性の自覚がやがて明治維新を
生んでいく大きな力になったことを
忘れることはできない。
』
ところで、政治にも目覚めていない柔道の「ヤワラちゃん」を、参議院議員立候補者に担ぎ出す民主党のおバカ振りには呆れてしまいます。有権者を舐めているというか、女性を舐めているとしか言えませんね。女性を招き猫の置物並みに扱っています。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月20日
女でいるより正義でいる
「幕末を生きた女101人」から
『
奥村五百子の言葉
「女らしくする為に悪いことを
見のがさねばならぬなら、
わたしは女になるのは嫌い」
』
こんな言葉を残す女性は「ブス」だと思われそうですが、姿態は抜群できりりとしていたというのですから素晴らしい。
それに引き換え、桂きん枝などを選挙に出してくるなんて、民主党も落ちぶれたものです。立候補者ぐらいは毅然とした人を出すべきです。明治女性を生き返らせて、選挙に立候補させてあげたいです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月15日
すべては一対多で繋がっている
福岡 伸一 著 「世界は分けてもわからない」から
『
この世界のあらゆる要素は、
互いに関連し、
すべてが一対多の関係で
つながりあっている。
つまり世界に部分はない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月14日
動的は理解し難い
福岡 伸一 著 「世界は分けてもわからない」から
『
動き続けている現象を見極めること。
それは私たちが最も苦手とするものである。
だから人間は
いつも時間を止めようとする。
止めてから世界を腑分けしようとする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月13日
フェイルセーフの基本
福岡 伸一 著 「世界は分けてもわからない」から
『
ヒトは常に間違える。
忘れる。混乱する。
だから、
それをしないように注意するのではなく、
それが起こらないための
仕組みを考えよ。
あるいはミスが起こったとき、
その被害が最小限にとどまるような
仕組みを考えよ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月11日
どんなに困難な時も助け合えるのが家族
【スタートレック・ヴォイジャー】キャスリン・ジェインウェイ艦長の言葉:
『
みんなそうでしょう、違う。
先のことなんて分からないわ。
それが探検というものなの。
私たちは家族(クルー)なんだから、
どんなに困難な時も、
お互いに助け合わなきゃいけないのよ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月10日
時の罠
映画 「アーサーとミニモイの不思議な国」から
『
時が経つと、
どんどん使えなくなる罠に
かかちゃったんだ。
』
ズバリ!日本の国家予算のことなのでしょう。
国債の利払いがどんどん膨らんで、税金がみんな借金返済に消えて行きます。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月08日
日本は高品質と新しさを求める
ルイ・ヴィトンCEO イヴ・カルセル さんの言葉から
『
高品質と新しさへの要求が
世界で最も厳しいのが日本。
さらに、高級品を理解する文化が
民衆レベルで伝統的にある点でも
日本は素晴らしい
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年05月05日
人が因果を創造する
2010年05月04日
京おんな
2010年05月03日
空目
福岡 伸一 著 「世界は分けてもわからない」から
『
ヒトの目が切り取った「部分」は
人工的なものであり、
ヒトの認識が見出した「関係」の多くは
妄想でしかない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月28日
生命現象の本質
福岡 伸一 著 「世界は分けてもわからない」から
『
生命現象の本質は、
物質的な基盤にあるのではなく、
そこでやりとりされる
エネルギーと情報が
もたらす効果にこそある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月27日
今に見ておれ
2010年04月26日
高い視点からしか絵柄は見えない
福岡 伸一 著 「世界は分けてもわからない」から
『
絵柄は高い視点から見下ろしたときだけ、
そのように見えるのであり、
私たち人間は、
そのような絵柄として生物を見なしている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月24日
リスクが無いのではなく隠されている
福岡 伸一 著 「世界は分けてもわからない」から
『
問題なのは、
現代の私たちの身のまわりでは、
リスクが極めて小声でしか囁かれない、
むしろわざと見えないように
されがちであるということです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月23日
性分でんねんと社員教育を蹴散らす
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
「性分でんねん」と唱えれば、
生きにくい年代の人々の人生も、
ややに風通しよくなるのではないかと思ったりし、
私はこのごろ、好んで、ひとり小さく、
「性分でんねん」とつぶやいてみたりしている。
』
「性分」を活かすのではなく、「性分」を捻じ曲げて企業の型に填(は)めようとする社員教育では、21世紀は乗り切れるのでしょうか。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月22日
現代=終戦時より荒涼とした社会
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
物はありあまるのに、
人は絶えず欲求不満にさいなまれるようになった。
生きる喜びを学ぶべき少女時代に、
いまの世の中は終戦時よりある意味では
更に荒涼とした環境ではないかと思われる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月18日
「をかし」の文化
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
「をかし」こそ、
文化の沃土(よくど)から開くべき花であるのに、
なぜか日本人は、
面白いもの、楽しいもの、軽やかなものを、
悲劇より一段下に見るクセがついている。
しかし「をかし」を愛さない文化は
片手落ちというものではなかろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月17日
愛はドラマ
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
人のよきものを吸収するほうも、
人によきものを照り映えさせるほうも、
どちらも
愛あってこそだろうと思われた。
人間と人間が影響し合うということは、
たぐいもないドラマである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月16日
交流で仲良くなる
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
願わくば破壊侵略でない交流が、
庶民次元で行われて、
地球上の人々が仲よくなる、
そういうのであれば、
いちばんすてきなことなんだけど。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月15日
アンチ日本=大阪
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
大形にいえば、
現代の大阪人は、
薩長閥によって基礎を作られた日本に対し、
徹底的に反抗しているとも見ることが出来ます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月13日
笑いは貴重な必需品
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
いま「笑い」は
たいそう貴重な、切実な、
人間の必需品になっている。
ストレス過重の現代、
心身不調の人々は生き悩み、
笑いを忘れる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月12日
大阪の町造りが失敗している訳
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
町を清潔に見た眼に美しく、
と思うなら、先ず、
悪い意味での個人主義や利己主義を
捨てなければ始まらない。
それに、
町造りにもセンスが必要だ。
悲しいかな、大阪にはこのセンスから
磨かねばならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月11日
どうしても真似られないもの
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
歌のよみぶりや状況は俗人にも
真似できるかもしれないが、
日常の中から詩を発見して掬い上げる、
その感性と、表現する言葉が、
どうしても真似られるものではないのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月10日
大阪には戦術はあるが戦略がない
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
大阪は官民ともに、
口で言っているが本心ではその意識が低い。
「大阪をファッションの発信基地に」と叫んでも、
文化としてではなく、
所詮は商売であることがあからさまである。
』
「大阪を○○の発信基地にする」という戯言を、歴代の知事はずっと語っていましたが、未だに実現したものはありません。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月09日
時間軸を長くとり見直す
分子生物学者 青山学院大教授 福岡 伸一 さんの言葉から
『
長い時間軸で見返してみると、
そんなに効率的でないことがわかる。
常に効率的に走りがちな科学にとって、
「時間軸を長くとる」ことが一種、
解毒剤的な効果があると思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月05日
大阪の上品
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
シック、シンプルが上品とは誰が言い初めし。
ごちゃごちゃした町の喧騒に負けない、
陽気で派手で明度のたかい服や
色彩を身につけることこそ、
大阪では上品なんである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月04日
根暗日本に風穴をあける
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
神戸はファッションを売り出すのに
力を入れているが、
パーティ上手、
という気風も日本中に拡めて、
集会下手の根暗日本に
風穴をあけてほしいものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年04月01日
大阪人以外の日本人の会話
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
大阪と比べて、
一般の日本人の会話は
伝達することが目的で、
会話にキャッチボールの呼吸がない。
故にユーモアやサービス精神が
ともすれば欠落する。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月31日
男のいい所
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
男というものは、
女が忌むべき根クラのワルクチを口にするとき、
自分も心ではそうは思っていても、
女同士のように口をそろえて
同調することはしない。
これは男のいい所だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月30日
権威社会は硬直社会
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
権威に従っていれば、
うまく責任逃れも出来る。
これは、ひとつ間違えると
事なかれ主義につながり、
その風潮が民間の大企業をも
侵食し出している。
権威社会であることは
即ち硬直社会である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月29日
地球を継続できなくすること
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
つまり儲けりゃいい、
強けりゃいい、
効率がよけりゃいい、
弱いものは踏みつぶせばいい、
武器は多けりゃいい、
というような文化では、
もうこの地球はやっていけないことがわかった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月28日
連続体でない世界
福岡 伸一 著 「世界は分けてもわからない」から
『
今見ている視野の一歩外の世界は、
視野内部の世界と均一に連続している
保証はどこにもないのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月27日
大阪人は商感
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
大阪人というのは、
職種のいかんを問わず、
何がしかの商人的感覚を
具(そな)えた人が多い。
損得勘定に敏感で利に敏(さと)く、
金銭のことを口にするのは卑しい、
などと思っている人は滅多にいない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月25日
大企業のサラリーマン氏
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
大企業のサラリーマン氏は、
一人でいるとおとなしいが、
群れると態度がデカくなっていけない。
そうして、
それらインテリ顔の諸氏ほど、
女にはえらそうにするようである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月23日
長いものは跨いでしまえ
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
日本人が長いものに巻かれていると、
その長いものを跨(また)ぐか、
横目で素知らぬふりして
通り過ぎて行くのが大阪人である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月21日
遠慮なく目立つ
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
目立つという行為に遠慮は禁物だ。
一歩でも二歩でも
前に出た方が勝者となる。
』
そう、目立つと言えば、叶姉妹の姉(小山 恭子)、そして、元アップルコンピュータ株式会社代表取締役の山元賢治氏は、私と同じ中学校の出身であり、同窓生だったりします。
特に山元賢治氏とは同じ学年であり、卒業アルバムには氏の写真が写っています。氏を知っている友人は、昔から頑張りやさんだったと語っていましたっけ。
やっぱり、大阪は凄いんヤ!
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月20日
商いで頼れるのは自分だけ
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
商い(ビジネス)とは、
最終的に突き詰めれば孤独なもので、
人対人、
ひとり対ひとりで
決定することが多い。
となれば、
頼れるのは自分だけである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月19日
縄ノレンの至福
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
縄ノレンをくぐって入ってきた兄ちゃんが、
「よろしおまっか」
と椅子をひいて横に坐ったりする、
私は、
「どうぞどうぞ」
という。
それがいい。
彼も至福のときを味わおうとして、
顔をハレバレさせている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月18日
無駄より才覚
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
大阪人はこの「無駄」というのが嫌いである。
その一方、
個人個人がそれぞれに
「知恵や才覚」を
働かせるのが好きである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月16日
大阪の偏狭性
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
どうも大阪という土地は、
特定のことへの思い込みが強過ぎ、
それが一種の偏狭性となって孤立化を招き、
健全に進むべき方向の
妨げになっているように思われてならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月15日
スレート型端末の巨大市場=シニア(オトナ)
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
日本の社会には
侘び寂びを尊びながら
根底に奇妙に未熟なところがあり、
不審に堪えない。
この日本にはヤングと老人ばかりのようだ。
オトナはどこへいっているのだろう?
』
GoogleやAppleのような市場訴求型アプローチでは、20年先の世界の大きな市場を逃がしています。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月13日
日系大阪人
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
実は大阪人は
日本人でありながら外国人なのです。
だから、
「日系大阪人」と名乗れば
分かり易いのではないでしょうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月12日
大阪沈下を止めるには
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
「地盤沈下」という四文字が
合言葉のごとく叫ばれる大阪だが、
創造性や智恵・知識には金がかかる、
という当たり前のことに気がつき、
正当な対価を払うことを実行しなければ、
半永久的に沈下し続けるのではなかろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月10日
大阪のビジネスマン
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
大阪のビジネスマンは
積極果敢である一方、
それが失敗に終わると、
努力が足りなかった、
責任は自分にあると反省する。
そして、
なぜ過ちに至ったかを考え、
次の行動の糧とする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月09日
大阪人の特性
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
大阪人の特性である、
形式主義や建て前論を嫌い、
合理主義や本音を尊ぶこと。
他人に対して妙に慣れ慣れしく、
ある種の同等観や平等観が強いこと。
権力というものに反抗的で信頼しないこと。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月07日
変化の速い世界で必要な能力
アショカ創設者 ビル・ドレインさんの言葉から
『
こんなに変化が速くなった世界では、
ルールを覚えたころには現実が変わっている。
そんな事態に対応するには、
共感力やチームワークを習得して他人を動かし、
改革のアイデアを実行に移す能力が必要です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月05日
大阪人がエネルギーを注ぎ込むもの
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
大阪人にとっては、
食べることを通じての団らんや
社交が殊(こと)の外大切で、
他の知的文化は放っておいても、
食文化だけには、
マメマメしくエネルギーを注ぎ込むのが
無上の喜びなのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月03日
大阪が派手になる訳
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
大阪人は流行だからといって
他人と横並びというのが性に合わない。
だから個性を強調するあまり
ますます派手になって来る。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年03月02日
それぞれがいい
田辺 聖子 著 「性分でんねん」から
『
なんとなく、
ナアナアのうちに、
みんなそれぞれ書きたいものを書き、
それぞれに面白いのがいい、
読者は読みたいものをそれぞれ読むがいい、
そんなことを思っている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月28日
変わり身のタイミングを逃すな
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
日本人はこの変わり身が苦手である。
「いまさら」
「面子にかかわる」
「恥ずかしい」
「言いわけがましい」
「信用を落とす」
等々という理由で、
変わり身のタイミングが後れる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月27日
大阪は武士道にこだわらない
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
商都大阪で、
この武士道にこだわっていては、
とんと商売にならない。
出し抜くことを禁じられていては、
取引き自体が成り立たないし、
頭の良くない上役の言いなりになっていては、
売り上げが伸びない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月26日
話題が生まれるところ
2010年02月25日
詐欺師 vs. 大阪世間ズレ
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
人間は、
いつも懐疑的であると夢がなく、
無味乾燥な人生になってしまうが、
こと詐欺と犯罪に関しては、
大阪的な世間ズレを身に付けた人の方が、
被害に遭いにくいといえるのではないか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月24日
死金と生金
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
見栄や自分の快楽のために遣う金は死金である。
そのせいで他人から何と言われようと、
外聞なんか気にしない。
金は生かして遣ってこそ金であり、
何に消えたか分からないような遣い方は、
ドブへ捨てたのと同じである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月20日
急ぐは利益
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
とにも角にも、
急ぐことは大阪人にとって利益をもたらす源であった。
それが暮らし全般の習い性となり、
あたかも、DNAにインプットされたかのごとき
気質を作り出したのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月19日
先見力とは
齋藤孝 著 「はじめての坂本龍馬」から
『
先見力とは、
いろいろな選択肢がある中で、
「これだ!」
と的をしぼって、
そこに全精力をかけられることです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月17日
わくわくする才能が大切
齋藤孝 著 「はじめての坂本龍馬」から
『
わくわくする才能は、
持って生まれた頭の良さよりもっと大切です。
技術や知識は
わくわくしているのであれば、
わりと簡単に身についていくものです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月16日
融通無碍(ゆうずうむげ)な合理性
藤本義一+丹波元 著 「大阪人と日本人」から
『
大阪人は規則があっても、
眼前に不都合があれば、
迷わずルールの方を無視する。
つまり、
杓子定規(しゃくしじょうぎ)を嫌い、
融通無碍(ゆうずうむげ)な合理性を尊ぶ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月14日
行動力とは
齋藤孝 著 「はじめての坂本龍馬」から
『
行動力とは
ただ足を動かすことではありません。
こうなったらいいなという筋が見えた上で
動くのが行動力です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月12日
ちょっとコーヒー
川口葉子 著 「京都カフェ散歩」から
『
少し時間をおいてふた口目を飲むと、
とつぜんコーヒーに羽根がはえて軽くなる。
三口目には甘みを感じる。
そして最後に飲み干すとき、
コーヒーは重力をふりきって舞いあがり、
一瞬にしてすっと消えるのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月10日
エリートとは
2010年02月08日
五感に素直に生きる
川口葉子 著 「京都カフェ散歩」から
『
人間は五感に素直に生きていれば、
出会うべき人や場所に
出会えるのかもしれない。
そしてこのカフェは、
出会いのきっかけをもたらす
何かを秘めている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月06日
アメリカとつき合っていく日本
河合隼雄 著 「日本人という病」から
『
アメリカ人の中には
自分たちの考えこそ「普遍的」と
思っている人もある。
そのような国とつき合いながら、
日本は自分の進む方向を
しっかりと見定めていかねばならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年02月03日
歴史を動かしていける人
齋藤孝 著 「はじめての坂本龍馬」から
『
いまの時代でも、
どうすれば日本の未来にとって
プラスになるかの結論は、
すぐには出ません。
とにかく長いスパンと視野の広さで、
先を見通して、
いまの方針を考えられる人が
歴史を動かしていくのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月28日
二十世紀の組織に縛られている
河合隼雄 著 「日本人という病」から
『
みんな自分の好き勝手なことをやっているつもりで、
我々がつくってきた二十世紀の組織の中に
自分が入ってしまっています。
その入ってることを楽しんでいるうちは華ですが、
そんなことで威張っている人もいる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月27日
理想の邁進は失敗しやすい
河合隼雄 著 「日本人という病」から
『
何でも目標を設定して、
それに向かって進んでいかなくては
ならないという考え方をするのではなく、
そういう考え方もあるし、
こういう考え方もある。
』
だから、カツマー(勝間)だけでは行き詰る訳です。
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月26日
個人主義は個性ではない
2010年01月24日
共通と相反
河合隼雄 著 「日本人という病」から
『
共通部分というのは
関係を維持していくのに役立っている。
相反する部分というのは、
関係を発展させるために役立っている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月21日
好きになるのは怖いこと
河合隼雄 著 「日本人という病」から
『
誰かを好きになるというのは、
ちょっと怖いことなのです。
ですから、人間というのは、
好きになることを防ごうとして、
好きになる人を、
はじめは嫌いな人だというふうに
思うことも多いのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月17日
人間関係があるから心が治まる
河合隼雄 著 「日本人という病」から
『
仲のいい人とか、
親類の人とか、
あるいは全然知らない人でも
同じ体験をした者同士だとか、
人間と人間の心の交流があるところで
怒りや悲しみを出すから
意味があるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月16日
阪神大震災では暴動も略奪もなかった
河合隼雄 著 「日本人という病」から
『
みんなが暴動も略奪もしないということと、
政府の対応が遅いというのは、
ひょっとしたら
日本人の同じ心のあり方から
来ていることではないかということです。
つまり、
日本人のよい面と悪い面が出ている
というふうに思いました。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月15日
日本人の一長一短
河合隼雄 著 「日本人という病」から
『
日本人は何もかも
自分で決めるということは
滅多にやらないですね。
あっちへ行ったり、
こっちへ行ったり、
いろいろつながりながらやります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月13日
常在戦場
佐々淳行 著 「危機管理最前線」から
『
至るところが、
いつ「戦場」になるかわからない
21世紀の危機の時代、
少なくとも指導者は、
《常在戦場》の心得で
日々臨まなければならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月12日
広告の小さい文字をよく読むことは
吉本佳生 著 「スタバではグランデを買え!」から
『
広告やパンフレットは、
あなたが賢い消費者であるか、
賢くない消費者であるかを、
企業側が見定めるために用意された
「消費者能力テスト」であると意識すれば、
広告やパンフレットの読み方も
かわってくるでしょう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月09日
国会ではシッカリ議論
佐々淳行 著 「危機管理最前線」から
『
国会は、
一日開けば二億円のコストがかかるという。
それだけ多額の税金を使っているのだから、
政府側もシッカリしなくてはいけない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月08日
予知できないが予測はできる
2010年01月07日
夢の繭
川口葉子 著 「京都カフェ散歩」から
『
戦争反対と、
発言することが命がけだった時代があり、
しかもそれがたかだか数十年前のことなのだと思うと、
今の私は夢の繭(まゆ)に幾重にもくるまれて
眠っているのかしらと心もとなくなる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2010年01月05日
東京にはなきゃあかん喫茶店がない
2010年01月01日
コーヒーを飲みながら
川口葉子 著 「京都カフェ散歩」から
『
喫茶店やカフェは
都市ならではのものだと思います。
仕事も嗜好を知らない者どうしが
隣りあわせてコーヒーを飲みながら、
自然につながったり離れたりするおもしろさ。
』
あなたにとって、2010年は誰と隣り合わせで、そして、新しい繋がりが生まれるのでしょうか。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月30日
自分が誰かを知っている人
本田健 著 「ユダヤ人大富豪の教え」から
『
自分が誰かを知っている人は、
他人の評価を求めたり、
必要以上の物を欲しがりません。
また、好きなことをやっている人は、
自然と自分の周りにやさしくなれます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月28日
危機管理はボランティア精神
佐々淳行 著 「危機管理最前線」から
『
「危機管理」とは、
事に臨んで「私がやらずに誰がやる」
という魂の内なる声に応じて身を挺して、
世のため、人のため、国のため行動する
ボランティア精神だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月26日
多くの人の助けがあって生きていける
本田健 著 「ユダヤ人大富豪の教え」から
『
この世の中の誰一人として、
一人で生きていけるものではない。
どんなに世界的に成功している人でも、
誰かのサービスを必要としているんだよ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月25日
達成できる目標は
本田健 著 「ユダヤ人大富豪の教え」から
『
モチベーションというガソリンがなければ、
走ることはできない。
それを考えただけで
ワクワクするような目標がなければ、
うまくいかないのだよ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月24日
幸せになるための心構え
本田健 著 「ユダヤ人大富豪の教え」から
『
起こる現象から
自分が何をできるかを考え、
そして目の前のことをこなしてゆく。
そういう心構えがあってこそ、
初めて幸せに豊かに生きることが
できるようになる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月23日
決断しないのが害
本田健 著 「ユダヤ人大富豪の教え」から
『
人生では、
良いことも悪いことも起こる。
それは、ある状況を
どう捉えるかによって変わってくる。
そう考えると、
決断をせずに、何もやらないというのが
いちばん害になることがわかるだろう
』
政府がガソリン税などの暫定税率分の課税は維持すると発表しました。カリプソ【官僚】の思い通りに動かされていますね。
22世紀まで日本が生き残れるかどうかの瀬戸際なのですから、きっぱりと課税を廃止するぐらいの気構えが欲しいものです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月22日
商品を長続きさせるには
本田健 著 「ユダヤ人大富豪の教え」から
『
急成長できるとしても、
ゆっくりと大きくなるのがいいんだ。
さばききれない注文は
断るぐらいでちょうどいい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月19日
トップの心得
2009年12月18日
自分の特性に合うことをやるのが幸せ
本田健 著 「ユダヤ人大富豪の教え」から
『
自分の特性に合わないことをやっても、
不幸になるだけだよ。
そしてそれぞれの立場で、
人を幸せにすることができれば、
君は十分に幸せで豊かな人生を
送ることができるからね
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月17日
金持ちになる人間は
2009年12月16日
お金を賢く使う
本田健 著 「ユダヤ人大富豪の教え」から
『
賢く使うとは、
それが人を喜ばせるように使うことだ。
幸せになることに成功した連中は
人にプレゼントをするのが大好きだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月15日
成功したければ
本田健 著 「ユダヤ人大富豪の教え」から
『
成功したければ、
少し格上の人間とつき合いなさい。
彼らから、
はじき出されないように頑張っていれば、
いずれふさわしい人間性ができてくる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月13日
ネガティブに吸い寄せるられるな
2009年12月10日
トップの一言
佐々淳行 著 「危機管理最前線」から
『
トップの最初の一言は、
その人の世界観、
人生観、教養、経験則などなど、
何十年という山あり谷ありの人生で
培ってきた全人格が凝集した、
いわば精神の瞬発力の表われである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月08日
アイデア手帳を持つ
本田健 著 「ユダヤ人大富豪の教え」から
『
彼らは、
スケジュール手帳の代わりにアイデア手帳をもっている。
フッと頭に浮かんだアイデアを書き留めるノートだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年12月05日
微妙で深い交わり
2009年12月03日
平成には維新の覚悟があるのか
白洲 正子 著 「心に残る人々」から
『
(明治)維新と名づける破天荒な事業は、
・・・
過去も未来を打ち捨てて、
ひたすた現実の中に
飛びこむことの出来た人々だけに
可能な革命であった。
悲しいことに、
それは為しとげなければ国が
危い止むに止まれぬ勢いであった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年11月29日
いちげんさんお断りのシステム
川口葉子 著 「京都カフェ散歩」から
『
いちげんさんお断りのシステムは、
不文律を知らない観光客から
お店を守ると同時に、
観光客に場違いで
いたたまれない思いをさせないための
親切な仕組みなのだと、
あるカフェのオーナーが教えてくれた。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年11月25日
人材行灯論
佐々淳行 著 「危機管理最前線」から
『
太陽が輝き、
電灯煌々と照らすとき、
行灯(あんどん)やぼんぼりは
その存在すら分からない。
しかし一旦夜の闇、
停電の暗黒が支配するとき、
あちこちから
行灯の明かりが一隅を照らし、
やがてそれが集まって
世は明るさを取り戻す。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年11月20日
生きた金を使う
白洲 正子 著 「心に残る人々」から
『
金使いの荒い人はいくらでもいようが、
生きた金を使う人は稀なのだ。
』
政府が行った仕分け作業で、国家予算は「生きた金」になったのでしょうか?
それとも・・・
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年11月19日
つまらなくしているのは先入観
白洲 正子 著 「心に残る人々」から
『
先入観ほど人をあやまつものはない。
それより、
世の中をせまく、つまらなくするものはない、
といった方がいいかも知れない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年11月16日
小さきものの小さき力
2009年11月15日
有為転変
2009年11月11日
怒らせて炙り出す
2009年11月10日
呆れられるぐらい極めよう
岡崎武志 著 「古本でお散歩」から
『
何かをとことん極めようと思ったら、
人から呆れられるくらいでないとダメだろう。
感心させている間はまだ半人前なのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年11月09日
因果律の地平線
2009年11月06日
カネは天下の回りもの
2009年11月05日
時間に任せて生きて行く
白洲 正子 著 「心に残る人々」から
『
技術は若い時に出来上がって、
あとはただ待つのです。
急いではいけない、
すべては時間に任せて
だまって生きて行く。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年11月02日
メーカーの思いが感動を呼ぶ
ホンダ社長 伊東 孝紳 さんの言葉から
『
いくらきれいで、
性能がいい車でも、
それだけでは評価されない。
人を感動させるのは、やはり
「製品に込められたメーカーの思い」
だと思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月31日
嫌いな人間と付き合うと破綻する
内田 樹 著 「知に働けば蔵が建つ」から
『
「嫌いな人間と付き合う」というのは
「できないこと」の一つである。
それを無理矢理やろうとすると、
どこかに破綻が生じる。
』
だから、ヒエラルヒーの上の人は、パワハラに走るのです。でも下の人は何もできませんから、萎縮してしまうこともあります。こんなときは、ブログに「上司のアホンダラ」と書きましょう。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月29日
チマチマで得する国民性
岡崎武志 著 「古本でお散歩」から
『
日本人にはそもそも、
チマチマした貧乏性が
国民性として根付いているのだと思う。
必要に迫られてというより、
好きなんだよ、もともとが。
あれこれ細かいことをやって
得したような気分になるのが。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月28日
古書夢想
岡崎武志 著 「古本でお散歩」から
『
ワンポイントだけで買って、
しばらく寝かせておいて、
あれこれとどういう本か考えてみる。
この時間がじつに楽しい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月25日
本当の世論のために
サステナ代表 マエキタミヤコ さんの言葉から
『
マスメディアが作り出す
「世論」は危険だ、
と思う人は多いのではないでしょうか。
ツイッターも
ユーチューブも
ブログも、
マスメディアだけでは
正しい情報を得られないと
思っている人たちがいて
生まれたものです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月24日
宿命の刻印
内田 樹 著 「知に働けば蔵が建つ」から
『
想像力の豊かな人は、
どのような人生を選んだ場合でも、
その人生の至るところに
「宿命の刻印」を感知する。
』
現政権が政策を誤ったり、内部分裂をすれば、今の国民をがっかりさせるだけでなく百年後の歴史家に、
「あの時にちゃんとやっていれば、日本はアジアの小国にならなかったのに!」
と揶揄されることになります。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月23日
決め打ちしないという生存戦略
内田 樹 著 「知に働けば蔵が建つ」から
『
世の中この先どうなるかわからない。
わからない以上は、
「決め打ち」はしたくないとい考え方は
生存戦略としては健全である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月22日
詩は体に必要なんだ
2009年10月21日
ことばにならない思い
内田 樹 著 「知に働けば蔵が建つ」から
『
「埋めがたい欠落感」
を抱いている人間だけが
それを埋めようとする。
「ことばにならない思い」
を抱いている人間だけが
それを「ことばにしよう」とする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月19日
都市は移ろい易く自然は永い
2009年10月17日
ヴィトンを持って「おでん」を買いに行く
2009年10月15日
超人
2009年10月14日
独創性とは他の誰によっても代替できないこと
内田 樹 著 「知に働けば蔵が建つ」から
『
自分の独創性というものを
引き受けることができないということは、
言い換えれば、
自分が
「どのような仕方で、
他の誰によっても代替できない固有の存在
であるか」
を言うことができないということである
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月13日
古本で自分の価値の体系を作る
2009年10月12日
何かを食べていかなくてはならないのだ
米原万里 著 「旅行者の朝食」から
『
「働かざる者、食うべからず」
とは言うものの、
働いていようといまいと、
生きていくには
何かを食べていかなくてはならない。
』
リストラになろうが、働き口がなかろうが、生きるためには食べなくてはならないのです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月11日
大衆社会
内田 樹 著 「知に働けば蔵が建つ」から
『
「多数派の偏見」が常識とみなされ、
「多数派の臆断(おくだん)」が
真理とみなされるのが
大衆社会である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月10日
古本屋の醍醐味
2009年10月09日
日本が海外派兵駐留できない訳
米原万里 著 「旅行者の朝食」から
『
本国の料理がうまかったら
長期駐留に耐えられるだろうか?
本国の料理に魅力がなく、
駐留先の方が美味しい料理を
たくさん口に出来るのならば、
里心がつきにくいのではないだろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年10月08日
食べ物占い
米原万里 著 「旅行者の朝食」から
『
その人が本質的に
保守的か革新的かを占うには、
未知の食べ物への対し方を見る方が
血液型よりはるかに当てになる気がする。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月28日
夢の仕事に就けるとは限らない
内田 樹 著 「知に働けば蔵が建つ」から
『
夢に向かって努力すれば
その夢は必ず実現するというのは
「ウソ」である。
すべての人が希望通りの職に
就けることはあり得ない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月25日
研究者の養成に必要なもの
木下是雄 著 「日本語の思考法」から
『
研究者の養成に必要なのは、
あまりたくさんのことを教えない教育、
その代わり
自然そのものとのつき合いから出発する教育
ある意味ではかたよった教育なのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月23日
ニートはニュータイプ
内田 樹 著 「知に働けば蔵が建つ」から
『
ニートは資本主義社会から
「脱落」
している人々ではない。
彼らは資本主義社会を
「追い越して」
しまった人々なのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月22日
既知の結末
内田 樹 著 「知に働けば蔵が建つ」から
『
私は話の結末をまだ言うことができない。
けれどもそれは
結末を知らないということではない。
結末はわかっているのだが、
まだそこまでたどりつかない
ということである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月20日
正邪善悪紙一重
2009年09月18日
みんな同じ面は見ない
木下是雄 著 「日本語の思考法」から
『
ものにはいろんな側面があるから、
ある側面を見させようとか
伝えよとかするのは
なかなかむずかしいんだね。
見る見方にはじつに自由度がある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月16日
英語よ驕るなかれ、日本語の力を知るべし
木下是雄 著 「日本語の思考法」から
『
日本は、物理学を
自国語で教えることのできる
数少ない国の一つなのだ。
・・・
多くの国のことばには、
抽象語の訳語をつくるだけの
造語力(と基礎語彙)がないので、
自国語では満足に高等教育を
おこなうことができないのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月14日
コミュニケーション・パターンを学ぶことが語学
木下是雄 著 「日本語の思考法」から
『
外国語を教えるには、
ことばという要素と
そのつなぎ方の規則を
教えるだけではだめで、
その言葉を母国語とするひとたちの
コミュニケーションのパターンを
じゅうぶん理解させることが必要だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月13日
簡略が簡潔なのではない
2009年09月11日
「日本」の本は大阪のこと
2009年09月10日
カタカナ語は日本以外に通じない
木下是雄 著 「日本語の思考法」から
『
欧語を材料にしてカタカナ語を濫造し、
それによって無制限に
語彙を拡張しつつあるのが
現代日本語の一つのすがたである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月09日
上方の常識
谷川彰英 著 「大阪 駅名の謎」から
『
上方の人々の「日本橋」に
対する思いは強いのである。
「日本一!」と叫ぶときは、
決して「にほん」とは言わず
「にっぽん」と声をあげる。
それが常識というものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月08日
日本人のアイデンティティ
木下是雄 著 「日本語の思考法」から
『
もし私たちが
婉曲で間接的な表現を尊ぶ心を失えば、
それは日本人としての
アイデンティティの喪失に通じかねない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月07日
武器よさらば情報こんにちは
2009年09月06日
セイギノミカタ
2009年09月04日
言伝が不得意な日本人
木下是雄 著 「日本語の思考法」から
『
明確にものを言うことを好まない国では、
明確にものを言わせる訓練がおこなわれない。
その結果として、
日本人はことばによって
正確に事実をつたえること、
理路整然と意見を述べることが
不得意である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年09月02日
話が聞き手に届くには
斎藤孝 著 「人を10分ひきつける 話す力」から
『
聞き手は、
話し手との間で場を共有してはじめて、
その話が腹に落ちてくる。
「いま、ここで、私たちの間で意味が生まれている」
という喜びが、
話を聞くモチベーションを高める。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年08月31日
本は話なり
斎藤孝 著 「人を10分ひきつける 話す力」から
『
話のおもしろい人ほど、
たくさん本を読んでいる。
本から仕入れた素材を使って、
再生しているのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年08月23日
聞いた人を変える話
斎藤孝 著 「人を10分ひきつける 話す力」から
『
話の中の何かが残っていて、
その後、
聞いた人の何かが変わっていくとなると、
話の効果は非常に大きい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年08月22日
言い換えが伝える
斎藤孝 著 「人を10分ひきつける 話す力」から
『
相手によって、
文脈によって、
言い換えることができなければ、
話はうまく伝わらない。
適切に言い換えることで、
伝える力は飛躍的に上がる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年08月19日
新しい角度で物を見る
米原万里 著 「ガセネッタ&シモネッタ」から
(地獄の沙汰も通訳次第)
『
人間のやることはどれも面白い、
という真理なんですが、
異なる部分の通訳をやるたびに、
新しい角度で物が見られるようになるのは
役得ですかねえ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年08月18日
意味の含有率
斎藤孝 著 「人を10分ひきつける 話す力」から
『
友達同士ならノリだけでもいいが、
相手が多くなれば、
話の中の意味の含有率が高くなければ
聞いてもらえない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年08月13日
曖昧な表現は文化が発達している証
米原万里 著 「ガセネッタ&シモネッタ」から
(地獄の沙汰も通訳次第)
『
曖昧ですが、相手を傷つけずに言いたいことが
表現できるのは日本語の非常に優れた財産で、
素晴らしいことだと思うんです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年08月11日
真実も大きすぎると
米原万里 著 「ガセネッタ&シモネッタ」から
(地獄の沙汰も通訳次第)
『
嘘は大きいほど信用される、
とヒットラーの宣伝相ゲッペルスは言ったそうだが、
真実は大きすぎると信じられなくなる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年08月08日
直感なくしては無理
エリヤフ・ゴールドラット著 「ザ・チョイス」から
『
論理を展開していくには、
直感に基づいて原因と結果の関係を
次から次へと供給していかなければいけない。
仮説を立てるにも、
あるいは結果を予測するにも、
直感なくしては無理なんだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年08月01日
抵抗に遭ったとき
エリヤフ・ゴールドラット著 「ザ・チョイス」から
『
抵抗に遭った場合、
本来は、相手にいかに
自分の考えを伝えたらいいのか、
周到に考えて行動すべきなのだが、
しかし人には、
妥協に逃げたがる強い傾向がある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月28日
文学が愛国心を育む
米原万里 著 「ガセネッタ&シモネッタ」から
(地獄の沙汰も通訳次第)
『
子供に自分の国の文学をたくさん読ませるということが、
結局、
わたしは愛国心を育てることだと思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月25日
感情以上のもの
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
誰かに出口をたずねたとき、
教えてくれた人の声の調子は問題ではない。
どんな声の調子でも、内容さえ正確なら、
出口は見つかるはずだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月24日
非を検証する
エリヤフ・ゴールドラット著 「ザ・チョイス」から
『
どんな仮説を立てるにしても、
いきなり人に非を求めるのではなく。
本当に相手に責任を求めていいのかどうか、
その検証がなされなければいけない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月19日
誇張という手段
米原万里 著 「ガセネッタ&シモネッタ」から
(地獄の沙汰も通訳次第)
『
受け手に確実にメッセージを届かせたい。
その手応えが欲しい。
そういう職業的使命感が高じると、
ついつい誇張という安易な手段に頼ってしまう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月18日
イタリア男はフリーパスだが
米原万里 著 「ガセネッタ&シモネッタ」から
(地獄の沙汰も通訳次第)
『
ここは、日本なのだ。
女の範疇分けされることが
通行証の役割を果たしてしまうなんてことは、
自民党政府がアメリカにNOと言うくらいに
可能性が低い。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月17日
チラリズム
米原万里 著 「ガセネッタ&シモネッタ」から
(地獄の沙汰も通訳次第)
『
チラリズムこそが。
つまりは見せているようでも見せないことこそが、
人の気を惹く容易にして効果的な手段であることだけは、
まことに正しいのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月16日
意見が一致するとき
2009年07月15日
完全な世界
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
現実の世界は、
果たして完全かどうかは、わからない。
しかし、少なくとも、
すぐれた文学の世界は完全である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月11日
文学を読むことは
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
文学の本をいかに読むかは、
知識の伝達を目的とする「教養書」を
いかに読むかということよりずっとむずかしい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月09日
時を軽視してはならない
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
時を軽視してはならない。
過去から現在へという方が自然であるが、
現在のものから過去のものへと
読んでもいっこうかまわない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月08日
あり得ない答えを探す
エリヤフ・ゴールドラット著 「ザ・チョイス」から
『
何が大変だって、
どう考えても答えなどあり得るはずがない
と確信している問題の答えを
探さなければいけないことほど、
大変なことはない。
』
「仕事が減っているのに、仕事を取って来い」とか、
「関空で路線が減っていくのに、黒字化しろ」
なんていうのが多い昨今です。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月07日
良い本の誤り
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
本当に良い本は、
推論で、すぐわかるような誤りを
犯したりはしないものだからである。
たとえ誤りがあっても、
たいていは、巧みに隠されていて、
洞察力のするどい読者でなければ、
これを見抜くことはむずかしい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月05日
企業家精神とは
英ヴァージン・グループ会長 リチャード・ブラウンさんの言葉から
『
企業家精神とは
他社と異なるユニークなもので、
できれば30~40年は続くアイデアを生み、
その詳細を一つひとつ詰めていくこと、
そのうえで望めれば収益面でも
成功するということなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月04日
前提を取り除こう
エリヤフ・ゴールドラット著 「ザ・チョイス」から
『
対立の根底にある前提を取り除くことで、
対立を解消しようというアプローチをとるべきなのだ。
対立を解消することで、
望ましい変化への道筋もできる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月02日
目先が人をダメにする
品川隆幸 著 「東大阪元気工場 ダメならほかのことせんかい!」から
『
日本はすぐに、
もうかるから向こうにもっていって
つくろうと目先のことばかりやっている。
人を利用することばかり考えているから
人までダメになる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年07月01日
人間は感情と偏見の動物
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
人間は理性の動物だから、
理性で他人を認めることもできる。
だが、その理性は完全とは言えない。
それで、とかく他人と争うことにもなる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月29日
人責め
エリヤフ・ゴールドラット著 「ザ・チョイス」から
『
人を責めると、
間違った方向に行ってしまう。
正しい方向からどんどん遠ざかってしまって、
よいソリューションなんか見つからなくなってしまう。
もし相手を排除することができたとしても、
ほとんどの場合、
本当の問題は残ったままになる。
』
不景気なると人責めが多くなります。企業では、わざと人責めしてリストラを行う、“shadow mission”が行われているところもあります。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月27日
意味のつかめない言葉
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
パラグラフが完全に理解できないのは、
意味のわからない単語があるからで、
読み手にとって意味のつかみにくい言葉こそ、
著者が特別の意味で使っている言葉であるかもしれない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月25日
ブレークスルーが訪れるとき
エリヤフ・ゴールドラット著 「ザ・チョイス」から
『
本当に有意義な機会とは、
閉じ込められた状況の中で、
どうすればその障害を克服できるのか、
そのことに気づいた時に
訪れるのではないだろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月24日
コミュニケーションの成立
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
コミュニケーションとは、
他人と何かを共有しようと努めることである。
互いに知識や情報を共有してはじめて、
コミュニケーションは成立する。
』
骨太だった国の予算方針が骨無し方針に転換されました。カリプソとデイヴィ・ジョーンズが、自分の好き勝手にやってくれています。
国民とカリプソ【官僚】、
国民とデイヴィ・ジョーンズ【自民党】
とは、コミュニケーションが成立していませんね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月23日
豪傑がいなくなった
品川隆幸 著 「東大阪元気工場 ダメならほかのことせんかい!」から
『
もう「あかんかったら辞めたるわ!」
というような人間はどこにもいない。
そんな豪傑がいなくなったことも、
日本の停滞を招いている要因の一つであろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月22日
状況を改善したいとき
エリヤフ・ゴールドラット著 「ザ・チョイス」から
『
何かの状況を改善しようとする時は、
小さな問題ばかり対象にしていてはダメだ。
そんなのは、時間の無駄でしかない。
それよりも、
もっと大きな問題に取り組まないといけない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月18日
感性を豊かにする
品川隆幸 著 「東大阪元気工場 ダメならほかのことせんかい!」から
『
モノづくりは感性が豊かでなければダメだと思う。
知識だけではモノづくりはできない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月17日
調子の悪いとき
品川隆幸 著 「東大阪元気工場 ダメならほかのことせんかい!」から
『
どうしてもみんな難しく考えてしまう。
特に調子の悪いときほど、
もがきすぎて泥沼にはまり、
次から次へと悪い方向に
引き寄せられてしまう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月16日
人間は気持ちで動く
品川隆幸 著 「東大阪元気工場 ダメならほかのことせんかい!」から
『
人間というのは気持ちで動く。
心で動く存在なのである。
心が躍動していなかったら、
体も躍動しない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月14日
すべては複合的
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
およそ人の知る限りのもの、
あるいは人間の作ったもので、
それほど極端に単純なものなどはない。
すべては複合的な統一体である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月11日
もっとも良い本
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
もっとも読みやすい本は、
著者が建築的に成功した作品である。
もっとも良い本は
もっとも明確な構造をもったものである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月09日
歴史の真髄
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
歴史の真髄は「語り」である。
歴史は、過去に存在したというだけでなく、
時の移り変わりの中で、
起きた一連の変化の底を流れる事件や
事物についての知識である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月04日
本に問いかける
M.J.アドラー/C.V.ドーレン 著 「本を読む本」から
『
意欲的な読み手は問いかけをする。
意欲的でない読み手は問いかけをしない
- だから答えも得られない
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年06月03日
共同体の智恵
民俗学研究者 土喰小組合長 ジェフリー・アイリッシュさんの言葉から
『
地球環境が危うくなっている今こそ、
身の丈に合わせて生きる、
共同体の智恵を
再認識すべきではないでしょうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月29日
市場経済と規制のバランス
根井雅弘 著 「経済学はこう考える」から
『
何事もバランス感覚は必要で、
市場経済の利点を生かすべき分野と、
政府がきちんと規制しなければならない分野とは
慎重に区別しなければなりません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月27日
輝くのは一瞬
2009年05月22日
21世紀の先進国の課題
福島清彦 著 「ヨーロッパ型資本主義」から
『
経済の効率と社会の平等・安定・福祉は
本来両立しにくいものである。
そのことを十分認識したうえで、
経済政策と社会政策を作っていくことが、
二十一世紀の先進国共通の課題なのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月21日
市場原理を利口に活用する
福島清彦 著 「ヨーロッパ型資本主義」から
『
ヨーロッパ各国は市場原理を
ただ無制限に適用するのではなく、
必要な場合は市場原理を抑制しながら、
利口に活用していくべきであることを知っている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月18日
「買い物」という営み
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
日本人にとって「買い物」とは、
物を入手する行為であるだけでなく、
ささやかな虚栄心と満足と、
王や神のように遇されることの心地よさを、
店主や店員から得る営みなのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月15日
定価
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
インド人にとって交渉は、
「定価を定めること」であり、
日本人にとっては
「定価を割り引く」ことだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月14日
悪の量
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
欲望というものが
それぞれの文化において
どのような形をとるかということだ。
悪の質が変わっても、
悪の量は世界中どこでも
変わらないのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月11日
時代にあわなくなったこと
斎藤美奈子 著 「紅一点論」から
『
戦士としての正義をふりかざす滅私奉公の企業社会や、
王子様との結婚が人生最大の目標だった女性の生き方じたいが、
時代にあわなくなったのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月07日
国際人としての資格
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
ジェントルマンとしての美徳、
「正義」、「判断力」、「批判能力」
の方がより重要で肝要だと思われる。
だが、これらの要素は彼ら(日本人)の
「国際人としての資格」
からまったく抜け落ちているのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月05日
メニュー文化
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
メニュー文化は
「提示と選択」を前提にした規格品の文化であり、
メニューやカタログは
消費拡大のために不可欠な刺激財の
役割を果たしている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月04日
政治が語るべき希望
東京大学社会科学研究所教授 玄田有史 さんの言葉から
『
社会全体に
希望を与えるような政治は警戒したい。
政治が語るべき希望は、
最高度の悪を回避することだと思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月03日
目的と手段を混同する日本人
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
日本人は、
目的よりも対面や
手段の在り方に拘泥(こうでい)し、
ややもすると目的を見失う。
いっぽうインド人は、
目的のためにあらゆる手段を講じ、
いかなる場合にも目的と手段とを
混同することがない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年05月02日
大阪商人の気質
建築家 安藤忠雄 さんの言葉から
『
名よりも実を、
理屈より行動を
かつての大阪商人の気質は、
時代を経ても変わらぬ
大阪らしさとして生き続けている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月29日
オタクという小社会
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
日本のこの異常な「小社会」現象は、
いったい何を意味するのだろうか。
意識を細分化し、アトム化することによって
既成の社会を解体し、
世界の構造化を拒絶しているようにも見える。
つまり、一種のアナーキズムのように思えなくもない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月27日
英語が通じないけど語学熱が高い国
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
あまり知られていないが、外国人にとって、
日本は言語事情が最も悪い国の一つである。
と同時に、矛盾するような現象だが、
語学熱がひじょうに高い国でもある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月22日
いい人
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
「いい人」という概念は、
日本独特の特記すべき人格の一つである。
もし日本人から「あなたはいい人だ」と言われたら、
それはひじょうに深い信頼を得たと考えてよい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月21日
「しくみ」を応用する
松岡正剛 著 「知の編集術」から
『
どんなことにも
どんなものにも
「しくみ」というものがあって、
その「しくみ」に入っていくこと、
またそこから出たら、
それをなんとか応用すること、
そのことに価値があると
おもえるようにすることである。
』
定額給付金の通知が来ました。金だけバラまいといて、「後で消費税あげますからね」とは、まったく無責任な話です。そして、デイヴィ・ジョーンズ【自民党】が、「選挙はよろしく~♪、ワン」(関西電力圏しか分からないネタです・・・)と鼻歌を歌ったりしています。
「経済のしくみ」を考えて、一番効果の上がるものに税金は使うべきですよね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月20日
男社会と女性像
2009年04月19日
日本は経済主役社会
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
人間中心の社会というより経済主役の社会であり、
人は消費の奴隷に成り下がってしまう恐れがある。
というのも、
そのような形の消費は幸福のためのものというより、
欲望のためのものであるからだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月18日
品質と価格のつりあい
小林カツ代 著 「小林カツ代のおいしい大阪」から
『
大阪人は金勘定にうるさいから、
安ければ売れるやろう、
と世間で言われているのは大まちがい。
安くてもまずいもの、
質の悪いものはアカン。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月17日
素晴らしい工芸の国
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
日頃インドの手仕事を自慢に思っていた私は、
テクノロジーの国日本で思わぬパンチを食らった。
日本は素晴らしい工芸の国でもあったのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月14日
ムリから出たドーリ
松岡正剛 著 「知の編集術」から
『
言葉を厳密につかおうとすると、
たいていはムリ(無理)が生じてくる。
そのムリを承知で、
ムリをドーリ(道理)にしようというのが
学問や思想というものである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月10日
グローバルよりローカル
東京大学院教授 西垣通 さんの言葉から
『
グローバルよりローカル。
金融市場の数字より
衣食住の細部に深い価値を見いだし、
充足感を味わうのが、
生物である人間の本来の姿でしょう
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月08日
若者文化というアヘン
M・K・シャルマ 著 「喪失の国、日本」
(インド・エリートビジネスマンの「日本体験記」)
『
日本経済は若者にターゲットを絞り、
若者文化を擁護し、
若者を主人にすることで利潤の追求を図った。
・・・
これは阿片の効果とどこか似ている。
売る側にはどんどん金が入ってくるが、
買う側の精神はしだいに蝕(むしば)まれていく。
』
日本のベケット卿傘下の企業が若者に消費を促し、その一方でセイフティネットのない派遣労働へ若者を追いやって行ったのでした。
そして、携帯電話は合法的なドラッグとも言えます。携帯依存症の若者は、仕事が無かっても料金を支払い続けているのですから。
昔は、
「書を捨てよ、街に出よう」
でしたが、今は
「携帯電話を捨てよ、図書館へ行こう」
でしょうか?
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月02日
大阪人は味に関して正直
小林カツ代 著 「小林カツ代のおいしい大阪」から
『
安いから、というだけで通ってくれるほど甘くないし、
大阪人はもうおそろしいほど、
おいしいもん/まずいもんにシビアですし、
味に関して正直なんですわ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年04月01日
日本も未来ビジョンの大切さを知るべきとき
福島清彦 著 「ヨーロッパ型資本主義」から
『
欧州連合内部の国際関係は、
瑣末(さまつ)な貿易摩擦問題だけが活発に議論され、
大事なことについては
目標なき漂流を続けている日米関係より、
はるかに強固である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年03月31日
「一芳亭」の中華料理
小林カツ代 著 「小林カツ代のおいしい大阪」から
『
なんかみんな、
食べていくうちに
どんどん幸せそうな顔になるんですよ。
そういうあったかい料理やし、
あったかい雰囲気の店なんですわ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年03月30日
「おいしい」は手を抜かないところで生まれる
小林カツ代 著 「小林カツ代のおいしい大阪」から
『
大阪の食べ物屋さんは、
値段がうんと高いところでも、
信じられへんくらい安いところでも、
「おいしい」と人々が認めて長く通う店は
料理にけっして手を抜いていません。
』
だから、カリプソ【官僚】が作った数々のシステム(J-SaaSなど)は、利便性とは程遠いものがあるのですね。おいしくない(役に立たない)から。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年03月28日
ヨーロッパ型資本主義の考え方
福島清彦 著 「ヨーロッパ型資本主義」から
『
経済成長最優先、効率至上主義で
資本主義社会を作るのではなく、
落ち着きとゆとりのある社会を作り、
貧富の格差をそう大きくせず、
治安のよい状態を維持していこうというのが、
ヨーロッパ型資本主義の考え方なのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年03月27日
21世紀の国づくりで大切なこと
福島清彦 著 「ヨーロッパ型資本主義」から
『
21世紀の国づくりで大切なことは、
指導者の力量や企業経営者の力だけではない。
むしろ、
政府が長期的な視野に立って、
教育、交通、医療などの人的、社会的基盤に、
どういう基本的な投資を行うかが大切になってきた。
』
カリプソ【官僚】とデイヴィ・ジョーンズ【自民党】の近視眼的な思考/施策が、医療現場の崩壊や子供たちの学力低下を招いてしまいました。
医師不足なら、高給を払ってでも海外からインターンを受け入れ、医療現場で学びながら短期的に日本で働いてもらうなど、常識を越える行動が求められているのかもしれません。政府の方が意思不足なのでしょう。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年03月26日
非アメリカ型モデルの有効性
福島清彦 著 「ヨーロッパ型資本主義」から
『
グローバル化に対する
有効な戦略が立てられないで
困っている日本の立場からすれば、
EUは非アメリカ型の、
「社会的な」モデルの有効性を
世界に示した点に大きな意義がある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年03月24日
情報の仮留め
松岡正剛 著 「知の編集術」から
『
情報を編集するには、
いくつもの見方を変える機能を
もつことが必要であるが、
それとともに
情報をすばやく適材適所に格納し、
それらの特徴を
仮に表示しておく機能も必要になる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年03月15日
市場原理が拡大させるもの
福島清彦 著 「ヨーロッパ型資本主義」から
『
市場原理は本来、
弱肉強食の論理を内包しており、
一国内でも、国際的にも、
貧富の格差をますます
拡大していくものである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年03月14日
大阪人は食べ物の贅沢を好む
小林カツ代 著 「小林カツ代のおいしい大阪」から
『
つねづねわたしは、
「大阪人はケチやない」と主張しているんですが、
とくにコーヒーの味には大阪人が食べるものに関して
ぜいたくを好むというところがよく出ていると思っています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年03月10日
dejavuと思わせないこと
2009年03月09日
大阪のホットケーキ
小林カツ代 著 「小林カツ代のおいしい大阪」から
『
なんや知らんけど、
大阪の老舗喫茶店で食べるホットケーキは
気持ちをあったかにしてくれるんですよ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年03月04日
リーマンショックは予言されていた
2009年02月27日
情報の連想
松岡正剛 著 「知の編集術」から
『
連想はこのような情報の
多様性や変換性をたくみにとらえて、
「そこにあるもの」から
「次にあるもの」へ
跳んでいく編集術である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年02月26日
薬店のオフサイド・ルール
松岡正剛 著 「知の編集術」から
『
ある一線に近づきすぎている
現象を禁止することによって、
その一線の特定の意義を保とうとすること、
それが社会のオフサイド・ルールなのである。
』
ネットでの薬販売禁止も、一種のオフサイド・ルールですね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年02月23日
柔らかい法
松岡正剛 著 「知の編集術」から
『
法が厳密すぎて人情にそぐわないときは、
事実のほうに嘘をさしはさみ、
そのさしはさんだ範囲で
裁定をすましてしまうという方法
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年02月22日
情報を創発する技術
松岡正剛 著 「知の編集術」から
『
あらかじめ準備しておく編集も大事だが、
その場に臨んでますます発揮できる編集力、
それが私がいちばん重視する
創発的な技術というものだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年02月21日
主題よりも方法
松岡正剛 著 「知の編集術」から
『
世の中では、
方法はおおむね縁の下に隠れ、
だいたいは主題や主人公のほうが
前面に出ているものなのだ。
』
定額給付金よりも、経済を良くする方法が大切なのですが・・・
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年02月18日
整理を面白くする
松岡正剛 著 「知の編集術」から
『
整理法がつまらないのは、
情報をただ整理袋に
分けようとしてばかりいるからだ。
おもしろくするには
分類された情報に関する辞書を
つけてみることだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年02月11日
唯一?
2009年02月08日
乱世は大いなるチャンス
松岡正剛 著 「知の編集術」から
『
乱世であればこそ
新たな発見に向かう可能性があるからで、
少なくとも、
「経済大国」とか「生活大国」などと嘯(うそぶ)いているより、
また不景気や教育低迷を嘆いているより、
ずっとおもしろい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年02月05日
情報化時代の教訓
2009年02月03日
ネットはナルシシズムの道具
東京外国語大学 亀山郁夫さんの言葉から
『
ネットは
自分の欲しい情報しかいらない、
というナルシシズムの道具。
ドストエフスキーが表現した生命力は、
異質なものを受け入れる努力によって
鍛えられるものです
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年02月01日
人と自然の境界線
玉村豊男 著 「里山ビジネス」から
『
人と自然には、
おたがいにもっとも妥当な
領分というものがあるのです。
日々の営みの中で、
その折り合いがうまくつく境界線を
手探りで見つけながら暮らすこと。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年01月30日
人間の言葉が消し去られている
栗山民也 著 「演出家の仕事」から
『
多くの情報の氾濫、
それを処理するための合理化、
簡略化の動きは、
私たち人間の
コミュニケーションのための言葉をも
暴力的に消し去っているのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年01月24日
いちばんの贅沢
桃白歩実 著 「関西弁で愉しむ漢詩」から
『
いちばんの贅沢は「ゆとり」、
ゆっくりした時間だ。
ゆとりが叫ばれて久しいが、
ワタシには「ゆとり」の
「ゆ」もやってこない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年01月22日
外から見える形で仕事をする
米国 第44代大統領 バラク・オバマ氏の就任演説から
『
私たち公金を扱う者は、
賢明に支出し、悪弊を改め、
外から見える形で仕事をするという、
説明責任を求められる。
』
この言葉をお札に書いて、日本の官僚のおでこに貼り付けてあげたいですね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年01月20日
小さな観光の必要性
玉村豊男 著 「里山ビジネス」から
『
生活の輪郭が曖昧になり、
日常の暮らしに漠然とした
不安を誰もが抱いているいま、
私たちは小さな観光を
必要としているのではないでしょうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年01月17日
いまは息苦しい
桃白歩実 著 「関西弁で愉しむ漢詩」から
『
もはや自分で決めたこと、
身体が決めたことで生きるなんて、
ちっともできないような
気にさえなってくる。
ゆとりは昔よりなくなって、
いまは身体に悪いことばっかりで
息苦しい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年01月13日
生活観光の時代
2009年01月10日
みんな兄弟みたいなもんや
桃白歩実 著 「関西弁で愉しむ漢詩」から
『
この世界に落ちてきた仲間やから
みんな兄弟みたいなもんや
肉親だけやて限定したない
』
ユダヤ人もパレスチナ人も・・・
企業経営者も、派遣労働者も・・・
お互いが共生する社会を考えるしかないのです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年01月07日
コンテンツと利益
玉村豊男 著 「里山ビジネス」から
『
コンテンツが先か、
利益の計算が先か、
という問題は、
どちらが先かを考えずに済むときに
もっとも成功の確率が
高いのかもしれません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2009年01月06日
強く印象づけるには
2009年01月05日
プロフィットとリスク
ファーストリテイリング会長兼社長 柳井正さんの言葉から
『
プロフィット(利潤)とリスクはイコールだ。
日本人の最大の欠点は
安心、安全、安定志向。
当然、プロフィットは生まれない
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年12月27日
共生を目指していく
栗山民也 著 「演出家の仕事」から
『
絶対的に異質なものがぶつかり合うなかで、
そこからお互いの差異と共通点を認め合いながら、
一本のボーダーに共生を目指していくべきなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年12月25日
勝手な思い込みで発信情報を減らさないこと
武永昭光 著 「伊勢丹に学ぶ「売れる!」店作り」から
『
「これくらいは知っているだろう」
と勝手に思い込み、
情報を発信しないのも問題です。
発信する情報が少なければ、
当然受信される情報も少なくなるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年12月20日
2009年のキーワード:「Hibernation」
栗山民也 著 「演出家の仕事」から
『
新しい情報にいち早く飛びつき、
すぐまた何の疑いも抱かず
次の新しい情報へと群がる。
それに遅れたものは社会から弾かれて、
一人ひとり疎外されていく。
』
社会が不安定になるときは、性急に情報を求め過ぎないことです。来年は、じっくりと沈思黙考し、今までの考え方を見直すのにいい時期なのです。
早く動くとロスが多くなり、好機が巡って来た時には、リソース不足になっているかもしれません。「Hibernation」も来年のキーワードなのです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年12月19日
情報を削ぎ落とす
2008年12月18日
真実を見せるには
2008年12月17日
洗練さは欲張らないこと
武永昭光 著 「伊勢丹に学ぶ「売れる!」店作り」から
『
感性面で重要なことは欲張らないこと
発信する情報、
見てもらいたい商品の量を欲張らないことです。
それが洗練さ、センスのよさにつながります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年12月13日
せりふは人間の言葉
2008年12月12日
決め方を明確にしておく
武永昭光 著 「伊勢丹に学ぶ「売れる!」店作り」から
『
感性には絶対はありませんから、
多数決でいくのか、
責任者が決めるのかを
明確にしておくことです。
決め方さえ明確にしておけば、
決めた後に不満が残ることもありません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年12月10日
言葉は多面的
栗山民也 著 「演出家の仕事」から
『
他者の言葉があることで、
自分の言葉が生まれ、
自分の言葉によって、
目の前の「あなた」の
言葉が導き出されるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年12月07日
リスクとコミュニケーション
佐々木良一 著 「ITリスクの考え方」から
『
個人情報が他人に知られるリスクを犯しても、
有意義なことがあると思えば、
いろいろなコミュニケーションを楽しみ
貴重な情報を得た方がよいと思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年12月06日
自分の考えを持って命令と向き合う
【スタートレック・ネクストジェネレーション】ピカード艦長の言葉:
『
「私は命令に従っただけです」という言葉で、
どれほど多くの過ちが正当化されてきたと思う。
自分の考えを持たず、ただ言われた通り
命令に従うだけの士官なら連邦にはいらない。
』
制度を無視し、年金記録を書き換えていたという社会保険庁の職員は、一体何なんでしょうね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年12月05日
学校という場
菅野仁 著 「友だち幻想」から
『
学校と言うのは、
あえて単純化していえば
個性的な子どもを育てる場ではありません。
普通の社会人になるための
基礎力を育てる場です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年12月03日
為政者に欠くことのできない資質
塩野七生 著「ローマ人の物語XV ローマ世界の終焉」から
『
人材を登用するだけでなく
その人材を活用する能力が
為政者には欠くことは許されない資質であることは、
人種にも民族にも関係のない、
個々人の器量である
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年12月02日
公共空間に必要なもの
栗山民也 著 「演出家の仕事」から
『
ヨーロッパでは、
生活の公共空間として絶対に必要なものを、
病院、学校、劇場
の三つの基本と考えていると聞きました。
三つとも人間の生命を扱う場所だからです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年11月28日
テロというものは
【スタートレック・ネクストジェネレーション】ピカード艦長の言葉:
『
戦争やテロというものは、
しばしば、正義という名の下で行われる
』
インド ムンバイの同時テロで、100人以上の方が亡くなられました。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年11月26日
現代の大国のファシズム
栗山民也 著 「演出家の仕事」から
『
アメリカを中心とした大国が
世界の隅々までを
勝手に自国の色に
染めようとしている構図が、
はっきりと示されています。
』
オバマ政権で、元米財務長官サマーズ氏が復帰するそうです。彼は日本に市場開放を強要し、その後の日本に歪な経済状況をもたらした人です。日本は、米国責の経済混乱修復に只で利用されないよう、戦略を練っておく必要があります。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年11月25日
つまらないことが歴史を動かす
塩野七生 著「ローマ人の物語XV ローマ世界の終焉」から
『
ときに歴史は、
微苦笑するしかないつまらないことによって動く
』
麻生首相の失言癖が、日本に新しい政治を生み出すかもしれません。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年11月21日
大人になることの課題
菅野仁 著 「友だち幻想」から
『
「ルール関係」と
「フィーリング共有関係」
を区別して考え、
使い分けができるようになること。
これが、「大人になる」ということにとっての、
一つの大切な課題だと思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年11月17日
合わない人と並存する
2008年11月14日
巨大な権力が国民の心を強制しようとしている
栗山民也 著 「演出家の仕事」から
『
あったことをなかったかのように、
かつての歴史を塗り替えようとする
人たちがいます。
今、問われているのは、
国家という巨大な権力が、
国民一人ひとりの心の領域までを定義し、
強制できるのかということでしょう。
』
東京大空襲から63年が経ちました。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年11月13日
ルール(政策)を決めるときに重要なこと
菅野仁 著 「友だち幻想」から
『
ルールを決めるときは、
どうしても最小限これだけは
必要というものに絞り込むこと、
「ルールのミニマム性」というものを
絶えず意識することが重要です。
』
おバカな政府(自民党&公明党)が、またやってくれました。定額給付金という名の税金の無駄使いを考え、所得制限などの雑用は市町村任せにするつもりです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年11月11日
既に一般化は崩壊している
辻井 喬、上野千鶴子 著 「ポスト消費社会のゆくえ」から
『
コミュニケーション媒体それ自体の
セグメンテーションが起きてきて、
偶発性の高いノイズはシャットアウトする。
つまり、人は自分が聞きたい情報しか
聞かなくなっているのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年11月09日
自己否定できる経営でないとダメ
2008年11月06日
人との関係を作る力
菅野仁 著 「友だち幻想」から
『
ちょっとでも違うと、
「あ、この人違う」となって、
関係を保つ努力を放棄していては、
人と関係を作る力もつきません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年11月05日
消費者の意識がマーケットを変える
黒川清 著 「イノベーション思考法」から
『
マーケットによっては、
消費者の意識は急激に変わります。
・・・
それを意識することが大事なのです。
その変化を察知して
先手を打つことが大事なのです。
』
乗用車の販売台数が、昭和43年の台数まで落ち込んだそうです。マイカー願望は既に過去のものとなっているのに、車一辺倒だった自動車製造業がおかしかったのだと思います。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年11月03日
歴史を消し去る罪
栗山民也 著 「演出家の仕事」から
『
なぜ、そのような歴史の罪を、
いとも簡単に忘れてしまったり、
消してしまおうとする人がいるのでしょうか。
忘れるどころか、
忘れたふりをして、
いつのまにか消し去ろうとしている。
』
太平洋戦争を、「侵略はぬれぎぬ」と主張する航空自衛隊トップ 田母神俊雄 氏。戦争を起こした罪よりも、戦争を忘れてしまう罪の方が大きいのです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年11月02日
日本の子どもたちの笑顔
アートディレクター 水谷孝次 さんの言葉から
『
途上国に比べて
恵まれているはずの
日本の子どもたちの笑顔が、
世界中で一番撮りづらい。
これって、どういうことなんだろうと、
時々考えさせられるんです。
』
それは、
栗山民也 著 「演出家の仕事」から
『
物が溢れているのに、
語り合える言葉は失われ、
どこにも溢れてなどいない。
』
なのだと思います。私たちは対話する言葉を失いつつあるのです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月28日
智恵を絞り速やかに実行する
黒川清 著 「イノベーション思考法」から
『
企業が考えるべきことは、
市場を理解して次の戦略を練り、
それを速やかに実行に移すことです。
あるいは次の実行のために
失敗を共有し、
負の経験を活かしながら、
智恵を絞って前に進むことです。
』
これから、みんなバブル後株価最安値を切り抜けなければなりません。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月25日
今、必要だと思うことを掴む
栗山民也 著 「演出家の仕事」から
『
今、必要だと思うことを、
曖昧なカタチのまま置き去りにすることなく、
見捨てず、その瞬間自分の手のなかに
掴もうと必死になればいいのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月24日
今の時代に大切なこと
栗山民也 著 「演出家の仕事」から
『
演劇に限らず、今の時代に、一番大切なことは、
「聞くこと」のように思えてなりません。
』
麻生首相の親族会社が、大量の欠陥パネル材料を納品していたそうです。顧客から沢山のクレームが来ていたにも拘らず、九州新幹線用に出荷していました。
顧客の声を聞かない会社。麻生総理は首相になる前、その会社の社長を務めていました。どうりで国民の声が聞こえないはずです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月21日
日本語で思想を伝達すべき
辻井 喬、上野千鶴子 著 「ポスト消費社会のゆくえ」から
『
文学者がここで頑張らないと、
ナショナリズムも伝統論も今日的なテーマも、
すべてどこかへ持っていかれてしまいますよ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月19日
裁判員制度=ドラキュラ制度
西野喜一 著 「裁判員制度の正体」から
『
裁判員の負担といっても
大したことはないだろうなどと誤解していて、
大きな事件に取り込まれると、
膨大な時間と労力が吸い取られて
人生が狂ってしまう恐れがあるのです。
』
裁判員に駆り出されている間は、会社は給与を払う義務はなく、有給休暇を使わなければ欠勤扱いです!
重大事件だから殆どは2~3日で終わるはずもなく、有給休暇を使い切れば査定にも響きます。まして、正社員でなければ、解雇だって有りえます。
日当一万円貰ったって、人生もお金も吸い取られて棺おけ行きですよ。裁判所が手を差し出して、「もっと、あなたの人生をくれ」と、迫ってきています。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月15日
アンノンがファッションに変えた
斎藤美奈子 著 「モダンガール論」から
『
アンノンが「女性解放」に果たした役割は、
おそらく電気洗濯機と同じくらい大きい。
なぜってそれは、すべてを
「趣味=ファッション」にかえてしまったからである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月14日
賢者は歴史に学ぶ
2008年10月13日
並列性の重視
菅野仁 著 「友だち幻想」から
『
現代のさまざまな人間関係の問題を
解消するための方法として、
「並列性の重視」ということをきちんと
主張すべき段階にきている
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月12日
政府はまともな法律一つ作られへんの?
西野喜一 著 「裁判員制度の正体」から
『
国民を裁判員に動員するということは、
その行為を必ず絶対的な悪として処罰せよ、
また処罰の範囲は必ずこの範囲でなければならない、
皆おなじように考えよ、
という一方的な制約を課しているわけです。
』
小泉政権で誕生した「裁判員制度」が2009/5/21から実施されます。経済危機、物価高を切り抜けるため、みんなギリギリの生活をしているのに、くじ引きで「裁判員」に選ばれたら自分の生活をほっぽり出して裁判所へ行かなければなりません。
行かない人には最大30万円の制裁が待っています。
こんなことしたら有権者の生活が大混乱するのに、自民党得意の「そんなの関係ネェ」で知らん振り。後期高齢者医療制度の大混乱、年金制度の制度破綻。
まともな法律一つ作れないんですね、今の政府(自民党)は。
この穀潰しの政治家集団は、演繹して物事を考えるという事ができなんでしょうか。この法律を作ったら、「こうなり」、「その後こう成る」、「だから、こうすべきなんだ」という風にね。そして、それを国民にちゃんと説明し、理解させる努力をする義務と責任があるはずです。→【説明責任】
なのに、小泉政権は闇討ちのように「裁判員制度」を作ってしまいました。法律の矛盾と不利益のしわ寄せは、いつも健全な国民に押し付けられています。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月09日
自分の思考と価値観
2008年10月08日
言葉は知的ツール
菅野仁 著 「友だち幻想」から
『
言葉というのは、
自分が関わっていく世界に対して
いわば網をかけて、
その世界から自分たちなりの
「意味」をすくいとることによって、
自分たちの情緒や論理を築き上げていく
知的ツールなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月07日
楽しい気分に浸りたいから
斎藤美奈子 著 「モダンガール論」から
『
なぜ私たちは、ときに「ケッ」と思いながらも
女性誌を読むのか。
なぜしちめんどくさい論壇誌を読まないのか。
楽しい気分に浸りたいからに決まっている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月04日
問題は先取りされていた
斎藤美奈子 著 「モダンガール論」から
『
職場の待遇差別から主婦の自立論まで、
現代の私たちが直面しているような問題は、
戦前に、
ほとんどすべて先取りされていたのである。
』
”年金の報酬月額の改ざん”、”汚染米の横流し”、無能な政府は、全ての問題を ”先送り” していたのです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月02日
より大きな幸福を味わうためには
菅野仁 著 「友だち幻想」から
『
自分一人だけで幸せを得るよりも、
身近な人たちを中心に
できれば多くの人と
幸せを感じることができれば、
その方が人はより大きな幸福を
味わえたことになるのではないでしょうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年10月01日
苦境を突破する経営者
辻井 喬、上野千鶴子 著 「ポスト消費社会のゆくえ」から
『
まあ、一遍ラクをしてしまうと、
自らリスクを背負って賭けをして、
その苦境を突破するという
タイプの経営者はなかなか生まれないでしょう。
』
バブル期に育てられた無能な経営者が色々な不祥事を起こしていましたが、米国発の金融危機がこんな経営者を一掃し、新しい経営者が育つ絶好の機会をもたらすでしょう。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月30日
行き過ぎは無い方がまし
辻井 喬、上野千鶴子 著 「ポスト消費社会のゆくえ」から
『
ユートピア思想とか
集合的な理想主義は
行き過ぎると、
「ないよりはあるほうがいい」、
どころか、
「ないほうがあるよりもっとまし」
だっていう事態を、必要以上に作り出す。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月28日
既存のメディアに成り代われる個人
ブラジルの世界的ミュージシャン ジルベルト・ジル さんの言葉から
『
ブロードバンド時代とは、
個人が新聞やテレビなどの
既存のメディアに成り代われること。
一人ひとりがジャーナリストで、編集者でもある。
民主主義の観点からも重要だ。
サイバースペースは伸縮自在だしね
』
既存メディアの前に立てる人物が、いつもスカタンばかり言っている。
(失言のため任命から数日で辞任する情けない中山国交相)
だから、個人がもっと多くを語ってやりましょうよ、ブログで。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月23日
戦争にハマってしまわないように
斎藤美奈子 著 「モダンガール論」から
『
戦争は変化を求めていた人々の気持ちを
パッと明るくした。
保守的で頑迷な昔風の女性ではなく、
前向きで活発な近代的センスをもった女性ほど、
戦争にはハマりやすいのですよ、
みなさん。
』
かつて婦人参政権運動をリードした市川房枝でも、最初は戦争に賛成していたのです。
「マンネリだ」、「退屈だ」、「不満だ」と、単なる愚痴を言っている人の心の隙間に、悪魔は忍び込んでくるものなのです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月22日
貧富格差のタイムスリップ
斎藤美奈子 著 「モダンガール論」から
『
断髪洋装のモダンガールと
「女工哀史」が、
まったく同時代の話だなんて、
いわれなければ気がつかないところである。
』
貧富格差が拡大する日本では、階級による社会の分断が明治時代に近づきつつあります。
一旦分断されてしまえば、各階級間での利害関係が一致しなくなり、これを権力者に利用されれば、益々社会は歪(いびつ)なものに変化して行きます。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月19日
高次元のイノベーションに行くには
黒川清 著 「イノベーション思考法」から
『
いまの日本では、
従来の自分たちの価値観で見ると、
一番権威が高いと思っているところ
にこそメスを入れる、
あるいはそのような
社会的地位の人こそが
思い切った行動を起こさないと
いけないのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月18日
明確な意思表現ができない日本人
2008年09月17日
ブランディングは豊かさを感じてもらうこと
黒川清 著 「イノベーション思考法」から
『
単なるものづくりではなく、
どうしたら顧客が豊かさを感じるか、
お金を使ってくれるかを
つねに配慮しています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月15日
失敗を共有して活かす
黒川清 著 「イノベーション思考法」から
『
人間には必ず失敗があります。
この失敗を共有し、
活かすことが大事で、
それがイノベーションを生む
大事なきっかけの一つになります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月14日
日本は打って出るべき
黒川清 著 「イノベーション思考法」から
『
日本はもはや
閉じこもることはできません。
それは国の自殺です。
旧世代の「おじさん」たちが
昔を懐かしんでいる余裕など
ないのです。
』
4人のおじさんと一人のおばさんが、意味の無い立会い演説会を「大阪なんば」で行いました。小泉改革など旧時代のことをどうのこうのという話はもういいです。
「何を変えるか」、「何に変えるか」、「如何に変えるか」
を、的確に述べてくれるだけでいいのですが・・・
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月11日
新思想
2008年09月10日
地方には多様性がある
辻井 喬、上野千鶴子 著 「ポスト消費社会のゆくえ」から
『
日本は画一的だとよく言われますが、
そう信じているのは東京の人だけじゃないでしょうか。
地方は本当に多様性があります。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月09日
企業は目標に向かって邁進するべき
黒川清 著 「イノベーション思考法」から
『
目標達成に向かって邁進するのが
企業のもっとも大事な使命であり、
それを実行せずに弁解だけしていても
仕方がないのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月06日
彼らに相応しい最後の言葉: ワールド・エンド
辻井 喬、上野千鶴子 著 「ポスト消費社会のゆくえ」から
『
「愛国心は卑怯者の最後の隠れ家」
という言葉もありますが、
たいへん危険な政治家が歴史も知らずに
「最後のレジームの改革」などと言い出したあげく、
再起不能なかたちで失脚してくれたことは
たいへん嬉しゅうございます。
』
そうだ、安倍さんが ”やらせタウンミーティング” で「教育基本法」を改正し、「日本国憲法」まで改悪しようとしていたことがありましたっけ・・・ その後の福田さんも、「やーめた」と政権を投げ出しました。
(ミセス・プリチャードは、「私には義務と責任がある」と言って首相を投げ出しませんでしたが、どこかの国には、「自分と永田町がある」というように投げ出す首相もいるのですね)
![]() 奥さまは首相~ミセス・プリチャードの挑戦
奥さまは首相~ミセス・プリチャードの挑戦
そして、日本のリーダーを2回も投げ出した党からは、次は俺だ私だと4人の総裁立候補者が出て来ています。
”自民丸”の船上で、「次の船長は俺だ」と4人が言い争っている間に、船は大きな渦の中に飲み込まれて行くのでありました・・・
★ワールド・エンド★
これが彼らに相応しい最後の言葉でしょう!
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月05日
いいビジネスという思い込み
2008年09月04日
保証がないからベンチャー
2008年09月02日
自己否定の論理
辻井 喬、上野千鶴子 著 「ポスト消費社会のゆくえ」から
『
経営者にとっては、常に自己が
否定されるような環境をつくることが、
企業の自己革新能力を維持する上で
必要不可欠な作業になってきている
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年09月01日
大人は子供に明確な目標を持たせてやること
林 壮一 著 「アメリカ下層教育現場」から
『
10代の子供なら、
いくらでもやり直しはきく筈なのだ。
ちょっとしたきっかけで、
やる気を起こすことがある。
大人は彼らに夢を与え、
明確な目標を
持たせてやることが重要だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年08月29日
ブランドが異なるものに変える
黒川清 著 「イノベーション思考法」から
『
同じものを売っても
ブランドによって
結果が全然異なってくる。
それがなぜかということを、
もっと考えなければ
ならないと思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年08月13日
聞くこともスキルがいる
伊藤 進 著 「<聞く力>を鍛える」から
『
複雑なプロセスからなることは
すべてそうであるが、
聞くことを適切に実行するには、
そのためのスキルが必要だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年08月12日
コミュニケーションは繋がること
伊藤 進 著 「<聞く力>を鍛える」から
『
コミュニケーションは、
他の人々、あるいは広く、
外の世界とさまざまなやり取りをする行為だが、
それはつまりは他の人々・世界と
つながる行為である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年08月07日
日本人はマイノリティーと呼ばれる
林 壮一 著 「アメリカ下層教育現場」から
『
アメリカ社会において
黄色い肌の日本人はマイノリティーと呼ばれ、
差別の対象となる。
日本人のなかには自らをホワイトのように
捉えている者も少なくないが、
我々は決して白人と同レベルに扱われない。
目に見えない大きな壁が存在するのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年08月06日
アメリカでの学歴
林 壮一 著 「アメリカ下層教育現場」から
『
残念ながら高校卒業の学歴では、
よほどの例外が無い限り
ブルーカラーやアルバイトのような仕事にしか就けない。
アメリカ合衆国とは、そういう国である。
』
シリコンバレーだけがアメリカじゃないということです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年08月05日
アメリカ礼賛は悪い癖
高橋克徳+河合太介+永田稔+渡部幹 著 「不機嫌な職場」から
『
ちょっと自信をなくすと、
すぐにアメリカ式がよいと礼賛するのは、
日本人の悪い癖である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年08月01日
コミュニケーションの邪魔者
伊藤 進 著 「<聞く力>を鍛える」から
『
コミュニケーションにおいては、
「一つの正解幻想」は禁物である。
同様に、「マニュアル依存」も禁物。
この二つは、
人間らしい心の通うコミュニケーションにとっては、
邪魔者以外の何者でもない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年07月25日
暮らしの邪魔者を自覚する
パトリス・ジュリアン 著 「ゆたかに生きる」から
『
今暮らしている環境のなかで、
あなたから場所を奪い、
エネルギーを浪費させているものを
すべて自覚することなんだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年07月24日
心配りの質が重要
パトリス・ジュリアン 著 「ゆたかに生きる」から
『
なんだって同じと思うんだ。
人生において重要なのは、
注意する、心を配る、
その質なんじゃないかって。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年07月23日
直観重視の誤りを防ぐには
2008年07月19日
理想と現実の中点主義
2008年07月16日
誤ったインテリジェンスの生産
北岡 元 著 「仕事に役立つインテリジェンス」から
『
因果関係やパターンがないのに、
「ある」と結論することは、
現実を実態と異なって認識することになり、
誤ったインテリジェンスが生産されてしまう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年07月10日
一人の人間の頭脳ではダメ
伊藤 進 著 「<聞く力>を鍛える」から
『
しょせん、一人の人間の頭脳で
なしうることには限りがある。
世の中は変化する。
一個の頭脳だけでは、
その変化を察知し、
変化に合わせて対応していくのは
きわめて難しい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年07月05日
子どもには食事のスタイルを習慣とさせておく
パトリス・ジュリアン 著 「ゆたかに生きる」から
『
子どもには最初から、
最低限のスタイルを持った食事というものを
習慣として経験させておく。
そうすればその子が大人になったときに、
きっと誰よりもずっと感受性豊かな人間に育つはずだって。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年07月02日
「スタイル」がものすごく大切なことを子供たちへ
パトリス・ジュリアン 著 「ゆたかに生きる」から
『
子供たちには、
「スタイル」がものすごく大切だってことを
ごく幼い時期から教えて、
感性を育ててあげるべきなんじゃないかな。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年06月30日
情報ではなく事実を見ることが大切
広中平祐 著 「可変思考」から
『
情報を、あたかもそのまま
事実であるかのように受け取ることは、
実に危険なことなのだ。
』
【ほぼ日手帳カバー印刷 Gallery:奈良公園 その1】

※ブラウザのキャッシュをクリアしないと、新しいデータが表示されない場合があります。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年06月25日
商品による消費者の教育
2008年06月19日
方針が結果をもたらしたのではない
北岡 元 著 「仕事に役立つインテリジェンス」から
『
当初の方針はもろくも崩れ去って、
その場しのぎの状況が続き、
気がついたらなんとなく
収まるところに収まっていた・・・
というのはよくあるパターンだ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年06月13日
実行力
2008年06月10日
現実の変化で予測も変化する
2008年05月28日
クリエイティブへは生活を楽しむことから
パトリス・ジュリアン 著 「生活はアート」から
『
生活を楽しみたいと思っている人には
クリエイティブの才能があると思います。
お金はクリエーションの源、
そしてエネルギーの一部だから、
素敵な経験には惜しみなく使ってしまいたい。
』
- Permalink
- by
- at 00:31
2008年05月23日
直感は諸刃
2008年05月19日
ポジティブ
2008年05月12日
日々の生活がエンジョイできると
パトリス・ジュリアン 著 「生活はアート」から
『
日々の生活を素敵にエンジョイしているからこそ、
旅行したときに多くのものをインプットできて、
プラス・アルファとなるのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年05月08日
物事が進まないことも楽しむ
2008年04月30日
美にするには美
パトリス・ジュリアン 著 「生活はアート」から
『
美しく収納するためには、
美しいものだけを厳選すればよいのです。
』
こんな部屋になればいいと思える部屋の写真集を見つけました。
書籍 「ベルリン大人の部屋」
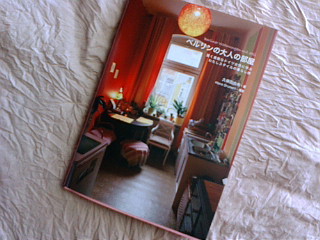
ただ、日本の四季や夏の高温多湿を考えると、こんな部屋は日本では不向きなような気がします。完全空調のお高いマンションなら別ですが。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年04月26日
スタイルはアート
パトリス・ジュリアン 著 「生活はアート」から
『
フランス語で生活スタイルと言うときは
「アール・ド・ヴィーヴル」といって、
「生活のアート」と表現します。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年04月22日
類似品が新鮮さを破壊する
パトリス・ジュリアン 著 「生活はアート」から
『
似たような(でもポリシーのない)商品の出現によって、
元のスタイルまでが新鮮さを失ってしまうのは
残念なことです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年04月21日
種から上位概念まで登って行ける話しは楽しい
2008年04月15日
マニュアルでは解決できないこと
畑村洋太郎 著 「わかる技術」から
『
必要なのは、
そのシステムの全体像を
きちんと考えたうえで、
現に起こっている問題と関連して
どこで何が起こっているかを
きちんと把握することです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年04月12日
流行なんかどうでもいい
2008年04月10日
時間が普通を変える
2008年04月09日
無いときは自分で作り出す
2008年04月08日
できないことはできる
パトリス・ジュリアン 著 「生活はアート」から
『
「できない」と言われていることで、
本当はできることは多いのです。
自分の気持ち次第で
なんでも変えることが出来るし、
なんでもできる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年03月31日
料理のオートクチュール
神戸北野ホテル総支配人・総料理長 山口 浩 さんの言葉から
『
料理の魅力を最大限に引き出すのは、
わくわくさせる雰囲気と、
自信を持って接する従業員の姿勢だ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年03月28日
形式論は悪用される
2008年03月26日
グローバル・センス
パトリス・ジュリアン 著 「生活はアート」から
『
グローバル・センスはもっているかいないかで、
毎日おいしいものが食べられるかどうか、
人生を楽しめるかどうかが決まってしまう、
そんな感性です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年03月23日
「リ」は事を起こすこと
パトリス・ジュリアン 著 「生活はアート」から
『
企業のリストラしかり、
リフォームしかり、
リサイクルしかり、
「リ」のつくことは
事なかれ主義からは生まれません。
なにかを「もっと!」よくしたいと
思うところからの発想です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年03月22日
喜んでする気持ちにさせること
塩野七生 著「ローマ人の物語XV ローマ世界の終焉」から
『
政治でも軍事でも行政でも、
人間世界の多くのことは
「苦」を伴わないでは済まない。
ゆえにそれを国民に求めなければならない
為政者に必要な資質は、
「苦」を「楽」と言いくるめることではなく、
「苦」は苦でも、
喜んでそれをする気持ちにさせることである。
』
「1年で消えた年金を解決する」などと大嘘をついた自民党は、永田町の住民でなくなる日、【ワールドエンド】が近づいているのですが、そんなことは気にならないようで、道路特定財源の確保に奔走しています。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年03月20日
節約ではなく得を得る
2008年03月18日
エネルギーが満ちると
パトリス・ジュリアン 著 「生活はアート」から
『
こんなこともしてみたい、
あんなこともしてみたい、
そう思うときにはエネルギーが
満ち満ちているのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年03月15日
美しさはハーモニー
パトリス・ジュリアン 著 「生活はアート」から
『
美しさはハーモニーだと思います。
美しいものって必ず周囲とのバランスがとれていて、
安心できて前向きな気持ちになれる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年03月11日
美しいモデル
リサ・ランドール 著 「ワープする宇宙 5次元時空の謎を解く」から
『
モデルはショーの舞台においても
物理学においても、
想像力豊かな作品を見にまとい、
さまざまな姿になって現れる。
そして、美しいモデルは
満場の注目を集める。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年03月08日
意地悪さのある英文学
新井潤美 著 「不機嫌なメアリー・ポピンズ」から
『
イギリスから「階級意識」がなくなることはないだろう。
だからこそ、この国の文学には独特の「意地悪さ」が
あり続けるのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年03月06日
強制は思考停止を生む
2008年03月03日
ロマンティックを認識すること
新井潤美 著 「不機嫌なメアリー・ポピンズ」から
『
ロマンティックな景色と呼ばれるものを
認識する力は本能的なものではない。
それどころか、これは、ゆっくり、
そしてだんだんと培われて、
はじめて得られるものである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年03月01日
深読みされていくもの
2008年02月28日
multicultural
2008年02月26日
満足感と尊厳を得る
新井潤美 著 「不機嫌なメアリー・ポピンズ」から
『
人生で犯した過ちを認めるというのは容易なことではないが、
そうすることによって満足感と尊厳を得ることはできる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年02月25日
尊敬されなくなる人
畑村洋太郎 著 「わかる技術」から
『
答えをたくさん知っていて、
問題解決が速いだけという人はいまの時代、
どんどん尊敬されなくなっています。
なぜなら現代は、こうすればよい、
というはっきりした答えが見つからない時代だからです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年02月24日
凡人の性向
新井潤美 著 「不機嫌なメアリー・ポピンズ」から
『
何かうまくいかないときには、
誰か他人のせいにして、
激しく非難するというのは、
世界中の凡人の自然な性向である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年02月23日
もとの世界から抜け出す
2008年02月20日
taveller の方が格が上
新井潤美 著 「不機嫌なメアリー・ポピンズ」から
『
「旅をする人」 traveller と
「観光客」 tourist という言葉が、
はっきりと使い分けられている。
』
Time traveller はあっても、Time tourist という言葉は聞きませんね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年02月17日
ハーマイオニーは手本
新井潤美 著 「不機嫌なメアリー・ポピンズ」から
『
「努力すれば報われる」手本となっているのは
むしろハーマイオニーであって、
作者のロウリングは、自分が学校に行っていたころは、
ハーマイオニーのような生徒であったと言っている
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年02月16日
イギリスは発音で階級が決まる
2008年02月14日
優しく見守る
2008年02月13日
お互いが歩み寄ること
2008年02月09日
ヨーロッパ人の笑いには意味がある
デュラン・けい子 著 「一度も植民地になったことがない日本」から
『
ヨーロッパの人々の笑いには
意味があることを忘れてはいけない。
ヨーロッパの人の笑顔に過大評価は禁物です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年02月08日
子どもは社会が育てるもの
デュラン・けい子 著 「一度も植民地になったことがない日本」から
『
ヨーロッパでは「今のしつけが大切」という、
大人のママの立場に立ってあげなければいけない。
東京在住のイギリス人の友人は言う、
「子どもは社会が育てるもの」なのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年02月07日
嫌な体験が相手を思いやる気持ちを生む
2008年02月05日
すべて言葉にしないと分からない人たち
デュラン・けい子 著 「一度も植民地になったことがない日本」から
『
ヨーロッパの人々の多くは、
すべて言葉にしないとわからないほど
鈍感と言ってもよい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年02月04日
やさしい自然が生むもの
デュラン・けい子 著 「一度も植民地になったことがない日本」から
『
日本の自然はヨーロッパや中東に比べて、
とてもやさしい。
やさしい自然からは、
やさしく思いやりのある神様が生まれるのかもしれない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年02月02日
感性を磨けば
2008年01月31日
人間と話術を磨くこと
2008年01月30日
子どもに伝わること
一龍斎貞水 著 「心を揺さぶる語り方」から
『
一生懸命に生きている大人が、
真剣に話をして、
子どもたちに何かを伝えようとする。
それを子どもたちは理解すると思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年01月27日
価値観の違いが面白い
2008年01月19日
心の色合い
2008年01月18日
言葉の情感が心を作る
2008年01月17日
心を大事にしなくなると
2008年01月16日
本当の共感を生む
2008年01月12日
リズムを良くすることも大事
2008年01月11日
問答無用で心を打つ
一龍斎貞水 著 「心を揺さぶる語り方」から
『
問答無用で人の心を打ってくる話というものもある。
それは、その人が心の底から思っている強い本音を
しゃべっているときです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年01月10日
場の「空気」は経験がないと読めない
一龍斎貞水 著 「心を揺さぶる語り方」から
『
どんなに思いやりがあって、
普段から相手の身になって考えている人でも、
経験が少なければ、
場の「空気」を読みながら話すことは、
できるようになりません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年01月09日
思いやりは日ごろの行いから
一龍斎貞水 著 「心を揺さぶる語り方」から
『
心を込めること、思いやりを持つことを
人前で話すときにだけ発揮しようとしても
できるものじゃありません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2008年01月08日
話を生む原動力
2008年01月05日
相手にどう伝わるかが大切
2008年01月04日
物理学はクリエイティブ
2008年01月03日
読者の心に生じさせる
2008年01月01日
今年はウェブをミラーボールとして使いたい
梅田望夫 著 「ウェブ時代をゆく」から
『
ウェブは、
「志」を持って能動的に対峙したときに、
まったく異なる相貌を私たちに見せるものである。
』
新年あけまして、おめでとうございます。
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年12月29日
目的意識を持った個が必要
梅田望夫 著 「ウェブ時代をゆく」から
『
リアル世界の物理的制約に規定されて
生きざるを得なかった昔に比べて、
制約が取り払われた分、
個の目的意識がより問われる時代に
なったということだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年12月25日
人を褒める能力
2007年12月24日
成功を導くサイクル
「フォーシーズンズ ホテル アンド リゾート」 クリストファー・ノートン氏の言葉から
『
我々にはゴールデン・ルールが存在します。
それは、人を大切にするということです。
ゲストを大切にし、
従業員を大切にし、
オーナーや関係者すべてを大切にする。
これが、成功を導くサイクルなのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年12月08日
それに世間は
2007年12月07日
マイナス思考で乗り切る
2007年12月05日
現実を変えるために
2007年12月04日
流れに乗って押す
2007年12月01日
自分のスタイルの正しさ
2007年11月30日
パイオニアワーク
2007年11月29日
勢いだけではリスクが大きい
2007年11月28日
威勢と綿密
2007年11月26日
何かを得るためには
石井政之 編著 「文筆生活の現場」から
『
何かを得るためには
何かを捨てなければならないのです。
逆に、何かを捨てれば、
必ず何かを得ます。
神様は公平です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年11月25日
仕込み量は多いほどいい
石井政之 編著 「文筆生活の現場」から
『
少ない手持ち量でやっている人の
いちばんの問題点は、
パースペクティブが狭くなること。
いま世間で言われている問題を、
いま世間で言われているような
視点から論じているだけ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年11月22日
名は当人へ
佐々木健一 著 「タイトルの魔力」から
『
名を汚すことは、
なまえそのものよりも
当の本人の受ける恥辱であり、
名を讃えることは、
当人への称賛である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年11月21日
理論の外から見る
2007年11月16日
ネーミングにおいて求められるもの
佐々木健一 著 「タイトルの魔力」から
『
ネーミングにおいて求められているのは、
「名は体をあらわす」ことであるよりも、
まずこの「名前としてのよさ」である
ように思われる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年11月15日
対象を聖化させる力
2007年11月13日
日本では図書館の可能性が埋もれている
菅谷明子 著 「未来をつくる図書館」から
『
日本の公共図書館は市民に広く利用され、
支持者も決して少なくないが、
その一方で、
図書館が本来持っている可能性を
ほとんど生かし切れていない
のではないだろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年11月12日
原因は結果に勝る
佐々木健一 著 「タイトルの魔力」から
『
原因は結果に勝る存在である。
なぜなら、
結果は原因に依存しているが、
原因は結果がなくとも存在しうるからである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年11月11日
デジタルではない学びのコミュニティ
菅谷明子 著 「未来をつくる図書館」から
『
空間をたやすく越えられる
デジタル時代においても、
図書館はあえて人と人とを
物理的な空間に「集める」ことによって、
学びのコミュニティという新しい価値を
作り出そうとしているのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年11月10日
創造には物理的なスペースも必要
2007年11月09日
優秀さは固有名に宿る
佐々木健一 著 「タイトルの魔力」から
『
いやしくも類似商品とは
異なる優秀さを誇るのであれば、
その商品は独自の名前、
つまり固有名を
もたなくてはならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年11月08日
市民社会の医療のあり方
菅谷明子 著 「未来をつくる図書館」から
『
市民社会の医療のあり方の選択肢のひとつとして、
誰もがアクセスできる信頼性の高い医療情報の整備が
日本でも必要になるのではないだろうか。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年11月07日
市民に理解されないと
菅谷明子 著 「未来をつくる図書館」から
『
どんなに素晴らしいことをいくら行っても、
それが市民に理解されるように伝わり、
さらなる行動を喚起するものでなければ
決して十分とは言えない。
』
民主党が大連立を考えてどうする! もし、米国の民主党と共和党が大連立をすれば、何でもできてしまいます。
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年11月04日
箱物に文化を入れよ
ニューヨーク公共図書館 広報担当 オヤマ氏の言葉から
『
日本企業は、
一般的に社会貢献の意識が希薄で、
なかなか協力が得られませんでした。
』
文化の日と大阪市長選挙の告示を見て考えました。
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年11月03日
自由で開かれた空間
2007年11月02日
ものづくりの本質
2007年10月29日
でも、笑えたなら
Disney・PIXAR 映画「モンスターズインク」から
『
そりゃまあ、会社は潰れちゃったし、
仕事なくなちゃったって事で、
・・・
でもさあ、結構笑えただろう、なあ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年10月26日
まず現場を見せてください
藤本隆宏 著 「ものづくり経営学」から
『
「まず本社帳簿を見せてください」
というコンサルタントと、
「まず現場を見せてください」
というコンサルタントの違い
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年10月20日
アメリカはアイデアのオープン製品で勝つ
2007年10月16日
先憂後楽
2007年10月13日
ええように生きる
2007年10月09日
コミュニケーションを深く上手にするには
斎藤 孝 著「子どもに伝えたい<三つの力>」から
『
自分の中に他者を住まわせる。
これが、コミュニケーションと自己形成の基礎となる。
コミュニケーションが深く上手にできる人は、
自分の中に多くの他者を住まわせることのできる人だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年10月05日
段取り力は場をデザインすること
斎藤 孝 著「子どもに伝えたい<三つの力>」から
『
場の組み替えは、
ライブの場面で自在に行うことはもちろん必要だが、
基本となるのはクリエイティブな場を
構造として作っていく段取り力である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年10月04日
自分の世界と他者の世界をすり合わせる
斎藤 孝 著「子どもに伝えたい<三つの力>」から
『
自分の内部に閉じ込もるのではなく、
自分の世界と他者の世界をすり合わせ、
そのすり合わせから自己の存在証明(アイデンティティ)
を豊かにしていく対話を作っていく。
こうしたトレーニングは、コミュニケーションの
基本である。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年09月26日
マニュアルを現実から作る能力
2007年09月24日
しっかりとしたコメントをする
斎藤 孝 著「子どもに伝えたい<三つの力>」
『
相手の存在を認める意味が、コメントにはある。
しっかりとしたコメントをすることが、
相手を認めたということを示す。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年09月23日
相手に対してレスポンスする
2007年09月22日
質問を考えながらメモをとる
斎藤 孝 著「子どもに伝えたい<三つの力>」
『
質問を考えながらメモをとる。
こうしたノートのとり方は、一般的ではないが、
やってみると実に効果的だ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年09月21日
不毛の時間をなくすには
2007年09月19日
要約力への意識の低さ
2007年09月18日
相手の世界を知ること
斎藤 孝 著「子どもに伝えたい<三つの力>」から
『
相手があこがれている世界について
まったく無知であれば、話はかみ合わない。
ある程度の知識を持っていることによって、
寄り添うこともできる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年09月15日
制度をずらしていく
斎藤 孝 著「子どもに伝えたい<三つの力>」
『
制度すべてを、個人の自由を阻むものとして
否定する考え方は幼稚だ。
制度をずらしていくことによって、
みんなが活性化する場を作っていく。
こうした技が、
複雑化した現代社会にはとりわけ求められている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年09月12日
あがきで権力の暴走を食い止める
辛 淑玉 著 「悪あがきのすすめ」から
『
あがき続けることで
権力の暴走を食い止められるのだ。
それは、今を生きる人たちの
未来に対する責任としてである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年09月10日
緩急自在に動きをつける
2007年09月09日
言われっぱなしだと
2007年09月08日
有料セミナーの罠
斎藤 孝 著「子どもに伝えたい<三つの力>」
『
一日のセミナーが終わった後、
そこで行われたレッスンやゲームの段取りを、
家に帰って思い出して克明にメモしてみる。
すると、
そうしたものが実に巧みに作られていることに気づくと同時に、
およその底が透けて見えてくる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年09月07日
レジスタンス
辛 淑玉 著 「悪あがきのすすめ」から
『
資本主義社会だからこそ、
買わない、
使わない、
工夫する
というちょとしたことが、じつは、
とても大きなレジスタンスになるのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年09月06日
正面突破は「悪あがき道」ではない
辛 淑玉 著 「悪あがきのすすめ」から
『
「正しいことをストレートにしか言わない」
ような正面突破では、玉砕するに決まっている。
それは、まっとうな「悪あがき」の道ではないのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年09月05日
国家権力に対して泣き寝入りしない方法
2007年09月04日
支えあえる人がいれば大きな力が発揮できる
辛 淑玉 著 「悪あがきのすすめ」から
『
信頼し、支えあえる人が一人でもいれば、
人は大きな力を発揮できる。
これこそ、究極の悪あがきであり、
泣き寝入りしない方法だと私は思う。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年09月02日
以外なところで見つかる
映画 「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」 ルーナ・ラブグッドの言葉から
『
ママが言ってたわ、
無くしたものは、最後には見つかるって。
以外なところで見つかるかもネ。
』
映画の中では、ファッジ魔法大臣とドローレス・アンブリッジ先生が、法律や規則を盾にとって生徒の有らゆる自由を奪い、自分達に跪かせようとします。
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年09月01日
勝ち組だけがいい思いをしたいという:悪人
辛 淑玉 著 「悪あがきのすすめ」から
『
「小さな政府」とか、
「構造改革」とか、
「美しい日本」とか、
強者はつぎつぎと新しい大儀名文を振りかざしている。
しかしその本質は、力こそが善だということ。
つまり、勝ち組だけがいい思いをしたい、ということなのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年08月29日
経験をコメントにすること
斎藤 孝 著「子どもに伝えたい<三つの力>」
『
何かを経験した後に、
何もコメントすることがなかったり、
あるいはまともなコメントをすることが
できなかったりするとすれば、
その経験の質自体が疑われる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年08月27日
ふうっと深呼吸をして周りを見渡す
辛 淑玉 著 「悪あがきのすすめ」から
『
できないと感じることが三回続くと、
なんにもできない気がしてしまう。
そんなとき、
ふうっと深呼吸をして周りを見渡すと、
できることが見えてくる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年08月26日
あがき続けること
辛 淑玉 著 「悪あがきのすすめ」から
『
私にとって、どんなにブザマであろうが、
どんなに微力であろうが、
あがき続けることが生きることなんだと思った。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年08月23日
空間を旅する
2007年08月22日
不都合が生じたら代える
梶井厚志 著 「戦略的思考の技術」から
『
使い慣れてきたサービスでも、
何か不都合が生じたら、
銀行だろうが学校だろうが
他店のサービスに代えるべきなのだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年08月21日
本当にすべき行動
梶井厚志 著 「戦略的思考の技術」から
『
客観的に測りうるということを強調しすぎて、
本当にすべき行動との連動という肝心の
部分を忘れてはならないということだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年08月18日
品質維持のインセンティブ
梶井厚志 著 「戦略的思考の技術」から
『
材料の質が落ちたり味が落ちたりしたときには、
罰則を発動して商品を買わないという行為で
対抗するのでなければ、
店側に品質維持のインセンティブは生まれてこない。
』
食の不祥事を起こした会社の社長が交代したぐらいで、消費者が同じ商品を再び買うという行為をしてしまうと、モラル・ハザードの温床になってしまいます。
だから我が家は、不二家の商品も石屋製菓の商品も今後買うつもりはありません。
- Permalink
- by
- at 00:05
2007年08月15日
目の前にあること
2007年08月12日
ホールドアップの可能性を避ける
2007年08月09日
女性の言うことを戦略的に考えると
梶井厚志 著 「戦略的思考の技術」から
『
少し女性におだてられると単に喜ぶだけにとどまらず
食事代でも洋服代でもなんでも支払ってしまうから、
戦略的思考以前の問題で話しにならない。
なぜ女性がそんなことをいうのかを
戦略的に考えることのできる男性がもう少し多ければ、
世の中はずっと違ったものになっていたはずである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年08月01日
知性や人間性に欠ける人
太田直子 著 「字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ」 から
『
いくら学校でお勉強ができても
仕事で出世できても、
知性や人間性に欠ける幼稚な馬鹿者は
世の中に掃いて捨てるほどいる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月30日
本当のコミュニケーション能力とは
太田直子 著 「字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ」 から
『
コミュニケーション能力とは、
だらだらしゃべりちらすのが
得意かどうかということではない。
深い思考を伴う本物の対話が
できるかどうかということだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月28日
質を保つことを惜しんだとき
太田直子 著 「字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ」 から
『
質を保つために必要な時間(労力)とカネを惜しめば、
世界は低劣で薄っぺらなものになってゆくだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月24日
見る側の心を動かすには
太田直子 著 「字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ」 から
『
くどくど説明せず、
最小限の的確な映像と言葉によって、
その背後にあるものを読み取ってもらい、
総体として見る側の心を動かす。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月22日
目指しているところ、そこに至る考えを明らかにする
JR東日本ステーションリテイリング社長 鎌田由美子 さんの言葉から
『
唯一、語っていいと思うのは、
目指しているところはここで、
自分はこう思うということ。
それを理解して、同じ方を向いて
一緒に働いてくれる部下に恵まれました。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月21日
人間中心主義のおごり
大谷大教授 延塚知道 さんの言葉から
『
私たちは科学の力ですべて思い通りにしてきましたが、
それは人間中心主義のおごりであり、
実は迷いを重ねているにすぎないのです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月17日
それは越境行為
太田直子 著 「字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ」 から
『
実際のせりふでは大したことを言っていないのに、
字幕でボケて笑いをとってどうする。
それは越境行為だろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月15日
正義の戦争なんてない
作家 小田実 さんの言葉から
『
戦争は殺し合いだよ。
正義の戦争なんてないんだよ。
その痛切な反省に基づいて
日本は平和憲法を持った。
その大事さ加減が、
今の人にはわかっていない
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月14日
気色悪い台詞
太田直子 著 「字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ」 から
『
現実の現代日本社会で
「うれしいわ」 「すてきだわ」
と言う女が何人いるだろう。
多少はいるかもしれないが、
私は生まれてこのかた、
そんな気色悪いせりふを
一度も口にしたことはない
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月13日
お菓子は心を満たすもの
和菓子 曙 社長 細野佳代 さんの言葉から
『
(お菓子とは)
お腹ではなく心を満たすもの。
食べなくても困らないけれど、
食べるとほっとしたり、
元気になったり。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月12日
ものごとが成し遂げられると
伊藤智義 著 「スーパーコンピュータを20万円で創る」から
『
ものごとは、
成し遂げられたその瞬間から、
あたかも昔から当たり前のごとく
存在していたように受け取られる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月10日
コンプレックスって
2007年07月09日
好奇心を満たす旅
女優 真矢みき さんの言葉から
『
(90歳になったら世界クルーズに出るのが夢)
各地を停泊しながら、
船の生活を楽しみたい。
好奇心を満たす旅こそ、
人生の醍醐味
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月05日
前の戦争で得たもの、それは憲法だけ
佐高信の「意義あり!」の思想 から
『
山城さん(故 山城三郎)は戦争で得たものは
憲法だけだと口癖のようにいっていました。
どうか、その遺言を受け止めて欲しい
』
ナチのヒットラーだって合法的な選挙で選ばれ、あれだけの悲劇を生みました。
民主主義であれば戦争の悲劇は起こらないと思うのは間違いです。国民がしっかりと権力を監視しないといけません。
はっきり言って、今度の参議院選挙では与党(自民党 & 公明党)に大敗北して欲しいと思っています。憲法を改正し戦争が合法化されれば、少子化の現代では徴兵制が復活するのは避けられません。
自分の子供にも戦場へは行って欲しくないのです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年07月04日
現代社会で求められているもの
2007年07月03日
欠点をあげつらうと、しっぺ返しを喰らう
梅田望夫/茂木健一郎 著 「フューチャリスト宣言」から
『
筋が良いけれどまだ小さい芽に対して、
欠点をあげつらって近視眼的に叩くようなことを言えば、
言っているとき少し利口に見えます。
でもいずれ必ずしっぺ返しを喰らう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年06月29日
未来を創り出したい
梅田望夫/茂木健一郎 著 「フューチャリスト宣言」から
『
未来は明るいはずである、
いろいろなことを努力していけば、
全体として未来は明るい、
そうあってほしい、
そういう未来を創り出したいという意識がある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年06月28日
強者の叫び、だから何んナン
香山リカ 著 「なぜ日本人は劣化したか」から
『
重要なのは、強者サイドにいる人たちが
「これがこれからの世界のスタンダードだよ」
といくら声のトーンを明るくして、
競争主義、成果主義の導入や
憲法改正を叫んだとしても、
いまの日本の状況の中で
自分や家族の安全・安心、
将来にまるきり不安を抱かずにいることは
むずかしい、ということだ。
』
今、年金記録紛失問題では、首相までが「ボーナス返上盆踊り」をしています。
一方、社会保険庁だけでなく年金システムを作ったITゼネコンにも、ちゃんとした相手確認サブシステムを組み込まなかった責任は大いにあります。
IT企業も社会的に問題となりそうなシステムには、受注前にちゃんとしたコンサルをする覚悟が必要で、そのコンサルを無視するようなクライアントからの仕事は受注しないぐらいの気構えがあるべきです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年06月27日
結局教育って
2007年06月26日
ブログが一個があれば良い
2007年06月25日
あいまいさが文化を豊かにする
ビズメディア共同会長 堀淵清治 さんの言葉から
『
日本人特有の「あいまいさ」を批判するのは簡単ですが、
実はこれが文化に豊かさをもたらしている。
世界で顕在化する立体構造に、
この日本独自の価値観が有効ではないかと
本気で思っています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年06月20日
自分自身に自身が持てなくなった人は
塩野七生 著「ローマ人の物語XV ローマ世界の終焉」から
『
自分自身に自身が持てなくなった人はしばしば、
違いをことさら強調することによって
自身をとりもどせた気になる
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年06月19日
盛者は常に必衰
2007年06月17日
不本意に演奏した曲は無い
2007年06月12日
何となく面白い
2007年06月10日
旗を掲げよ!
映画「パイレーツ・オブ・カリビアン ワールドエンド」から
『
みなの者、旗(海賊旗)を掲げよ!
』
国民と国家権力との戦いが今日、始まりました。
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年06月09日
情報に基づかない政策は国を滅ぼす
2007年06月08日
行動しようとする人間が情報を扱うと
小谷 賢 著「日本軍のインテリジェンス」から
『
これは一般的に情報の政治化と呼ばれる問題であり、
行動しようとする人間が情報を扱い出すと、
手段と目的が入り混じるために
客観的な情勢判断がむずかしくなってしまう現象である。
』
だから第三者機関を作って、消えた年金問題を調査する必要があるのです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年06月07日
日本の政策決定はゴミ箱モデルである
小谷 賢 著「日本軍のインテリジェンス」から
『
日本の政策決定過程を「ゴミ箱モデル」と呼ぶ。
「ゴミ箱モデル」とは文字通り、各自がゴミ箱にゴミを投げ入れるように議論を交わし、
一致した結論の出ないままいつの間にかゴミが収集される。
そして、また新しいゴミ箱が用意され・・・
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年06月04日
豊かな感情
脚本家 筒井ともみ さんの言葉から
『
何を見ても「チョーかわいい」だけではダメ。
せつない、かなしい、寂しい、やるせない、
といった豊かな感情を育ててほしい
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年06月02日
トップが明確な作戦計画を指示することが大切
小谷 賢 著「日本軍のインテリジェンス」から
『
トップが明確な作戦計画を指示すれば、その参謀達は綿密な作戦計画と情報収集を行うようになり、インテリジェンス・サイクルが機能し出すのである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年06月01日
インテリジェンスを有効に活用するには
小谷 賢 著「日本軍のインテリジェンス」から
『
インテリジェンスが有効に機能するためには、組織間の水平的協力関係と情報の共有が不可欠である。
』
偽メールはインフォメーション【生情報】ではあっても、インテリジェンス【情報の本質】ではありませんでした。インテリジェンスを理解していない人は、政治の表舞台に立って欲しくないですね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年05月31日
日本人は客観的に物事を見ない
旧日本軍 樋口季一郎 元中将 の言葉から
『
大よそ情報収集の目的は、
「事象の実体を客観的に究明する」にある。
ところが日本人は主観を好む。
主観は「夢」であり「我」である。
これは己個人に関する限り自由であるが、
我観及び主観を国家の問題に及ぼすにおいては、
危険これより甚だしきはあるまい。
』
主観的な話しかしない政治家が、国家を運営する危うさ!
年金が消えたことの本質を理解していない首相のいる国の空しさ!
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年05月29日
最高権力者がしばしば変わることは
塩野七生 著「ローマ人の物語XV ローマ世界の終焉」から
『
一国の最高権力者がしばしば変わるのは、痛みにたえかねるあまり寝床で身体の向きを始終変える病人に似ている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年05月28日
見ようと欲ししているものしか見えない
2007年05月27日
塔に登れ
2007年05月25日
意欲を高めるには
2007年05月23日
表現力豊かに話すこと
2007年05月22日
きちんとした組み立てで話すこと
築山 節 著「脳が冴える15の習慣」から
『
単語だけでも通じるような相手でも、
きちんとした組み立てで話すことを心がけて下さい。
前頭葉の系列化する力が鍛えられます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年05月21日
断言してあげたほうが親切
2007年05月17日
子どもの頃は日本語をしっかり身につけること
築山 節 著「脳が冴える15の習慣」から
『
脳の性質から考えると、
子どもの頃に日本語の言語体系をしっかり身につけさせておく、
その中でパッと概念化する能力を鍛えておく、
使える語彙を増やしておくということは、
もっとも重要なことです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年05月15日
睡眠も思考の一部
築山 節 著「脳が冴える15の習慣」から
『
「睡眠も思考の一部」と考えて、早く寝るようにしましょう。十分に寝て、起きてから熟考する習慣を身につけた方が絶対に合理的です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年05月14日
誰かを頼ることに慣れると
2007年05月13日
戦争を知らない子供たちのこどもたちは、戦争知った子供たちだ
塩野七生 著「ローマ人の物語XV ローマ世界の終焉」から
『
人間には、絶対に譲れない一線というものがある。
』
憲法を変えるだけの「国民投票法」が成立!!
子供のころ、「戦争を知らない子供たち」という今思えば脳天気なフォーク・ソングが流行っていました。その唄も今では時の中に置き去りになり、「戦争をしてもいいではないか!」という首相も現れて。
日本人にとって、憲法第9条は「絶対譲れない一線」だったはずなのですが・・・
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年05月12日
日本語のいろんな言い回しを楽しみたい
2007年05月08日
大事を成すには冷徹さも必要
塩野七生 著「ローマ人の物語XV ローマ世界の終焉」から
『
大事を成すには、情熱的でエネルギッシュであるだけでは不十分で、そのうえさらに冷徹さが求められる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年05月06日
Deterioration
Google エリック・シュミットCEO の言葉から
『
グーグルを常に使うようになったとき、私の人生が変わったといった方がいいでしょう。
』
これをもじって、
「成果主義を常に使うようになったとき、日本の劣化が始まったと言った方がいいでしょう」
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年05月04日
建前だけの人間関係は
塩野七生 著「ローマ人の物語XV ローマ世界の終焉」から
『
互いに本音は出さずに建前だけで相対する人間関係は、問題は収拾できてもしこりを残さずにはすまない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年04月28日
ホームレスのおちゃんを持ってホストを制す
塩野七生 著「ローマ人の物語XV ローマ世界の終焉」から
『
「毒をもって毒を制す」式の戦略は、
・・・
国家ローマにとっては、共和政・帝政を問わず、
長年にわたって使い慣れた政略であり戦略であったのだ。
』
女性の敵であるホストが客狙いをしているところへ、ホームレスのおっちゃんがホストに絡んできました。大阪のホームレスのおっちゃんはねっちこいので、ホストもタジタジ。正に「毒を持って毒を制す」ですね。
大阪市も客のいない今里線を造るお金があったら、悪質ホスト撲滅のためにホームレスのおっちゃんを雇用したらどうでしょうか!
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年04月27日
見たくない現実を突きつけられると
塩野七生 著「ローマ人の物語XV ローマ世界の終焉」から
『
人間とはしばしば、見たくないと思っている現実を突きつけてくる人を、突きつけたというだけで憎むようになる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年04月25日
妥協を急がない鉄則
2007年04月24日
伝統でないものは効果を期待できない
塩野七生 著「ローマ人の物語XV ローマ世界の終焉」から
『
伝統とは、できるならば変えてはならないこと、であり、伝統でないということは、たとえ変えようとたいした効果は期待できない、ということでもある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年04月20日
大阪名物、役人の浅知恵
4月19日付 朝日新聞夕刊(大阪版)に、
「大阪市がカーネギーメロン大大学院の海外拠点を誘致」
とありました。
『
外人の発想を当てにして、発想する土壌を造ることを忘れるな。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年04月15日
昔魚がいた川で魚を釣る
とても魚が住んでいそうもない川で、いつも熱心にリールを仕掛けている初老の人を見ます。たぶん、この人が若い頃は、ここで魚を一杯釣ったんでしょう。
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年03月30日
人間の問題に人間らしく取り組ませること
早川書房 トム・ケリー&ジョナサン・リットマン著「イノベーションの達人!」から
『
物語以上に人を深くテーマにかかわらせるものはない。
それは、チームを団結させて、
人間の問題に人間らしく取り組ませることにも役立つ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年03月25日
欧州にも目を向ける必要がある
脇阪紀行 著 「大欧州の時代」から
『
市場原理を掲げる米国と異なってEUは、
競争力強化を進めつつ、
社会的連帯や公正、
平等実現への努力を払おうとしている。
日本の未来戦略の構築にあたっては
米国の動きを追うだけでなく、
欧州にも目を向ける必要があろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年03月23日
もっとほかのことに振り向ければ
中野麻美 著 「労働ダンピング」から
『
差別や暴力との闘いに費やすエネルギーを
もっとほかのことに振り向ければ、
社会はもっと平和になり、
一人ひとりが尊重されるように
つくり替えられていくだろう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年03月16日
心と体に忠実にしていると
栗岡多恵子 さんの言葉から
『
生きているのがしんどい時って、
だれにでもあるけれど、
心と体に忠実にしていると、
心の底から生きる力と勇気が
わき上がってきてくれるはずです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年03月13日
うまい台詞を言える役者とは
2007年02月23日
安くても高くても
奈良市法蓮町で雑貨・カフェを開く 石村 由起子 さんの言葉から
『
安くても、それで心地よい空間ができるなら、
安っぽくならない。
高くても、大切に使う年月で割れば
おつりがきますよ
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年02月22日
ハートを入れ忘れたとき
映画「オズの魔法使い」 ブリキ男の言葉から
『
僕にはハートが無いんだ。
ブリキ職人が入れ忘れたから。
』
派遣法や労基法が改正され過酷な労働が常態化した結果、これを誘引とした事故や事件が多くなってきました。ハートを入れ忘れた法律には、誰がハートを入れるのでしょうか?
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年02月19日
評価するのは利用者
2007年02月17日
テイストを統一させる
2007年02月12日
現代の都市空間にもってくるだけではダメ
2007年02月02日
緊張とリラックスのバランス
2007年01月18日
「痛い」決定をする能力
2007年01月14日
生チョコレートケーキが消えた日
モンリーブ 山川和子名誉会長の言葉から
『
手元に10万円しかなければ
10万円分だけ仕入れる。
安全圏に身を置くのではなく、
ある範囲に全責任をかけて臨み、
必ず結果を出すということです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年01月12日
作り出すものの方がおもしろい
2007年01月10日
どれだけ素晴らしい気持ちか
阪神大震災でボランティアを行ったボビー氏が、ボランティアの日々を振り返った言葉から
『
あちこちで壊れた家に花が供えてあって・・・。
楽しい思い出じゃない。
でも、すべてを失った人にさえ喜んでもらえる。
それがどれだけ素晴らしい気持ちか、分かるかい
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年01月07日
権力を手中にして考え実行することは
塩野七生 著「ローマ人の物語 すべての道はローマに通ず」から
『
ある一つの考え方で社会は統一されるべきと考える人々が
権力を手中にするや考え実行するのは、
教育と福祉を自分たちの考えに沿って
組織し直すことである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2007年01月05日
中身を期待させる演出
2006年12月29日
オチで話をスムーズに終了させる
酒井 順子 さんの言葉から
『
関西の人と話している時に感じるのは、
話にかならずオチがついているということ。
ある方向にずっと話が続いていても、
最後になってハンドルを急に切ることによって、
その話がスムーズに終了する。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年12月27日
ごった煮の中の真実
2006年12月19日
いかにしてそうなったかを見る
2006年12月17日
政治家や官僚は客観的規準のある基礎作りに専念すべき
塩野七生 著「ローマ人の物語 すべての道はローマに通ず」から
『
夢とかゆとりとかは各人各様のものであって、政策化には欠かせない客観的規準は存在しない。政治家や官僚が、リードするたぐいの問題ではないのです。
政治家や官僚の仕事は、国民一人一人が各人各様の夢やゆとりをもてるような、基礎を整えることにあると思います。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年12月15日
認められるために戦う
2006年12月02日
農業の大切さ
2006年11月22日
手紙は他人に話しかける最良の方法
新潮社 キングスレイ・ウォード著「ビジネスマン、生涯の過ごし方」から
『
手紙は他人に話しかける最良の方法だと思う。
しかし、あわただしい現代の世の中では、
他の方法に頼りがちである。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年11月19日
楽しみながら走っていた
2006年11月17日
物語を作る人になりたい
2006年11月14日
学びの豊かさが人間を大きくする
2006年11月09日
現実をはっきりつかむ
2006年11月07日
もの言うときは直接的にダイレクトに
白洲次郎 著「プリンシプルのない日本」から
『
それじゃお前は何だって訊くと、何も持っていないんだ。
日本人のものの言い方は、もっと直接的に、ダイレクトに言わなきゃいけないよ。
そういう言い方を習わなきゃいけないよ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年11月02日
良くする他に道はない
白洲次郎 著「日本人という存在」から
『
悪い現状を認識して、どうやったら国民が幸福になるかを考えるべきなんだ。
よくなるかとかならんというよりも、よくするほかにみちがないことを認識すべきだというんだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年10月28日
勇敢に発言する
白洲次郎 著「政界立腹帳」から
『
私は財界人といわず誰でも日本国民は、もっとはっきり政治に対する意見をいうべきだと考える。法律的に政治は天皇のものであった時代はいざ知らず、現在は国民全部がもっともっと政治に関心を持って、勇敢に発言するにあらずんば民主主義は発展しないし、政治もよくならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年10月24日
外国のことを知ろうとする意欲を起こすこと
白洲次郎 著「まっぴら御免」から
『
世界各国がお互いのことをなるたけ早く、よく、知り合わないと科学の進歩に間に合わなくなるかもしれぬ。もっともっと外国のことを知ろうとする意欲を起こすことだ。
とくにその外国人の立場に立って その外国を知ることだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年10月20日
広い世界へまっしぐらに飛び出しましょう
3Dバーチャルゲーム「Second Life」がもうすぐ日本に上陸するそうです。ゲームといっても名前が示す通り、仮想空間で他人とコミュニケーションを取りながら社会生活まで行えます。
ただ、心配なのはこういうものは人間が本来が持っているパーソナル・スペース(心理的ななわばり)を混乱させるので、その結果どういう社会問題が起きるか分からないところにあります。
たとえば「mixi」のようなソーシャルネットワークでも、依存性や中毒のことが問題となっています。やはり、やり過ぎないためのシステム的リミッタが必要だと思うのですが・・・
押井守氏が監督した映画「アヴァロン」には、仮想世界から帰れなくなった"無帰還者"の話が出てきます。人が現実と仮想との間合いを上手く取れるには、もう少し時間が必要なのかもしれません。
ただ、本当に気をつけなければいけないのは、人々が仮想現実にのめり込んでいる間に、そのすきまを突いて現実世界で悪いことを考える政治家や悪徳官僚が、虎視耽耽と狙っていることなのです。現実世界の不満を、仮想世界へ隠してはいけません。
ゲーテの「ファウスト」でメフィストファレスが次のように言っています。
『
思索なんかに耽る奴は、水汲みのために井戸の周りをぐるぐる引き回されているロバのようなものだ。さあ、広い世界へまっしぐらに飛び出しましょう。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年10月17日
正しいことを堂々と言う
白洲次郎 著「おおそれながら」から
『
弱い奴が強い奴に抑え付けられるのは世の常で致し方なしとあきらめもするが、
言うことだけは正しいことを堂々と言って欲しい。
その後で言い分が通らなくても何をか言わんやだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年10月14日
提供される良質の経験によって
2006年10月12日
自分の思想が出発点
白洲次郎 著「日曜日の食卓にて」から
『
イデオロギーというものは、あくまでも自分の思想というものが出発点となってでき上がったものの筈だ。ところが日本の政治家を見てるのに、なんかひょっとしたはずみに本を読んだり、人に聞いたりしたことを全部鵜呑みにして暗記するらしい。それが彼のイデオロギーなんだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年10月08日
本を残す方がいい人生だと
新風舎社長 松崎義行 さんの言葉から
『
なんか、みんなが本を出せばいいと思うんですね。
お金やビルを残すより、
本を残す方がいい人生だと個人的には思います。
僕も本を残したいし。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年10月02日
日本語のリズムや感情に気づいて
コピーライター 村上美香 さんの言葉から
『
メールが普及して、文字で人に思いを伝える機会は増えたけど、絵文字に頼りがち。
もっと日本語のリズムや感情に気づいてほしいと思って。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年09月22日
ステキなものがいっぱい詰まっている
コピーライター 村上美香 さんの言葉から
『
日常のちょっとした言葉の中に、ステキなものがいっぱい詰まっている。その言葉をすくい上げて多くの人に届けたい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年09月18日
意思表示や自尊心を育む躾
大阪市立大学名誉教授 北浦かほる さんの言葉から
『
欧米では、子育ての目標は、自己主張でき、リーダーシップと社会性を身につけた子どもに育てる、と明確です。そのために、意思表示や自尊心を育む躾が幼児期から各家庭独自のルールのもとで実践されています。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年09月17日
未来に希望がある限り
2006年09月16日
子どもと行為の共有が不可欠
大阪市立大学名誉教授 北浦かほる さんの言葉から
『
幼児期や小学生期から親子の絆を強固なものにするには、行為の共有が不可欠です。会話や遊び、スポーツなどを親子ですることで、強いコミュニケーションが生まれ、お互いの信頼が強められます。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年09月12日
お菓子は文化のバロメーター
2006年09月11日
胸を張って本社は大阪
2006年09月09日
見えない部分を想像する力
思想・文化史研究者 小倉孝誠 氏の言葉から
『
光に照らされた表面だけに目が向かい、暗い部分や見えない部分を想像する力が衰退した。だから他人の苦痛や痛みに対する感覚も希薄になっている。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年09月02日
正しいこと言う人は
東心斎橋 旅館「たわらや」女将 湯浅良子 さんの言葉から
『
正しいこと言う人は、そら怖いでっせ。
でもけったいなこという人間なんか、
ちょっとも怖いことあらしません。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年08月27日
常識に囚われず行動する
2006年08月25日
紅茶はゆったりした気分で飲むこと
2006年08月23日
人は愛されて育って
2006年08月20日
比べものにならない喜びがある
ブックオフコーポレーション社長 橋本真由美 さんの言葉から
『
よい母、よい妻が目標でした。でも、夫の出世や娘の成績とは比べものにならない喜びがあると、気づいたんです。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年08月18日
言い方の知恵
作家 田辺聖子 さんの言葉から
『
大阪弁の大きな特徴は人を傷つけないこと。
派手な服をにぎやかな服やなあ、
という言い方をする知恵がある。
人と人とを結び付け、あれっと思わせる、
面白いやんけと思わせる親和力、融和力が強い。
のけ者になっているような人も振り向かせて
仲間にするような言葉。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年08月15日
何百万はもちろん、一人だって、命は犠牲にできない
【スタートレック・ヴォイジャー】キャスリン・ジェインウェイ艦長の言葉:
『
だからって、命を犠牲にしていいわけないわ。
何百万はもちろん、一人だって!
』
やっと停戦かと思われるレバノン。
ウィキペディア(Wikipedia)によると、この国からイスラエルを挟んで南側にあるヨルダンのアブドゥッラー2世国王は、スタートレックの大ファンで、【スタートレック・ヴォイジャー】にエキストラとして出演したそうです。
イスラエル首相もスタートレックを観て、命について考えてもらいたいのものです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年08月12日
1年が100年に思えるほど濃い時間
復活したOSK日本歌劇団 桜花昇 さんの言葉から
『
1年が100年に思えるほど濃い時間を過ごし、
今までを駆け抜けてきた。
今が正念場だと思っています。
だからこそ焦らずに落ち着きながら、
人間同士の気遣いや信頼し合える関係を大切にした
OSKの舞台をお見せしたい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年08月09日
人生のヒーロー
2006年08月04日
「ALOHA」は五つの言葉
2006年07月30日
字から想像すること
作家 田辺聖子 さんの言葉から
『
本を読むと、内容を自分の頭で想像するでしょ。
映像のようにすぐわかるものではなく、
字から想像することが人間の精神力になる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年07月29日
いい言葉は書き留めよう
作家 田辺聖子 さんの言葉から
『
私は本から言葉を覚えました。
いい言葉は書き留める、
そんなまめまめしさが欲しいですね。
もとは好奇心ですよ。
いい言葉はもらって、
覚えて、使って、広めよう!
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年07月25日
音楽の魔法
2006年07月24日
今いる場所でどう助けられるか
2006年07月21日
受信する感度を高めること
神戸女学院大教授 内田樹 さんの言葉から
『
メディアが流す、バーチャルで定型的な言葉でなく、目の前の人の発するリアルで個別的でわかりにくいメッセージを受信する感度を高めることが大事。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年07月19日
舞の中に人がいた
2006年07月12日
言葉で伝わらないものは
2006年07月10日
かならず楽しいところがある
早川書房 トム・ケリー&ジョナサン・リットマン著「The Art of Innovation 発想する会社」から
『
やらなければならない仕事にも、かならず楽しいところがある。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年07月09日
みんながブラックジャックにならないと
2006年07月07日
食の力ってすごい
インド料理教室を開いておられるナフィーサ・トラバリーさんの言葉から
『
日本に1人も知り合いのいなかった私が、料理を介してインドの文化や伝統を伝えられる。食の力ってすごいと思わない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年07月04日
舞台とは全員のアンサンブル
2006年07月03日
声だけが心に残るほうが
CMソングの隠れた女王 のこいのこ さんの言葉から
『
名前が出ないのがかっこいいと思っていた。声だけが心に残るほうが、歌手として、すごいと思いません?
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年07月02日
自分のやっていることを考えるべきじゃ
バイオリニスト 高嶋ちさ子 さんの言葉から
『
やってはいけないことをやる大人がこれだけ多いと、子供にどれだけの悪影響を及ぼすのか考えてみたことがあるのかと問いたいです。
「最近の子供は・・・」
という前に、自分のやっていることを考えるべきじゃ!
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年06月25日
当たり前の暮らし方
武庫川女子大教授 大谷孝彦 氏の言葉から
『
英語の「健康で持続可能な生活様式」の頭文字を取った「ロハス」も「スローライフ」も、ひと昔まえの日本では当たり前の暮らし方やった。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年06月24日
義務じゃなく権利なんだ
女優 岸根季衣 さんの言葉から
『
色んな問題を普段の会話でフランクに言い合える、そんな雰囲気になったらと思います。
義務じゃなく権利なんだと、主張の強いフランス人が、ちょっと羨ましいです。
』
今、「共謀罪」の立法化を急ぎ、反対意見も問答無用という、恐ろしい社会となってしまいました。
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年06月23日
人の子の心の底を温かく保つ
数学者 岡潔 氏の言葉から
『
教育は何よりも人の子の心の底を温かく保つことに留意しなければならない。人を愛さなければ人ではないし、学ぶを愛せなければ学ぶは教えられない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年06月17日
違う世界の人と出会うと
2006年06月15日
気持ちで感じ合える関係
「まんが日本昔ばなし」の語り 俳優 常田富士男 氏の言葉から
『
語りは人間同士の往復作業。
正直に正面から向かい合えば、
感謝の気持ちが自然と生まれる。
気持ちで感じ合える関係を
大切にできる世の中であってほしい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年06月14日
それだけが本当に私の願いでした
元郵政相 故・箕輪登 氏の言葉から
『
(自分は)やがて死んでいくが、
死んでもやっぱり、
日本の国がどうか平和で、
働き者の国民で、
幸せに暮らして欲しいなと、
それだけが本当に私の願いでした。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年06月12日
戦う敵は外じゃない
2006年06月11日
奥行きはずっと深くして
ワタベウェディング社長 渡辺隆夫 氏の言葉から
『
京都の商法は、家の建て方と同様に、間口は小さく、おとなしくして、奥行きはずっと深く、いろいろな変化に対応できるようにします。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年06月08日
恐ろしい言葉
福田誠治 著「競争をやめたら学力世界一:フィンランド教育の成功」から
元教育課程審議会会長 三浦朱門 氏が語った言葉:
『
・・・
つまり、できん者はできんままで結構。
・・・
限りなくできない非才、無才には、せめて実直な精神だけを養っておいてもらえばいいんです。
』
日本の教育行政がこの程度ではね。「愛国心」とは、”文句も言わず、国のためだけに働くこと(死ぬこと)” を強制するための布石なのですか?
国が民の二極分化をよしとし、「狼は生きろ、豚は死ね」 ということを実践しているようでは、この国の将来はありません。
今、金子みすづ の『みんな違ってみんないい』 という詩が、時代を超越して21世紀の日本人に語りかけています。
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年06月07日
笑う前に笑えるか?
最近、近所の人や親戚に不幸がありました。最後がハッピーエンドでなかったので、本人はさぞかし心残りだったと思います。
『
人間、笑う前に笑わなければならない。
』
という格言があります。
笑える程の吉事を待っていては、いつまでたっても笑うことができず、ついには命が尽きてしまうという例えです。そうならないよう、「平凡な生活の中に幸せを作り出そう」という気構えを持ちたいものです。
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年06月03日
質の高いほっとする時間
マイボトルカフェ:すいとう帳委員会 藤本智士 氏の言葉から
『
せわしない現代人にとっては、空いた短い時間をどれだけ質の高い ほっとする時間にできるかが大事です。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年05月31日
欠点をエネルギーにする
2006年05月30日
コミュニケーション不足
2006年05月28日
”今”が面白くなくなったら最後
女優 白石加代子 さんの言葉から
『
師匠もなく自分勝手流だから、昨日をなぞらぬよう肝に銘じて、ひたすら前に進むだけです。
役者は、”今”が面白くなくなったら最後ですから。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年05月27日
命がキラッとする瞬間
ジャズボーカリスト 鈴木重子 さんの言葉から
『
安心して幸せな気分で歌えるから、
魔法みたいに自分の命がキラッとする瞬間がある。
きれいな泉から水がわくような。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年05月26日
新鮮な風を求めると
2006年05月25日
解決がないものは
批評家 陣野俊史 氏の言葉から
『
解決がない小説はエンターテイメントとして成立していない。
陰湿なだけだ。
』
結論のないBLOGや、結論が曖昧な会社の企画書も同じですね。
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年05月24日
分かりにくいけど面白い
劇作家・演出家・女優 渡辺えり子 氏の言葉から
『
演劇まで「勝ち組」「負け組」と選別されるのが許せない。
分かりにくいけど面白い、
そんな舞台を作るために頑張りたい。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年05月23日
新しい人間の姿が生まれる
フランス・ストラスブール大名誉教授 ジャンリュック・ナンシー氏の言葉から
『
インターネットによる人間関係は、乾いていて冷たいと言われるが、そこから新しい人間の姿が生まれるのかもしれない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年05月22日
何をしてはいけないか
【スタートレック・エンタープライズ】アーチャ艦長の言葉:
『
やがて人間にも規律ができるだろう。
この宇宙で何ができて、何をしてはいけないかを。
しかし、それまでは自分自身を戒めなければならない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年05月18日
メカの詰まった唯の箱
2006年05月17日
よっしゃ頑張ろう
落語家 桂坊枝 氏の言葉から
劇団四季 ミュージカル「マンマ・ミーア!」を観て
『
最初は滑稽な姿が次第に格好よう見えてくる。
よっしゃ頑張ろう、という気になる。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年05月16日
勝つことが好き
競泳選手 森田 智己 氏の言葉から
『
やっぱり好きなんですよね。
泳ぐことが、ではなく、
勝つことが好き。
・・・
かっこいいじゃないですか、
一番って。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年05月11日
嫌いなものを時代遅れにする
2006年05月10日
のっぴきならん時でも
裏千家前家元 千 玄室 氏の言葉から
『
人生には山あり谷あり、がけもありで、
がけっぷちに立たされ、
のっぴきならん時でも、
自分を見失ってはいけません。
本当に。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年05月06日
やさしさに包まれたなら
5月5日付の朝日新聞に 「ブログに群がる”ネット右翼”」 の記事がありました。
それは、ネットに依存して自己主張を繰り返し、特定のブログを攻撃する人達がいるという話です。
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年04月30日
人間には守るべき規範というものが
【スタートレック・エンタープライズ】アーチャ艦長の言葉:
『
人間には、守るべき規範というものがあるだろう。
地球で生まれようが、生まれまいが、それは同じはずだ。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年04月16日
望まなくても
2006年04月13日
ものは言うてみ
2006年04月02日
物語はまだ続くんだから
2006年03月31日
君の生涯でもっとも輝かしい日は
『
君の生涯でもっとも輝かしい日は
いわゆる成功の日ではなく
悲観と絶望の中から
「今に見ていろ、やってみせるぞ」
という気持ちが湧き上がるのを
感じる日である
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年03月29日
季節は忘れず来たり
桜の花が咲き出しました。寒かった冬なのに平年より2日早いそうです。
この季節になると、昔 コンピュータ雑誌の表紙にあった次の詩を思い出します。
誰の詩だったのか不明なのですが・・・
『
季節は忘れず来たり
振り向けば、幾千の時は流れ
・・・
そっと寄り添い 紅に染まる
忘れ得ぬ日々の証(あかし)
金の針で綴じよう
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年03月28日
幸せは待っちゃだめさ
最近の子供番組を見ると、テーマソングの歌詞や番組内容に鋭角的な表現が多いように思えます。
しかし、昔のテレビ番組はもっとまろやかでした。例えば、子供向番組に「ゆびきりげんまん」というのがあり、歌詞に次のフレーズがありました。
『
幸せは待っちゃだめさ、自分で作るんだ。
夢をいぱい育てよう。
皆で指きりげんまん。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年03月27日
癒しではなく活気
2006年03月22日
結果が間違っていたからといって
【スタートレック・ヴォイジャー】キャスリン・ジェインウェイ艦長の言葉:
『
結果が間違っていたからといって、後戻りはできない。
それは役に立ったこともあるはず。
それを踏まえて進んで行くこと。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年03月21日
知識とはそうして得るもの
【スタートレック・ヴォイジャー】 キャスリン・ジェインウェイ艦長の言葉:
『
リスクを犯して行動すること。
ときには失敗するけれど、知識とはそうして得るものなの。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年03月20日
成功が不足している
2006年03月17日
ほっとスポット
『
生活は簡素に。思想は高貴に。
』
勤め帰りに、ほっとしたいことってあります。
お金さえ掛ければ、いくらでも「ほっと」するところはありますが、慎ましい小遣いで行けるところがいいですね。
近所のネットカフェだと、静かですが全体的に薄暗く落ち着きません。また、本屋の喫茶コーナーは明る過ぎて、これも落ち着かないんです。本を読むには良いのですが。
間接照明で適度な明るさと、座り心地のよい椅子があるのが理想です。スターバックスなんか結構それに近いんですが、人の出入りも結構あるので、やっぱり落ち着きませんでした。
インターネットへ接続するためのホットスポットだけでなく、理想のほっとスポットもあればいいのですが・・・
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年03月14日
1光年行くごとに
【スタートレック・エンタープライズ】アーチャ艦長の言葉:
『
提督は1光年行くごとに歴史が作られると言ったが、箱(宇宙船)の中にいるだけでは何も起きない。
』
- Permalink
- by
- at 00:00
2006年03月13日
その時の人々の喜びは
フランスの僧ゴドウィン(17世紀)が『月世界の人、または韋駄天の飛脚ドミンゴ・ゴンザレスによる彼方への旅の物語』を著したとき、次のように語ったと言われています。
『
いつの日か困難を克服した人々は月に到達するであろう。
その時の人々の喜びは、如何ばかりのことか!
』
- Permalink
- by
- at 00:22
2006年03月12日
ういにぃ
『
すべての権利は義務を含み、すべての自由は責任を含む。
』
Winnyによる情報漏洩が毎日のように報道されています。まあ、Winnyなんか使っている個人にも問題があります。しかし・・・
- Permalink
- by
- at 00:56
2006年02月27日
娘さんの食べたかったのは
2006年02月17日
桃花水
2006年02月15日
今やるべき重要なことは
オズ様がおっしゃった。
『
計画は、成功するために立てるもの。
フルライン/フルスペックは計画ではない。失敗する計画を立ててどうする。
今やるべき重要なことは、一つだけである。
』
- Permalink
- by
- at 23:00
2006年01月01日
みんな違ってみんないい
・・・みんな違ってみんないい・・・
「詩人:金子みすづ」のこの言葉が好きです。
勝ち組、負け組み という言葉を当たり前のように使う人が多くなりましたが、100人いれば100通りの評価を創り、皆が勝ち組みでいいではありませんか!
- Permalink
- by
- at 01:51